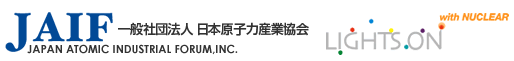【論人】十市 勉 日本エネルギー経済研究所 専務理事・首席研究員 クライメート・ゲート事件とその教訓地球温暖化の科学を巡って、世界的に大きな論争が起きている。その契機になったのは、昨年11月に英国イースト・アングリア大学の気候研究ユニット(CRU)のサーバーにハッカーが侵入し、大量のメールと文書が流出した事件である。その結果、1980年以降世界の地表気温データの取りまとめの責任機関となっているCRUが、過去の気温データを不正に操作して温暖化を演出したり、査察班を作って温暖化に否定的な論文を却下するなどの不正を働いたとの疑惑が持たれるようになった。いわゆる「クライメート・ゲート事件」と呼ばれるものである。 これに続いて、今年1月には、国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第4次評価報告書の「ヒマラヤの氷河が2035年までに消滅する」との記述に科学的根拠はなく、インド人科学者の憶測意見を誤って引用したことが判明し、IPCCのパチャウリ議長もその事実を認めた。さらに同報告書では、アマゾン熱帯雨林の破壊や温暖化による台風・ハリケーンの増加等のリスクが指摘されているが、それらは妥当性を欠く研究に準拠しているとの批判が相次いで出された。 気候変動研究のバイブルともいえるIPCCの報告書に疑念が相次いだことで、世界の温暖化懐疑論者は勢いを増している。日本でも、大気中のCO2濃度の上昇は温暖化の原因ではなく結果であり、これからは地球寒冷化に向かうとする説、また20世紀に入っての温暖化は15〜16世紀の小氷河期からの回復過程での温度上昇で、その主な原因は自然変動であり、人間活動による影響は小さいとする説(アラスカ大学の赤祖父俊一氏)など懐疑的な意見も根強くある。 言うまでもなく、地球という生命体は、開放型の複雑系システムであり、人間活動だけではなく、太陽や火山活動など自然変動の影響を大きく受けている。そのため、「地球平均気温」の上昇について、人間活動と自然変動の影響を厳密に評価するのは容易なことではない。しかし重要なことは、大気中のCO2濃度が産業革命前の280ppmから現在では380ppmを超えるまで上昇していること、また大気中のCO2の増加が確実に地表の温度上昇を引き起こすという厳然たる科学的な事実である。 今回のクライメート・ゲート事件が提起しているのは、科学的な不確実性を持つ地球温暖化のリスクを、科学者が社会にどのように伝えていくべきかという問題である。英国政府が任命した調査委員会の報告書では、データの改ざんなどの不正は見出せなかったが、気温データの透明性や公開性の欠如、また統計データの分析方法などで問題があるとの指摘がなされている。このような背景には、多くの気象専門家が、温暖化は複雑で一般国民には理解が難しいので、科学的な不確実性を捨象して、単純化かつ誇張して伝えることで、社会に強い警告を発するとの意図があったと思われる。 先日、IPCCの科学的知見の分野で中心的な役割を果たしている日本の研究者と対談する機会があった。その際、彼の言によると、欧州特にドイツの専門家が、科学的な検証が十分ではないにもかかわらず、地球の平均気温を産業革命前に比べて2度C以内に抑えることをアプリオリ(自明的)に絶対視して、非現実的な世界のCO2削減シナリオを強引に推し進めようとしているのは非常に問題が多いとの指摘があった。 失敗に帰した昨年12月の国連気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)コペンハーゲン会合の教訓として、全人類的な課題である地球温暖化を防ぐためには、カント的な理想主義的よりも、プラグマティズム(現実主義)に立脚した実行可能なアプローチをとるべきではないかと思われる。その意味で、IPCCに求められるのは、特定の政策を主導することではなく、科学者として中立的な立場から、客観的で透明性を持ったデータや質の高い研究成果を示し、政策の選択肢を提示することである。それに基づいて、政策立案者や政治家は、バランスのとれた実行可能な政策を国民に説明し、実行に移すことが重要である。 |
|
お問い合わせは、情報・コミュニケーション部(03-6812-7103)まで |