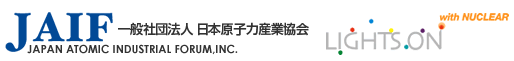【日米協定の検証】日米原子力協定の成立 経緯と今後の問題点〈第2回〉 遠藤 哲也 元原子力委員会委員長代理、元外務省科学技術担当審議官 協定交渉の背景 インドの核実験と世界的な核不拡散の強化、東海再処理交渉〈インドの核実験と世界的な核不拡散強化の動き〉 「春風が吹けば桶屋がもうかる」のたとえ話ではないが、現行の日米原子力協定交渉の始まりは、1974年のインドの第1回核実験、それを契機としての世界的な核不拡散強化の動き、1977年の日米の東海再処理交渉にたどりつく。 インドの核実験は、1970年に発足したばかりの核不拡散条約(NPT)体制に深刻な衝撃を与えた。インドは、平和核爆発と称していたが、これを額面通り受け取る国はなく(現在の技術では、平和核爆発と軍事核爆発とは区別できない)、1998年の第2回目の核爆発では、この仮面を脱ぎすててしまった。インドの核実験以降、核拡散防止に対する関心が急速に国際的なレベルで広まっていった。 多国間レベルでは、ロンドン・ガイドライン(現在の核供給国グループ(NSG)の前身)と称する先進国グループによる共通の輸出基準の作成であり、国際核燃料サイクル評価(INFCE)の作業であった。後者は原子力の平和利用、特に核燃料サイクルと核不拡散は両立しうるかを探るため、カーター米大統領の提唱によって始まったもので、2年以上を費やした莫大な作業であった(77年10月より80年2月まで)。 検討の結果は、両立可能というもので、カーター大統領の意にはそぐわなかったが、日本にとっては一応満足すべきものであった。 二国間レベルでは、米、カナダ、オーストラリア等供給国側による核拡散防止の規制を強化するための原子力協定改定交渉の動きであった。 カナダは、インドの実験に使われたプルトニウムが、カナダからインドに輸出された原子炉によって生産されたものであったことに、非常に衝撃を受けていた。問題は米国である。米国の核不拡散政策というと、カーター大統領時代を思い浮かべるが、核不拡散政策は米国の原子力政策の底流にあり、超党派的なところがあって、共和党も民主党も一皮むけば濃淡の差があるものの同じといったところがある。インドの核実験を受けて、フォード大統領も核拡散防止の強化を目的として政策を打出したが、これが一層強化された形で次のカーター大統領に引継がれていった。カーター大統領は就任早々の77年4月に、要旨次のような非常に厳しい核不拡散政策を発表した。 ①米国内での商業用再処理とプルトニウム・リサイクルの無期限延期 加えて、米国議会は1978年に「核不拡散法」(Nuclear Non-Proliferation Act=NNPA)を制定した。この法律の最大の問題は、米国からの原子力設備および核物質の輸出に際して、これまでの協定では何ら限定されていなかった新しい基準を設け(例えばウラン高濃縮とか核物質防護(PP)など)、その輸出基準を満たすよう、関係国との原子力協定の内容を大幅に変更するというもので、日本について言えば、日米原子力協定の改定を求めるもので、日本に対して大きな波紋を投げかけるものであった。 〈東海再処理交渉〉 日本は1950年代の原子力開発の黎明期から、一貫して核燃料サイクルの追求を原子力政策の中核に置いており、濃縮、再処理の開発に取組んできた。ところが、日本最初の再処理工場である東海工場が完成し、いよいよ77年7月から運転開始という段階になって、突然米側から日米原子力協定(1968年)の8条(C)の「共同決定」条項によって、待ったがかかった。 プルトニウムだけの単体抽出では、「効果的な保障措置」がかからないから、このような再処理は認めることはできない。どうしても再処理をしたいのならば、ウランとプルトニウムが混合した混合抽出法でやるべきだと主張して来た。 交渉は難航をきわめたが、期限、処理量の制限付で妥結し、何とか運転が可能となった。 一言で言って、カーターの核政策はプルトニウムは悪というものであり、プルトニウムの利用は平和目的であっても認めない、控え目に言っても厳しい制限を課すというものであった。70年代のカーター時代は、原子力にとって悪夢であった、というのは言い過ぎだろうか。少なくとも、日本にとってはやりにくい時代であった。 |
|
お問い合わせは、情報・コミュニケーション部(03-6812-7103)まで |