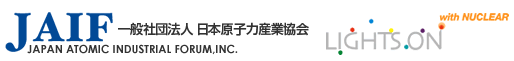【論人】西川 正純 前柏崎市長(新潟県) 雨降って地は固まったか平成19年7月16日(月)は「海の記念日」の祭日。週末からの3連休を利用して、家内とともに関西方面を旅していた私は、宿泊先の神戸ホテルオークラで出発までの空き時間を利用して、隣接する海浜公園の散策に。そこは、「阪神淡路大震災メモリアルパーク」と言った感じで、崩れた岸壁、倒れ掛かった街路灯など、被災当時の惨状が生々しく再現されていた。当時の村山連立内閣の屋台骨をも揺るがせかけた大震災。 私はその震災から4日後に現地入りしたが、そのとき目のあたりにした火災の余燼くすぶる長田区、大勢の被災者が避難していた神戸市役所のロビー……、フラッシュバックのように蘇る記憶に複雑な思いを新たにした。 ホテルの部屋に戻りボチボチ出発の準備をというそのとき、東京の友人から「柏崎の方で大きな地震があった・・」との緊迫した一報が携帯に入り、あわててテレビのスイッチをONに。画面には見慣れた故郷の景色のあれこれが映るものの、地震の被害の様子はなかなか正確に伝わってこず、心配しつつも「それほどの被害ではないのでは・・」と気を鎮めようとしていたところ、突如として原子力発電所の全景と、黒煙立ち上がる3号機の不気味な様子が映し出され、以後は全国の皆さんご承知のような「中越沖地震」の惨状が現実のものとなってきた。 マグニチュード6.8の激震、黒煙に包まれた原発・・。世界最大規模の柏崎刈羽原子力発電所の地元住民を驚愕させたひとしきりの豪雨だったが、その後、果たして地はしっかりと固まったのかどうか・・。 原子力発電所にとっての非常時における「命綱」は、「止める」「冷やす」そして「閉じ込める」――この3つの安全対策が機能するかどうかである。今回の場合、6号、7号機でごく微量の放射性物資が外部に放出され、新聞の見出しを見る限りはやや「ぎょっとする」場面もあったが、実態は自然界から受ける放射線の量をはるかに下回る量であり、炉心にある大量の放射性物資を閉じ込めるという点では、設計どおりの機能を充分に果たしていた。そして原子力安全・保安院は同年11月、国際原子力事故評価尺度(INES)に基づく評価を最も軽微な「0マイナス(安全に影響を与えない事象)」と位置づけ、国際原子力機関(IAEA)に報告をした。 こうした点について、関係者はもとより地元住民ももっと「核心的事実」として受け止めるべきだと思う。何故ならば、今回の「地震に見舞われた原発」という未曾有の事態の帰結は、すべてここに凝縮されていると思うからである。 然しながら一方において、地震発生直後の変圧器の火災映像が何の解説もないままに、しかも世界中に喧伝されて「チェルノブイリやスリーマイルアイランドの二の舞か」と危惧された、あの「空白の時間帯」を原発と隣合わせで共有していた地元住民の心情もまた大いに理解されなければならない。「こんな大きな地震に見舞われて・・、これから先もずっと原発と付き合わなきゃいけないのか・・」、夏の日差しが日毎強くなる中、汗だくで復旧作業に悪戦苦闘しつつ、地元住民が抱いていた至極ごもっともな不安感。 災害に対する同情と支援の手は差し伸べていただいても、そうした深層の気持ちまではなかなか理解していただけなかったとも思うのである。「理論としての自己評価尺度」と「現場で住民が被った災害の苦しみや心理的被害」の間には、言うに言われぬ埋めがたい乖離が存在したことは否めない。 そうした「不幸な乖離」を縮めるべく、事業者の東京電力は不眠不休の努力を続けてきた。原発の復旧工事も、地元の復興もまだ道半ばではあるが、天災とも言うべき大きな試練に遭遇して、それを乗り越えようとの時空を共にしたことは事実である。 雨の後の地が固まるかどうか、お互いの見識と努力は今だに継続中である。 |
|
お問い合わせは、情報・コミュニケーション部(03-6812-7103)まで |