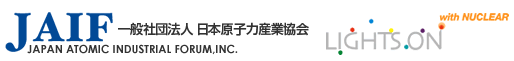数字ではなく信頼が必要 原文振シンポ 低線量被ばく偏向情報で不安に日本原子力文化振興財団は10月25日、東京の有楽町朝日ホールで、シンポジウム「考えよう低線量被ばく」を開催した。福島原子力発電所事故発生以降、放射線に関する多くの情報があふれるところ、健康影響、食品汚染に関するリスクコミュニケーションのあり方、メディアや教育の役割などを巡り討論が行われた。 討論に先立って、事故後、国の低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループをリードした長崎大学名誉教授の長瀧重信氏が講演を行い、広島・長崎の原爆被爆者に対する疫学調査結果の検証などから、100mSv以下の被ばく線量では、他の要因による影響に隠れてしまい、発がんリスクの明らかな増加を証明することが難しいことを述べた。また、福島県民の健康調査で99%超が被ばく線量3mSv以下、国連科学委員会も「福島の事故による健康影響は予測されない」との見解を示しているとする一方で、長瀧氏は、被災地住民の避難生活長期化などによる精神面への影響も危惧し、今後、放射線の健康影響を考える上で、被ばく線量の表現方法、避難住民の帰還意思、国の除染目標にも配慮し、すべての利害関係者を交えた対話が必要となることを主張した。 討論に移り、情報の扱い方に関し、マスコミの立場から、小島正美氏(毎日新聞社)が、「メディアは全体像を伝えるよりも個別的なことに興味を持つ」として、偏った記事やコメントで受け手に過剰な不安を与えている事例をあげるなどした。これに対し、消費者の立場から、市川まりこ氏(食のコミュニケーション会議代表)は、「何万ベクレルとか、桁の大きな数字にまず驚く」と述べると、専門家として、高村昇氏(長崎大学教授)、遠藤啓吾氏(京都医療科学大学学長)は、数字の意味を説明するメディアの役割、教育の不十分さをそれぞれ指摘した。 また、高村氏は、チェルノブイリを訪問した経験から、被災地でコミュニティが復活することの困難さにも触れ、川内村での支援活動を通じ、「集団の不安から個人の不安」に変わりつつあることを感じたとして、個人線量計携行の意義とともに、専門家によるきめ細かなケアの必要を述べた。 討論のコーディネーターを務めた宮崎緑氏(千葉商科大学政策情報学部長)は、「科学の世界で決着のついていないことに対し、われわれははるかに高いリスクを感じる」として、リスクコミュニケーションのあり方について、さらに議論を引き出し、「数字だけではなく、『信頼の軸』が必要なのでは」などと述べ締めくくった。 お問い合わせは、政策・コミュニケーション部(03-6812-7103)まで |