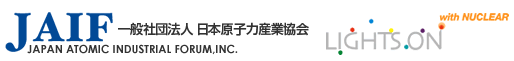精神医療分野に道筋 須原哲也 分子イメージング研究センタープログラムリーダー分子イメージングは、外側から見ることのできない身体の内部で起こっている現象を、外部から分子レベルで捉えて画像化し見えるようにする研究分野。主な画像診断技術としては、ポジトロン断層撮影法(PET)や磁気共鳴画像法(MRI)などがある。ここでは主に創薬に関わる分野での利用について説明する。 <抗精神病薬の適正量>抗精神病薬は、統合失調症に対してドーパミン神経伝達を抑え精神症状を改善する。ドーパミンD2受容体に結合することで、伝達物質が後シナプスニューロンに結合できなくするが、運動機能障害や内分泌異常などを引き起こす副作用がある。 かつての投薬の判断は、患者が主観的に訴える症状を医者がやはり主観的に評価していた。しかし、特に精神科においては主観による判断が難しく、薬の過剰投与が続くことになりかねない。 そこで分子イメージング技術により、薬が脳内の標的分子にどのくらい結合しているかを画像化した。まず標的受容体に特異的に化合する物質「PETリガンド」を用いて薬の作用部位を特定し、投薬後に脳内受容体に対する薬の占有率を測定し、副作用との関係性を照らし合わせた。 すると副作用を最小限にして効き目を最大限にできるのは、70%から80%までの間であることがわかった。 この方法で第1世代の抗精神病薬であるスルトプリドの国内認可臨床使用量は、至適治療量の10倍にも及んでいたことも判明した。 現在では、医薬品を評価するプロセスとしてこのような臨床試験が組み込まれている。このことで投薬の適切な容量を設定することができる。 <認知症異常分子を画像化>近年の研究でアルツハイマー病の原因は、異常たんぱく質である「アミロイドベータ」と「タウ」の蓄積にともなって神経細胞が死ぬことだとされてきた。しかし脳は直接組織をとって確認することが難しく、患者の死後に切片を取り出して確認することしかできなかった。 PETの登場でアミロイドベータは画像化に成功した。しかしワクチンでアミロイドベータを減らしても症状が改善されず、タウのほうが重要なのではないかと考えるようになってきていた。 放医研では、タウを画像化するためのPET薬剤「PBB3」の開発に成功し、認知症モデルマウスとヒトの両方でアルツハイマー症状の進行とタウの蓄積の相関性を画像で確認できた。タウは神経の中に蓄積し徐々に全脳に広がる性質を持つことなどから今後の治療法開発に向けた研究の方向性にも示唆を与えた。 薬の開発は診断とともにPET分野で大きなターゲットである。製薬会社にとっても画像化は利用価値が高い分野で、共同で標識リガンドを開発するなどの連携を図っている。 がんに関してはかなり治療法が確立されてきたが、精神の分野はまだ研究の余地があり、今後の進展が期待されている。 お問い合わせは、政策・コミュニケーション部(03-6812-7103)まで |