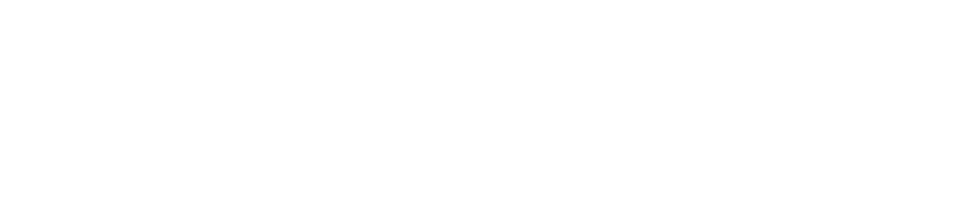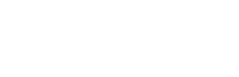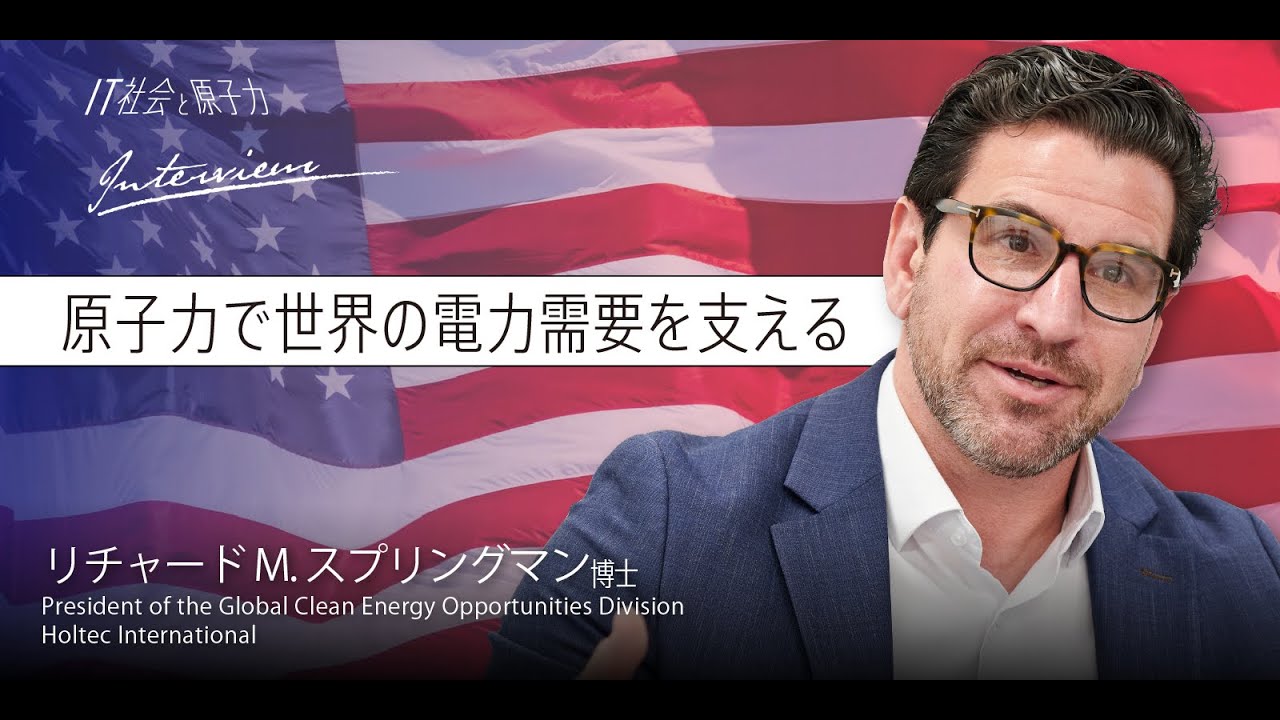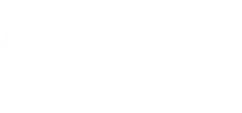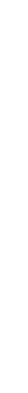原子力産業が「回帰」の動きを見せる中、その最前線を走るのがHoltec社だ。使用済み燃料の管理技術や廃炉事業で知られていた同社だが、いまや小型炉の建設や運転を停止した発電所の再稼働にも乗り出し、米国の原子力産業の活性化を象徴する企業となっている。
ミシガン州のパリセード原子力発電所(PWR、85.7万kW)は、1971年に営業運転を開始。その後、2022年5月に経済性を理由に永久的に運転を停止され、翌6月には所有者・運転者であったエンタジー社から、廃止措置を担うHoltec社に売却された。しかし、各国がCO2排出の抑制に取り組み、原子力のように発電時にCO2を排出しないエネルギー源が重視されるなか、同社はパリセード発電所を再稼働する方針に転換し、2023年9月には米原子力規制委員会(NRC)に運転認可の再交付を申請した。
パリセード発電所の再稼働、SMR-300(小型モジュール炉)の開発、さらにはデータセンター業界との連携強化──。Holtec社は、クリーンで安定した電力供給を実現するための新たなロードマップを描き、未来のエネルギー市場における原子力の役割を再定義しようとしている。
Holtec社のグローバルクリーンエネルギー部門トップであるリチャード・スプリングマン博士にお会いし、同社の戦略の本質に迫った。
AI・データセンターと原子力
AIやデータセンターの発展に伴い、エネルギー需要が飛躍的に増大しています。特に安定供給が求められるこの分野において、原子力の役割をどのように捉えていますか?

スプリングマン博士:AI、クラウドコンピューティング、そしてデータセンターは、これまでにないほどの電力を必要としています。そして、この需要は今後さらに加速するでしょう。その中で、原子力が果たす役割は非常に大きいと考えています。
まず、原子力の最大の特徴の一つは、その「単位設置面積当たりの発電量の大きさ」です。従来の発電方式と比較して、原子力は「極めて小さな土地で大量のエネルギーを生み出せる」というメリットがあります。都市部や工業地域に隣接するデータセンターにとって、これは大きなアドバンテージになります。
次に、「原子力発電所は24時間365日稼働可能」であり、設備利用率は通常90%以上です。つまり原子力であれば、安定した電力供給を確実に保証できるという点が、データセンターの運営において極めて重要な要素となるのです。データセンターは一瞬の停電でも大きな損害を被るため、電力供給が不安定な再生可能エネルギーだけに依存することはできません。
さらに、環境面の観点からも、原子力は最適な選択肢の一つです。世界中で企業がカーボンフリーのエネルギーを求めるようになり、投資家などからの圧力も増しています。原子力は温室効果ガスを排出せず、長期的にクリーンな電力を供給できるため、IT業界の持続可能目標にも合致します。
Holtec社は、こうしたニーズにどのように応えようとしているのですか?

スプリングマン博士:私たちは小型モジュール炉である「SMR-300」で、この問題に対応しようと考えています。SMR-300は出力30万kWの小型原子炉を2基組み合わせることで、合計60万kWの発電が可能です。このモデルは、データセンターの需要に最適化された電源供給を実現します。
また、ツインのSMR構成は、片方の原子炉が定期点検で停止していても、もう一方の原子炉は運転を続けられるメリットがあります。これにより、データセンターに安定した電力供給を保証することができます。
パリセード原子力発電所で発電される電力の供給先は、決まっているのですか?
スプリングマン博士:現時点での電力購入者(オフテイカー)は、データセンターではなく、Wolverine PowerやHoosier Electricといった農業系の協同組合 です。これは、米国の電力市場の特徴で、地方における電力供給では長期契約を結ぶ協同組合が主体となります。
ただしここで重要なのは、協同組合が購入した電力の販売先は、協同組合が自由に決められるという点です。したがって、最終的にデータセンターに供給される可能性は十分にあるということです。
将来的には、データセンター事業者と直接契約を結ぶ可能性もあるのでしょうか?

スプリングマン博士:はい、当然のことながら、データセンター事業者との直接的な関係構築も視野に入れています。特に、ミシガン州ではデータセンター誘致のための税制優遇措置が進められており、この地域のデータセンター事業者は、パリセード原子力発電所から供給される電力に強い関心を示しています。
また、同発電所サイト内ではSMR-300の設置計画も進行中です。これにより、データセンター事業者が直接原子力を活用する選択肢が、さらに広がると考えています。
データセンター向け電力供給の展望は?
スプリングマン博士:私たちは、クリーンで安定したベースロード電源を提供することが、データセンターの未来を支える鍵だと考えています。再生可能エネルギーと併用しながら、原子力が持つ「安定性」「持続可能性」「環境負荷の低さ」を最大限に活かし、世界中のデータセンターのエネルギー問題を解決していきたいと考えています。
SMR-300プロジェクトは、2030年の初号機稼働を目標にしており、それまでにIT業界との連携を深め、実用的な原子力ソリューションの提供を目指します。
Holtec社は、急速に進化するIT市場において、どのような立ち位置を目指しているのでしょうか?
スプリングマン博士:AIやデータセンターが急成長する中で、私たちは原子力を活用した持続可能なエネルギー供給の新しいモデルを確立しようとしています。その中心にあるのがSMR-300です。
私たちは、このSMRを活用して、全米各地のデータセンターに電力を供給できるようなインフラを構築したいと考えています。理想としては、既存の電力会社と連携し、データセンターが求める安定した電力を提供する形です。現在、2040年までに全米で1,000万kW規模のSMRを展開することを目標に掲げています。
また、米国内だけでなく、欧州市場にも積極的に乗り出しています。米国の電力グリッドは60Hz、一方で欧州は50Hzが一般的です。そのため、私たちは現在、この違いに適応できるよう設計の改良を進めています。これが完了すれば、欧州のみならず、世界中の50Hzの国々にもSMRを輸出する道が開けることになります。
つまり、SMR計画はデータセンターだけでなく、グローバルな電力供給戦略の要でもあるということですね。
スプリングマン博士:その通りです。私たちは、原子力が持つ安定性とクリーンエネルギーの特性を活かし、データセンターのみならず、世界の電力需要を支える存在を目指しています。
IT業界とのスピードギャップ
ただ、IT業界の進化スピードは非常に速く、AIやデータセンターの開発スピードと、原子力の導入スピードにはギャップがあるように思いますが、どうお考えですか?

スプリングマン博士:まさにその通りです(笑)。AIの進化スピードが非常に速い一方で、原子力業界は歴史的に迅速な導入が難しいという課題を抱えています。
データセンター関係者に話を聞くと、彼らは「今すぐにでも電気が欲しい」とおっしゃいます。特に、2027年から2029年にかけて、電力供給が必要になると考えている企業が多いのです。しかし、私たちのSMR-300初号機の商業運転は2030年を予定しています。このギャップをどう埋めるかが、大きな課題です。
ギャップを埋める、具体的な方策があるのですか?
スプリングマン博士:以下の3つを考えています。
- 規制の効率化: 現在、米国、英国をはじめ多くの国で、原子力に関する規制の合理化が進められています。許認可手続きの迅速化が実現すれば、原子力の導入スピードを上げることができます。
- 既存インフラの活用: 既存の発電所と電力グリッドのインフラを活用することにより、2030年までの需給ギャップを埋め、SMRが稼働するまでの間、安定的かつ継続的な電力供給を確保します。
- 送配電インフラの最適化: データセンターへの電力供給は、発電所単体の問題ではなく、送電・配電インフラの問題でもあります。そのため、送配電システムの最適化にも力を入れています。
原子力は不可欠なインフラ
原子力の役割は、単なるエネルギー供給にとどまらず、国家安全保障とも関係していると思いますが、その点についてはどうお考えですか?

スプリングマン博士:とても重要な視点です。原子力が持つもう一つの側面は、国家のエネルギー安全保障を強化する役割です。
現在、米国や英国はAI分野でのリーダーシップを目指しています。しかし、電力がなければAIの進化も止まります。データセンターが拡大し続ける中で、その安定的な電力供給が確保できなければ、技術開発のリーダーシップを維持することはできません。
そのため、クリーンで安定したベースロード電源としての原子力は、AI産業を支える上で欠かせない存在です。
原子力はAIとデータセンターの成長を支えながら、国の競争力にも直結している?
スプリングマン博士:まさにその通りです。原子力は、単に電力を供給するだけでなく、その国の経済と技術競争力を維持するために不可欠なインフラの一部になっているのです。私たちは原子力を単なるエネルギー供給手段ではなく、IT社会全体の成長を支えるインフラとしても位置付け、国際展開を進めています。
私たちは次世代のエネルギー供給戦略として、SMR-300の導入を加速させると同時に、政府との協力や規制緩和を進めることで、IT業界が求める迅速なエネルギー転換を実現しようとしています。
GAFAMと原子力
Amazon、Microsoft、Googleといった大手IT企業は、長期的な持続可能性戦略の一環として原子力に投資しています。Holtec社も、IT企業とデータセンター向け電力供給について協議を進めているのですか?
スプリングマン博士:詳細についてはまだお話しできませんが、確かに私たちは米国の「ハイパースケーラー」と呼ばれる大手IT企業と積極的に対話を行っています。彼らは持続可能な社会の実現に向けて意識が高く、原子力一般にも高い興味を示しています。
データセンターの拡張が進む中、これらの企業はクリーンで安定したエネルギーを求めており、原子力がその解決策となる可能性が高いことを認識しています。私たちは、彼らの持続可能なエネルギー需要を支援するために、どのようなソリューションを提供できるか検討している最中です。
将来的にHoltec社がIT企業と直接提携し、原子力を活用してクラウドインフラを支えるとすると、どのような形になるでしょうか?

スプリングマン博士:それは、やはりデータセンターに対する電力供給そのものです。各大手IT企業にはそれぞれ異なる戦略があります。データセンターに発電設備を併設すること(コロケーション)を重視する企業もあれば、既存の電力グリッドを活用する企業もあります。
現在米国では、「ビハインド・ザ・メーター」(Behind-the-meter)に発電所を設置する(発電所を需要地に直結する)プロジェクトが検討されています。これは非常に重要な動きです。なぜなら、米国の電気料金の約50%が送電・配電コストだからです。この部分のコストを削減できれば、大きな競争優位性が生まれます。
Holtec社がデータセンター向けに注力している具体的なポイントは何ですか?
スプリングマン博士:一つは、長期的にどのように価値を提供できるかです。多くの議論では、「初号機(FOAK=first of a kind)のリスクとコスト」と「シリーズ建設による後続機のコスト」の比較が重要視されています。
私たちのユニークな点は、定額請負契約のプロジェクト遂行を長年実施していることです。通常、電力会社やサプライヤーは価格リスクを恐れて躊躇しますが、私たちは定額請負契約を得意としています。
具体的に、Holtec社の競争力の源泉はどこにあるのでしょうか?
スプリングマン博士:私たちの大きな強みは、自社でコストをコントロールできることです。私たちは技術プロバイダーです。例えばパリセード発電所では、①発電所の所有、②運転認可の取得、③米国内の3か所の製造工場での大型機器製造、④三菱電機製計装制御(I&C)システムの採用、⑤韓国の現代E&C(現代建設)との提携によるBOP(バランスオブプラント=原子炉以外のタービン、発電機等の付帯設備)の設計および建設――等を通し、全てを自社の管理下に置くことで、プロジェクト全体のコスト管理と品質確保を可能にしています。
プロジェクトの展開にあたっては、どのようにコストを抑えているのですか?
スプリングマン博士:設計や建設プロセスを標準化し、経験を活かすことでコストを削減しています。私たちは単に「精緻な工学レポート」を作るのではなく、実際の現場で設計の細部を調整し、効率を向上させることでコストダウンを図っています。
そのため、Holtec社と現代E&Cが構築した統合スマートプラントモデル(統合設計環境)を活用し、実際の建設で得られた教訓を設計に反映しながら、プラントごとにコストを下げていくことが可能です。
全てのプロセスで クリーンでグリーンな電力を
データセンター業界の関心が高まる中で、今後の展望をどのようにお考えですか?
スプリングマン博士:データセンター事業者は「クリーンでグリーン」な電力にこだわっています。これは、単なる電力供給の話ではなく、私たちの使用済み燃料管理事業にも関わってきます。私たちは使用済み燃料と放射性廃棄物の管理分野で、長い歴史があります。Holtec社の最先端のキャニスタ式乾式貯蔵技術は、過酷な立地条件においても、安全で費用対効果の高い中間貯蔵を確実に実現します。
また、データセンター事業者など電力購入者は、「カーボンフリー」であるだけでなく、「廃棄物をどう管理するのか」についても関心を持っています。放射性廃棄物管理や廃炉ソリューションなどHoltec社のバックエンド技術は、SMR-300の設計に統合され、プラントのライフサイクル全体を通じてクリーンなエネルギー生産を実現します。特に日本では、この点が非常に重要な課題となるのではないでしょうか。
具体的に、廃棄物管理の課題解決に貢献できる技術とは?
スプリングマン博士:私たちは、地下設置型キャニスタ式乾式貯蔵システムを推進しています。現在使われているあらゆる乾式貯蔵システムは安全ですが、溶接蓋構造および地下貯蔵設備により、キャニスタシステムはさらに高い安全性を提供できると考えています。
データセンターへの電力供給と並行して、廃棄物管理の分野でも新技術を展開するということでしょうか?

スプリングマン博士:その通りです。データセンター業界と連携することで、廃棄物管理の技術革新も進めていくことが必要です。SMR-300の設計にはすでに実証済みの技術が導入されており、事業者や一般市民に最高の利益をもたらします。
私たちは、データセンター事業者に対して「市場で最も安全な技術を使用している」と自信を持って言えるように、業界全体の発展をリードしていきたいと考えています。