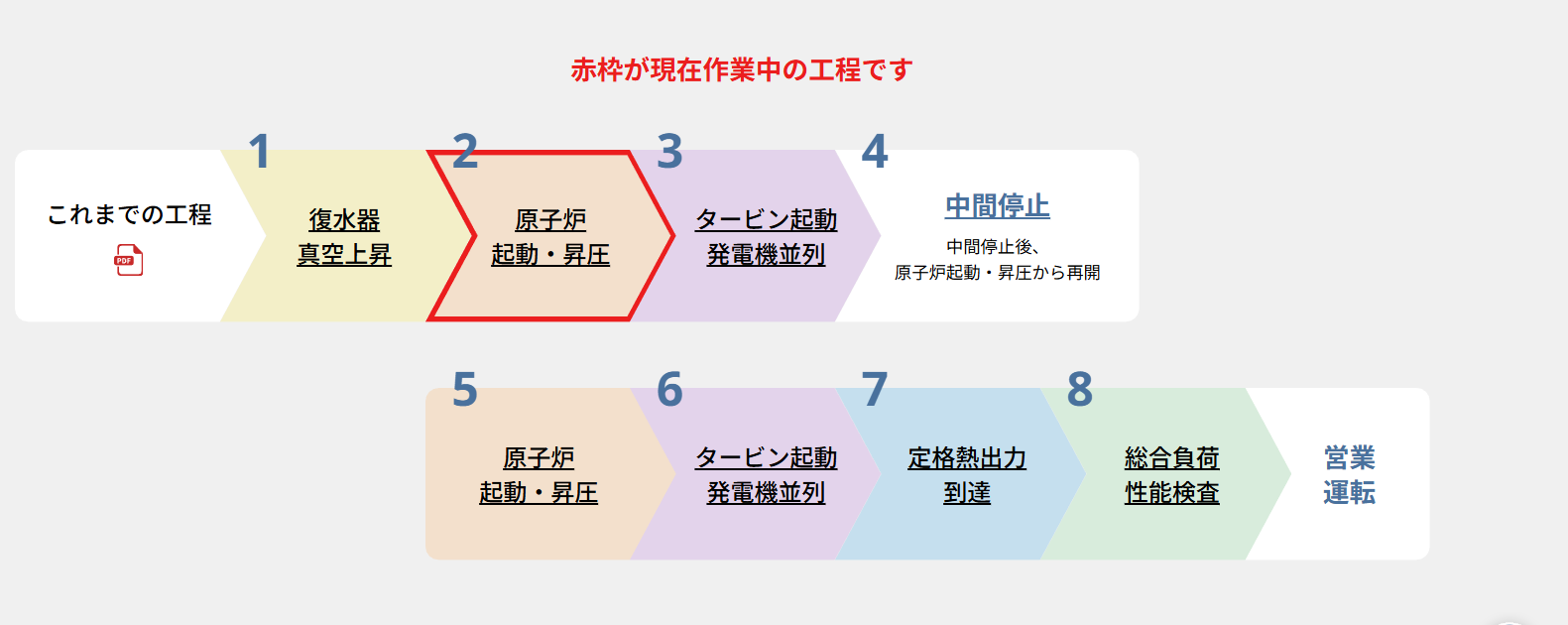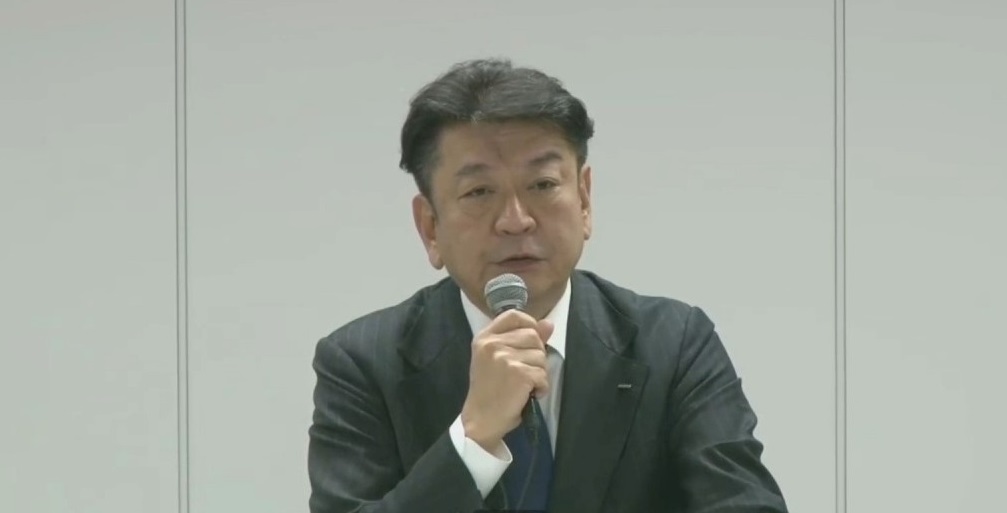規制委 原子力災害指針を一部改正「屋内退避も有効」
11 Sep 2025
原子力規制委員会は9月10日の委員長定例会見にて、原子力災害時の放射線防護の措置などの対応方針をまとめた「原子力災害対策指針」の改正を公表した。
同指針の目的は、緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な影響を回避または最小化することであり、防護措置として、「予防的避難」と「屋内退避」の2点が重要な観点だと定められている。
これまでも、原子力発電所にて事故が起きた場合、原則以下のような指針が定められてきた。
①発電所から概ね5km以内のPAZ(予防的防護措置区域)においては、放射性物質が放出される前段階から予防的に避難等を行う
②発電所から概ね5km~30km以内のUPZ(緊急防護措置区域)においては、予防的な防護措置を含め、段階的に屋内退避、避難、一時移転を行う
今回の同指針の改正では、「屋内退避」に関する運用の考え方(実施期間や解除要件)に、一部、加筆修正がなされた。
具体的には、屋内退避の継続は実施後3日目を目安に国が判断することや、発電所の状態(放射性物質の放出が無い場合)によっては、屋内退避期間中の外出も許可されること、放射性物質を含む空気の塊が周囲に留まらない場合には退避を解除できること等が、新たに盛り込まれた。
記者から「屋内退避の継続判断の3日という期間の根拠はどこにあるか」と問われた山中伸介委員長は、「住民の心理的ストレス等を鑑み、国際的な基準と照らし合わせて導いた。また、福島第一原子力発電所の事故の教訓として、無計画な避難は住民に健康被害を及ぼす可能性があること、防災関連備品のストックの目安が3日とされていることも考慮している」と答えた。
また、同指針の改正によって期待していることや、今後の課題について問われた山中委員長は「対話の場をこれからも増やし、遮蔽機能を持った建物に留まることも有効な防護措置であることをご理解いただく。そして、各自治体が定める防災計画と照らし合わせ、指針に不十分な部分があれば随時修正し、複合災害対策として、これまで以上に関係省庁間の密な連携を図る必要がある」と述べた。