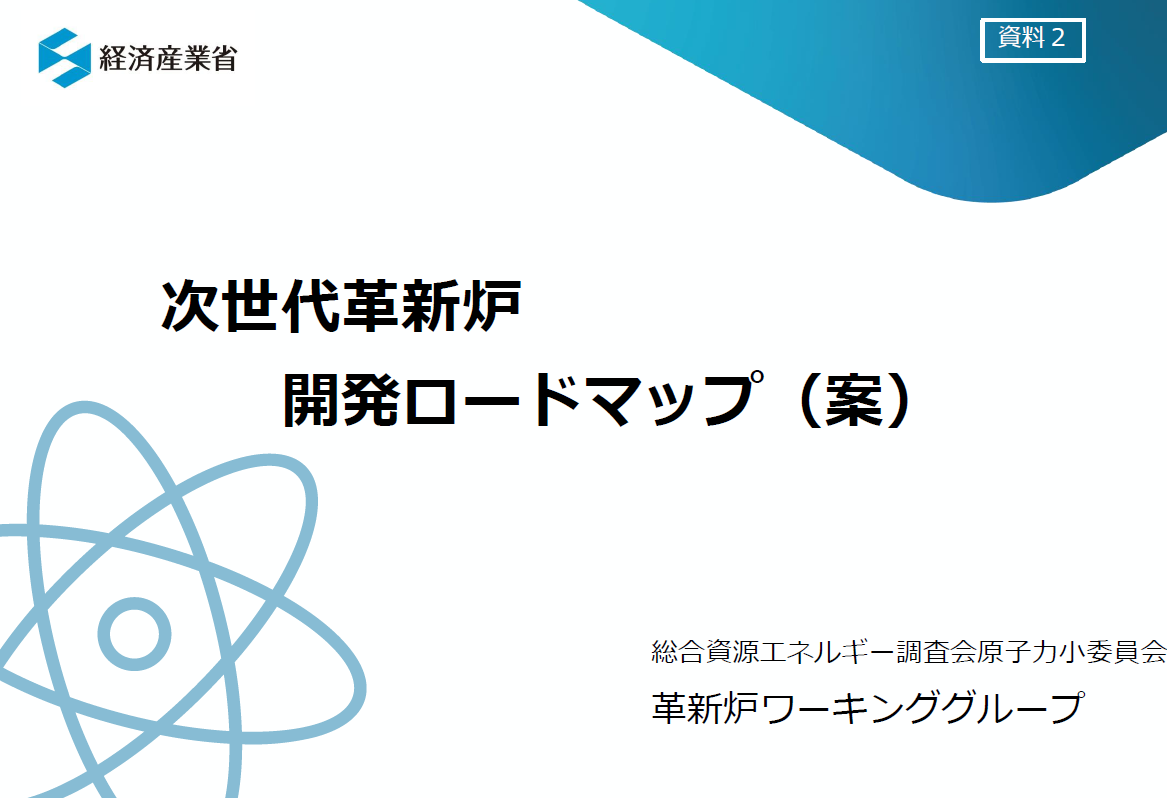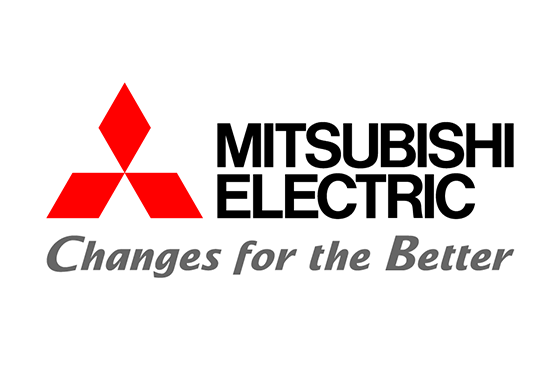【第54回原産年次大会】セッション2「福島のさらなる復興に向けて」
15 Apr 2021
4月14日のセッション2「福島のさらなる復興に向けて」は、福島第一原子力発電所事故発生から1年後の2012年以来、続いているテーマ。今年は事故から10年が経過した福島第一原子力発電所の廃炉の現状を踏まえつつ、今後の福島復興の展望に向け意見交換が行われた。
 セッション冒頭、東京電力ホールディングス株式会社 常執執行役で福島第一廃炉推進カンパニーのプレジデント 小野明氏が福島第一原子力発電所の現状と課題を報告。まず、小野氏は今般の柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に関する不備の問題について、深く反省と謝罪の意を表した。
セッション冒頭、東京電力ホールディングス株式会社 常執執行役で福島第一廃炉推進カンパニーのプレジデント 小野明氏が福島第一原子力発電所の現状と課題を報告。まず、小野氏は今般の柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に関する不備の問題について、深く反省と謝罪の意を表した。
その上で、福島第一原子力発電所の汚染水対策について、小野氏は、地下水・雨水の流入を抑制することによって、汚染水の発生が2020年には140㎥/日まで低下しているほか、多核種除去設備(ALPS)処理水貯蔵のために、計画通り2020年末で137万トン分のタンクを確保済みであるが、タンク貯蔵量が2021年2月時点で約125万トンに達している中、計画容量を超えてタンクをさらに建設すると、必要な施設の建設に支障を来し、今後の廃炉の進捗に多大な影響を与える可能性があることを懸念。ALPS処理水については、前日の4月13日に海洋放出の政府方針決定が発表されたところ。これに関し、小野氏は「当社としては、国の方針を受けて、関係者との協調を図りながら今後の処理に向けた具体的な作業を進めていく。しっかりやっていきたい」と述べた。
小野氏は続いて、使用済燃料プールからの燃料取り出し、燃料デブリ取り出しに向けた作業の進捗状況、固体廃棄物管理、そして、「復興と廃炉の両立」について説明。
「とくに、福島の復興について、我々はいかに1F(福島第一原子力発電所)の廃炉を復興に向けて活用していけるか、を考える必要がある。その鍵は、1Fの廃炉作業に地元の企業のみなさまに積極的に参入していただくことだ」と述べ、そのための企業向け説明会や地元企業と元請企業とのマッチングを増やしていく考えを示した。
また、去る2月13日の地震発生時、3号機原子炉建屋の地震計が7月の大雨の影響により故障していたことを始め、タイムリーな情報発信がなされておらず、地元の方々による受け止めと東京電力の取組姿勢にギャップがあると自省し、「そうしたギャップを埋めていくことがまず必要。地域目線でしっかりと双方向のコミュニケーションに取り組んでいきたい」とも述べた。
 続いて、福島大学国際交流センター 副センター長のウィリアム・マクマイケル氏(モデレーター)の進行のもと、「震災から10年 福島が拓く未来」と題して、福島復興の第一線に関わってきた若手のパネリストたちが語り合った。
続いて、福島大学国際交流センター 副センター長のウィリアム・マクマイケル氏(モデレーター)の進行のもと、「震災から10年 福島が拓く未来」と題して、福島復興の第一線に関わってきた若手のパネリストたちが語り合った。
株式会社小高ワーカーズベース代表取締役の和田智行氏は、南相馬市小高区に生まれ育った。震災前に東京からUターンし、地元でITベンチャー企業を経営していたが、福島第一原子力発電所事故により避難生活を余儀なくされた。2014年2月、当時まだ避難指示区域で居住が認められていなかった南相馬市小高区に株式会社コワーカーズスペースを創業。小高区は2016年7月に避難指示が解除され帰還が進んではいるが、元は1万2千人を超えていた人口が、3分の1程度の約3,700人にまで減少。その半数を高齢者が占めるとともに、子どもの数も激減し、超少子高齢化の状況となっている。
 「本当に厳しい状況で、地域には課題が多く、それが帰還を阻んでいるが、見方を変えれば課題はすべてビジネスの種。ここでしか生み出せないビジネスがある」と、和田氏は反骨精神をみせる。
「本当に厳しい状況で、地域には課題が多く、それが帰還を阻んでいるが、見方を変えれば課題はすべてビジネスの種。ここでしか生み出せないビジネスがある」と、和田氏は反骨精神をみせる。
最初に手がけたのは、人がいない町で働く場としてコワーキングスペースをつくること。また、食堂や仮設スーパーもつくった。生活環境が整っても若い世代がなかなか戻って来ないという課題に対し、若者にとっても魅力的な仕事として、ガラスアクセサリーの工房を立ち上げると、地元の若い女性たちが工房で働き、カフェのオープンや若者の来訪にもつながるという好循環が生まれた。今は、この地域の可能性を感じてチャレンジする起業家へのサポートと、コミュニティづくりのフェーズに移っており、これまでに全国から8人の起業家が集まっている。さらに、ゲストハウスやキッチンを備えたコワーキングスペース「小高パイオニアヴィレッジ」も新設。ここでは、地域の事業者と外部からの来訪者の交流の場として、コロナ禍中リモートワークで滞在しながら一緒に仕事をする人も増えている。最近、震災当時10代だった若者たちの起業支援や人材育成のためのプロジェクトも始めた。
「最終的にこの地域を自立した地域にしたい」と和田氏は語る。そして、「先人たちの努力で豊かに成熟した現代日本だが、そこで閉塞感を抱える人も多い。逆にこの地域には何もなく、新しく創るしかない。その意味で、この地域は現代日本唯一で最後のフロンティアだ。予測不能な未来を楽しみ、フロンティアを開拓していく」と、意気込んだ。
双葉郡未来会議「ふたばいんふぉ」の辺見珠美氏は、東京都生まれ。大学で原子力と放射線について学んだ。2011年、福島第一原子力発電所事故により富岡町から東京に避難してきた子どもたちの学習支援のボランティアに取り組む中で双葉郡とのつながりができ、2012年、川内村に移住し、福島大学川内村サテライト職員として、放射線についての相談受付などの住民対応を行った。2020年から富岡町に移住。双葉郡のインフォメーションセンター「ふたばいんふぉ」のスタッフとして双葉郡の情報発信や草の根の活動に取り組んでいる。辺見氏は地図を示しながら、「冬は出稼ぎに行く地域だったが、東京に出稼ぎに行く代わりに東京の電気をつくることで電源供給地となった」と、双葉郡の歴史に触れた後、2011年の福島第一原子力発電所事故発生からの避難区域設定の変遷を振り返った。現在の帰還困難区域の人口22,332人の規模感について、各電力会社の従業員数と比較したグラフで表現。
 「原子力発電所の事故は、『それまで』をすべて失うことだった」と辺見氏は言う。さらに、「ひと、もの、こと、思い出、いつもの日常がどれだけ幸せなことか。私の周りには、小学生の時に震災に遭い、いつもそばにあった夜ノ森の桜並木が帰還困難区域のバリケードで隔てられ、その桜を特別に感じてしまうこと自体に嫌悪感がある、という複雑な心情を抱えた若者たちがいる」と。そんな想いを抱き、双葉郡で活動する。
「原子力発電所の事故は、『それまで』をすべて失うことだった」と辺見氏は言う。さらに、「ひと、もの、こと、思い出、いつもの日常がどれだけ幸せなことか。私の周りには、小学生の時に震災に遭い、いつもそばにあった夜ノ森の桜並木が帰還困難区域のバリケードで隔てられ、その桜を特別に感じてしまうこと自体に嫌悪感がある、という複雑な心情を抱えた若者たちがいる」と。そんな想いを抱き、双葉郡で活動する。
新しく未来を築き、暮らしを取り戻すために、川内村で「村の暮らしを楽しもう」をコンセプトに、村内外の人々が楽しめる企画を展開している。中には養鶏を営む農家で「鶏をさばくところから始めるソーセージづくり」など、ここでしかできない講座もある。また、富岡町での「とみおかこども食堂」の活動は、廃炉作業員など移住してきた人々や帰還者を含めて、子どもたちを通して地域のコミュニティを再構築しようというユニークな試みである。
「避難、軋轢、格差、高齢化、コミュニティの崩壊、考え方の違いなど、いろいろなことが原子力発電所の事故で引き起こされた。しかし、これらはどこにでも起こりうることだ」と辺見氏は指摘。さらに、「より良い未来をつくっていくには、『お互いを知り、対話を重ね、理解し合うこと』に丁寧に取り組むことが遠回りなようで近道であり、様々な課題に対して解決へ導く鍵となるのではないか」とも述べる。そして、原子力関係者に対しても「再稼働や処理水の海洋放出などに関して行われる説明会や公聴会も、一方的なものではなく、双方の立場の違いを理解し合った上での話し合いを丁寧にやってもらえればと思う」と強調した上で、「ぜひ双葉郡の方々の生の声を聞きに来てほしい」と呼びかけた。
一般社団法人ふくしま学びのネットワーク理事・事務局長の前川直哉氏は、兵庫県尼崎市に生まれ、1995年、高校3年生の時の阪神・淡路大震災で被災した。大学卒業後、母校の灘中学校・高校の教壇に立ち、2011年の東日本大震災以降、たびたび生徒たちと福島や宮城の被災地を訪れるうちに福島県で仕事をしたいと思うようになり、2014年、福島市に移住して非営利団体「ふくしま学びのネットワーク」を設立。2018年からは福島大学の特任准教授も務める。前川氏は元同僚や大手予備校の講師などを招き、福島の高校生を対象とした無料セミナーを延べ14回開催。セミナーの講師陣は完全手弁当で、面白い授業にはリピーターも多い。
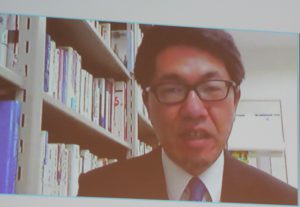 「そういう『カッコいい大人』として誰かの力になるには力をつけなければならない。学校はそのための場所だと生徒たちに伝えている」と前川氏は語る。
「そういう『カッコいい大人』として誰かの力になるには力をつけなければならない。学校はそのための場所だと生徒たちに伝えている」と前川氏は語る。
20年後の日本ではロボットやAIが人間の仕事を奪っていく時代になると言われている。しかし、正解のない問い、自ら課題を発見し、解決策を探ることはロボットやAIには決してできない。たとえば、「双葉郡の方々が少しでも日常を取り戻すにはどうすればよいか」を考えるのも人間にしかできない仕事だ。福島では高校生が県内各地で復興や地域貢献のため多様な活動を展開しており、こうした高校生の活動をサービス・ラーニングとして顕彰し、さらなる活性化を図っている。また、福島大学では地域実践特集プログラム「ふくしま未来学」にも取り組む。
「福島は、自分のためではなく、誰かのための学びであることが伝わり、知識偏重教育でなく、正解のない問いにチャレンジできる場所。限界に来ている日本の教育を変えられるのは福島からだ」と前川氏は強調。一方で、教育者として、「子どもたちの活動を誇らしいと思うと同時に、福島の問題をどうしても遺してしまい、子どもたちを復興にしばりつけているのではないかと、忸怩たる思いも正直ある」とも。同氏は、そんな葛藤も抱えながらも「今後も子どもたちと向き合っていきたい」と語った。
 続いて、パネル討論に移り、自他共に認める「カナダ人で一番の福島ファン」マクマイケル氏が30年後の「FUKUSHIMA」について、あるべきイメージを問うと、和田氏は、「住民が自立した暮らしを実現している」ことをあげ、そのために、自社のミッションとして掲げる「地域の100の課題から100のビジネスを創出する」を遂行し、「旧避難指示区域で事業やプロジェクトを興せる風土を醸成していく」と抱負を語った。また、辺見氏は「地層をつくる」と標榜。その心は、「原子力発電所の事故により暮らしが失われ、豊かな思い出まで『除染』されて、はぎ取られ、町として『欠けている感』が生じてしまった双葉郡の『まちを耕す』。つまり、一度人がいなくなり、それまで培ってきた暮らしが失われてしまった土地に、喪失を埋める『土』となる人の営みを積み重ねていく30年間」だという。また、前川氏は、30年後の福島に「地球と人類の最後の砦」をイメージ。そのためには「教訓の継承」が欠かせないとする同氏は、「原子力発電所の事故を『なかったこと』にせず、失敗を直視し、そこから学ぶこと」と強調した。
続いて、パネル討論に移り、自他共に認める「カナダ人で一番の福島ファン」マクマイケル氏が30年後の「FUKUSHIMA」について、あるべきイメージを問うと、和田氏は、「住民が自立した暮らしを実現している」ことをあげ、そのために、自社のミッションとして掲げる「地域の100の課題から100のビジネスを創出する」を遂行し、「旧避難指示区域で事業やプロジェクトを興せる風土を醸成していく」と抱負を語った。また、辺見氏は「地層をつくる」と標榜。その心は、「原子力発電所の事故により暮らしが失われ、豊かな思い出まで『除染』されて、はぎ取られ、町として『欠けている感』が生じてしまった双葉郡の『まちを耕す』。つまり、一度人がいなくなり、それまで培ってきた暮らしが失われてしまった土地に、喪失を埋める『土』となる人の営みを積み重ねていく30年間」だという。また、前川氏は、30年後の福島に「地球と人類の最後の砦」をイメージ。そのためには「教訓の継承」が欠かせないとする同氏は、「原子力発電所の事故を『なかったこと』にせず、失敗を直視し、そこから学ぶこと」と強調した。
最後に、「原子力産業に期待することは?」と、マクマイケル氏が投げかけると、和田氏は「幸せな社会をつくりたいのは共通の願いだと思うので、何か一緒にできることがあれば協働していきたい」との姿勢を示し、辺見氏は「原子力は一般市民にとって専門性が高くて遠いものなので、もっと社会との距離を近づけてお互いの理解を深めたほうが良い」と指摘。前川氏は「福島から学べることはたくさんある。ぜひ福島を訪ねてもらい、見聞きしたことを周りの人たちにも伝えてもらえると嬉しい」と期待した。
マクマイケル氏は、「福島の人たちに今見えている課題、そして、今後の可能性について、多くの人に共感していただける時間になったと思う。今日の登壇者のみなさんが大切に育んでいる福島の再生の芽は、必ずや世界の未来にもつながると私は信じている。復興を地元で支えている人たちへの敬意を持ちながら、共に未来を形成していく姿勢を持ちたい」と語り、セッションをしめくくった。