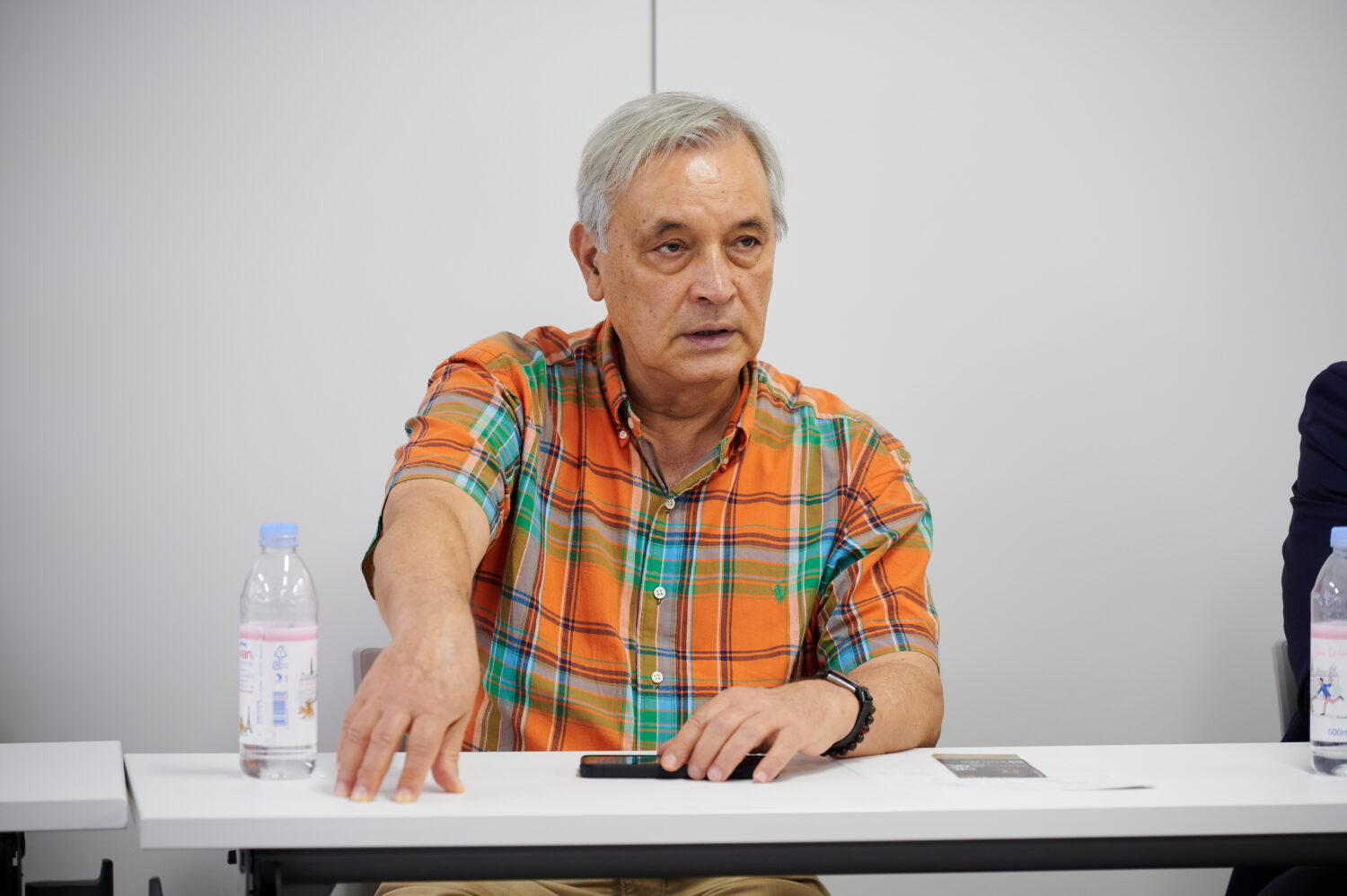ポーランド 石炭の町が描く“次の10年”
16 Sep 2025
ポーランドの原子力プロジェクトをめぐるオピニオンリーダーたちが、このほど来日した。顔ぶれの多くは、かつて石炭で栄えた自治体の副市長クラスや議会関係者である。脱炭素とエネルギー安全保障の双方をにらみ、石炭火力の終幕と次の主役探しを同時に迫られる地域が、日本の原子力発電をめぐる非常時対応や廃止措置など、“現場”をその目で確かめに来た——その動機は切実だ。
ポーランドは大型炉とSMRの“二正面作戦”を採る。大型炉はポモージェ県ルビアトボ=コパリノでAP1000×3基の建設計画が進み、8月末に県知事から準備作業許可を取得した。今秋から測量・フェンス設置・伐採・整地などの先行作業が順次始まる見込みで、2036~38年の段階的運転開始を見通すという。一方、SMRはGE日立製BWRX‑300を採用し、初号機建設サイトを化学コンビナートの街ブウォツワベクに決定。合弁会社OSGEが独占使用権を持ち、環境影響評価(EIA)と立地調査が進行している。
今回来日したリーダーたちは、ベウハトフやコニンなどの石炭・褐炭地域が中心。これに中央政府のエネルギー省担当官が同行した形だ。一行は、日本原子力研究開発機構の「原子力緊急時支援・研修センター(NEAT)」(茨城県)でオフサイトセンターの運用や日本の緊急時システムについて見学した。福島第一サイトでは、工程管理や情報公開の透明性が、どのように社会的信頼を支えるのか、時間軸で追体験。玄海原子力発電所(佐賀県)では多重防護や特重施設、地震津波対策の考え方などを、福井県庁では原子力担当部署より、行政としての原子力との関わり方などを学んだ。4日間で日本各地を、駆け足で回ったことになる。
ポーランドの石炭地域が他産業への移行を迫られているのは、欧州連合(EU)加盟後に強化されたEUの環境規制(LCPDからIED/BAT)への適合や欧州排出量取引制度(EU-ETS)の炭素価格上昇といった、規制および市場からの圧力に加え、主力であった褐炭資源の先細りが重なったためである。これに伴う雇用・地域経済の痛みを和らげる政策枠組みとしてJust Transition(公正な移行)が整備されてきた。地域の住民からは、期待と不安が入り混じった声があるという。現実的な移行が目前に迫る中、地域のリーダーたちが語った「次の10年」はきわめて実務的だ。
第一に一貫した人材育成の道筋である。初等・中等から大学、工科系へと、地域の若者が段階的に学び、将来の担い手へと育つ道筋を用意する。「学校で論理的に説明すること」を重視し、テクノロジーや安全文化を丁寧に説明していく姿勢が強調された。チョルノービリ事故を知らない若い世代には、「感情的な賛否より、なぜ必要かを自分の言葉で理解してもらうことが効く」という。
第二に既存の雇用や産業の連続性だ。鉱山や火力発電所の閉鎖が目前に迫る地域もあり、人口・雇用の大規模な減少への懸念は切実なようだ。20万人だった人口が、すでに5万人に激減している地域もあるという。だからこそ、石炭で培ったスキルを土台に、次の仕事を地元に残す(原子力の運転・建設・保全などへ職能を移す)という発想が中核になる。産業の維持の観点から、BWRX-300への期待が多く寄せられており、「SMRのサプライチェーンへ参画することで、既存の企業や人材の受け皿を広げていきたい」との声もあった。
そして第三に、避難計画の策定など行政としての準備である。日本のシステムを学んだ上で、ポーランド版の緊急時システムをどう整えるか、引き続き検討していくという。また、特に日本に対し、施設運用や人材育成などの面で、実務的なセミナーやワークショップをポーランドで開催して欲しいとの要望が上がっていた。
原子力産業新聞から「ポーランドの原子力プロジェクトにとっての最大の課題」を問われた、エネルギー省のZ.クバツキ原子力担当参事官は、「時間」と即答した。「許認可のプロセスがとにかく長い。ポーランドの場合、欧州委員会との調整も必要になる。調整を終えた後も着工から運開まで、ほぼ10年かかるだろう。時間が延びれば延びるほど、コストや制度面の前提が崩れやすくなる」。同氏は差額の清算で収入を安定させる仕組み、いわゆるCfDs(差金決済)にも触れ、「市場価格が高いときは事業者が払い戻し、低ければ差額を受け取るという設計は理解している。しかし、これが本格的に効果を発揮するのは運開後だろう。工期が長引けば長引くほど建設コストを吸収し切れなくなる」と懸念を示し、改めて「だからこそ“時間”が最大の課題だ」と強調した。