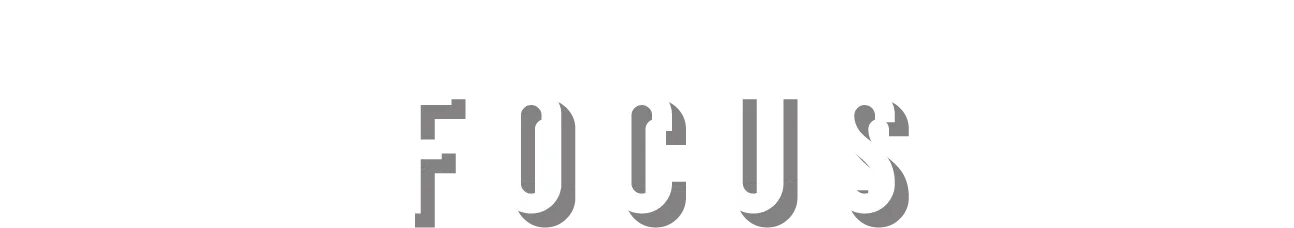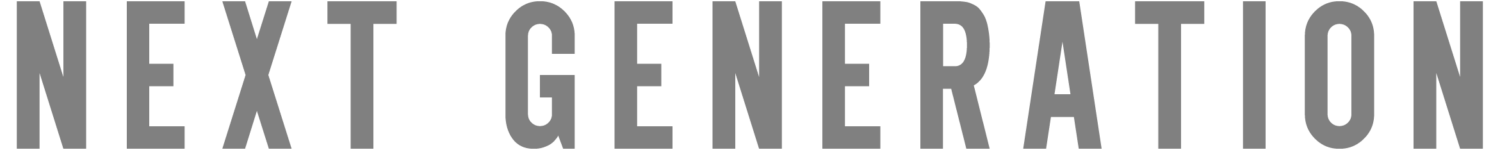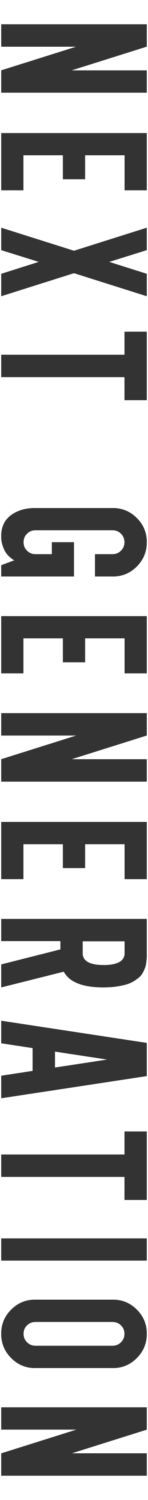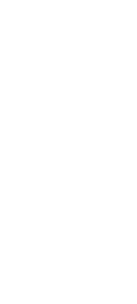今回の特別授業には3学年から約380名が参加し、8月に控えた大阪・関西万博での生徒による対話型アウトリーチ活動に向けた「情報インプット」の場となった。文部科学省の主催で8月14~19日に大阪・関西万博会場で開催される「わたしとみらい、つながるサイエンス展」に、Nプロとして大阪高校の生徒たちが参加することになっており、今年の2月に東京で開催されたプレ・イベントは、万博での活動の予行演習のような位置付けだった。
前半は京都大学の中村秀仁助教(日本保健物理学会理事)が「科学を通じて社会と対話する」と題して講義を行い、後半は電力中央研究所の佐々木道也氏(日本保健物理学会副会長)が、放射線のリスク評価と医療・工業応用等に関する講義を担当。それぞれ放射線にまつわる科学知識と社会との橋渡しの方法について、工夫を凝らした参加型の授業が展開された。会場では生徒たちがスライドやクイズに積極的に反応し、熱心にメモを取るなど、熱気に包まれており、その場に居合わせた私なども熱気に当てられて汗だくとなったほどだ。以下、熱い講義内容と、その教育的意義について詳述する。

科学を通じて社会と語り合う対話プロジェクト
特別授業の前半は、中村秀仁助教が登壇し、放射線の基礎を平易な例えを用いて解説するとともに、科学コミュニケーションの手法を体現した講義を行った。
中村助教は冒頭、「Nプロは科学を通じて社会のみなさんと語り合う対話プロジェクトです」と強調し、単に科学知識を学ぶのではなく科学を使って社会と対話することが目的であると生徒たちに説明した。その題材としてあえて放射線を選んだ理由について、「放射線は社会的にセンシティブな内容だからこそ、多くの人が知らない分、クイズを交えて自分のワクワク感や楽しさを相手に共有すれば、きっと耳を傾けてもらえる」と狙いを語った。放射線という難しいテーマをあえて扱い、好奇心を引き出しつつ自らの熱意を伝えていく姿勢は、科学コミュニケーションのお手本と言えるだろう。
そうなのだ。この場にいる生徒たちは全員、8月の関西万博というステージで、スケッチブックを片手に道ゆく人を捕まえ、自分が調べた科学知識を見知らぬ人に披露するという重責を担っているのである。少しでも相手の関心を惹くべく、生徒たちはどんな掴みが相手の好奇心を引き寄せるのか、どんなプレゼンテーションが相手に響くのか、中村助教が伝える知識のみならず、プレゼン手法に至るまで、全てを参考にしなければいけないのである。
講義ではまず、虹や紫外線・赤外線といった身近な光の話題から始まり、放射線は「目に見えない光の仲間」であり我々の身の回りに普通に存在するものだと解説された。可視光より波長の長い赤外線(infrared)や波長の短い紫外線(ultraviolet)の話を引き合いに、放射線も電磁波の一種で目に見えないだけなのだと強調。実際「放射線は虹の仲間、光の仲間です。見たり聞いたり触ったり匂いや味も感じないけれど、そこにある」と、中村助教は生徒たちに語りかけ、放射線を特別視しすぎず光の延長として捉える視点を提供した。
さらに放射線にはどんな種類があるかという問いかけから、放射線の代表的な4種類(アルファ線、ベータ線、ガンマ線、中性子線)が紹介された。それぞれ性質が異なることを理解してもらうため、「よーいドンでスタートしたら速く飛んでいく放射線もあれば、ゆっくりのものもある」といった具合に粒子の大きさと速度の違いを例示 。例えば一番重く動きの遅いアルファ線が、以前は家庭用の火災報知器(煙探知機)に使われており、「見えないところで昔から私たちの生活を守ってくれている」身近な存在だというエピソードも紹介された。生徒たちは、自分たちの身の回りで放射線が利用されている具体例に驚きつつメモを走らせていた。
中村助教の講義は終始インタラクティブに進められた。可視光の専門用語や放射線の分類に関する質問が次々と投げかけられ、生徒たちは考えながら、二択で「A」「B」のフリップを上げて回答して講義に参加した。「虹を見たことあるよね?目に見える光のことを何と言うか覚えているかな?」と問いかけると、生徒たちは隣同士で小声で相談しつつ、「可視光!」といった答えを導き出す場面も見られた。また「放射線は全部で何種類に分けられるでしょう?」という質問には多くの生徒が正解するなど、対話を交えて講義内容を絶えず振り返ることで、生徒たちは能動的に思考しながら知識を吸収していた。

放射線のリスク評価と応用
後半は、電力中央研究所サステナブルシステム研究本部の佐々木道也上席研究員が講師を務め、放射線のリスク評価と医療・工業への応用について講義が行われた。佐々木氏はまず「リスクとは何か?」という基本概念から話を切り出し、生徒に対してリスクの意味合いを質問した。「良いことが起こる可能性も含むか、悪いことが起こる可能性だけを指すか?」との問いに対し、生徒の大半は「良くないことが起こるかもしれないという意味で使うことが多い」と正しく回答。佐々木氏(趣味がサッカー)は「サッカーでも『リスクを取って攻める』というと失点のリスク(危険)を冒すという意味ですね」と補足しつつ、本題の放射線リスクの話へとつなげた。
佐々木氏は放射線被ばくと健康影響について、科学的データに基づき解説。広島・長崎で被爆された方々を長年追跡調査した研究や、実験用マウスに放射線を照射して観察した結果などを紹介し、「被ばく量が多い人ほどがんになるリスク(発生確率)が高まることが分かっている」と説明 。ここでも生徒の理解を確認するクイズが挟まれ、「がんリスクを調べるには少数のネズミを見るのと、数千~十万人規模の集団を見るのと、どちらが有効か?」という問いに対し、生徒たちは見事「B: 数千人から十万以上の大集団を調べる」を選び正答 。佐々木氏は「たくさんの人のデータを集めて初めて統計的にリスクの増加を捉えられます。このような大規模追跡研究を疫学調査とかコホート研究と呼びます」と解説し、科学的なリスク評価の手法についても触れた。
続いて佐々木氏は、リスクがある放射線をなぜ医療であえて使うのかという点について言及した。ここでは以前の特別授業で別の講師から紹介されていた「ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)」なども引き合いに出しながら、「医療では放射線を当てるリスクよりも、それによって得られる治療効果や診断のメリットの方が大きいから使われている」と指摘。たとえば中性子を照射して発生させた粒子でがん細胞を狙い撃ちする先端治療や、X線撮影・CTスキャンで体内の異変を発見する診断など、放射線利用には人々の健康に資する大きな利点があると説明した。もちろん「世の中の全てのがんが放射線で治せるわけではないので、場合によっては他の治療法を選ぶこともあります」と補足しつつ、「医療現場では患者さんが安心して放射線治療や検査を受けられるよう機器を改良したり、被ばく線量を最小限に抑える工夫を常に行っています」と述べ、安全面への配慮とリスク低減の取り組みにも言及した。メリット(効果)を可能な限り大きくし、デメリット(リスク)を小さくすることで、放射線は有益なツールとして社会で活躍しているというメッセージだ。
また佐々木氏は「放射線は医療以外の工業分野でもいろいろ使われています 。ぜひ皆さんもそういった分野の利用例を調べてみてください」と呼びかけ、時間の都合上詳細には踏み込めなかった産業利用(非破壊検査や食品照射、放射線による材料改質などさまざまな分野がある)について、生徒自身が探究を深めるよう促した。講義の合間には、「実は私たちの体の中にもカリウム由来の放射線(ベータ線やガンマ線)が常に出ているんですよ。怖い怖いと言っても、人間自体が微量の放射線を出しながら生きているんです」という豆知識も紹介され、生徒たちは「自分も放射線と無縁ではない」と知って目を丸くしていた。佐々木氏はグラフなど難解な図表の使用を最小限に留め、平易な言葉と身近なたとえで話すことで、多くの生徒(数多くの文系の生徒が含まれている)の理解を助けていた。そして(中村助教の指示により)適宜クイズ形式で問いかけ、生徒の反応を拾いながら進めるスタイルは、大勢の高校生を飽きさせず引きつける工夫が随所に凝らされていた。

佐々木道也氏
続きを読む 2/2
グループ制と参加型クイズで沸く
今回の特別授業は、大人数にもかかわらず終始アクティブな双方向型で進行した。その裏には運営側の工夫がある。まず、生徒たちは班活動の体制で臨んでいた。会場では開幕早々に「班長さん起立!」という掛け声がかかり、各班のリーダー役を務める生徒(班長)が起ち上がって全員に紹介された 。班長は本プロジェクトに以前から参加している経験者であり、新規参加の生徒をサポートする役割だ。講師からは「特に後日みんなでスケッチブックを作る段階でどうしたらいいか迷うと思うが、班長は経験者なので一緒に作っていきます」と説明があり 、班長たちが各班でメンバーをリードしながら学びを深めていく体制が整えられていた。ちなみに初顔合わせのメンバーたちも多いようで、班長が自身のアカウントのQRコードを示し「グループLI⚫︎Eを作るから登録して、返事送って!」と呼びかけ、あっという間に班内の連絡システムを構築していた。380名という大規模な参加人数でも、生徒たちが受け身にならず積極的に参加できたのは、このような班長制度による手厚いサポートがあってこそだ。
講義中、各所で繰り出されるクイズや質問にも、生徒たちは班ごとに相談したり即座にフリップを上げたりといった形で反応した。講師陣はそうした双方向のやりとりを巧みに受け止め、「今のポイントは大事だからぜひ覚えてね」と笑顔でフォローするなど、終始和やかながら熱気ある空間を作り上げていた。生徒たちも手を動かしてノートを取りつつ、「自分が誰かに話すつもりで、使えそうなクイズはどんどんメモして持ち帰ってほしい」という講師の呼びかけに応えて 、後日のアウトリーチ活動に向けて熱心に知識を蓄えている様子だった。
特に盛り上がりを見せたのが、授業の締めくくりに行われたスマホを使った復習クイズ大会である。これは講義内容のおさらいを兼ねたゲーム形式のクイズで、各班対抗戦として実施された 。生徒たちは班長のスマートフォンを通じてオンラインクイズシステムにログインし、ユニークなチーム名で参加登録。全班が揃うと「豪華景品を懸けた熾烈な戦いが今から始まります!」との宣言とともにクイズがスタート。出題は全部で10問程度、内容は「講師の名前の正しい読みは?」「放射線の種類は何種類?」など、この日に学んだ知識に関するものだ。問題ごとに選択肢が提示され、各班は議論の上で解答を選択するが、正答だけでなく解答スピードも得点に影響するルールのため、どの班も真剣そのもの。画面に残り秒数が表示される中、「急げ!」「こっちだ!」といった声があちこちの班から上がり、隣同士顔を寄せ合ってスマホ画面を見つめる姿が見られた。回答ロック後、正解が発表されると「やった!」「しまった~」という歓声や悔しがる声が飛び交い、大いに盛り上がっていた。クイズの途中経過はリアルタイムで順位表に反映され、後半になるにつれ「◯◯班がトップを猛追!」といった実況が入ると、生徒たちは一喜一憂しながら熱狂。最終的に優勝が発表されると、会場は拍手喝采に包まれた。勝利した班のメンバーには豪華景品として記念品(「ねんりょう棒」「せいぎょ棒」と名付けられた「うまい棒」のセット)が贈られ、生徒たちは笑顔で受け取っていた。

見事に優勝した班の班長(中央)
自作スケッチブックで万博へ━━STEAM教育の集大成
上述の通り、今回の特別授業で得た知識やアイデアは、8月に開催される大阪・関西万博の会場で生徒たち自身が一般来場者と対話するアウトリーチ活動に活かされる。Nプロに参加する生徒たちは万博会場で、自ら手作りしたカラフルなスケッチブック(大型のフリップボード状の教材)を手に、道行く人々に積極的に話しかけなければならない。こうした「スケッチブック対話」によるアウトリーチは、本プロジェクトならではのユニークな手法である。通りすがりの人の興味を引き会話のきっかけを作るには、視覚的にキャッチーな仕掛けが有効だ。Nプロの指導陣は「手作りのスケッチブックこそ最強の武器」だと考えており、「一人二人が怪しげに掲げるのではなく、大勢の生徒全員が色とりどりのスケッチブックを持って立てば注目を集め、話を聞いてもらいやすくなる」と説いている。実際、生徒たちは今後のワークショップで思い思いのデザインでスケッチブックを作成し、そこに今回の講義で得た豆知識やクイズ、図解などを盛り込みながら、人々に伝えたいメッセージを整理していくという。
中村助教は「皆さんがNプロに参加した理由や、ここで学んで楽しかったことをぜひ万博で来場者に伝えてほしい」と呼びかけていた 。高校生が自分の言葉で科学の面白さを語る姿は、聞き手にとっても新鮮で心を動かすものとなるだろう。生徒たちは万博本番で、「科学を通じて社会と語り合う」実践に挑む 。
今回の特別授業は、そうしたアウトリーチ活動に向けた準備として STEAM教育 の要素が随所に発揮された場でもあった。STEAMとは、科学・技術・工学・芸術・数学の分野を横断して総合的な理解を促す教育のことだ。Nプロジェクトでもその考え方が取り入れられており、科学(Science)として放射線に関する基礎知識を学び、技術(Technology)としては原子炉制御技術や放射線を利用した医療・工業技術への理解を深めている。また、工学(Engineering)では放射線を安全かつ効果的に扱うための仕組みや工夫を知り、芸術(Art)ではスケッチブックの作成やデザインを通じて、自らの知識を社会に魅力的に伝える創造力を育んでいる。さらに数学(Mathematics)として、放射線のリスク評価などをデータや統計的視点から理解し、論理的に考察する力も養っている。こうした多様な視点と分野が融合した活動こそが、本プロジェクトにおけるSTEAM教育の実践だと言える。特に「伝える力」や「創造性」といった部分は学校の教科学習だけでは得がたいが、今回のようなプロジェクト学習を通じて生徒たちは自然とそれらを身につけつつあるようだ。実際、会場では生徒同士で「あの例え分かりやすいね」「このクイズ、スケッチブックでも使おう」といった前向きな会話も聞かれ、単に知識を暗記するのでなく学んだことをアウトプットする前提で吸収していることが伺えた。
原子力産業界にとっても、将来を担う若者がこのように放射線やエネルギーについて主体的に学び、一般の人々に発信する取り組みは心強いと言えるだろう。中村助教は「放射線そのものを探求することが目的ではなく、放射線を題材にコミュニケーション能力を養うのがNプロ」と述べており 、科学技術と社会をつなぐ人材育成の重要性を示唆している。特別授業を通じて培われた知識と対話スキルを武器に、生徒たちは万博の場で来場者との科学対話に挑む。その姿はSTEAM教育の成功例であるとともに、原子力・放射線分野の理解促進に向けた新たなアプローチとして大いに注目される。今回の授業で得た学びと自信を胸に、若き「科学コミュニケーター」たちがどんな活躍を見せてくれるのか、8月の本番が待ち遠しい。

158か国語をひとりひとり分担して活動することを発表する中村助教
おっと、大事なことを言い忘れていた。もうお気づきかもしれないが、万博会場を行き交う人々は国籍もバラバラな人々である。日本語で訴えても何一つ伝わらないかもしれない。実は大阪高校の生徒たちは、手作りのスケッチブックを「158か国語」で制作する予定なのだ。万博とはいえ、このような活動は稀ではないだろうか。
この「158か国語」のスケッチブック制作という試みには、生徒たち自身の創意工夫が大きく求められることも見逃せない。各生徒は担当する国の言語や文化、習慣について自ら調査を行い、異文化への敬意と理解を深めながらスケッチブックをデザインする。単に翻訳した情報を伝えるのではなく、現地の人々が関心を持つような伝え方、コミュニケーションの工夫を凝らしているのだ。
中村助教は「世界は多様です。異文化を理解し、その多様性を体感しながら対話する能力こそ、科学技術の国際化が進む現代において重要なスキルです」と強調する。この取り組みは、原子力や放射線など専門性の高い分野においても、「技術開発」だけでなく、異なる文化的背景を持つ人々との対話を通じて、社会的合意形成や理解促進に貢献できる人材を育成することにつながるだろう。
なおNプロでは、スケッチブック購入費や見学会参加に係る交通費などの支援を、広く呼びかけていることを、申し添えておく。
(原子力産業新聞 編集長)