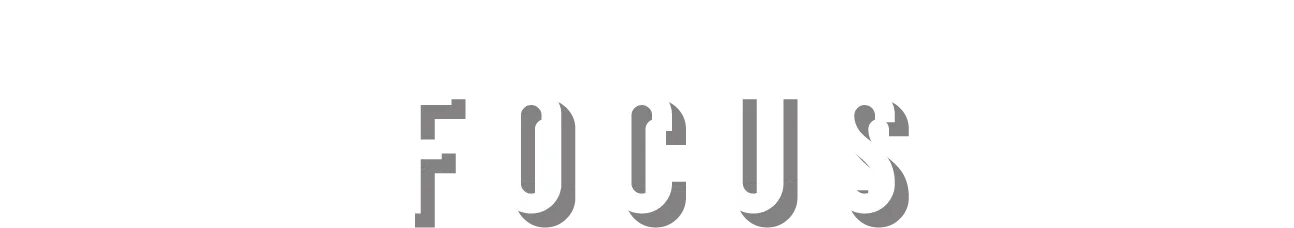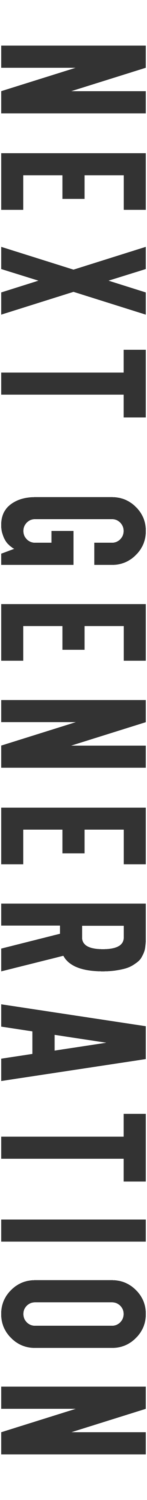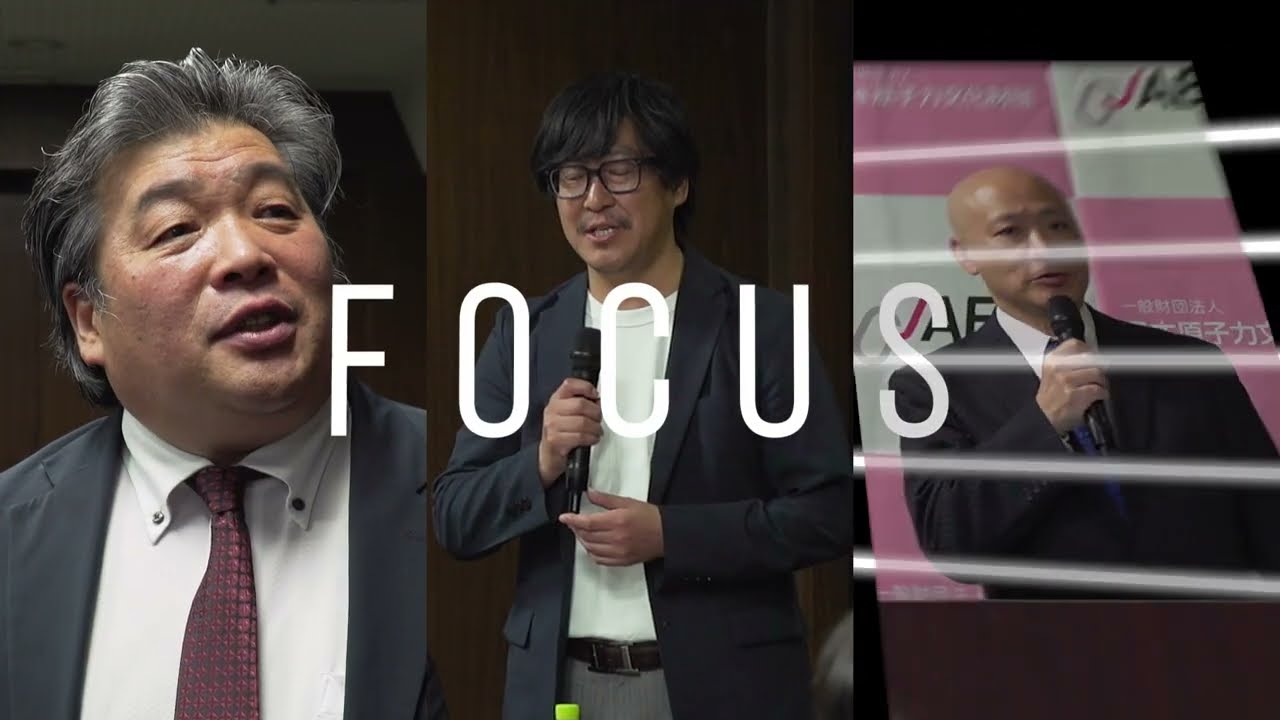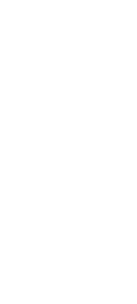第7次エネルギー基本計画が「原子力の最大限活用」を打ち出す中で、行政と若い世代が真正面から原子力の未来を語り合うシンポジウムが11月9日、東京理科大学で開かれた。経済産業省の吉村一元エネルギー・地域政策統括調整官、東京理科大学と早稲田大学の学生、高校生、研究者らが参加し、政策転換の背景や教育、人材育成、地域との信頼構築などを多角的に議論。原子力を「自分事」として捉えるための対話の最前線を追った。
政策転換を共有する場に
日本原子力文化財団(JAERO)が主催した「エネルギーイノベーションシンポジウム」には、東京理科大学、東京電力ホールディングス、電気事業連合会が協力し、会場とオンラインで約200名が参加した。東京理科大学の記念講堂に設けられた会場では、高校生や大学生、研究者、政府関係者らが集い、チャット機能を備えたオンライン配信を通じて遠隔地の聴衆も議論に加わった。
開会挨拶に立ったJAEROの矢野伸一郎専務理事は、今年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画を振り返り、「原子力について“最大限活用”と明記されたことは大きな政策転換。転換の意義を若い世代と共有し、自分たちの生活や進路と結びつけて考える場にしたい」と呼びかけた。プログラムは基調講演2本、学生報告、パネル討論という三部構成。会場後方では高校生ポスターセッションが開催され、休憩時間には大学生や行政担当者、一般来場者が高校生と活発に意見交換する姿が見られた。
第1部では、経済産業省資源エネルギー庁の吉村統括調整官が登壇した。吉村氏は日本の脆弱なエネルギー構造を概説し、エネルギー政策の基本方針である「S+3E」――安全性(Safety)を大前提に安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合性(Environment)を同時に追求する――を改めて整理した。自給率はわずか15.3%、電力の国産比率も3割に届かない。「燃料価格の高騰や地政学リスクを踏まえると、特定電源への依存を減らすことは喫緊の課題だ」と警鐘を鳴らした。
2030年代以降に向けては、再生可能エネルギーの導入拡大と原子力の活用を両立させる必要があるとして「需要増と脱炭素の双方に投資する“二重投資”の時代に入った」と指摘。2040年には脱炭素電源比率を6~7割に高め、原子力を2割程度確保するシナリオを示した。特にAIやデータセンターの拡大によって電力需要が大都市圏で急増していることを挙げ、「電力コストの地域差が企業立地を左右する時代になった。西日本では再稼働が進み電力コストが抑えられている事例もあるが、地域によっては火力依存が高く、電力料金が突出している」と述べた。さらに「化石燃料の輸入に頼る現状では、2023年だけで約26兆円もの国富が海外に流出している。原子力も含め、脱炭素電源は国産電源であることから、国全体の負担を考えれば、脱炭素電源への投資は先送りできない」と危機感を示した。
続いて登壇した東京理科大学創域理工学部の髙嶋隆太教授は、情報環境が世論形成に与える影響を分析した研究成果を紹介。「情報量が急激に増えるSNS時代では、同じ情報でも受け取り手のリテラシーや価値観によって態度が二極化しやすい」としたうえで、「二極化は社会の劣化ではなく、慎重派と推進派が前提を共有し、建設的に議論を始めるための出発点」と指摘した。情報の信頼性を高めるためには、教育現場での科学的リテラシー育成と、行政・事業者による透明性の高い発信が不可欠だと訴えた。こうした情報発信の課題や対話の継続性については、後半のパネル討論でも改めて議論された。
若者の視点が浮き彫りにした課題
第2部では、9月に柏崎刈羽原子力発電所を視察した早稲田大学と東京理科大学の学生が、現地で得た学びを報告した。東京電力の安全対策センターや中央制御室のシミュレータ、津波対策としてかさ上げされた防潮堤、水密扉や海水ポンプの二重化、非常用電源車の常設配置など、津波・多重災害を想定したハード・ソフト両面の強化策を紹介。「安全対策に終わりはない」という現場の姿勢に触れ、学生たちはその真剣さに圧倒されたという。その一方で、専門用語が多く一般には理解しづらい説明も多いことや、ネガティブな側面を強調するメディア報道(「オールドメディア」と言及された)とのギャップを実感したと語る。
学生たちは、柏崎市や刈羽村の企業や、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の担当者からのヒアリング内容についても具体的に紹介。柏崎市を本拠とする株式会社竹内電設の竹内一公社長は「柏崎が原子力を受け入れたのは国の発展に貢献するため。しかし原発が止まっている期間が長く、地元が直接潤う場面は多くない。『国のため』という思いで支え続けている」と語ったという。学生たちは、「経済効果が地元に直接還元されるわけではないが、国益のために支え続ける地域の姿勢に深く心を打たれた」と振り返る。「原子力政策を語る際には“国全体”と“地域の現実”を同時に見つめる必要がある」との声も上がった。
視察を踏まえた提言として、学生たちは①学校教育でエネルギーリテラシーを体系的に扱い生活者としての判断力を養う、②SNSなど若者がアクセスしやすい媒体で中立的な情報を届ける、③再稼働のメリットとリスクを安全性・経済性の両面から丁寧に説明する、④地域住民との対話とフィードバックを継続する、の4点を提示。行政に対しては家庭単位での負担感が伝わる説明の充実を求めた。
報告後には互いの大学からコメントが寄せられ、短いディスカッションが交わされた。エネルギー問題に無関心な現役世代への対策として、多様なデジタル媒体を通じて情報へのアクセスの機会を提供していくだけでなく、学校教育と同様に電力という社会インフラを取り巻く現実を伝えていくことが大事だと強調された。また地元住民が抱える課題は技術的リスクへの不安だけでなく、「国のために犠牲になっている」という感情的側面が大きいことも問題視され、原子力発電に対する良いイメージを打ち出すことで、「日本を支えている」という誇りを持てるようにするべきだとの意見が出された。
若者と行政が交わした“本音”――パネル討論
第3部のパネル討論には、吉村氏と学生代表4名が登壇した。議論は学生からの率直な問いかけで始まった。ある学生が「政権が変わり、エネルギー政策の優先順位はどうなるのか」と新政権の方針を質した。吉村氏は「安全性を最優先に、原子力を産業競争力の基盤とする方針は変わらない」と明言した。そのうえで、「政策の信頼性を高めるには、情報の見せ方もアップデートしなければならない」と続け、行政側の課題を率直に語った。
続いて別の学生が「政策の温度感について、現場の実務者と一般市民との間に差がある」と指摘。これに対し吉村氏は、「行政側は説明資料の正確性を優先するあまり、生活者の実感から遠い表現になってしまうことがある。家庭の電気料金がどう変わるのかという視点で情報を加工する努力をしていきたい」と応じた。吉村氏は「恣意性を排除するためにデータの羅列になってしまうが、理解されなければ意味がない」とも述べ、行政の情報発信を改善する姿勢を示した。学生たちはその率直さに頷きながら、「伝わる行政」への期待を感じ取っていた。
さらに別の学生が「小中高校でのエネルギー教育の拡充は進んでいるのか」と問うと、吉村氏は「資源エネルギー庁では小学生から大学生までを対象にした副読本を整備しているが、授業での使われ方を追跡し、教師が扱いやすい形に改善する必要がある」と回答。スマホで遊べる体験型教材「電力バランスゲーム」についても紹介し、「原子力だけでなく再エネや省エネも含め、電源バランスを自ら体験できる環境を整えたい」と話した。
また、学生からは「政府資料は信頼できるが専門的すぎてわかりにくい」との指摘も出た。吉村氏は、行政側の説明が生活者の実感に届きづらい現状を認め、学生との対話を通じて情報の見せ方や伝え方を磨き直したいとの考えを示した。髙嶋教授も「立場が異なる人と議論する際には、信頼できるデータを基にしながらも、相手の価値観を尊重する姿勢が不可欠」とコメントした。
討論の終盤には、参加していた高校生から「核融合研究はこれからどう進むのか」という質問が寄せられた。吉村氏は「核融合は廃棄物が少なく将来性のある技術として国家戦略に位置づけている。長期的な投資が必要だが、国内外の実証プロジェクトに資源を集中させている」と説明し、次世代技術への期待を語った。また、他の参加者からは「太陽光や風力の廃棄物・環境問題といったリスクは当初から想定できたのではないか」との指摘があり、吉村氏は対応が後手に回っていることを率直に認めた上で「自治体との調整や廃棄物対策を含め、今後は対策を着実に進めていきたい」と応じた。
なお、会場後方では、埼玉・千葉・栃木の高校生グループがポスターセッションを行い、それぞれが独自の研究成果を発表していた。栄東高校(埼玉県さいたま市)のあるグループは、「原子力発電の普及に向けて」と題し、校内アンケートの分析結果や、柏崎刈羽原子力発電所の経済波及効果を紹介。さらに、災害時の補償責任を国・自治体・事業者がどう分担すべきかを海外の制度と比較し、日本での課題を整理した。発表後には、「SNSやショート動画を活用して同世代にわかりやすく伝える方法を探っている」と語る生徒の姿も。会場には、“自分たちの手で原子力を伝える”という若い意志が静かに広がっていた。
国も積極的に関与
シンポジウム閉会後に吉村氏は、「若い世代から意見やアイデアをもらえる機会は貴重。こうした機会を捉え、私も同僚もどんどん参加していきたい」と行政としても次世代層と積極的に関わっていく姿勢を示した。またエネルギー庁が整備している副読本についても、活用状況を把握するだけでなく、授業で使いやすい形に改善することが課題だとし、「電力バランスゲームのような体験型教材を充実させ、エネルギーミックスを自分ごととして考えられる環境を広げたい」と意気込んだ。
人材育成については、「原子力の現場が長く止まっていたが、問題意識が業界大で共有されている今こそ、技術と人材を取り戻すチャンス」と強調。同じく力を入れている原子力サプライチェーンの再構築と合わせ、産官学が連携して次世代人材を育てる重要性に言及した。
原子力政策をめぐる議論は、専門性の高さや、行政・事業者と住民の間で共有される情報量に差が生じやすいという情報の非対称性、地域の複雑な思いなど、多層的なハードルに直面する。今回のシンポジウムは、学生が現場を訪れて自ら取材した成果を持ち寄り、それに行政が真摯に応じる「共創」の場となった。原子力を支持するか否かの前に、事実を学び、自分の言葉で語り合い、相手の立場を理解する。その積み重ねが、持続可能なエネルギー政策と地域社会の信頼を築く土台になる。今後も対話を継続し、「知る」から「考え、行動する」社会への歩みを確かなものにしたい。
(原子力産業新聞 編集長)