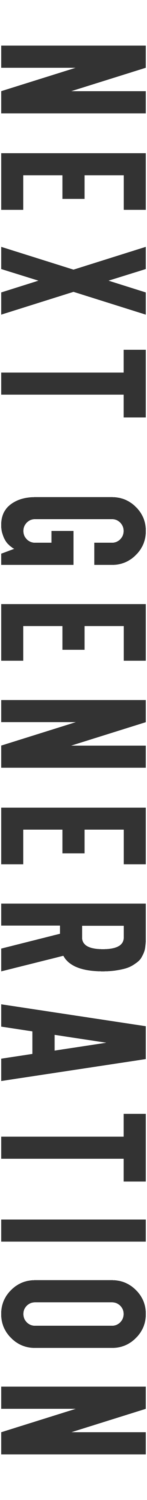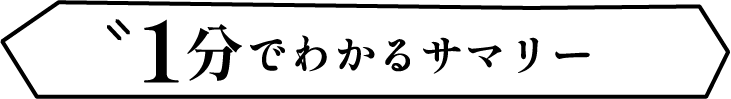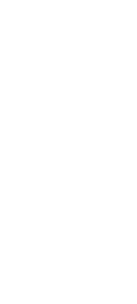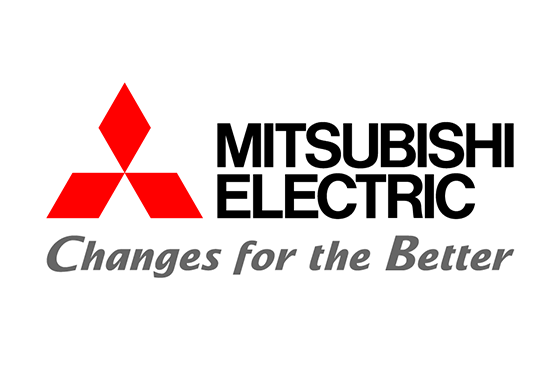京都大学で12月15日から17日までの3日間にわたり、日本放射線安全管理学会の第24回学術大会が開催された。会期中、「教育・社会的啓発活動・リスクコミュニケーション」をテーマとしたセッションB4では、放射線教育の現場で直面する課題と、それに対する具体的な実践が報告された。ICTを活用した教材開発、確率モデルによる教科横断的教育、文系学生を対象とした教養教育――いずれの発表も、放射線を「どう教えるか」という問いに正面から向き合う内容だった。
同じ学会会場では、中学生による研究発表も行われていた。放射線の身体影響、原子力発電の必要性、高レベル放射性廃棄物の地層処分――中学1年生が選んだテーマは、いずれも社会的議論を伴うものだ。本稿では、セッションB4を軸に、研究者・教育者が模索する放射線教育の方向性と、それを受け止める側としての中学生の取り組みを重ね合わせ、放射線教育とリスクコミュニケーションの現在地を考える。
「測って終わり」にしないために
セッションB4の冒頭を飾ったのは、愛媛大学・学術支援センター・講師の岩﨑智之氏による「既存の放射線実習を活かしたICT教材の開発」だった。岩﨑氏は、教材開発の背景として、文部科学省が進める「GIGAスクール構想」により、児童生徒一人一台の端末配備と校内ネットワーク環境が整備され、学校現場でICT(Information and Communication Technology)を前提とした授業設計が可能になっている点を挙げた。こうした環境の下で、従来から行われてきた放射線実習にICTを組み合わせることで、測定結果の整理や可視化、考察までを一体的に扱える教材を開発したというわけだ。
岩﨑氏が対象としたのは、高校での放射線教育で広く行われてきた二つの実習である。一つは、外部被ばくの三原則(時間・距離・遮蔽)を学ぶ実習。もう一つは、身の回りの放射線を測定する実習だ。いずれも教育現場で定着しているが、岩﨑氏によると、「測定結果を記録するところで終わってしまい、その後の考察に十分な時間を割けないことが多い」と指摘した。
そこで開発したのが、Pythonを用いた二つの教育支援アプリである。一つは、外部被ばくの三原則に関する測定データを入力すると、平均値や標準偏差を自動的に算出し、グラフ化するアプリだ。理論値と測定結果を同時に表示することで、逆二乗則などの考え方を視覚的に確認できるようにした。もう一つは、身の回りの放射線測定結果を地図上にマッピングするアプリで、測定ルートや線量の変化を可視化する。
岩﨑氏はさらに、APIを活用した機能拡張にも触れた。原子力規制委員会のモニタリングポストデータや、産業技術総合研究所が提供する地質情報を取得し、生徒自身の測定結果と重ね合わせて表示できる仕組みを組み込んだという。これにより、「自分で測ったデータ」と「公的に公開されているデータ」を比較しながら考察することが可能になる。
発表では、これらの教材を用いることで、測定結果の可視化や比較検討が容易になり、実習後の議論や考察に時間を割けるようになる点が強調された。岩﨑氏は「データを自分で扱い、考えることに意味がある」と述べ、ICTはあくまでそのための支援手段であると位置づけた。
質疑応答では、教材開発における生成AIの活用についても話題に上った。岩﨑氏は、基本的なプログラムは自ら作成しつつ、改善や修正の段階で複数の生成AIを補助的に用いていると説明した。「どのエージェントが最適かは一概に言えないが、サポートツールとして活用している」との発言は、ICT教材開発の現実的な姿を示していた。
確率をどう教えるか
続くB4-2では、東京大学の若林昌吾氏が、「確率モデル教材による教科横断型放射線教育の実践と考察」を報告した。若林氏は発表の冒頭で、自身が千葉県の中学校に所属する現役の理科教員であることを明らかにし、現在は東京大学において教育研究員として放射線教育の研究に携わっていると説明した。現職教員としての経験を踏まえ、「中学生に放射線による細胞の損傷や修復をどのように伝えるか」という現場の課題意識が、本研究の出発点にあることを強調した。
若林氏によれば、放射線による生物影響はDNAや遺伝子といった専門的概念を伴うため、中学生にとって直感的に理解しにくい。そこで、BB弾を用いた物理モデル教材を開発し、細胞の損傷と修復、さらには発がんが確率的な事象であることを視覚的・体験的に示す試みを行っているという。
このモデルでは、BB弾を細胞に見立て、障害物を経て「完全修復」「異常修復」「細胞排除」という三つの結果に分岐する過程を再現する。発がんが一回の事象ではなく、確率的なプロセスの積み重ねであることを、直感的に理解させる狙いがある。
若林氏は、理科の枠を超え、このモデルが保健体育(がん教育)や社会科、道徳といった教科横断的な学びにつながる可能性に言及した。一方で、がんや死を扱う際には、生徒一人一人が異なる背景を持つステークホルダーであることを意識し、伝え方に配慮する必要があるとも述べた。
文系学生にどう届けるか
B4-3では、名古屋大学・アイソトープ総合センター・研究教育部・教授の柴田理尋氏が、文系学生を主対象とする教養科目「放射線と放射能」の実践を紹介した。対象は文系学部の2〜3年生で、高校で物理・化学の基礎は履修しているものの、大学受験向けの専門的学習を経ていない学生を想定している。授業の達成目標として、放射線・放射能の基本的性質を学び、その知識を基に利用の実態を理解し、社会での取り扱いを「正しく考えられる」能力の獲得を掲げた。
内容面では、医療、物理・化学、農業、工業、自然環境、社会環境といった複数領域を組み合わせ、座学中心としながらも、理解の“入口”を体験で作る工夫を重ねている。たとえば授業内では、サイコロを多数用いて確率現象を体感させる活動や、サーベイメータを用いた遮蔽の実験(鉛板やプラスチック板による遮蔽の違いの測定)、一定時間測定を多数回繰り返して得たデータから分布(ポアソン分布など)を扱う作業などを取り入れ、数式よりも「量」「ばらつき」「確率的ふるまい」を具体的な手触りとして理解させようとしている。
その上で柴田氏は、授業後の学生の反応には一方向の変化ではなく、少なくとも次の3パターンが見られると整理した。第一は、「無関心から関心へ」である。放射線を自分と無関係と捉えていた学生が、医療・産業などの利用の広がりや社会的論点に触れ、「いろいろ知るようになった」「大事だと分かった」と関心を持つようになる。
第二は、「ネガティブからポジティブへ」である。事故報道などを通じて否定的な印象が先行していた学生が、授業を通じて利用の実態や有用性を知り、見方を改める。柴田氏は、事故など「悪いイメージばかり取り上げていたが、非常に有用なことを改めて知った」といった趣旨の反応があることを示し、情報の偏りが認識を固定化し得る点を示唆した。
第三は、今回とりわけ重要な論点として、「ポジティブから再考へ」である。放射線の利用の幅広さに触れたことで「便利で、安全なものだと思っていた」学生が、事故や廃棄物など“不都合”の側面も同時に学ぶことで、無条件に肯定するのではなく「便利だからこそ安全に使うにはどうすべきか」と、前提を問い直す方向へ進む。柴田氏は、この変化を「ポジティブからネガティブへ」ではなく、受け入れていたものを改めて考え直すというニュアンスで説明した。
以上の3類型は、放射線教育が「賛否の誘導」ではなく、学習者の出発点(無関心/否定的/肯定的)に応じて、関心形成・理解の更新・前提の再検討へと学びを進めうることを示していた。
同じ空間で発表していた中学1年生
セッションB4で語られた放射線教育の課題と手法は、別の形で会場内に現れていた。京都教育大学附属京都小中学校の中学1年生による、3点のポスターセッションである。
一つ目のグループは「放射線による身体への影響について」をテーマに、DNA損傷と修復に注目した。インタビューで生徒は、「学校では基本的な内容は学んだが、DNAがどう修復されるかまでは扱われなかったため、自分たちで調べようと思った」と語ったうえで、「怖いというイメージだけでなく、『どのくらいの線量なら体が直そうとするのか』『直しきれなかったときに何が起こるのか』を自分の言葉で説明できるようにしたかった」と話した。班員同士で論文や教科書、インターネットの資料を読み合い、イラストを使った図解も加えながら、「最悪の場合、死に至る」という断片的な理解から、日常的に起こっているDNA損傷と修復の仕組みを踏まえた理解へと視点が変わっていったという。
二つ目のグループは「原子力発電は必要か」をテーマに、調査前後での意見の変化を示した。調査前は、事故の印象や使用済み燃料の処分問題から「必要ではない」と考えていた生徒が多かったという。しかし、CO2排出削減や電力の安定供給に関する資料を読み込んだ結果、「リスクはあるけれど、今の社会で電気を使い続けるには、原発をなくすのではなく、安全に使う方向を考える必要がある」として、「必要だと思うようになった」と説明した。同世代に向けては、「不安だけで判断せず、まず知識を知ってほしい」と訴え、SNSなど一部の情報だけに頼らず、賛成・反対の両方の情報に触れることの大切さを強調していた。
三つ目のグループは「放射性廃棄物の地層処分」を取り上げた。日本が文献調査段階にとどまっている現状と、フィンランドやスウェーデンで処分が進んでいる理由を比較し、地盤条件に加え、丁寧な説明やイメージ形成の重要性を指摘した。生徒たちは政府や事業者のウェブサイト、海外の映像資料などを見比べ、「日本では“危ないものが埋められる”というイメージが強いのに対し、北欧では、最終処分場が単なるゴミ捨て場ではなく、最先端技術が集まる場所として前向きに捉えられている点が印象的だった」と語る。日本では福島第一原子力発電所事故の影響もあり、放射線や地層処分に対してマイナスのイメージが強いと感じた一方で、「自分たち自身が知識を身につけ、日本の人たちに伝えることが大切だと思った」とも話していた。
なお、参考文献には資源エネルギー庁や、電気事業連合会、原子力発電環境整備機構、日本原子力文化財団などのウェブサイトが含まれていたが、原子力産業新聞を挙げていたグループは皆無であった。
教育とリスクコミュニケーションの交点
セッションB4で示された教育実践と、中学生のポスター発表に共通していたのは、放射線を「特別視する対象」ではなく、「理解し、判断する対象」として扱おうとする姿勢だった。ICTによる可視化、確率モデルによる理解、体験型授業――いずれも、知識を一方的に伝えるのではなく、学習者自身が考えるための手がかりを与える試みと言える。
リスクコミュニケーションは、説明する側の工夫だけで完結するものではない。受け止め、考え、判断する側をどう育てるかという教育の問題と密接に結びついている。今回の学術大会では、その両者が同じ空間で示されていた。学会で語られた教育の方向性と、中学生の言葉が交差した点に、本大会の一つの意味を見出すことができるだろう。
(原子力産業新聞 編集長)