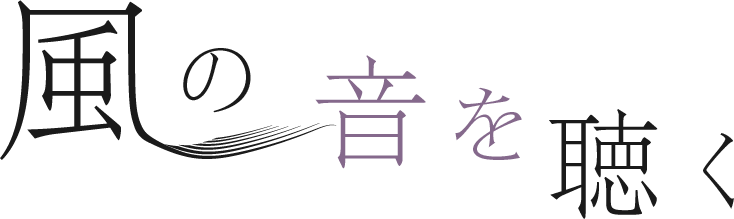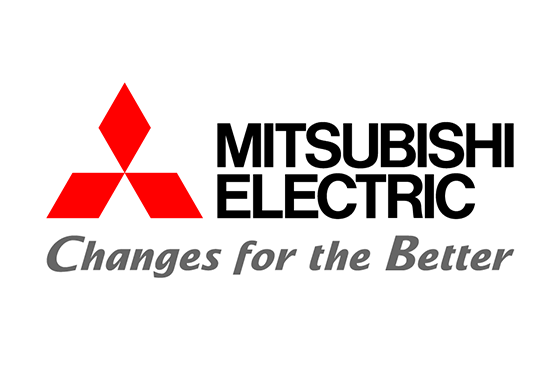大熊町再訪 帰還を切望するSさんの今
12 Jun 2019
東日本大震災被災者たちの前向きな姿勢に触発され、前を見るばかりで回顧が不十分だったという、振り返る大切さについての医師、越智小枝さんのコラム「9年目の福島 振り返る大切さ」に共感した。
前を見ることと振り返ることの大切さに軽重はなく、正解は両方大切だとは言っても、現実が常に正解通りとは限らないから難しい。
新聞記者として半世紀近く報道に携わりながらジレンマであり続けたのも、報道者はどう頑張っても当事者にはなれない、そのもどかしさの中で報道の役割をどう果たして行くかということだった。私が辿りついた一つの答えも振り返る、つまり「忘れない」ことである。90年代の冷戦終結後に世界で頻発した内戦や民族紛争などを取材して、一層そのことを痛感した。
政治レベルで妥結や合意が図られても、それは内戦や紛争の終わりを意味しない。復興や人々の帰還がより重要な問題として存在する。ところが大半の人々はその段階で関心が薄れ、やがて「忘れる」。
しかし当事者とくに巻き込まれた難民や被災者たちは、しばしば「忘れられる」ことこそもっとも辛いことだと語る。困難な道のりに伴走者のいない孤独。目の前の苦難は何とか乗り越えることが出来ても、忘れられることの精神的苦痛は耐えがたいのが人間というものだろう。
つい前置きが長くなった。桜がまさに満開を迎えた4月半ば、大熊町を再訪した。帰還を切望する当時92歳のSさんに会って以来だから2年ぶりのことだ(当欄2017年3月14日付「ルポ・大熊町を訪ねて」参照)。折しも同町の一部は東京電力福島第一原発立地町として初めて避難指示が解除され、役場の新庁舎が大川原地区に完成し、開庁を待つばかりとなっていた。
新たに盛り土をした高台に建つモダンなデザインの新庁舎から町を眺め渡すと、役場のホームページの復興通信にある「小さなまち」作りの第一歩が始まったことがしみじみ実感された。
ただそこにSさんがいないことが残念だった。2年前は自ら先頭に立って町を案内してくれたが、体調を少し崩したと知人から聞いていた。もっともいわき市の新しい復興住宅で会ったSさんは思いのほか元気な様子で、「参考になるかどうか分からないけれど」と言いつつ、町や福島の復興状況を伝える地元紙の束を下さったのには、ちょっと胸が熱くなった。
Sさんに初めて会ったのは2011年10月、会津若松市の仮設住宅時代のことだ。大熊町は町民が離散しないよう町ごと会津若松に避難していた。インタビューを固辞する人が多い中で、「お役に立つなら」と快く応じてくれたSさんは言わば取材の恩人だった。
大熊町に生まれ育ち、農業の傍ら福島第一原発の建設作業に関わり、人生の大半を原発とともに生きた。「原発がこんなに危ないものだったとはなあ」と深いため息をつきながらも、「原発のお陰で良い暮らしが出来たのも確か。今更手のひら返しでは罰が当たる」と事故にも事後対応にも非難や怒り、グチめいた言葉はほとんど聞かれなかった。そして一貫して将来に前向きなことに、むしろ私の方が勇気づけられたような気がした。
その後いわき市の仮設住宅、災害復興住宅と転居を余儀なくされたSさんを支えたのは、故郷に帰還する信念であり夢だったに違いない。だから自宅の除染される日を心待ちし、除染について語る時の口調は一段と軽快だった。
だがこの2年間、Sさんに除染の朗報は届かなかった。除染には当然とは言え、優先順位がある。また復興全体に言えることだが、人手不足もネックだ。加えて復興五輪を謳う東京五輪も近づく。聖火リレーは2020年3月26日、サッカー施設Jヴィレッジ(福島県楢葉町、広野町)からスタートする。復興に取り組む福島を世界に知らせるまたとないチャンス。そのことに異存はない。しかし被災者の暮らしにしわ寄せが行くのは極力避けなければならない。
復興には除染が不可欠だ。そこから生活も始まる。今回は訪れることが出来なかった、イノシシに踏み荒らされたSさんの自宅の玄関には今も「必づ帰る」の張り紙が掛かっているだろうか。
人生100年時代。幸いSさんは病身の奥さんに代わって食事の支度もするなど元気だ。来年はまたSさんと一緒に大熊町を訪れようと密かに誓った。