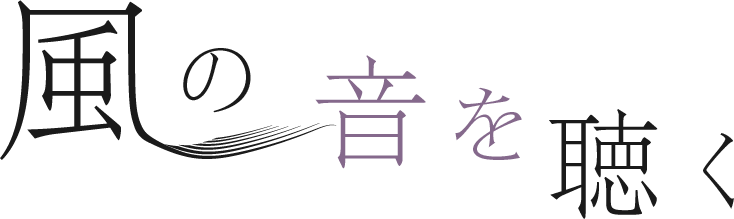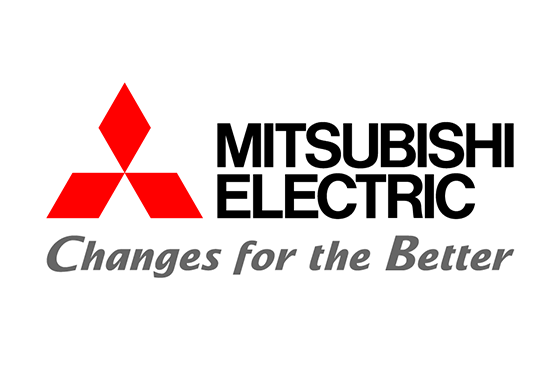「西高東低」で終わってはもったいない大阪・関西万博
02 Jul 2025
大阪・関西万博2025が開幕して1か月ほど経った5月頃、関西では日々の挨拶が「もう万博に行った?」になったとか。7月の今では「もう万博に何回行った?」と、挨拶も進化?していることだろう。
私が訪れた6月初めのある日も、土砂降りにも関わらず入場ゲートからパビリオン、レストラン…どこも人、人、人の波だった。
リピーターも多く、「今度行くと4回目」と言う若い女性にも会った。行けば行くほど通になる。万博は奥が深いのかもしれない。
しかし残念なのは、東西で万博熱の落差が大きいことだ。「西高東低」、日本の半分だけの祭典で終わりかねない。もったいないことだと思う。
というわけで今回は、題して大阪・関西万博2025の魅力3題。あくまで個人的見解であり、どこぞの回し者ではありませぬ。念のため。
魅力の1. 出たとこ勝負も楽し、万博は裏切らない
当初、予約の煩雑さ、難しさが万博への出足を挫いたのは確かである。しかしパビリオンに限って言えば、数時間待ちの超人気館だけでなく、予約なし、出入り自由の国・地域・機関を訪ねるのも一興だ。
ハズレなら失礼して次に行けば良いし、アタリなら感激は倍加する。参加規模158か国・地域、7国際機関は国連級で、世界をよりどりみどり出来るのは万博をおいてない。万博の精神は、今やメダル争いが熾烈化する一途の五輪と違って、参加することに意義があるのである。
私のアタリは25か国・地域が入るコモンズD館のパキスタンだった。待ち時間はゼロ、展示の見せ場はピンクソルト(ピンク色の岩塩)。簡素と言えば簡素。だが薄暗いピンクソルトの林をぬって進むのは、まるで鍾乳洞に紛れ込んだような、稀なる不思議な体験だ。
「嘗めても大丈夫ですか?」と係員に皆、同じことを聞いている。つい触って嘗めたくなる誘惑にかられるのだ。ホントに嘗めている人は目撃しなかったけれど。
林の途中で椅子に座り、岩塩セラピーも体験出来る。定期的にソルト入り蒸気が噴出されるそうだ。ささやかな「未知との遭遇」だった。
コモンズ館はAからDまで4館ある。いずれも小国を中心に世界中の国・地域・機関が多数入り、待つことはほとんどない。
入館記念のスタンプ・ラリーの数を稼ぐのに格好だから、ノートを抱えた子供たちの出入りが引きも切らない。
好奇心一杯、嬉々とした彼らに、もし日本中の小中学生たちが同じような経験が出来たら、ちょっと大袈裟かもしれないが、民族共有の楽しい思い出になるのに——と思った。
魅力の2. 国家は食の魅力で競う
4回目を目指す件の女性は、万博の楽しさはパビリオンに付設するレストラン巡りと言っていた。歩き回るとお腹も空くし、確かに「食」は万博の魅力を高める重要な要素だ。
彼女のイチ押しは「クウェート」とやや意表を突く答え。料理の珍しさに加えて、場所を見つけにくいのが功を奏し?穴場との評判らしい。イスラムだからアルコールはないが、カクテルならぬモクテルと称するノンアルコール飲料が沢山揃っている。
私のイチ押しは高原レストラン「水空」。サントリーとダイキンの共創で、一歩入れば、もうそこは森や川が流れる爽やかな高原の雰囲気、窓越しに大屋根リングと水辺が望める格好の立地にある。これだけでも満足感十分な上に、和を基本にした創作料理が申し分ないのはもちろんだ。
日本の活路はやっぱり「おもてなし」か、なんて思ってしまった。
魅力の3. 大阪・関西万博2025の最高傑作・大屋根リング
奈良・法隆寺が世界最古の木造建築なら、大屋根リングは世界最大級の木造建築。まさに木は日本の魅力そのものだ。これが鉄骨だったら、入場者たちの心をこれほど虜にしただろうか。
リングの内を歩けば香(かぐわ)しく、上に登れば景観が素晴らしい。
土砂降りの雨が上がると、海の向うには淡路島や明石海峡大橋がうっすらと見えた。眼下には今しがた訪ね歩いたパビリオンや豆粒のような人々が広がる。地上の喧噪も届かず、何とも平和でイイ空気が流れている。
まるで1つの宇宙、地球の生業のよう。
大屋根リングのデザインの理念は「多様でありながらひとつ」だそうだ。
現実の地球は、今や分断・対立が各地で先鋭化し、ひとつになれず苦しみもがいている。美食でなく銃弾で競っているのだ。
だが大屋根リングという、もう1つの宇宙には、清々しいほどの開放感がある。1周2キロ。立ち止まれば大空や海原、山なみ、よく手入れされたカラフルな花壇が次々に目に飛び込んで来る。
悠久の自然の見事さ。力強さ。地球の争い事など何ほどのことがあるのだろうかと、何だか粛然とした気分になった。
報道によれば、閉幕後は解体される予定だった大屋根リングに、保存案が持ち上がっている。維持管理など保存のコストを考えると議論は簡単ではないだろう。
どちらでもご自由に。大屋根リングは2025の万博レガシーとして、訪れた人々の心の中にきっと姿を留め続けるに違いないはずだから。