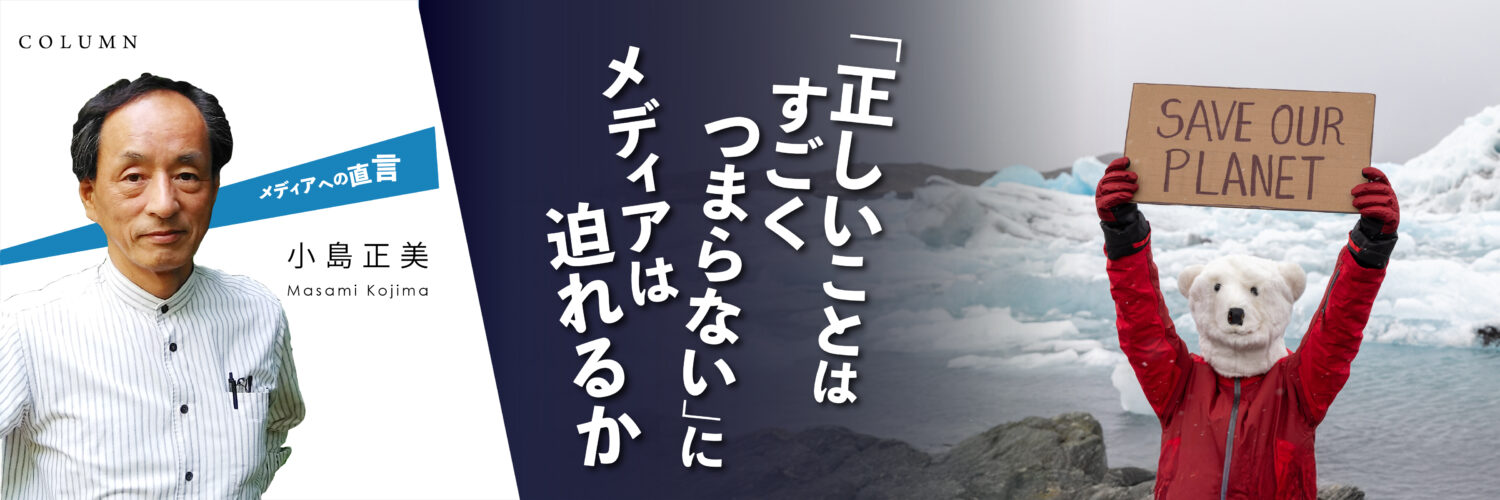「正しいことはすごくつまらない」にメディアは迫れるか
二〇二五年五月七日
気候危機を煽るニュースが毎日のように流れているが、今回は「それって本当にエビデンス(科学的根拠)があるのですか」と真摯に問いかける書籍を紹介したい。世の中が熱くなっているときこそ、世間の「空気」に抗う冷静な思考が必要だ。メディア関係者や気象関係者にとっては必読のテキストといってもよいだろう。
大規模停電でも
地球温暖化が関係?
四月二十九日朝に放映されたテレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」を見ていて、びっくり仰天した。スペインで起きた大規模停電の原因について、アナウンサーの羽鳥慎一氏が「これも地球温暖化の影響かな」と言ったのだ。そして、ゲストコメンテーターも「サイバー攻撃かもしれないが、急に暑くなって一斉に電気を使ったのか」とのコメントも流れた。
常識的に考えて、突然の大規模停電が地球の温暖化によって起きたと想像するのは難しい。地球温暖化といっても、百年間で一℃程度の気温上昇でしかない。それが大規模停電を引き起こしたと考えるのはあまりにも論理の飛躍である。にもかかわらず、テレビや新聞のメディア関係者はことあるごとに「温暖化が原因では」という言葉を安易に気軽に使う。
テレビ朝日の『有働Times』(三月三十日放送)でも「世界的に温暖化が進むと山火事が起こりやすくなる」と報じていた。いうまでもなく温暖化があまり進んでいなかったときでも、山林火災は世界で発生していた。「温暖化が原因」という言葉が安易に使われている状況を見ていると、メディア関係者は温暖化による地球規模の影響を正しく(科学的かつ統計的に)見ていないのではないかと思う。
台風は激甚化していない
そういうメディアのゆがみ(バイアス思考)に対して、うってつけのテキストが登場した。キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の杉山大志氏(物理学)が著した『データが語る気候変動問題のホントとウソ』(電気書院)だ。杉山氏は気候変動問題やエネルギー政策の論客だ。この本は難しいテーマを非常に分かりやすい言葉で解説し、中学生でもスラスラと読める。
杉山氏は温暖化自体を否定しているわけではない。しかし、「温暖化によって山林火災など自然災害が激甚化している」という言説には疑問を呈する。
たとえば、よく「地球温暖化のせいで台風が激甚化し、頻発している」とのニュースが流れるが、杉山氏は「そんな事実はない」と気象庁などのデータを用いて、詳しく反論している。日本のスーパー台風のランキングをみても、一九五〇年~六〇年代に頻発していた。昭和の三大台風(室戸台風、枕崎台風、伊勢湾台風)は一九三〇年代~五〇年代に起きている。私の自宅(愛知県犬山市)は伊勢湾台風(一九五九年)で半壊した。そんな辛い経験をもつ私にとっては、このことはとても実感できる。いまメディアにいる人たちはそのころの台風を知らない。知らなければ疑問の持ちようがない。
ホッキョクグマは
減っていない
同書によると、メディアが知っておくべき事実はほかにもたくさんある。「ホッキョクグマは減っていない」「気象災害による死亡数は減っている」「豪州最大のサンゴ礁(グレートバリアリーフ)は一時、半分消滅したといわれていたが、いまはV字回復した」(豪州海洋科学研究所は回復したデータを公表しなくなったという)「太平洋の島しょ国は水没の危機にはない」「世界の食料生産は過去五十年間、温暖化が進んだのに増え続けている」「米国の山火事による森林燃焼面積は一九三〇年代のほうがはるかに多かった」「世界の沿岸の陸地面積は拡大している」。
メディアは都合のよいデータだけを探す
ではなぜ、メディアは気候危機を煽るのか。それは、大しておもしろくもない統計的事実よりも、感情に訴える刺激的な物語(ストーリー)を好むからだ。
台風の激甚化に関して、杉山氏は次のように述べる。「地球温暖化によって台風が激甚化するといったストーリーを決めていて、それに合うデータだけを探し回る。ストーリーに合わない不都合なデータは無視する」。
全くその通りだ。森林火災や大洪水が起きると、メディアは勝手に温暖化のせいだと決め込んで物語(記事やテレビ番組)を作る。そういうメディア(特にNHKの特集番組はひどい)のバイアスぶりに関しては、私を含め十三人で執筆した「SDGsエコバブルの終焉」(宝島社)の第4章に書いたので、重複は避けたいが、ひと言でいえば、メディアの記者たちは温暖化が進んでいなかった時代にも、同様の大災害が起きていたのではないか、という記者なら常識的な想像力を全く働かせていない。
もうひとつ、杉山氏の本から例を挙げれば、東京では寒さによる死亡(呼吸器疾患や心臓まひなど)は暑さによる死亡(熱中症など)よりも三〇倍も多い。だが、メディアは暑いときに死亡した例を大きくニュースにする傾向がある。東京の例以外でも、「インドで熱波によって一〇〇人が死亡した」といった具合に、温暖化にかかわる事件となるとビッグニュースになりやすいバイアスがある。
太陽光や風力への幻想
「エネルギー政策」と題した4章も一読に値する。朝日新聞、毎日新聞をはじめとするリベラル系メディアは依然として反原子力のスタンスだが、その背景には太陽光や風力発電を拡大すれば、化石燃料や原子力がなくても豊かな経済は維持できるという前提(思い込み)があるように思える。しかし、これは幻想である。
よく太陽光で電気代が安くなるといわれるが、これは太陽光パネルが夜や雨などで止まっているときに火力発電や原子力発電などの支援を受けているトータルコストが計算に含まれていないからだ。西欧を見れば分かるように、太陽光や風力が増えた国ほど電気代は高い。しかも太陽光パネルの約八割は中国でつくられる。これだけ中国依存が高いと、むしろそのほうが危機的だと私は思うが、メディアはそういう事実にほとんど触れない。
世間の空気に抗う勇気を
どうしたら、メディアのバイアスが食い止められるのかと思っていたところ、毎日新聞が四月二十五日付紙面で戦後80年を振り返る特集記事(専門家を交えた座談会)を組んだ。その中で作家の温又柔(おん・ゆうじゅう)さんは、SNS(交流サイト)では正しくない話のほうが波及するという見方に対して、「正しいことはすごくつまらない。だからこそ、こうしたつまらなさに耐えるのが今とても重要だ」と述べた。確かにそうだ。
それに対し、毎日新聞主筆の前田浩智氏は、「『空気』に抗する勇気」と題した総括的コメントとして、戦争反対を唱える国民の声はかき消されたという過去を踏まえ、「つまらない正しさがゆがんだ空気に水を差す。改めてかみしめたいポイントです」と書いた。
これを気候変動問題に置き換えてみる。統計的事実を無視して、温暖化の危機を散々煽るメディアの刺激的な空気に対して、「台風は激甚化していない」「ホッキョクグマは減っていない」といった事実は、大して興味をそそらず、つまらないほどの正しさだ。
だが、はたして、いまになってメディアはその「つまらない正しさ」に耐えられるのだろうか。メディアの使命は事実を突きつけることだ。少なくとも空気に抗う勇気を見せてほしい。