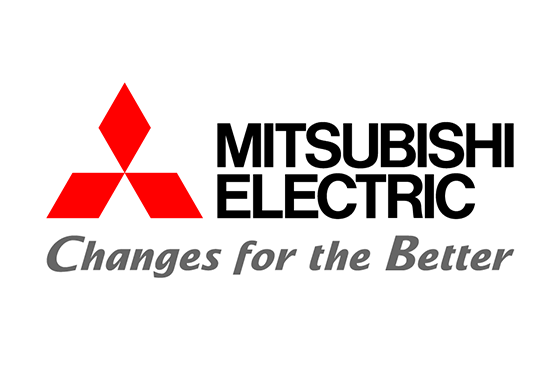寿都町の勇気ある一石の行為にどう報いるか
01 Dec 2020
日本の原子力発電所から発生する高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場の選定をめぐって、北海道の寿都町と神恵内(かもえない)村が名乗りを上げた。だれもが避けて通れない難題に、寿都町が果敢な一石を投じたといえるが、新聞をはじめメディアの反応は冷ややかだ。誠に不思議である。だれもが引き受けることを忌み嫌う国家的なプロジェクトに協力の姿勢を見せた人への感謝の念として、20億円はあまりにも少な過ぎる。100億円でもまだ少ない。寿都町町長が投げかけた一石の意義をしっかりと考えたい。
いまそこにある危機をどう打開するか
核のごみ問題の本質とは何だろうか? それは、だれかがいつかは必ずやらねばならない難題(一大国家プロジェクト)にどう立ち向かうかということだ。今後、原子力発電所の増設をゼロにするかどうか、再稼働を認めるかどうかという政策的な選択の問題ではない。たとえ今後、原発の建設をゼロにしたとしても、すでに発生している放射性廃棄物が消えてなくなるわけではない。いまそこにある危機をどう解決するかという哲学的難題(アポリア)だという認識がまず必要である。
いま全国には1718の市町村(2019年1月1日時点)がある。この小さな国で放射性廃棄物をどう解決すべきかという設定で考えると理解しやすい。
日本は民主主義と自由の国なので、処分場の受け入れをだれかに強制させることはできない。そこで一国の議長はこう提案する。「長きにわたり、みなが原子力発電所の恩恵を受けてきましたが、そのエネルギーの副産物を国内のどこかに捨てねばならなくなりました。まず、国内で処分することに賛成ですか、反対ですか」。すると、予想通り全員が「国内処分に賛成」と手を挙げる。
そこで、次のステップに進み、議長は「分かりました。では、自分の住む場所に処分場を引き受けてもよいと考える人は手を挙げてください。公共的な視点に立って、市民的な義務を果たしてもよいと考える人はぜひ手を挙げてください」と提案する。
ところが、議場に集まった1718人の代表者は一言も声を発せず、場内は沈黙の空気が続く。来る日も来る日もだれも手を挙げない。とうとう13年たっても、手を挙げる人は出てこない。どの人も、だれかが手を挙げるだろうと他人の利他的精神を期待したが、その期待はかなわなかった。
この状況は、だれもが総論では賛成するが、各論では反対するという古くて新しい政治哲学的な難題である。
どのような形で感謝するのが妥当なのか
この難題がもはや暗礁に乗り上げたかに見えたそのとき、日本の中心部から遠く離れた寿都町の代表者が手を挙げた。だれも引き受けたがらない仕事を、あえて引き受けようという勇気ある挙手だった。

文献調査応募書を手渡す片岡町長(左)
その人が寿都町の片岡春雄町長だ。「日本は核のごみに関してあまりにも無責任だ。一石を投じたい」(朝日新聞デジタル 9月3日付)と力強く言い放った。
1718人の中でだれ一人、公共的な視点に立って責任ある行動を示そうとしなかった中で、片岡町長は貴重な一石を投じたといえるが、共感を示す声は少ない(ように思える)。
この行き詰まりを打開する行為に対しては、まずもって、敬意を払うのがこの国の住人のモラルだと私は思う。傍観者だった人が、名乗り上げた人を非難することなど、できようはずはない。もちろんこの国は言論の自由が保障されているので、どんな反対意見を言っても自由だし、どんな思想を訴えようとかまわないけれど、まずは「よく手を挙げてくれました」と労いと感謝の言葉を発するのが市民的義務を分かち合う人としての礼儀というものだろう。「礼」とは思いやりを、みなに見える形で表す礼儀作法のことだ。
メディアは冷ややかで無責任な論調ばかり
しかし、メディアの論調はどうだろう。「自治体を多額の補助金で誘導するような方法で安全で国民が納得できる最終処分場を選べるとは思えない」(河北新報 10月14日)。「交付金で誘導するような手法は見直すべきだ。財政難に苦しむ自治体には、現実の地域課題に対応した交付金や政策で支援するのが筋ではないか」(京都新聞 8月18日)。「鈴木北海道知事は『ほおを札束ではたくようなやりかた』と疑問を呈する」(朝日新聞 9月21日)と報じている。
何という温かみに欠ける反応だろう。みなが忌み嫌う国家プロジェクトに対し、初期段階の文献調査とはいえ、協力してもよいと勇気ある決断を下した人に対して、あまりにも冷た過ぎるのではないか。
感謝の気持ちは100億円でも少ない
では、どういう感謝の表し方がよいのだろうか。
仮に、将来処分場になるとしたら、みなで拠出したお金を「処分場を引き受けていただき、ありがとうございます」とその当人に渡すのは理にかなったことだ。第一段階の文献調査に応じただけなので、その拠出額は20億円だというが、この難題に一石を投じた人がだれ一人現れなかったことを考えると、20億円はあまりにも安すぎる。橋脚を一つつくれば、なくなってしまう額である。あまり役に立ったとは思えないコロナ禍のマスク配布でさえ466億円の税金を費やしたことを考慮すると、だれもやりたがらない一大国家プロジェクトを引き受ける価値は100億円でも安いはずだ。
寿都のまちづくりを支援するのがよい
寿都の人々に対して、私たち国民は次のように言うべきではないだろうか。
「傍観者だった私たち国民は何もできませんが、せめて寿都町のみなさんがその町で末永く安心して暮らせるような町づくりの実現にお手伝いしたいと思います。そのために今後100年間にわたり、私たちの税金から、毎年20億円をお使いください。これは町づくりへの支援です。痛みの分かち合いであり、決して札束でほおをはたくのではありません。せめてもの私たちの感謝の印です」。

寿都町の弁慶岬
哲学者のマイケル・サンデル氏は「これから『正義』の話をしよう」(早川書房 15ページ)で「良い社会は困難な時期に団結するものだ」と言っている。つまり、公益のために犠牲を分かち合う正義(道徳)が称賛される社会が良い社会だというわけだ。
私は片岡町長と会ったことはないし、どういう人かは知らない。それでも、世に議論の一石を投じた行為を高く評価したいと思う。
いまのメディアの論調に欠けているのは、こういう倫理的、市民的な公共精神のあり方を問いかける視点ではないだろうか。