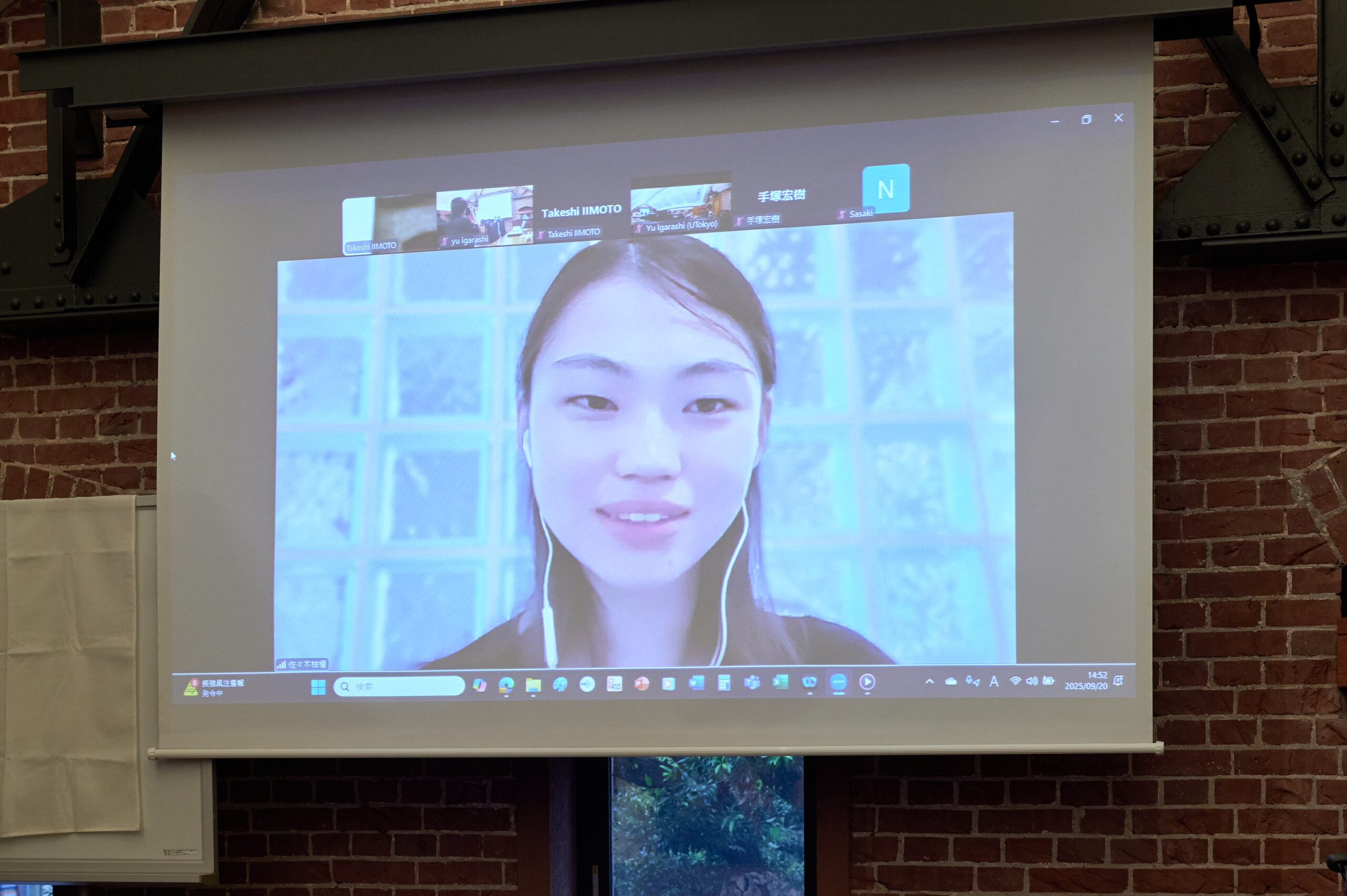INSO2025 日本チームが解団式
24 Sep 2025
第2回国際原子力科学オリンピック(INSO)が7月末から8月にかけてマレーシアで開催され、日本代表として初出場した高校生4名が金1、銀2、銅1を獲得した。さらに実験最高得点賞と最優秀女性選手賞の特別賞も受賞する快挙となった。9月20日に東京大学で開かれた報告会と解団式では、支援委員会代表の飯本武志教授(東京大学)や育成チームの佐藤大樹氏(日本原子力研究開発機構)らが経緯を報告。選手たち自身も国際舞台で得た成長を語った。
報告会で挨拶した飯本教授は、INSOの背景を解説。IAEAが中心となり、アジア太平洋地域を含む各国の要望を受けて設立された経緯を紹介し、「次世代のNST(原子力科学=Nuclear Science and Technology)人材を育成する国際的な試み」と位置づけた。
INSOは数学・物理オリンピックの流れを汲み、原子力科学を題材に理論(5時間)と実験(3.5時間)の試験を行う。2024年の第1回大会はフィリピンで開催された。日本はフィリピン大会を視察した関係者の強い要望を受け、今年初めてナショナルチームを結成し、大会に参加した。
今回の日本代表派遣は、多くの企業・団体・個人からの支援によって実現した。飯本教授は「完全ボランティアで運営している支援委員会の活動は、多くの方々に支えていただいている」と感謝を表明。「6人のメンバー(リーダー2名+選手4名)を海外へ派遣するだけでもそれなりにかかる」との内情を明かし、感謝の念を述べた。支援企業には匿名希望も含まれているが、原子力関連企業を中心に幅広い業界からの協力があった。また、個人支援者も多数に上り、原子力分野の専門家をはじめ、次世代人材育成に関心を持つ多くの方々から寄付金が集まったという。
角山雄一・京都大学准教授とともに選手団リーダーを務めた佐藤氏は、2024年12月の教材提供/勉強会に始まる、国内での準備活動について報告した。2025年4月に筆記・英語面接による選抜試験を実施し、18名から4名の代表選手を選出。選抜試験では、カリウム40を題材とした計算・知識問題と英語面接を実施した。筆記試験は文章理解と計算問題、知識を問う問題で構成され、英語面接では「おすすめの日本食は何ですか」「放射能って何ですか」といった質問に、20秒で考えて45秒で回答することが求められ、頭の回転が問われたという。
その後、選ばれた4名の代表選手たちに、DiscordやZoomを活用した遠隔指導を実施。大会直前には茨城県東海村にある日本原子力研究開発機構の施設で、測定技術合宿を実施、そのまま東京へ移動して壮行会を実施し、羽田からマレーシアへ向けて出国といった極めてタイトなスケジュールだったことが紹介された。
マレーシア大会での成果
大会には14か国から56名が参加。既報だが、日本は以下の成績を収めた。
- 金メダル:田中 優之介 選手(私立東海高等学校3年)
- 銀メダル:田部 主真 選手(国立筑波大学附属駒場高等学校3年)
堀 航士朗 選手(私立武蔵高等学校3年) - 銅メダル:佐々木 柚榎 選手(大阪府立北野高等学校2年)
さらに田部選手が実験最高得点賞、佐々木選手が最優秀女性選手賞を受賞した。なお試験では、核分裂、環境放射線、資源利用から、ビタミンCの放射線安定性や紛失線源の探索といった高度な課題が出題された。
佐藤リーダーは舞台裏で行われる採点会議での事例として、途中式が省略された日本選手の答案が0点とされたことを紹介。粘り強く食い下がった結果、「『この場で途中式が補完できるなら減点しない』ということになったので、私が必死に解きました!」と語り、判定を覆したエピソードを明かした。
一方選手たちは、国際舞台での経験を通じて大きな成長を実感していた。金メダルを獲得した田中選手は「原子力は未知だったが学べば学ぶほど面白く、将来は原子力分野に進みたいと考えている。研修での施設見学も貴重だった」と語り、銀メダルの堀選手はビデオメッセージで「世界中の参加者と交流できたのが大きな財産。試験だけでなく文化の違いを体験できた」と振り返った。
同じく銀メダルと実験最高得点賞を獲得した田部選手は「シンガポールやシリアの学生との議論で、多様な才能に触れた。受験期にこうした経験ができ感謝」と述べ、銅メダルと最優秀女性選手賞を獲得した佐々木選手はZOOM画面を通して「女子は少数だったが、最優秀女性選手賞を通じて後輩に勇気を与えたい。世界中に同世代の仲間がいることを実感した」と語った。
報告会には、原子力業界の支援者たちが駆けつけ、学生たちの快挙を心から祝福した。
日本原子力研究開発機構理事の上田光幸氏は、現在の原子力業界の動向に触れながら激励の言葉を述べた。「世界的に原子力が再評価される中で、高校生の活躍は心強い」と語り、Microsoft、Amazon、Googleといった巨大IT企業が原子力発電所に投資を開始するなど、まさに生き馬の目を抜くような時代になっていると指摘。「みなさんのような優秀な人材がこの分野で活躍してくれることを心から期待している」と結んだ。
日本アイソトープ協会専務理事の上蓑義朋氏は、受験期という重要な時期に高度な問題に挑戦した学生たちの姿勢を高く評価した。「基礎的なことしか知らない高校生のみなさんが、自分で種を見つけていかないといけないような高度な問題を解かれたのは驚きだ」と称賛。問題の難易度と学生たちの成果の大きさを強調した。
日本原子力文化財団専務理事の矢野伸一郎氏は、業界全体の期待を込めて語った。「原子力の世界は後継者不足、次への継承が非常に難しくなってきている」と現状を憂慮しながらも、「みなさんの活躍を素晴らしいニュースとして関心を持っていただいた」と、学生たちの成果が業界に与えた影響の大きさを強調した。
電気事業連合会広報部部長の風間章光氏は、国際大会という貴重な経験の価値を語った。「国際交流を通じて得た経験は人生の大きな財産となる」と述べ、緊張や不安を乗り越えて勇気を振り絞った経験そのものが、将来の大きな糧になると激励した。
文部科学省原子力課長の有林浩二氏はメッセージを寄せ、「今回のみなさんの取り組みは、確実に次の年、次の高校生たちに引き継がれたのだと確信しました。原子力分野の人材育成に新たな道筋を与えてくれました」と代読され、今回の成果が後輩たちへの大きな励みとなったことが強調された。
式典の最後には、来年度の第3回INSOに向けた準備が進められていることが発表された。2026年1月に一次選考、4月に二次選考を実施予定。飯本代表は「手作りの形で、みんなで盛り上げて、みんなで作り上げているような雰囲気の国際原子力科学オリンピック、さらには日本チームに育ったらいいなと思っている」と語り、継続的な支援を呼びかけた。
なお支援委員会の宮村浩子氏(JAEA)から、「来年度は原子力人材育成ネットワークが事務局を引き継ぎ、全力でサポートしていく」と明かされ、INSOが産官学連携による人材育成活動の一環として認知されたことが明らかになった。