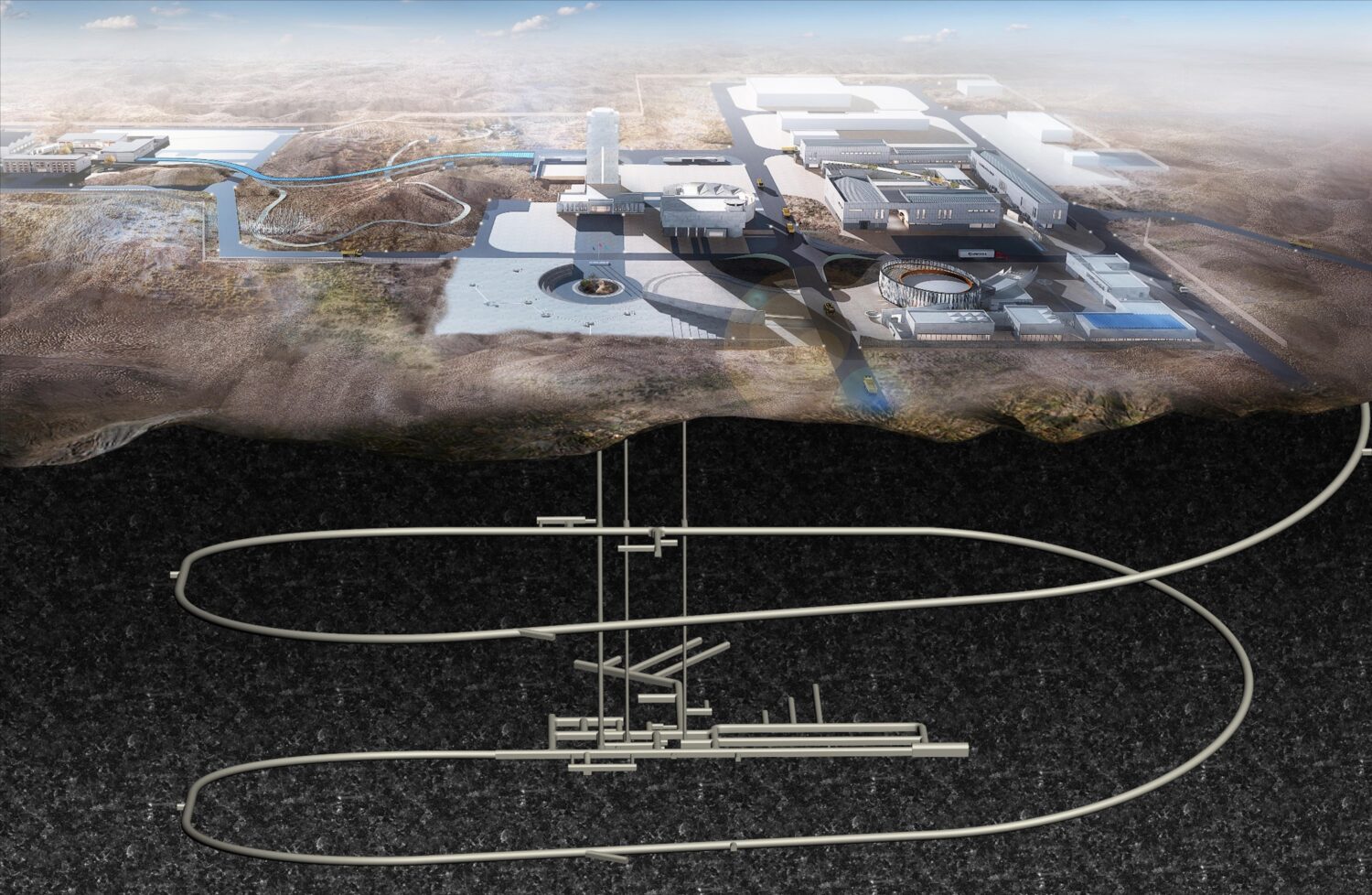「社会的合意に時間をかけることこそ成功のカギ」マグウッド事務局長
09 Oct 2025
経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)主催の国際シンポジウムで来日したW.D.マグウッド事務局長は10月7日、記者会見に臨み、放射性廃棄物処分をめぐる知識・データ管理(Information, Data and Knowledge Management=IDKM)の重要性と、国際的な協力の方向性について語った。
日本では2000年に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が制定され、2002年にNUMOが文献調査の公募を開始。実際の文献調査は、2020年に北海道の寿都町・神恵内村で始まっているとはいえ、すでに公募開始から四半世紀が経過している。この点についてマグウッド事務局長は、「国ごとの文化や制度、社会的背景を踏まえ、社会的合意を得るための時間を十分に取ることが不可欠だ」と強調。「20年、30年、あるいはそれ以上をかけてでも、拙速な決定で失敗するよりははるかに良い」と述べた。
さらに、事務局長は過去の失敗事例として米国のマクシーフラッツ(Maxey Flats)低レベル処分場を挙げ、「記録や知識の欠如が、地域住民の不安や巨額の除染費用を招いた」と指摘。記録と知識の管理が、いかに将来の社会的信頼の基盤となるかを強調した上で、「私たちは未来の世代に、問題だけを残すのではなく、それを管理するための知識を伝える責任がある」と語った。
原子力産業新聞は、NEAが公表した『SMRダッシュボード』に関連して、長期にわたり燃料交換不要や、密閉炉心を謳うSMR(小型モジュール炉)であっても、最終的には廃棄物が発生することから、NEAはどのように世界規模での廃棄物管理対策を検討しているのか質問。事務局長は、「NEAは、新型炉による廃棄物の発生量と性状を正確に把握し、対応策を準備することを最優先課題としている」と説明。「新しい技術を導入しても、処分経路が確立していないのでは本末転倒だ。各国の制度や環境は異なるため、廃棄物処理基準の『国際的な調和(harmonization)』は容易ではないが、今こそ将来に向けた共通基盤づくりを始める好機である」との認識を示した。
また、デジタル技術の採用について本紙が、NEAが以前指摘していた「原子力分野はデジタル技術の採用で取り残されてはならない」との考え方を踏まえ、AIは知識管理だけでなく安全文化、意思決定をどのように改善しうるか、事務局長の見解を求めたところ、事務局長は「AIは今後、情報整理や検索機能などで極めて大きな役割を果たすだろう」としつつも、「長期的な影響や応用範囲についてはまだ見通せない部分が多い」と慎重な見方を示した。そして「AIは強力なツールであると同時に、文脈や人間的判断を失わせる危険もある。長期的な知識の継承と信頼性確保の観点から、慎重に統合していく必要がある」と述べた。
そのほか質疑では、「データとは何か」との問いに対し、数値やテキスト等の事実情報に限らず、公開対話や協議の記録、当時の社会状況や意思決定の経緯といった文脈や暗黙知も含めて捉えるべきだとし、将来世代が全体像を理解できるよう記録の幅と質を確保する重要性を強調した。NUMOについては、「NUMOの技術的能力は世界のいかなる処分機関にも劣らない」と評価。スウェーデンやフィンランドなど先行国の知見を吸収しながら、段階的で慎重なプロセスを進めているとし、「NUMOの公開・レビュー活動は国際的にも透明性の高い取り組み」であり、今後もNEAが継続的に支援していく考えを示した。
会見とシンポジウムを通じて、技術・制度の整備だけでなく、「記録・知識・記憶」の継承こそが社会的信頼を築く鍵であるという趣旨が、繰り返し強調されていた。NEAが提唱する情報・データ・知識管理(IDKM)は、NUMOが進める地層処分の長期的な安全性と社会的合意形成の双方を支える基盤となるだろう。