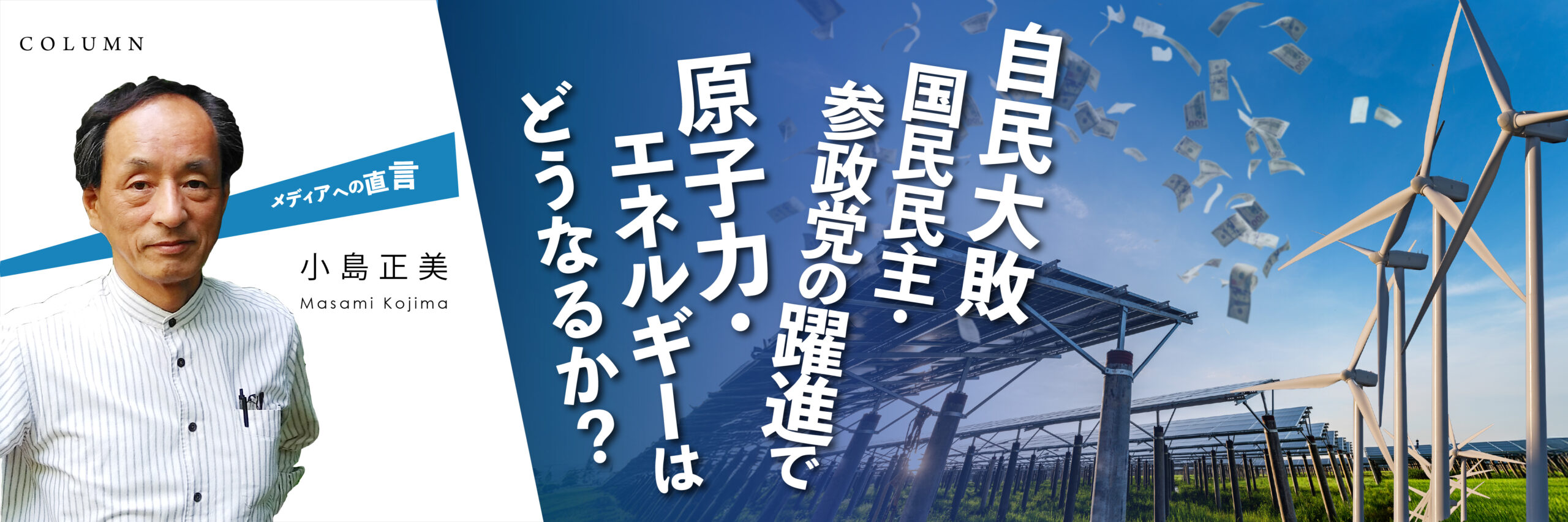自民大敗 国民民主・参政党の躍進で原子力・エネルギーはどうなるか?
二〇二五年八月十二日
七月の参議院議員選挙で自民党が大敗し、国民民主党と参政党が大きく躍進した。この結果は原子力や太陽光など再生可能エネルギー問題にどう影響するのだろうか。「原子力を最大限活用する」としていた自民党が負けたことで原子力に逆風が吹くかと思いきや、意外にも原子力には追い風が吹いたといえる。その理由は?
原発賛成の政党が
約七割の票を獲得
参院選で最も躍進したのは、一議席から十四議席(選挙区七人、比例区七人)に急伸した参政党だろう。その急伸ぶりを見せつけたのが比例区での得票数だ。自民党(約一二八一万票)、国民民主党(約七六二万票)に次ぎ、第三位の約七四三万票を獲得した。前回(二〇二二年の参院選では約一七七万票)に比べ、四倍以上の伸びだ。この約七四三万票は立憲民主党(約七四〇万票)をも上回り、公明党(約五二二万票)、日本維新の会(約四三八万票)を大きく引き離した。
どの政党が原子力の必要性を認めているかについては、前回のコラムでも述べたように、自民党、公明党、国民民主党、参政党、維新、日本保守党の六党は原子力の推進に理解を示す(公明党は自民党に比べると消極的な賛成だが)。これに対し、立憲民主、れいわ新選組(約三八八万票)、共産党(約二八六万票)、社民党(約一二二万票)の四党は原発の推進に反対だ。そこで、今回の比例区の政党別の得票数を足して、原発推進派と反対派の割合を比べてみた。すると、原発推進の六党の合計得票数は約七割、反対の政党は約三割となった。もちろん、有権者がどこまで原子力を意識して一票を投じたかは分からないが、結果的にみれば、約七割の有権者が原発を推進する政党を選んだことになる。
参政党は再エネ賦課金廃止
あらためて原子力・エネルギー関係に関する参政党の公約を見てみよう。公約は主に二つあり、ひとつは「次世代型小型原発や核融合など新たな原子力活用技術の研究開発を推進する」。もうひとつは「高コストの再生可能エネルギーを縮小し、FIT(電気の固定価格買取制度)、再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金=再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が買い取るときの費用を国民が一部負担するもの)を廃止する」。この公約を私なりに解釈すると、電気代が高くつく太陽光や風力発電を縮小し、年間二兆円以上もの国民負担を強いている再エネ賦課金を廃止する。そして、原子力の再稼働を早め、原子力の利点を活用していこうという政策だ。
七月の選挙戦では原子力やエネルギー問題はほとんど争点にならなかったが、参政党の議員は以前から国会の質問で再エネ賦課金の廃止を訴えてきた。このスタンスは、再生可能エネルギーの推進を訴えてきた反原発の立憲民主党とはかなり異なる。参政党に一票を投じた有権者が参政党の原子力政策をどこまで理解していたかは分からない。だが、参議院で得た十四議席は、予算を伴わない法案を単独で提出することを可能にするだけに、今後の政策展開は大きな関心を浴びるだろう。
参政党は大手メディアの批判をはねのけて躍進
参政党の躍進で特筆すべきことは、大手新聞やテレビの批判をかわして勢力を拡大したことだ。たとえば、参政党の神谷宗幣代表は参議院選挙の第一声の街頭演説で「高齢の女性は子どもは産めない」と発言し、リベラル系新聞やテレビから一斉に批判を受けた。
また、選挙戦中の七月十二日、TBS「報道特集」は参政党の主張は外国人排斥運動やヘイトスピーチを誘発していると批判。さらに同番組ではアナウンサーが「これまで以上に想像力をもって、投票しなければいけないと感じています」と参政党の勢いをけん制するかのような主張を述べた。これに対し、参政党は「公平性、中立性を欠く」と強く抗議し、TBSも「有権者に判断材料を示すという高い公共性、公益性がある」と反論するなど、双方の対立はいまも続いている(デイリー新潮・七月三十一日オンライン参照)。
これまでなら、大手マスコミから猛批判を受ければ、有権者の支持を失い、選挙では不利になるはずだが、そうはならなかった。参政党は次々にSNSで動画を発信し、「マスコミは事実を切り取って報じている。日本の六〇〇兆円のGDPをまず日本国民のために使う。これが自国民ファーストだ。そこの何が問題なのか」と切り返していった。SNSを見る限り、参政党を推す声のほうが圧倒的に強いと感じた。ここで強調したいのは、リベラル系の大手テレビや新聞(番組によってはNHKも)が一斉に参政党への批判を繰り広げたにもかかわらず。参政党がその批判をはねのけて躍進したことだ。既存の大手メディアの影響力が低下していることをまざまざと見せつけられた一幕だった。
国民民主党は
原発推進で勝利
一方、十七議席を獲得した国民民主党は二〇二二年参院選の二倍を超す七六二万票を得て自民党に次ぐ二位の躍進を見せた。その結果、非改選と合わせて、二十二議席を確保、予算をともなう法案(参議院では二十議席が必要)を単独で提出する力を得た。
すでに多くの方がご存じのように、国民民主党は二四年秋の衆議院選挙のときから原発の積極的な推進を公約に掲げているが、有権者からの支持は増えている。以前は選挙で「原発を推進します」と言うと票が減ってしまうため、「原発推進」は選挙に不利な言葉として定着していたが、それを見事にひっくり返したのが国民民主党である。その存在意義は大きい。
一方、日本保守党はエネルギー関連で「再エネ賦課金の廃止」「エネルギー分野への外国資本の参入を禁止する法整備」「わが国の持つ優れた火力発電技術の有効活用」を公約にし、二議席を獲得した。
日本保守党の島田洋一・衆議院議員(福井県立大学名誉教授・国際政治学者)は二四年十二月に提出した石破内閣のエネルギー政策に対する質問主意書で「原子力発電所は発電量当たりの人命リスクがもっとも低い電源であり、燃料の輸入が途絶えた場合でも約三年にわたり発電を続けることができ、エネルギーの安全保障として重要だ」などと述べており、日本の高効率の石炭火力発電所の持続・発展にも高い理解を示している。
興味深いのは、国民民主党、参政党、日本保守党の3党とも「再エネ賦課金の廃止」を訴えていることだ。私はこれまでにも太陽光や風力への過剰な期待(幻想)が反原発運動を支えていると書いてきたが、新たに国会の舞台にニューフェイスとして登場してきた国民民主党、参政党、日本保守党は再生可能エネルギーに過剰な期待を寄せていない。これに対し、自民党には「再生可能エネルギー普及拡大議員連盟」(柴山昌彦会長)があり、太陽光や風力などへの期待を抱く議員たちがたくさんいる。しかも洋上風力発電事業をめぐる汚職事件で秋本真利元衆院議員が起訴(秋本氏は無罪を主張)されるなど、議員と事業者に利権がらみのイメージもあるせいか、国民に良い印象を与えているとはいいがたい。
原発は
より推進されるのか?
日本経済新聞は選挙が終わった七月二十一日、「与党が大敗し、自公政権の土台は揺らぐが、原子力発電の推進策は維持されるとみられる。議席を伸ばした国民民主党は原発の新増設、参政党は次世代型原発への研究開発を掲げており、原発の推進には前向きな姿勢を示す」と報じた。
自民党が負けたものの、原発推進の国民民主党と参政党が躍進したことで原子力発電の推進策は維持されるという判断だろうが、「維持される」というよりも、むしろ「より推進力が増した」と解したい。原発を推進する力は、再生可能エネルギーに過剰な期待を抱いていない国民民主党、参政党、日本保守党の三党のほうが強いからだ。
今後、三党が国会の場で、原子力政策と再生可能エネルギー政策でどのような言動を見せてくれるのか、注視していきたい。