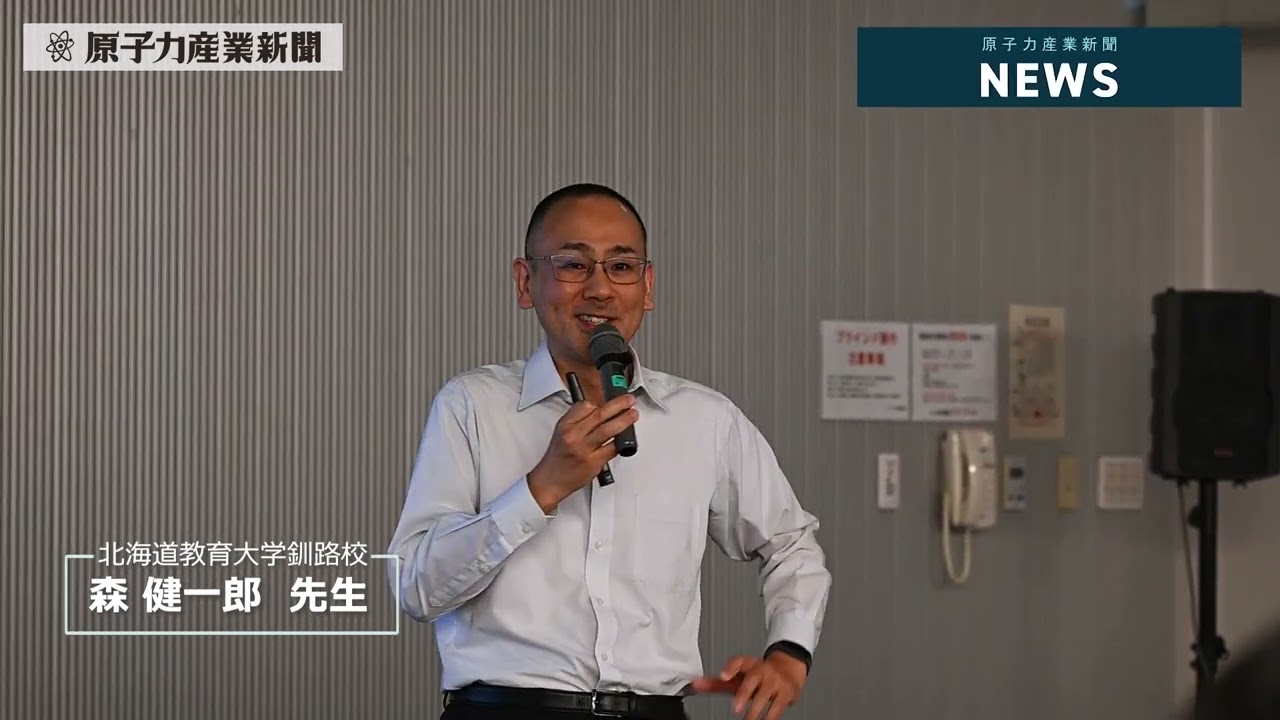盛岡で勉強会
― 学習指導要領とエネルギー・放射線教育の最前線
26 Sep 2025
岩手県盛岡市内において9月21日、静岡大学の大矢恭久教授らが企画した「STEAM教育手法を活用し、エネルギー・環境問題を基盤とした原子力人材育成 2025年度夏 勉強会」が開催された。文部科学省国際原子力人材育成イニシアティブ事業の一環。対象は小中高の理科教員を目指す教育学部の学生および大学教員であり、文部科学省や大学研究者による講義を通じて、中学校理科における放射線教育、エネルギー環境教育、そしてSTEAM教育のあり方について専門的な議論が交わされた。
文部科学省国立教育政策研究所の神孝幸先生は、「中学校理科における放射線教育の可能性 ~現場の実践から考える~」をテーマに講義した。神先生は、広島市での放射線教育実践例として、霧箱を使った2本の授業動画を比較しながら、効果的な授業展開のあり方について詳しく解説した。
1本目の動画は、広島市美鈴が丘中学校での理科の授業であった。この授業では、霧箱を提示して放射線の観察を行ったが、生徒たちは平和学習で培った放射線に関する知識から、原子爆弾や放射線の危険性といった社会科学的なアプローチで思考が展開された。神先生は、この授業では「理科らしい展開にはならなかった」と振り返った。
2本目の動画は、同じ学校での総合的な学習の時間の授業であった。この授業では、霧箱の観察から始まり、最終的にシーベルトの単位や品種改良、ポテトチップスの製造過程での放射線利用など、理科的な身近な利用について生徒たちの思考が向けられた。神先生は「こちらの方が理科らしい展開になった」と評価した。
神先生は、この2つの授業の違いを通じて、同じ教材を使っても授業の枠組みや教師のアプローチによって生徒の思考の方向性が大きく変わることを示した。特に、広島という地域の特性(平和学習の影響)を踏まえながら、理科教育として適切な方向に生徒の思考を導くことの重要性を強調した。
中央大学理工学部の栢野彰秀先生は、「本勉強会が意図するエネルギー環境教育 / 学習指導要領がめざすエネルギー環境教育」をテーマに講義した。栢野先生は、SDGs(持続可能な開発目標)の背景にある1987年の国連での持続可能な開発の考え方について説明し、ブルントラント報告書[1]「環境と開発に関する世界委員会」が1987年に公表した報告書「Our Common … Continue readingの内容を引用しながら、「エネルギーと環境はセットである」ことを強調した。そして、学習指導要領の大きな変化について「見方・考え方がゴールなのか、それとも見方・考え方を授業の中で発揮させるものなのか、これは大きな違い」と説明し、「目的が手段になった」と指摘。また、現行の学習指導要領は「内容(コンテンツ)中心」から「資質・能力(コンピテンシー)中心」への転換であり、小中高の全教科で探究学習が導入されていることを指摘した。
エネルギー環境教育については、「エネルギーの教育」(エネルギーそのものの概念理解)と「エネルギーについての教育」(エネルギー資源の保全や省エネ、再生可能エネルギー、原子力などを扱う)の二層構造で捉えることが重要であることを説明した。また、科学的プラクティス(第1~6単元)と工学的プラクティス(第7単元)を使い分ける必要性について詳しく解説し、STEAM教育の要素を指導案に組み込む具体的な方法についても言及した。
北海道教育大学釧路校の森健一郎先生は、「STEAM教育とエネルギー環境教育 ―『見方・考え方』に着目して―」をテーマに講義した。森先生は、STEAM教育の視点からエネルギー環境教育を再考し、「見方・考え方」に着目した授業設計と評価の重要性を説いた。特に印象的だったのは、過去に中学校で実際に使われていた「水からの伝言」という道徳教材についての言及である。
森先生は、当時中学校教員として勤務していた際に、この教材が道徳の授業で大真面目に使われていた経験を語った。「水に『バカ野郎』と言って凍らせると結晶が汚くなり、『可愛いね』や『ありがとう』という綺麗な言葉を話しかけて凍らせると綺麗な結晶になる」という内容の教材で、文化祭の意見発表でこのテーマについて話した生徒が最優秀賞を取って市の大会に出場したという。森先生は「なぜ止めなかったのか」と自問しながらも、当時の状況では受け入れられていたことを振り返った。
この経験を通じて森先生は、教材の良し悪しを見分ける力の重要性を強調した。科学的根拠のない教材が教育現場で使われる危険性を指摘し、STEAM教育の視点から正しい科学教育を実践することの大切さを訴えた。特に、放射線教育においても「正しく怖がる」ことの重要性を説き、根拠のない恐怖ではなく、科学的な理解に基づいた判断力の育成が不可欠であることを強調した。
神先生の講義後の質疑応答では、参加した学生たちから実践的な質問が相次いだ。カリキュラムマネジメントに関する質問として、「教科横断という言葉だけが先走りして、教科横断の要素が入った指導案を作って満足してしまう場面が多いが、実際に良い実践が行われた後の先生たちの話し合いやカリキュラムマネジメントの現状はどうなのか」という具体的な疑問が寄せられた。神先生は、授業の目的について「子どもたちが考えるきっかけができれば十分であり、必ずしもゴールを示す必要はない。考えるきっかけとなって、次の授業や評価、学習段階でいつか答えが出てくればよい」と回答した。また、「カリキュラムマネジメントも重要だが、教科横断に欲張るよりは、本時で子どもたちに何を身につけさせたいのかを明確にし、その目標に到達できたかどうか、できなかった場合はどこを改善すべきかを、まず自分の教科で解決することが重要」と助言した。
今回の勉強会は、小中高の理科教員を目指す教育学部の学生にとって、学習指導要領の背景にある考え方を理解し、今後の教育現場での指導に活かす重要な機会となった。特に、理論と実践の橋渡しとなる具体的な指導法について、三人の講師から多角的な視点が提供された。エネルギーや放射線といったテーマは、社会的にも関心が高く、誤解や感情的議論を招きやすい領域である。だからこそ、教育の現場で「見方・考え方」を養うことが、次世代の科学的リテラシーを育むカギとなる。
参加者からは「学習指導要領の変革について、これまで漠然と理解していた部分が明確になった」「STEAM教育の具体的な実践方法が分かり、指導案作成への意欲が高まった」「現場での実践に向けて、継続的な学習の必要性を実感した」といった声が寄せられた。今後、放射線教育に関する教師のリテラシー向上や、エネルギー環境教育とSTEAM教育の統合による新しい教育モデルの確立が課題となる。今回の勉強会は、これらの課題に取り組む人材育成に向けた重要な一歩となった。
脚注
| ↑1 | 「環境と開発に関する世界委員会」が1987年に公表した報告書「Our Common Future」のこと。同委員会の委員長を務めたのが、当時ノルウェー首相だったG.H.ブルントラント氏だったため、こう呼ばれる。 |
|---|