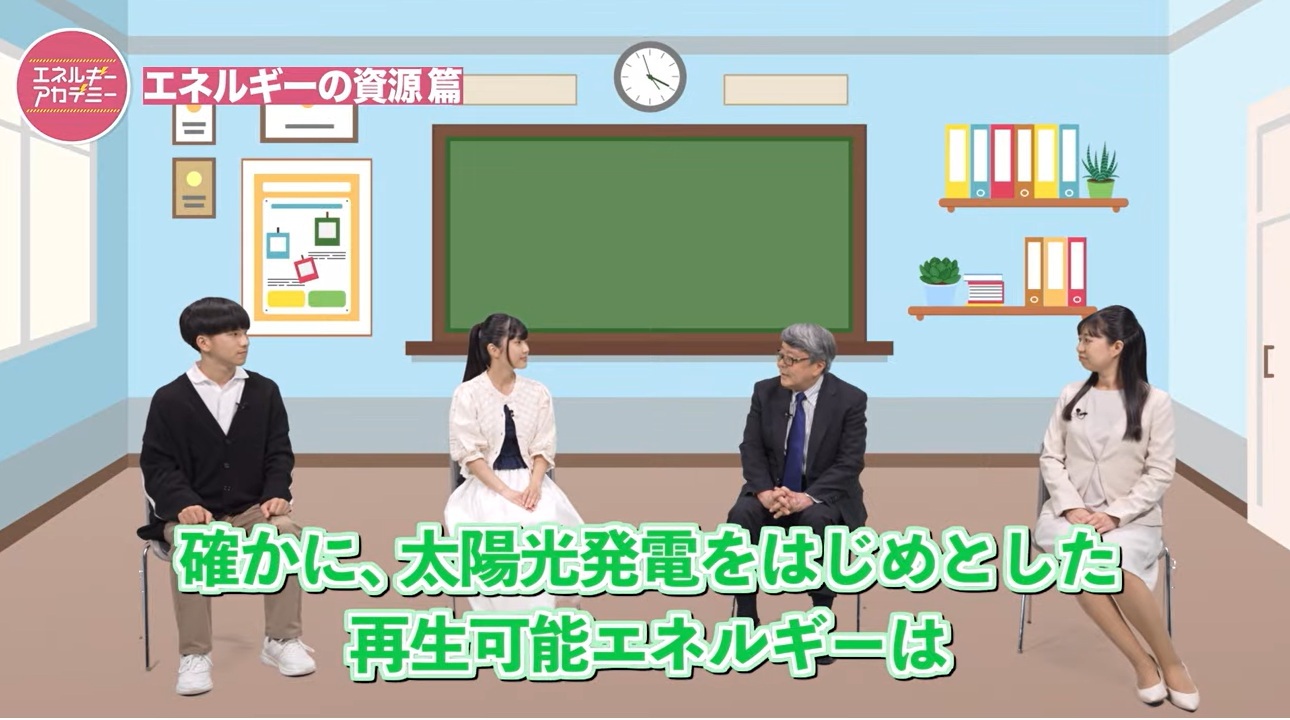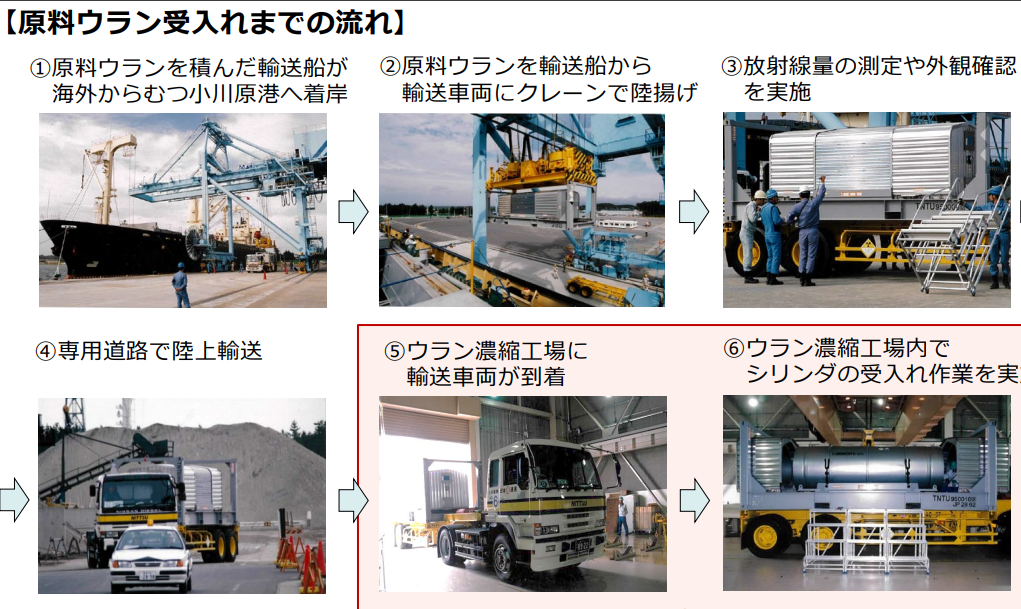サイクルをテーマに専門知と市民意思の“接続”を議論
17 Sep 2025
JST/RISTEXプロジェクトの成果報告に合わせ、9月16日に都内で開かれたシンポジウムでは、「専門知の多様性」と「市民の意思」を核に、原子力政策を社会にどう実装するかが議論された。政策選択と技術選択の峻別、評価軸の偏り、市民参加の設計――浮かび上がったのは、専門知と市民意思をつなぐ「接続の設計指針」だ。
本シンポジウムは、科学技術振興機構(JST)・社会技術研究開発センター(RISTEX)の第3期研究開発プロジェクト「原子燃料サイクル政策の受容に対する熟議的アプローチ」の成果発表を兼ねて開催された。原子燃料サイクルは高度な科学技術政策の象徴であり、限られた専門家と政策当局の間で決定が進められる傾向が強い。そのため、多様な知見や市民意思を政策に反映させることが難しいという課題が指摘されてきた。午前は研究成果の報告、午後は有識者によるパネル討論という構成で、政策形成の新たな枠組みが議論された。
午前の部では、研究プロジェクトの成果報告が行われた。社会科学グループ(報告者=林嶺那・法政大学教授)、自然科学グループ(同=深谷裕司・日本原子力研究開発機構)、政策実装グループ(同=松尾雄司・立命館アジア太平洋大学教授)の三領域での取り組みが紹介され、専門家の多様性、市民との対話、コンジョイント実験による選好調査、AIを活用した情報提供のあり方などが議論された。研究報告はいずれも、午後のパネル討論につながる問題意識を提示した。
午後の部では、村上朋子氏(日本エネルギー経済研究所)がモデレータを務め、4人の研究者が登壇した。
- 鈴木達治郎氏(ピースデポ代表、長崎大客員教授)は、政策選択と技術選択を明確に分けるべきだと強調。「全量再処理」「直接処分」「併存」という三択をまず提示し、その上で技術開発を位置づけるべきだと主張した。また、核不拡散/核セキュリティや費用転嫁のリスクを政策議論に組み込む必要性も訴えた。
- 寿楽浩太教授(東京電機大)は、STS(科学技術社会論)の観点から「政策固着」の構造を分析。AIや原子力における「期待→投資→失望」のサイクル、テクノロジカル・イマジナリー、制度化された無知が重なり、柔軟な政策選択が阻害されると指摘した。プレファレンスを調べる手法を技術選択だけでなく、社会の期待を掘り起こす手法として活用すべきだと提案した。
- 山本章夫教授(名古屋大)は、技術と社会の接続方法として4つのアプローチを提示。政府の強制実行、技術を社会に合わせる、社会を技術に合わせる、対話・調整のうち、理想的なのは「技術を社会に合わせる」だが条件付きだと指摘。遺伝子組み換え技術の例を挙げ、社会の選好に基づく技術調整の可能性を示した。
- 城山英明教授(東京大)は、固着の概念について、原子力政策と原子燃料サイクル政策で意味が異なると指摘。軽水炉は経路依存的な固着、核燃料サイクルはビジョンの固着化だと分析した。また、政策フレーミングの重要性と将来世代の人材育成が最重要課題だと述べた。
討論全体を通じて、政策選択と技術選択の峻別、専門知の多様性の活用、市民参加の設計、第三者機関の必要性など、原子力政策の合意形成を前進させるための具体的な課題が浮き彫りになった。
シンポジウムでは、専門知と市民意思を接続するための具体的な方策が多角的に議論された。政策選択と技術選択の峻別、専門知の多様性の活用、市民参加の設計、第三者機関の必要性など、原子燃料サイクルをめぐる議論はなお揺れているが、合意形成を前進させるための条件は少しずつ見えてきたようだ。