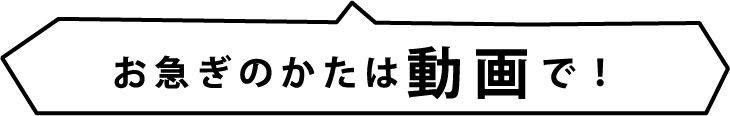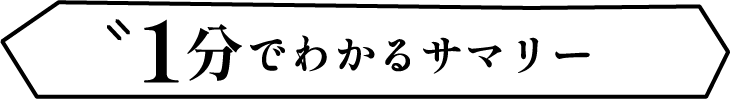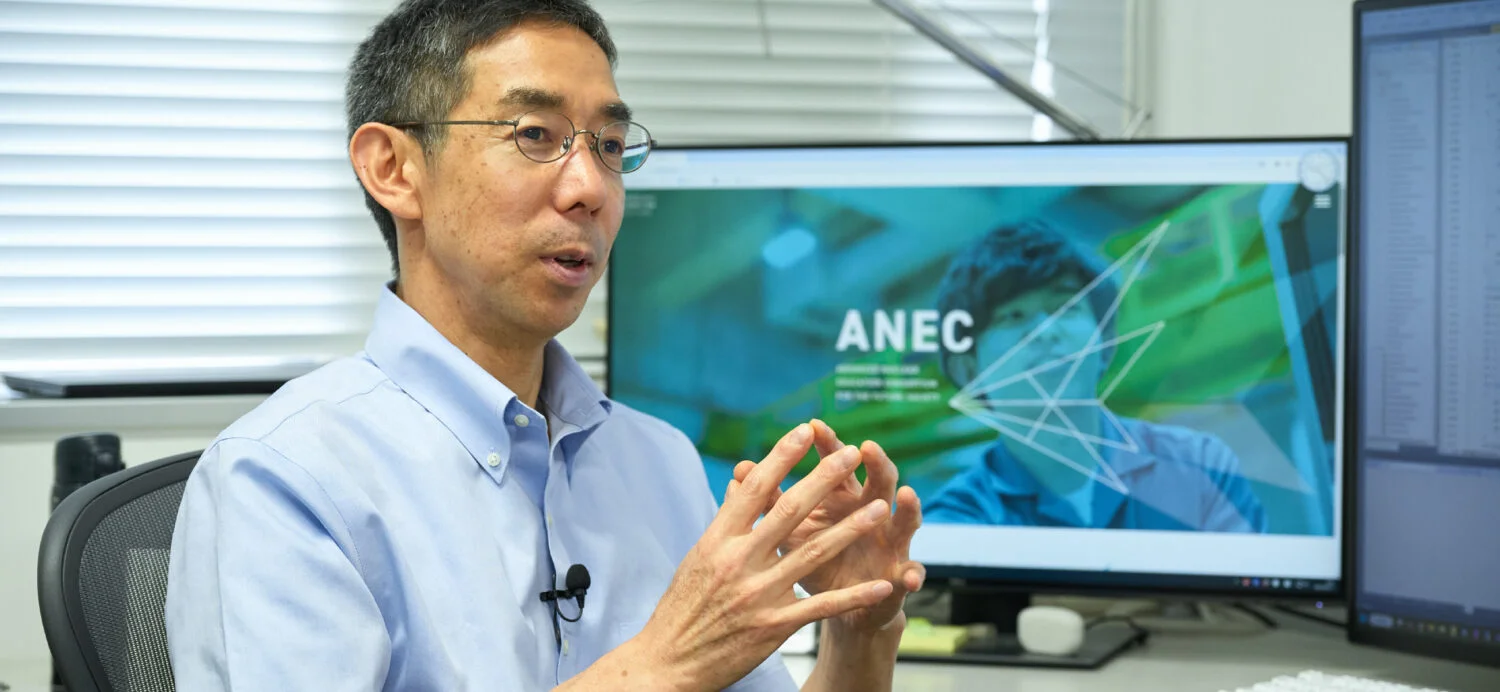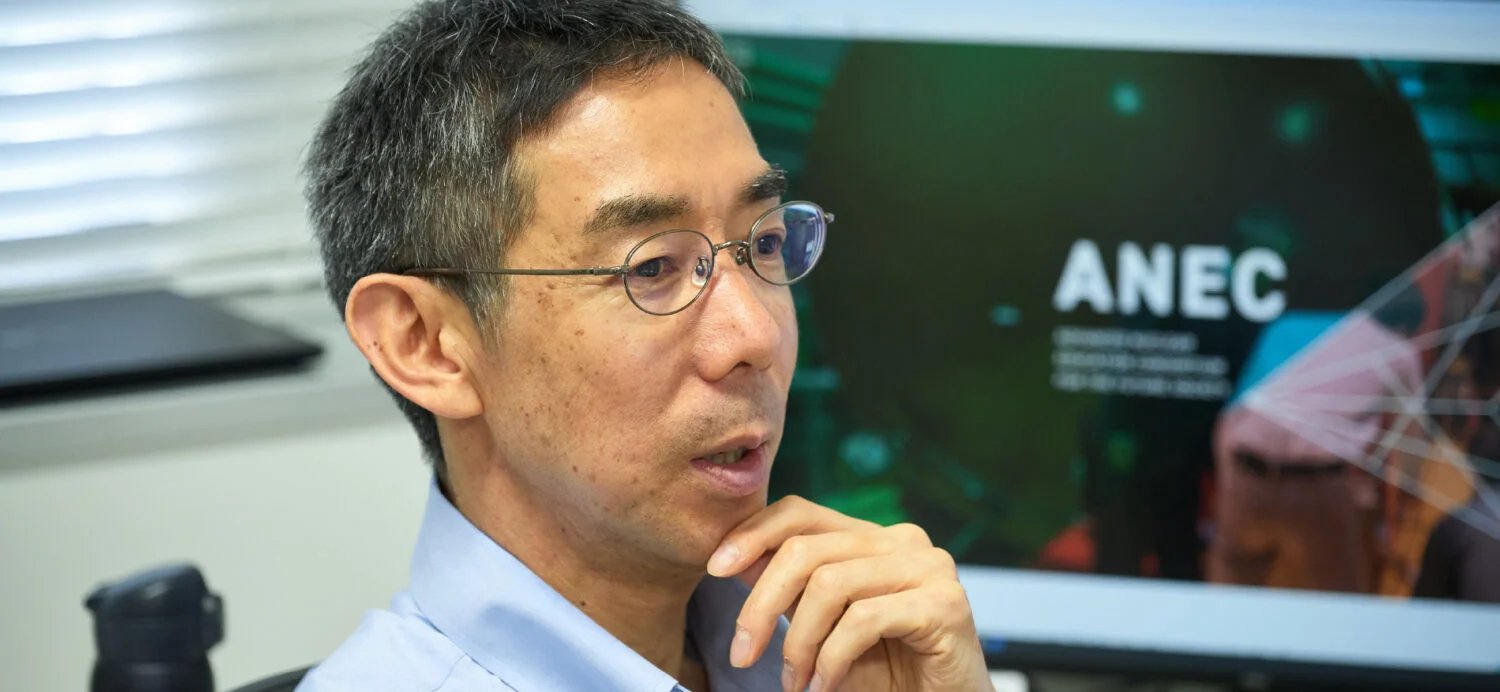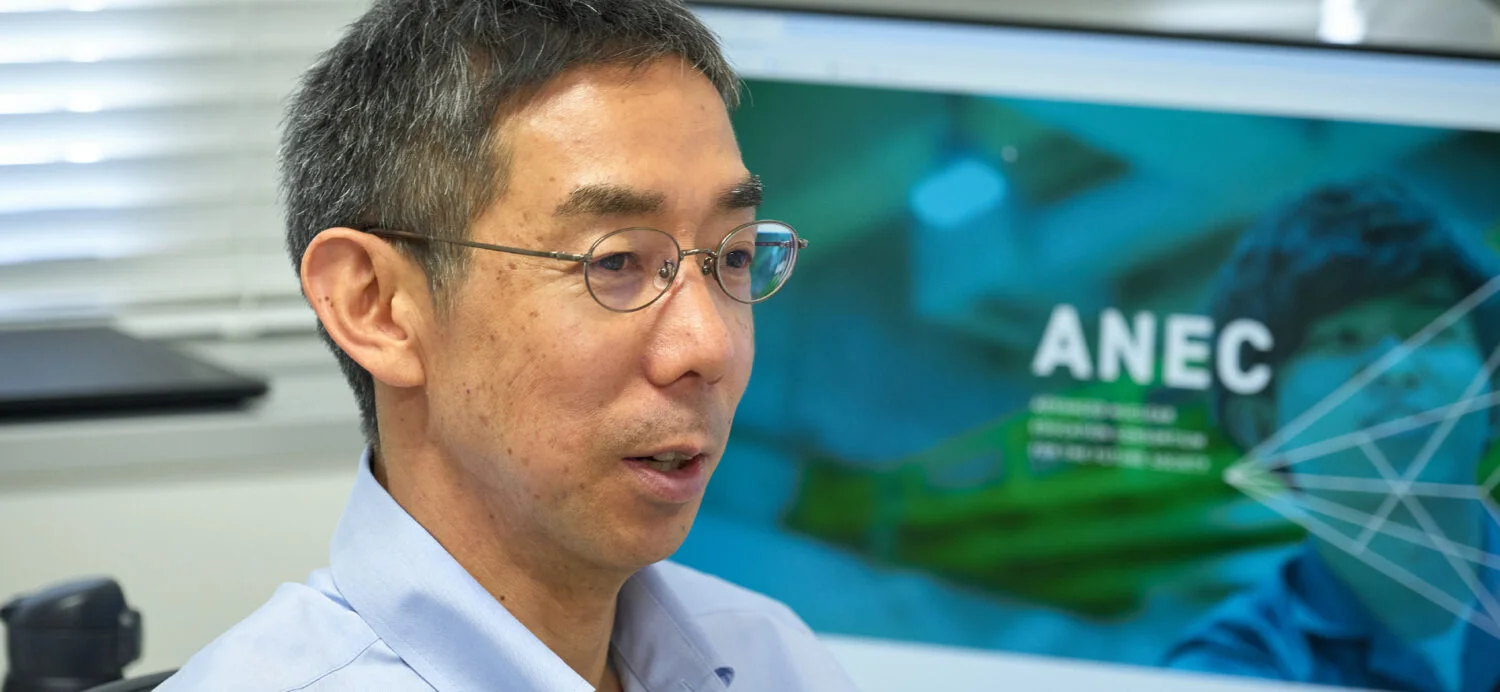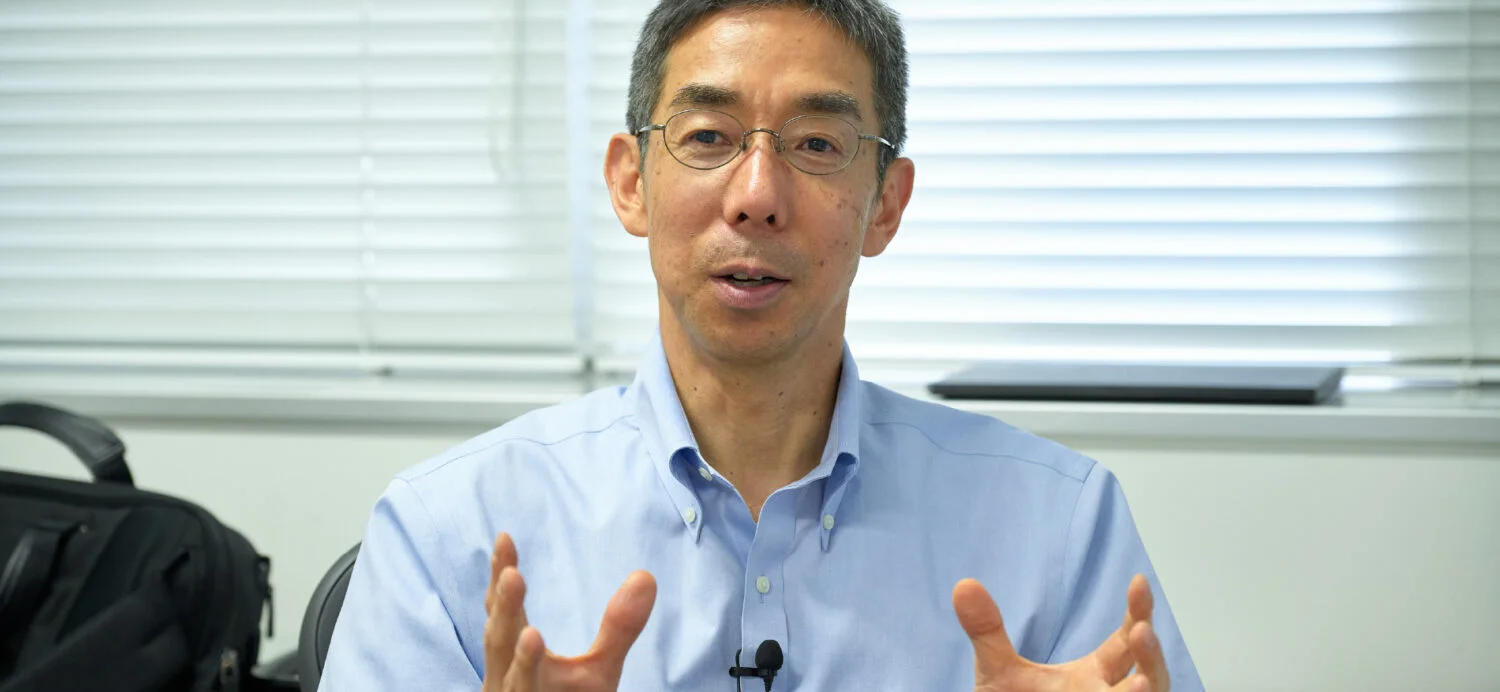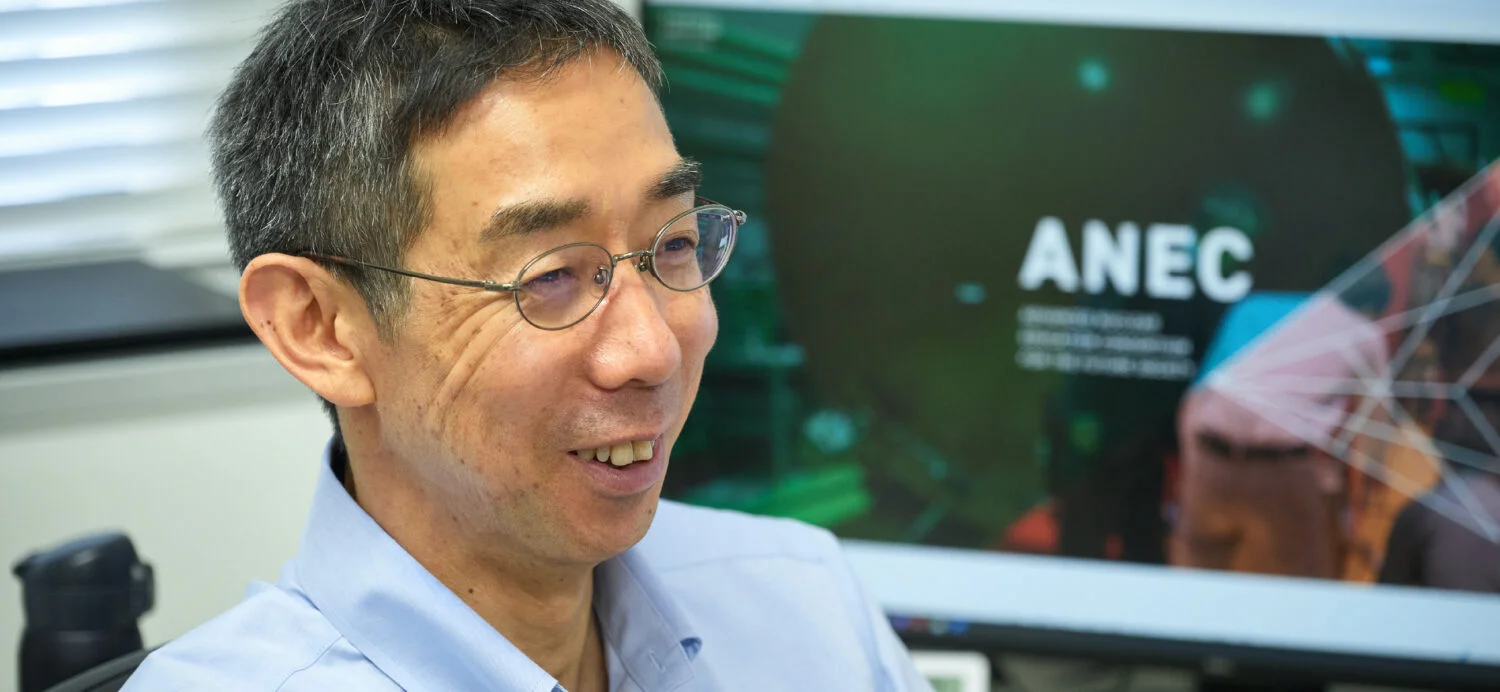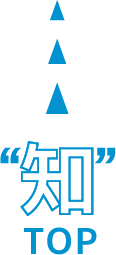山本先生は、ANEC(未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム)のプログラムディレクターとして、原子力人材育成に取り組む。東日本大震災以降、教育基盤の弱体化を背景に、産学官連携で教育リソースを共有する仕組みを構築。1大学ではカバーしきれないカリキュラムを、全国の大学が連携してカバーする体制を整えた。原子力の中核分野に加え、社会科学的視点も統合したカリキュラムを設計し、現場実習や地域連携を重視している。高校生向けオープンキャンパスでは約200名が参加し、進路選択の具体化に寄与した。今後は、技能者と技術者の連携強化、総合的なエネルギー・環境教育への発展を目指す。
炉物理の専門家でありながら、人材育成に注力する理由は「原子力の将来を左右する極めて重要なテーマ」だからである。学生には科学リテラシーと批判的思考の重要性を説き、産学官が一体となった継続的な人材育成の必要性を強調している。
ANEC創設の背景と役割
Q1 ANEC(未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム)創設の背景や目的について教えてください
【山本先生】
ANEC創設の背景としては、原子力分野の人材育成の基盤が弱体化していたことが挙げられます。もともと原子力を冠した学部や学科というのは、昭和期に比べると平成の時代、特に1990年代以降には減少傾向にありました。平成の原子力ルネッサンスの時期に復活・新設したところもあるのですが、東日本大震災後はさらに状況が深刻化しました。原子力関連教育を行う教員の高齢化や若手教員の不足など、専門的な教育を維持することが困難になってきていたわけです。
恥ずかしながら私ども名古屋大学でも、学内で原子力分野の全分野の教育をカバーすることが出来なくなっていました。一般に「原子力分野の教育」と言いますと、社会学的要素まで入り裾野が広いのですが、ここでいう原子力分野の教育とはまさに、原子力技術そのものの中核的分野のことです。燃料工学や炉物理などが、気が付くと全国的に絶滅危惧種になっておりました。もはや全国的に、単一の大学や研究機関だけでは、十分な教育を行うことが難しくなっていたのです。そのため、全国の大学/研究機関/産業界が協力して、人材育成機能を維持・強化する仕組みが必要になりました。
そこで文部科学省の「国際原子力人材育成イニシアティブ事業」の下で、2021年度に設立されたのがANEC(未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム)です。
ANECの主な目的としては、原子力を中心としつつ、多様なエネルギーの俯瞰的な理解を促し、持続可能な社会の実現に貢献する人材を育成することです。産学官が協力し、それぞれの強みを生かした教育プログラムや実習を提供することで、次世代を担う質の高い人材を効果的に育成していくことを目指しています。
具体的には、大学/研究機関/産業界が保有する教員、カリキュラム、実験装置、設備といった教育リソースを相互補完し合うことで、国内の原子力教育基盤の強化・維持を図っています。また、「専門教育の共用」「大型実験施設での実習・インターン」「国際研鑽機会」「産業界・他分野との連携」を4本柱として展開し、国内外の多様な視点と実践経験に裏打ちされた質の高い教育プログラムを提供しています。
Q2 ANECのプログラムディレクターとして特に注力された点や、具体的な役割について教えてください
【山本先生】
まず、本プログラムに参加していただき、事業をしっかり推進していただいている皆さんに感謝申し上げたいと思います。皆さんのご協力なしには進まない事業なので、参加者が熱意を持って取り組んでいただいていることを大変ありがたいと思っています。
プログラムディレクター(PD)として私が特に注力した点は、まず関係者間で「原子力分野の人材育成が直面する現状と課題に対する認識を共有すること」でした。関係する大学や研究機関、産業界の皆さんが、それぞれ異なる背景や考え方を持っている中で、現状の課題や危機感を明確に共有してもらうことが、円滑な連携や協働体制を作るためには不可欠だったからです。
具体的な役割としては、各大学や企業が提案する教育プログラムやカリキュラムを評価し、全体として抜けや漏れがないようにバランスよく調整する役割を担いました。例えば、原子炉工学や核燃料工学、放射線利用、さらに社会科学的な要素など、幅広い領域を網羅したカリキュラム設計になるように配慮しました。
また、実習プログラムや企業との連携プログラムなどについても、それぞれの機関の強みを最大限に活かせるよう調整を行いました。大学ごとに設備や専門家が限られる中で、相互に施設や教育資源を補完し合えるような連携体制を整えました。
これらを通じて、プログラムオフィサー(PO)である黒﨑健先生(京都大学複合原子力科学研究所所長)と共に、ANECとして全国規模で一貫性のある質の高い教育プログラムを提供できるよう、ディレクターとしての役割を果たすよう、務めてきたつもりです。
Q3 山本先生は炉物理の第一線でご活躍される研究者でいらっしゃいますが、なぜ人材育成に注力されたのですか?ご自身の研究が止まってしまう等の御心配はなかったのですか?
【山本先生】
私はもともと炉物理を専門としてきましたし、研究者としては原子炉物理や安全技術の最前線で活動してきました。ただ、東日本大震災以降、新規制基準の策定や安全性向上など、原子力分野全体に関わる仕事をする機会が増えたことで、私自身も原子力分野を支える人材の重要性や、大学での人材育成基盤が弱体化している現状に対して強い危機感を持つようになりました。
研究活動との関係についてですが、確かにこうした活動には一定の時間と労力が必要ですから、個人として研究の時間が多少影響を受けることはあります。ただ、私自身は原子力安全や人材育成という課題は、原子力の将来を左右する極めて重要なテーマであると考えており、そこに自分が貢献することが研究者としての責務の一つであるとも感じています。
また、こうした活動を通じて、業界や社会との接点が増えることで新たな研究課題を発見したり、産学連携を通じて新しいアプローチが見つかることもあります。むしろ研究活動との相乗効果がある面も感じていますので、人材育成に注力することを躊躇するような心配はありませんでしたね。
ANECの教育プログラム設計方針
Q4 原子力だけでなく再生可能エネルギーなど多様な要素が含まれていますが、どのようにカリキュラムのバランスを設計されていますか?
【山本先生】
ANECのカリキュラム設計については、基本的に各大学や研究機関が自主的に提案してきた内容をベースに構築しています。私たちプログラムディレクター、プログラムオフィサーや採択にあたっていただいている評価委員会などが、そうした各大学から出てきた多様な提案を全体として俯瞰し、「原子力分野を抜けることなくバランスよくカバーできているか」「再エネや社会科学的要素なども含め、総合的な視野で整合性が取れているか」という観点から評価・調整してきました。
こちらから一方的に「この分野をカバーしてください」といった形で依頼をしていません。あくまでも各大学が自発的に手を挙げて頂いた提案を基に、それらを最適な形で組み合わせ、抜け漏れができるだけないように最終的なカリキュラムを構築しました。
まず基本的な考え方として、「原子力の中核となる分野をしっかりカバーすること」を目標としました。さらに、原子力だけでなく再生可能エネルギーや脱炭素社会に向けた幅広い視点なども盛り込み、それらをバランスよく統合する必要があると考えました。
具体的な設計にあたっては、原子炉工学や炉物理、燃料材料、放射線計測、サイクル・処分などの原子力の中核的な専門分野を軸に置きつつ、それに加えて再エネやカーボンニュートラル、さらには社会科学的な視点も入れています。
こうした設計において工夫したのは、各大学が得意な分野や既に持っている施設や教材を積極的に活用し、足りない分野についてはオープン教材などを整備して、各大学や機関で共有できるようにしたことです。オンライン教材についても、学生が場所や時間を選ばずに自由に学べる環境を整えるために幅広く取り入れました。
また、実践的なフィールドワークや現場実習を取り入れることで、座学だけでは学べない現実の課題や実務に近い経験を得る機会を提供しています。このような仕組みにより、理論と実践、専門性と幅広い視野を兼ね備えた、バランスの良い教育カリキュラムを作り上げています。
Q5 フィールドワークや地域連携をプログラムに盛り込んだ理由や、狙いについて教えてください
【山本先生】
フィールドワークや地域連携をプログラムに盛り込んだ大きな理由としては、やはり学生たちが教室内の学習だけでは得られない「現場感」や「リアルな課題」を学んでもらうことにあります。
原子力分野というのは、単なる科学技術だけでは解決できない社会的課題や地域の理解・協力が必要不可欠な分野です。例えば高レベル放射性廃棄物の処分問題、あるいは原子力施設を立地する地域の住民との関係性など、科学技術だけでは簡単に答えが出ない課題が多々あります。
そこで、学生が実際に現場や地域に足を運び、地域の方や企業・自治体の方と直接意見交換することで、多様な視点を持ち、コミュニケーション能力を養ってもらう狙いがあります。また、このような取り組みを通じて、エネルギー問題を俯瞰的に捉える力を育てることも重要な目的です。
こうした現場体験や地域連携を通じて、学生たちがよりリアルな社会課題に対応できる力を身につけ、原子力を中心としたエネルギー問題に対して幅広い視野と深い理解を持つ人材として育ってほしい、というのが私たちの一番の願いです。もちろん対話の場について学ぶ講座も用意しています。
view more 2/3
「産学官連携とその成果」
産学官連携とその成果
Q6 大学・企業・研究機関との協働体制を構築・運営する際、特に工夫された点や苦労された点をお聞かせください
【山本先生】
産学官連携の協働体制を作る上で特に工夫した点は、まず「価値観と課題意識の共有」でした。各大学、企業、研究機関それぞれが異なる背景や考え方を持っている中で、原子力分野の人材育成が抱える課題やその重要性を明確に共有し、理解してもらうことにかなりの時間とエネルギーを注ぎました。
また、役割分担や連携の仕組みについても工夫をしました。各機関が自発的に提案してくれた教育プログラムをもとに、それぞれの強みを最大限に引き出しつつ、全体として抜け漏れのない体系的なカリキュラムや実習体制を作るために調整や調和を図ることが必要でした。そのために、密なコミュニケーションや議論を重ねて進めていきました。
一方で苦労した点としては、やはり異なる組織間での調整や、教育内容・プログラム設計に対する考え方の違いを埋めていくことです。教育に関しては、それぞれがこだわりや独自の視点を持っていますので、全体の整合性を取ることは、現時点でも苦労しています。
そうした工夫や苦労を通じて、結果的にはANECとしての明確な目的や理念を共有した産学官連携の体制を構築できたと思っています。もちろん、要改善事項は多数あり、継続的に改善に取り組んでいます。
なお、官の役割としては、文部科学省が資金提供や政策的枠組みの構築という形で後押しをしてくださり、産学の取り組みを支援してくださっています。国として、このような形で原子力人材育成の重要性を認識・ご理解いただき、しっかり支援いただいているのは大変心強いです。
Q7 ANEC開始以降、参加した学生や連携先企業・地域から得られた具体的成果や反応で、特に印象に残っていることは何でしょうか?
【山本先生】
特に印象深かったのは、企業や地域との連携プログラムでの大学生たちの反応ですね。例えば、三菱重工や関西電力と共同で実施した企業現場での実習では、参加した大学生から「教科書や講義で学んだ理論が実際の現場でどのように活用されているのか、明確に理解できた」「自分の専門分野に対する視野が広がった」という非常に前向きな評価を受けました。
また、地域の方々との交流を取り入れたフィールドワークでは、学生たちが地域の課題や住民の意見を直接聞くことで、「技術だけでなく社会的な側面の重要性を実感した」「エネルギー問題への関心や理解がより深まった」という感想を多く寄せてくれました。
こうした成果を通じて、産学官が連携したプログラムの効果を実感し、私たちが目指している「多様な視点を持ち、現場感覚を兼ね備えた人材育成」という目的が着実に実現されつつあると感じています。
次世代層へのアプローチ
Q8 高校生を対象としたオープンキャンパスも実施されたそうですね?
【山本先生】
はい。2023年に近畿大学で試行的に実施しました。昨年は、東京工業大学(現 東京科学大学)で開催したオープンキャンパスには、約200名の高校生が参加しました。受け入れ側の企業や大学はポスターセッションを準備し、高校生たちにアピールしていました。
高校生向けのオープンキャンパスを実施した目的としては、主に次のようなことがあります。
まず一つ目は、原子力分野を将来のキャリアとして選択する可能性を高校生に示すことです。現在、原子力工学科という名前を冠した学部が少なくなっているため、高校生から見ると、どこで原子力を学べるのかが非常にわかりにくくなっています。こうしたオープンキャンパスを通じて、「原子力を学べる大学や研究機関がしっかり存在していること」を伝えることで、進路選択の際の具体的な道筋を提示したいという狙いがありました。
二つ目は、原子力やエネルギーの問題を、学校での座学ではなく、実際の研究現場や実験設備を通じて体験的に学んでもらい、関心を深めてもらうことです。原子力に限らず、エネルギー問題を身近に感じ、多角的な視野を持ってもらいたいという意図がありました。
さらに三つ目として、高校生同士が交流することで、自分と同じ興味を持つ仲間が全国にいることを感じてもらい、将来の進路選択や学習意欲を高めてもらいたい、という目的もありました。
Q9 高校生からどのような反応や評価が寄せられましたか?特に原子力分野に対する理解や関心の変化などがあれば教えてください
【山本先生】
高校生からの反応や評価として特に印象的だったのは、「原子力分野が将来の進路選択の一つとして明確に見えるようになった」という声です。実際にオープンキャンパスで原子力の現場や研究施設を見学したことで、「原子力を勉強する場が存在し、それが具体的にどのような内容なのか、実感をもって理解できた」という意見が数多く寄せられました。
また、「高校の物理や科学の授業では抽象的でわかりづらかった原子や放射線の仕組みが、具体的な実験や実習を通じてはっきり理解できた」という声もあり、教科書の知識と現実の問題が結びついたという評価が得られました。
さらに、多くの高校生が口を揃えて述べていたのが、「原子力やエネルギーに興味を持っている同世代の仲間が全国にこんなにいるとは知らなかった」という点です。自分以外にも同じ関心を持つ仲間がいることを知り、それが大きな励みや刺激になったという感想がとても多かったですね。実は私たちもそれを聞いて、大変勇気づけられました(笑)
全体として、オープンキャンパスを通じて高校生の原子力分野への理解や関心が深まり、進路として真剣に考えるきっかけになったことを実感しています。
Q10 高校生向けイベントの経験から、大学生・教員養成プログラムに生かせる学びはありましたか?
【山本先生】
高校生向けのイベントを実施して得られた重要な学びとしては、「リアルな体験を通じた学習の効果の高さ」と「多様な視点や分野横断的な視野を育むことの重要性」ですね。
まず、実際の現場や施設を体験することによって、単なる知識のインプットだけでなく、「具体的な問題や課題に対して自ら考え、学ぶ姿勢」を促すことができると再認識しました。これは高校生だけでなく、大学生や教員養成プログラムでも非常に重要であり、座学だけではなく、現地実習やフィールドワークをさらに積極的に取り入れる必要性を感じました。
また、高校生との交流の中で、「異分野との連携や社会的視点の導入」が極めて重要だと改めて認識しました。特に原子力分野は、科学技術だけでは解決できない社会的課題や倫理的問題を含んでいます。高校生が素朴な疑問や多様な視点から質問を投げかけてくることで、改めて大学生や教員養成のプログラムでも、社会との対話力や総合的な問題解決能力を養うカリキュラム設計が必要であることを感じました。
こうした高校生向けイベントの経験を踏まえて、大学生や教員養成プログラムの内容も、より実践的で社会とつながりを意識したものへと発展させていくことが重要だと考えています。
view more 3/3
「原子力業界における人材育成の視点」
原子力業界における人材育成の視点
Q11 ANECの教育活動を通じて、原子力業界が今後求める人材像についてどのようにお考えになっていますか?
【山本先生】
ANECの教育活動を通じて感じていることは、今後、原子力業界が求める人材像は、従来のような高度な専門知識だけではなく、多様な視点を備え、社会との対話やコミュニケーション能力に優れた人材であるということです。
原子力分野は技術的には非常に高度で専門的ですが、一方で、社会的な課題や地域との調和、エネルギー政策や環境問題といった、幅広い分野と深く関わっています。特に近年では、脱炭素社会の実現という観点から、原子力だけでなく再生可能エネルギーを含めた総合的な視野を持つ人材が強く求められています。
さらに、福島第一での事故以降、原子力分野への信頼回復や社会的理解促進のために、ステークホルダーとの対話力や情報発信力を備えた人材も不可欠となっています。
こうしたことから、今後の原子力業界では、単なる技術的な専門家というよりは、社会とのつながりを理解し、多様な視点から課題解決に取り組むことができる「総合力を持った人材」が求められると考えています。ANECの教育活動も、こうした視点を持った人材を育成することを大きな目標としています。
Q12 産業界に対して、今後の人材育成で期待する具体的な取り組みや改善点はありますか?
【山本先生】
産業界の皆さんには、今後、人材育成の取り組みにおいて、特に次の2つの点を強化していただきたいと考えています。
ひとつ目は、「産学連携の一層の強化」です。現在も企業の現場実習やインターンシップを実施していますが、さらに拡大し、より多くの学生が実際の企業現場や施設での実習や研究開発活動を体験できる機会を作ってほしいと思います。実際の現場を体験することで、座学や理論での学びを具体化し、学生がより広い視野で原子力の現実的課題に取り組む能力を育むことができます。
二つ目は、「業界全体としての人材育成に対する継続的支援と関与」です。ANECとしての取り組みは、最終的には産業界で活躍する人材を育成するためのものです。産業界の皆さんには、この取り組みの重要性を継続的に認識していただき、資金的な支援のみならず、現場スタッフの派遣や共同研究、教育プログラムへの積極的な参画などを通じて、積極的な関与をお願いしたいと思います。
産学連携と業界の継続的な支援が一体となることで、次世代を担う優秀で多様な人材の育成が可能になると考えています。
今後の展望とメッセージ
Q13 ANECは2027年3月で一旦終了となりますが、今後の取り組みや目指す方向性について教えてください
【山本先生】
ANECの文部科学省からの補助事業としての現在の取り組みは2026年度末(2027年3月末)で一旦終了しますが、個人的にはその後もこの取り組みを何らかの形で継続する必要があると考えています。
これまでのANECの活動を通じて、産学官が協働する教育ネットワークとしての基盤が整ってきました。これを単なる一過性のプロジェクトで終わらせず、長期的に維持・発展させていくべきだと考えています。
今後の方向性として考えられるのは、まず、これまで以上に産業界との連携を深めることです。企業現場での実習を拡充したり、教育プログラムの設計や教材開発においても企業とより緊密に協力したりすることで、さらに実践的な教育を提供したいと思っています。
また、原子力施設を安全に利用していくためには、原子力分野だけではなく、機械や電気、化学といった幅広い工学分野やまた、社会科学的視点をより強化し、すそ野拡大、をキーワードとした総合的なエネルギー・環境教育へとプログラムを進化させることも考えています。
具体的な運営体制については、さまざまな政府機関や産業界を含めた多様な関係機関との連携を深めていくことが必要になるでしょう。そうした議論を今後、本格化させていきたいと考えています。
Q14 経済産業省さんのサプライヤー人材育成との棲み分けはあるのですか?
【山本先生】
経済産業省のサプライチェーン人材育成とANECの取り組みは、基本的に対象や役割が異なりますので、棲み分けはなされています 。
経済産業省のサプライチェーン人材育成は、主に「技能者」といわれる、ものづくりの現場を支える技術者の育成が中心で、メーカーや高等専門学校(高専)を主な対象にしていると理解しています。一方、私たちANECは、主に大学や大学院を対象として「技術者」、つまり研究開発や設計、規制対応などの専門性をもった人材の育成に重点を置いています。
ただし、国際的な流れや実際の産業界のニーズを考えると、「技能者」と「技術者」という分類自体が明確に分かれているわけではありません。今後は両者がより連携を深め、一体的に取り組むことも必要だと感じています。
こうした連携 を通じて、双方の強みを活かしながら、より包括的かつ効果的な人材育成体制を築いていきたいと考えています。
Q15 次世代の原子力人材育成を目指す業界や教育現場への、メッセージやアドバイスをお願いします
【山本先生】
原子力の人材育成に取り組まれている産業界や教育現場の皆さんには、改めて感謝を申し上げます。人材育成というのは非常に息の長い取り組みですが、将来の原子力分野を支える大切な活動だと思っています。
産業界の皆さんには、ぜひ現場での実習や体験的な教育に、これまで以上に積極的にご協力いただきたいと思っています。実際の現場を経験することで学生たちは理論と実践の両方を学べますし、それが原子力に対する関心や理解を深めることにつながります。また、業界が抱えるリアルな課題や魅力を、若い世代に直接伝えていただければと思います。
教育現場の皆さんには、従来の専門教育だけでなく、広い視野を持ち、多様な視点から物事を捉えられるような教育を進めていただきたいと思っています。原子力は技術的な分野であると同時に、社会的課題を含んだ分野ですから、社会科学的視点やコミュニケーション能力の育成が非常に重要になってきます。
最後に、次世代を担う学生の皆さんには、ぜひ幅広い視野を持って積極的にチャレンジしてほしいと願っています。原子力に限らず多様なエネルギー問題に関心を持ち、自分たちが将来のエネルギー政策や社会を支えていくんだという意識で学んでいただけることを期待しています。
産学官が一体となって、人材育成に継続的に取り組んでいくことが、原子力分野の明るい未来につながると信じています。一緒に頑張りましょう。
Q16 余談ですが、山本先生は学部1年生を対象に、エセ科学をテーマにした授業をされてると伺いましたが
【山本先生】
はい、そうなんです。私が担当している名古屋大学の学部1年生向けの「基礎セミナー」という授業で、「エセ科学」をテーマに取り上げています。
具体的なやり方としては、学生にいわゆる「エセ科学」や、科学的根拠が不十分とされる話題について、あえてその立場に立ってプレゼンテーションをしてもらっています。たとえば「コラーゲンやマイナスイオンの効果 」といったテーマを学生自身が選んで、それをいかにも説得力があるように主張するわけです。
そして、その発表を受けて、他の学生たちが質問や反論をしながら、「どこが科学的に根拠が不足しているのか」「どのように論理がすり替わっているのか」といったことをディスカッションします。
この授業の狙いとしては、情報が氾濫する現代社会で、学生たち自身が科学的根拠に基づいて物事を判断できる力、つまり「科学リテラシー」を養うことにあります。私自身、原子力分野でもエネルギー政策でも、科学リテラシーの重要性を常々感じているので、こういった授業を通じて学生が科学的な思考や批判的な視点を養ってくれればと願っています。
Q17 学生さんたちよりも私たち中高年の方が怪しい気もします(笑)
【山本先生】
おっしゃる通りですね(笑)。年齢や経験に関係なく、誰もがエセ科学やフェイクニュースに惑わされる可能性があります。特に私たち中高年層は、自分の過去の経験や先入観が邪魔をして、逆に新しい情報を客観的に見ることが難しくなることもありますよね。だからこそ、学生たちと同じように、我々自身も常に科学リテラシーや批判的思考を磨いていく必要があると強く感じています。
こうした「エセ科学」や科学リテラシーの話は、学生だけでなく私たち大人世代にとっても、非常に重要なテーマだと改めて認識しています。