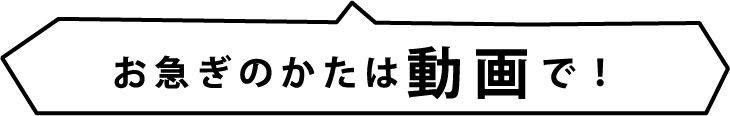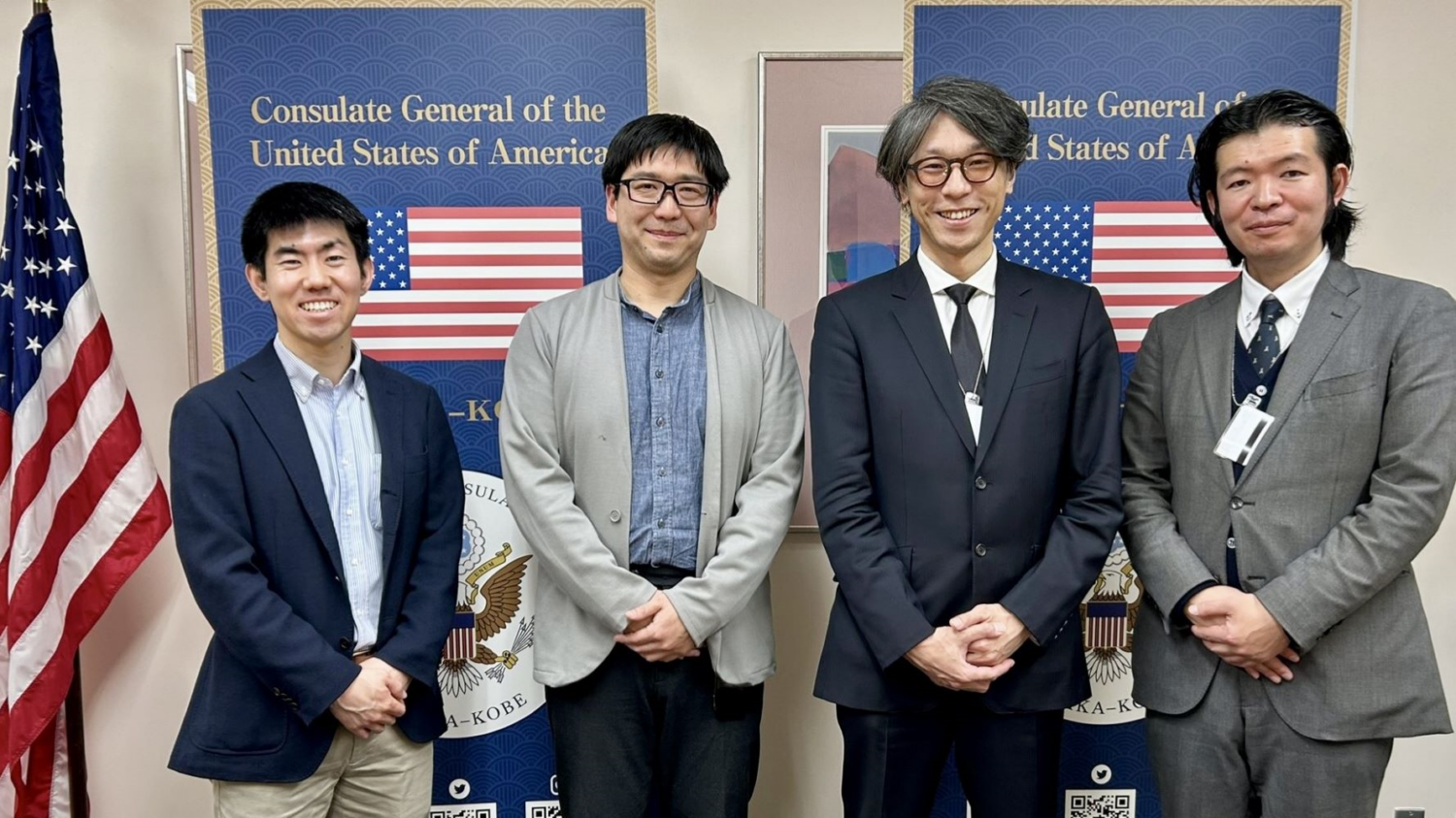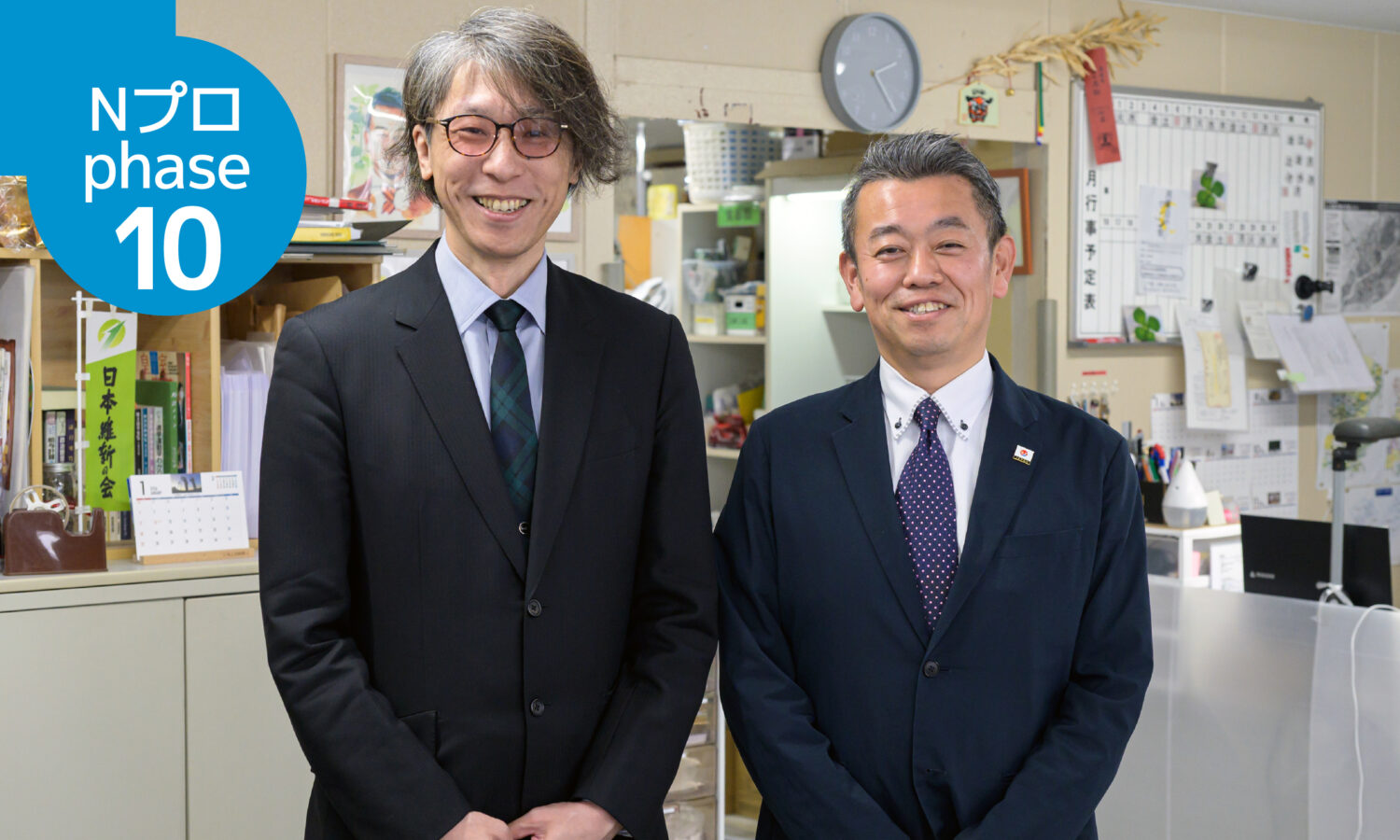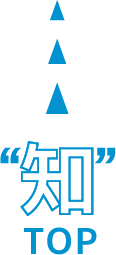2025.11.07
460名の高校生が挑んだ「学びのアウトプット」
「人、人、人」――2025年8月13日から6日間にわたって開設された、大阪・関西万博内に設置されたNプロジェクトのブースには、放射線について語る460名の高校生と、約1万人の来場者が集った。これほど多くの一般市民が放射線というテーマに耳を傾けた機会が、かつてあっただろうか。この前例のない盛況は、若者が主体となって放射線を伝えるという、Nプロが開発した新たなアプローチの成果にほかならない。
分かっているようで、実はよく知られていない放射線の話題を、高校生たちは自らの言葉で、来場者一人ひとりに丁寧に語りかけた。特に印象的だったのは、来場者の多くが女性だったこと。幼い子どもを連れた母親から高齢の女性まで、幅広い世代が足を止め、熱心に耳を傾けていた。高校生たちは膝をつき、目線を合わせ、笑顔で語りかける。「放射線は怖いものではありません。自然界にもある現象なんです」。母親が頷きながら話を聞く姿、年配の来場者が「初めて分かった」と微笑む瞬間――それら一つひとつが、科学と社会を結ぶ「小さな対話」だった。
そして忘れてはならないのは、これを担っていたのが、いわゆる「学力の平均層」に位置する高校生たちであるということだ。社会を支えるボリュームゾーンこそが、社会を動かす力を持つ――それは歴史が証明している。中村助教は語る。「社会を支えるのは特別な人ではなく、こうした普通の高校生たちなんです」。その言葉どおり、6日間のブースには、彼らの誠実なエネルギーが満ちていた。
158か国語のスケッチブック――"科学は世界共通語"
大阪・関西万博には、158か国・地域が参加している。この国際的な舞台を最大限に活用しようと、「Nプロジェクト」は、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」の実現を目指し、参加国・地域の母語に対応したスケッチブックを手描きで制作した。この挑戦に取り組んだのは、460名の高校生たち。制作されたスケッチブックは、なんと900冊にのぼる。
もちろん、多くの高校生は他国の言語を自在に操れるわけではない。だが、彼らはCTB(Cross Talk Board)という翻訳支援ツールを駆使し、言語の壁を一つひとつ乗り越えていった。未知の言語に挑みながら、彼らは「伝える」ことの本質に向き合い続けた。対応済みの言語は、まるで選挙の当選発表のように、赤い花で飾られていく――そんな遊び心あふれる演出を提案したのは、やはり中村助教。「選挙速報みたいで楽しいでしょう?」と笑うその茶目っ気が、高校生たちの創作意欲をさらに刺激した。
完成したスケッチブックは、訪日外国人の来場者とのコミュニケーションを可能にし、科学を通じた交流の架け橋となった。まさに「科学は学問ではなく、世界共通の言語である」と語る中村助教の言葉を体現する取り組みである。この実践は、高校生たちの主体性を大きく育んだ。来場者からの質問に答えられなかった悔しさ、友人が描いた創意工夫に満ちたスケッチブックに刺激を受けた経験――それらすべてが、彼らの表現力と伝える力を磨く糧となった。設営されたブースのバックヤードでは、活動期間の6日間を通じてスケッチブックが日々ブラッシュアップされていった。より伝わる表現を求めて、言葉を選び、絵を描き直し、工夫を重ねる。高校生たちは、国境を越えた対話の可能性を、自らの手で広げていったのである。
会場を巻き込む「放射線クイズ」――科学がエンタメに変わる瞬間
大阪・関西万博の会場では、Nプロジェクトのブース出展に加え、特別ステージイベントも開催された。会場の袖では、今夏460名の高校生に放射線のリスクについて講義を行った電力中央研究所の佐々木道也上席研究員が見守る中、またしても中村助教は仕掛けた。なんと、高校生向けの授業を、一般来場者に対して実施したのである。
会場を歩く来場者に高校生がA/Bフリップを手渡し、放射線に関する二者択一のクイズ大会がスタート。参加型の工夫が会場全体を巻き込み、学内だけでなく万博の空間そのものを一体化させた。特設ステージでは、Nプロおなじみの”二択クイズ”が始まった。高校生が観客にA/Bフリップを手渡し、中村助教がマイクで呼びかける。
「車内で体を固定するものは? AかBか!」来場者たちは一斉にフリップを掲げ、会場は瞬く間に一体化。「シートベルトでなくシーベルト(Sv)を覚えて帰ってほしい」とのユーモアを交えた解説に、笑いと拍手が広がった。放射線を“学ぶ”ではなく“楽しむ”空間――科学がエンターテインメントへと変貌した瞬間だった。放射線のクイズで会場が盛り上がる――そんな誰もが想像しなかった空間が、万博の中に生まれたのだ。
驚くべきことに、このステージイベントには米国総領事館を代表して広報文化外交部の阪田隆治氏も参加。日米に関わる放射線のクイズ大会が行われ、万博の会場は放射線というテーマで見事に染まった。科学を軸に、人と人、国と国が交わる。万博の本質が、そこにあった。
ゆうちゃみさんとの再会――笑いと科学のコラボレーション
万博プレイベントをきっかけに交流を深めてきたタレントのゆうちゃみさんと、Nプロジェクトのメンバーが再会を果たした。会場には多くの報道陣が詰めかけ、注目の中での再会となった。中村助教はスケッチブックを手に、ゆうちゃみさんに二者択一形式のクイズを出題。ゆうちゃみさんは、すっかりお馴染みとなったA/Bフリップボードを使い、笑顔でテンポよく回答した。
「放射線って、ほんまに目に見えへんの?」――率直な質問に、生徒たちはスケッチブックを広げて答える。A/Bフリップを掲げてテンポよく反応する彼女の笑顔に、観客から歓声が上がった。会場は終始和やかな雰囲気に包まれ、生徒たちからは歓声と拍手が沸き起こった。ゆうちゃみさんとNプロの温かなやりとりは、参加した生徒たちにとっても忘れがたいひとときとなった。
「ギャルでも科学を語れるやん!」というひと言に、科学が一気に”日常”へと引き寄せられた。
前回の万博プレイベントで”ギャルピース”(手のひらを上に向けて前に突き出すポーズ)に挑戦するも、うまく決められず恥ずかしい思いをした中村助教は「この日のために460名の生徒とともにトレーニングを重ねてきた。「もう一度写真を!」と、ゆうちゃみさんにリベンジを願い出た中村助教に、ゆうちゃみさんは即座に快諾。再挑戦の場面では、“ギャルピース”に似て非なる“スパイダーマン”ポーズを仕込まれた高校生や教員とともに、中村助教が見事に雪辱を果たした。会場は大きな笑いと拍手に包まれ、和やかな雰囲気に包まれた。ゆうちゃみさんは「スパイダーマンやん!」と笑顔で応じ、会場を後にした。科学とポップカルチャーが交差したこのひと幕は、イベントに参加した生徒たちにとっても忘れがたい思い出となった。
スケッチブックはアートへ――STEAM教育としての到達点
丹精込めて描かれた数千冊のスケッチブック――その価値にいち早く注目し、STEAM教育として高く評価したのが米国総領事館だった。100円ショップで購入されたシンプルなスケッチブックが、高校生の手によって命を吹き込まれ、100冊、200冊と並ぶと、もはや芸術作品。つまり「アート」としての存在感を放つ。整然と並んだスケッチブックの列を見て、在大阪・神戸米国総領事館の担当者は息をのんだ。「これは教育を超えた”アート”ですね」。
この創造的な取り組みは、生徒の主体性を軸に、まさにSTEAM教育の本質を体現していた。前回のルポでも触れたが、中村助教自身は、当初STEAM教育を意識していたわけではないという。その自然体こそが、学びの本質を突いていたのではないだろうか。中村助教は語る。「私は最初、STEAMという言葉すら知らなかった。でも、生徒たちが自ら学び、表現し、人と対話する姿を見て、これこそが本物の学びだと思った」。 Nプロジェクトは、高校生の創造力と主体性、そして国際的な連携が融合した象徴的な取り組みとして、今冬、国際機関より紹介される予定だ。米国総領事館の心を動かした「自然体の哲学」が、国際的な教育の舞台でも注目を集めている。なお余談ではあるが、原子力産業新聞制作によるNプロジェクトの特集動画が万博会場で上映される機会を得た。国際舞台でその動画が日の目を浴びたことは、関係者にとっても大きな喜びとなった。
科学は世界をつなぐ“共通のことば”
6日間の万博ステージを終えた高校生たちは、単なる参加者ではなく“語り手”へと成長していた。
科学は学問ではなく、世界をつなぐ共通言語――それを信じて描いた900冊のスケッチブックが、国籍も世代も越えて心をつないだ。
この夏、万博の片隅で生まれた小さな奇跡。そこには、笑顔と対話に満ちた“未来の科学”の姿があった。