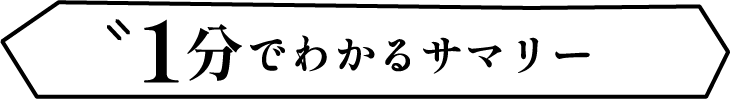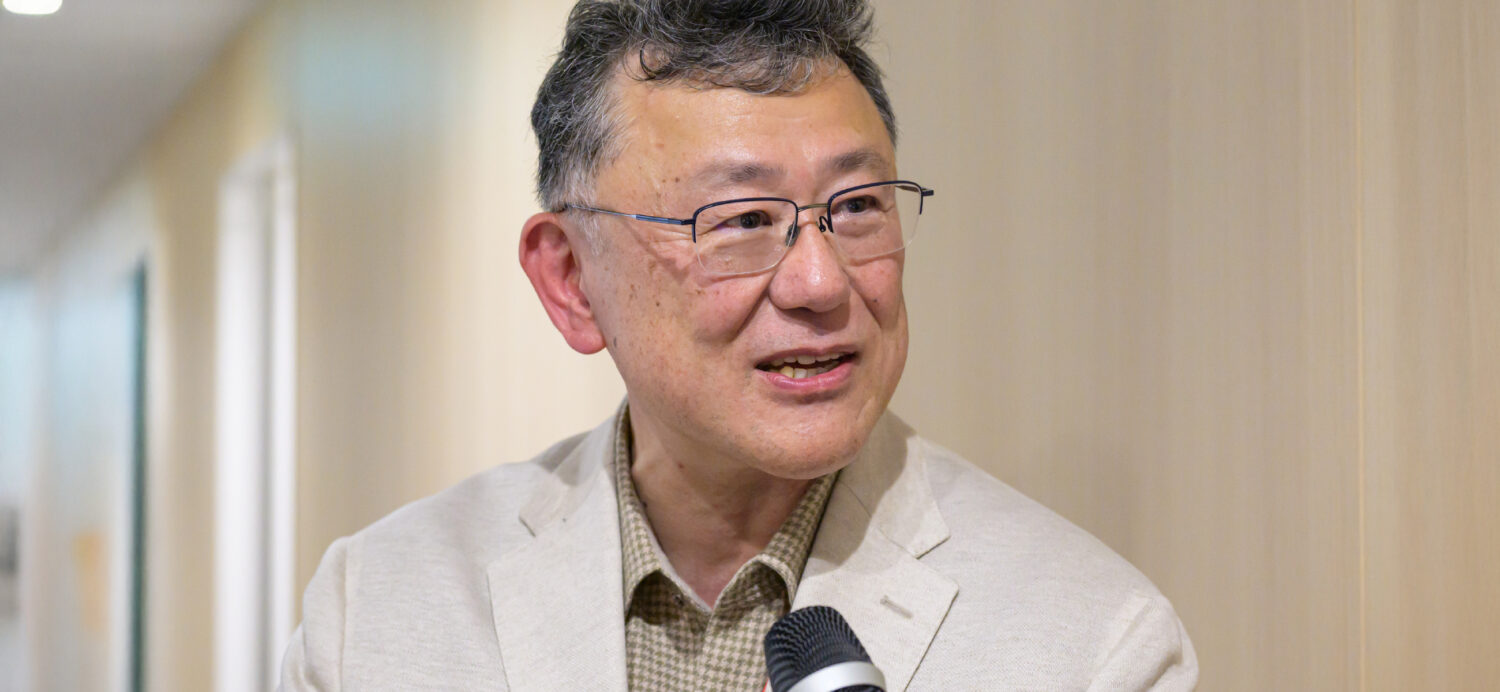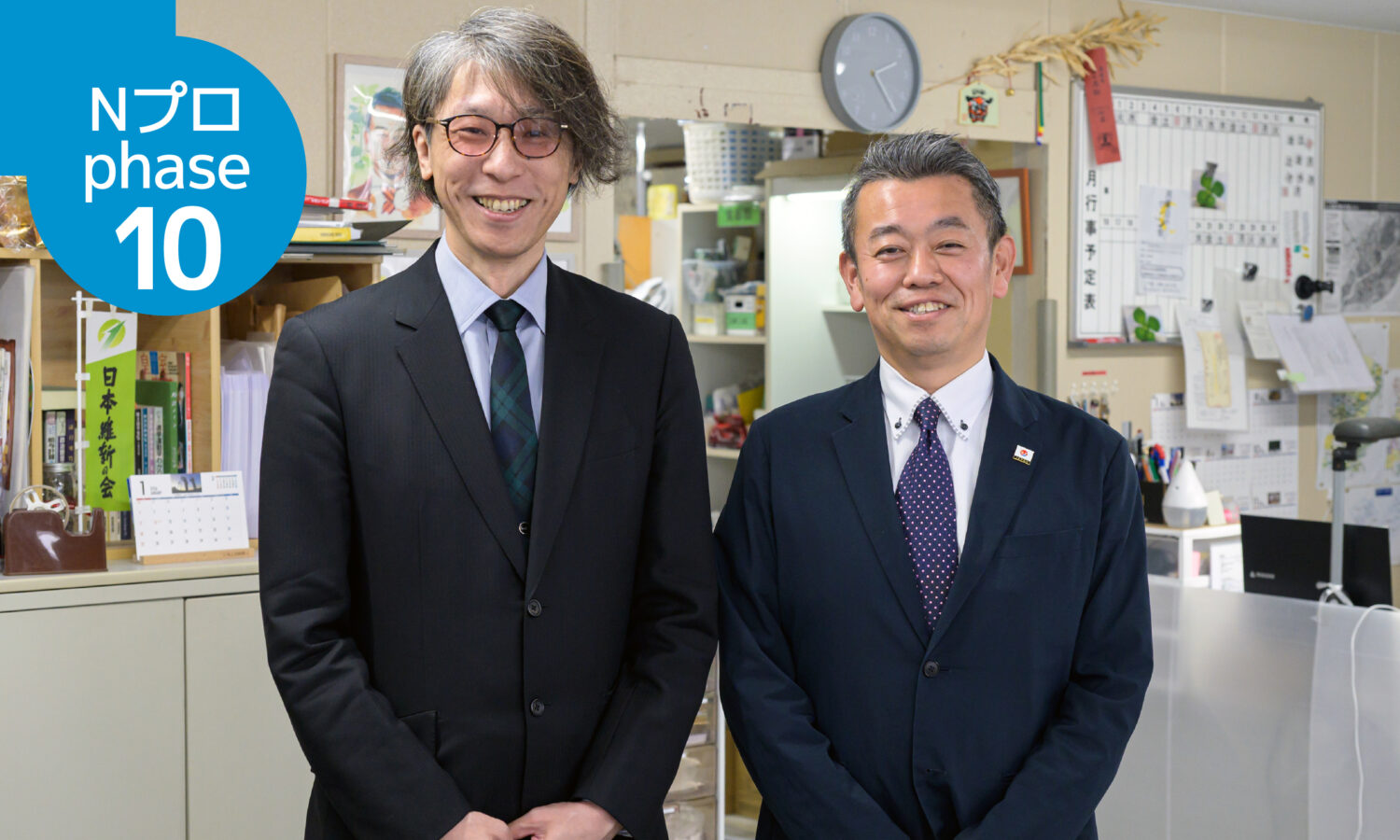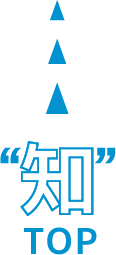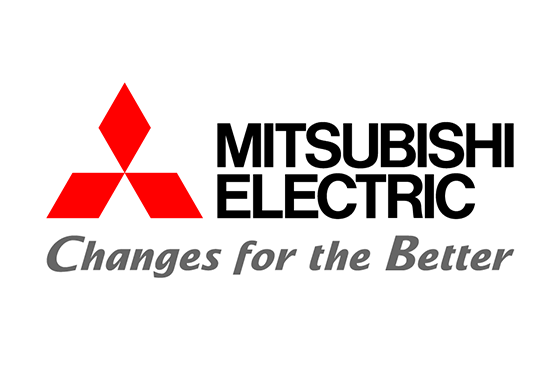2026.01.22
内閣府で開かれた原子力委員会定例会合で、京都大学の中村秀仁助教が進める「Nプロジェクト」が紹介された。高校生が科学を学び、社会に向けて発信する実践を核とする同プロジェクトは、原子力・放射線の理解促進にとどまらず、文理の壁を越えた対話型学習として評価を集めた。議論では、“校務分掌”に位置づけられた点や教育効果データの蓄積が注目され、汎用性や人材育成との接続について委員から多角的な問いが投げかけられた。
これに対し中村助教は、地域性を踏まえたモデル化や論文化の方針を説明。総括した上坂委員長は、Nプロジェクトは教育学の先進的研究であり、大学・大学院の一講座として成立しうる段階に達していると位置づけた。現場発の教育実践が国の場で承認された意義は、極めて大きい。
2026年1月13日。内閣府で開かれた原子力委員会定例会合において、京都大学の中村秀仁助教が進める「Nプロジェクト」の活動概要が紹介された。
科学を共通言語として社会と対話するこの教育実践は、単なる原子力・放射線の理解増進活動や人材育成の枠を超え、教育学の一講座として成立しうる先進的研究として、原子力委員会の場で明確に位置づけられた。
この日の議論は、Nプロジェクトが「紹介された」場ではなかった。会場内の席を埋め尽くした傍聴者たちは、Nプロジェクトが「承認された」瞬間を目撃したのだった。
原子力委員会で何が示されたのか
今回の原子力委員会で中村助教が示したのは、単なる活動報告ではなく、明確な教育メソッドとしての構造だった。
発表の柱は、大きく分けて三つである。
①インプットとアウトプットを不可分にした学び
Nプロジェクトの最大の特徴は、
「学ぶこと」と「社会に語ること」を一体として設計している点にある。
高校生は、放射線やエネルギーといった社会的に敏感なテーマについて学んだ後、その内容を手書きのスケッチブックにまとめ、駅前や街中、地域イベントなどの場で、一般市民に向けて説明する。
中村助教は、
- 一方向の講義では知識は定着しない
- 社会に語る経験を通じて、初めて理解が深まる
と強調した。
このアウトプットの反復が、生徒自身の理解を深めるだけでなく、社会側にとっても「科学を聞く経験」を生み出しているという。
②文系・理系の壁を越える設計
発表では、日本の教育に根強く残る「文系・理系の分断」にも踏み込んだ。
中村助教は、算数が苦手という理由だけで「文系」を選ばざるを得なかった高校生たちとの対話を通じ、
- 文系・理系という区分そのものが科学への距離感を生んでいる
- “放射線”や“処理水”といった社会と直結した題材は、文理の垣根を越える起爆剤になりうる
ことを明らかにした。
実際、大阪高校では、文系生徒を含む多数の生徒が自ら説明役を買って出るようになり、参加者数は年々拡大していることが示された。
③校務分掌による制度化
そして、委員の関心を最も集めたのが、この活動が校務分掌に明記された点である。
この聞きなれない“校務分掌”という言葉。これは学校運営の中核をなす役割分担のことであり、Nプロジェクトの活動がそこに位置づけられたということは、活動が一研究者の試みではなく、学校全体で支える正式な教育活動になったことを意味する。
中村助教は、
「校務分掌に明記されたことで、教員、保護者、生徒との公式な対話が可能になった」
と述べ、制度化が活動の持続性と拡張性を支えたと説明した。
原子力委員会での議論
中村助教発表後の議論では、上坂充委員長が全体の進行役として議論をリードし、Nプロジェクトの位置づけを段階的に明確にしていった。議論は、単なる所感の応酬ではなく、「この取り組みを、原子力委員会としてどう捉えるのか」という問いを軸に進められた。
発表直後の受け止め――原子力理解活動を超える可能性
冒頭、上坂委員長は、中村助教の発表が原子力理解活動の枠に収まらない点に着目し、科学教育・人材育成という観点から、より広い射程で捉える必要があるとの認識を示した。とりわけ、高校生が学んだ内容を社会に向けて発信し、その反応を再び学びに取り込むという循環構造が、従来の一方向型教育とは異なる点を評価した。
これを受け、中村助教は、インプットとアウトプットを不可分に設計した理由を説明し、社会との対話そのものが学習効果を高める仕組みとして機能しているとの考えを示した。
議論の中盤では、岡嶋成晃参与(上坂委員長代読)、直井洋介委員、吉橋幸子委員、小笠原一郎参与から、それぞれ異なる角度の問いが示された。
上坂委員長は、これらの発言を単発のコメントとして扱うのではなく、
- 地域性と汎用性
- 教育現場をどう動かしたか
- 原子力人材育成との接続
- 社会的文脈への波及
という論点群として整理し、Nプロジェクトが持つ多層的な意味を浮かび上がらせた。
中村助教はこれに応じ、校務分掌による制度化の意義や、生徒の主体性が現場を動かしたプロセス、さらには原子力分野に限らない人材育成の裾野拡大という観点から、それぞれの問いに具体的に説明を加えた。
議論の終盤、上坂委員長は、これまでの委員・参与とのやり取りを踏まえ、Nプロジェクトの位置づけを改めて整理した。
上坂委員長は、この取り組みを原子力理解活動や人材育成施策の一事例としてではなく、教育学の先進的な研究実践として捉えるべき対象であるとの認識を示した。特に、高校生から小・中学生までを含む大規模な実践を通じて、教育効果を検証可能なデータが蓄積されつつある点に言及し、研究としての成熟度が高まっていることを評価した。
そのうえで上坂委員長は、熱のこもった口調で、Nプロジェクトは、もはや先進的な取り組みという段階を超え、教育学として大学・大学院に「講座」を設けるに値する「分野」が成立しうるレベルにまで達しているとの見方を示した。これは、現場発の教育実践が、高等教育の枠組みに組み込まれる可能性を示唆するものであり、Nプロジェクトを学術的に位置づける評価の到達点といえる。
これに対し中村助教は、小学校・中学校を含む実践から得られたデータを基に、教育効果を学術的に検証し、論文化を通じて発信していく意向を改めて示した。あわせて、特定の個人に依存しない形で展開できるよう、手法の整理やマニュアル化を進め、他地域・他校でも実施可能なモデルへと発展させたいと応答した。
この応答を受け、上坂委員長は、Nプロジェクトが今後、原子力委員会としても継続的に注視すべき重要な対象になったとの認識を示した上で、原子力委員会からは吉橋委員を中心に有志を募ることで、Nプロジェクトをよりシステマティックに発展させることができるとの考えが示され、一連の議論を締めくくった。
学界からの裏打ち
会合終了後、傍聴していた京都大学の中島健名誉教授(元日本原子力学会会長)にコメントを伺った。
「中村先生本人から『こういうことをやっている』という報告は度々受けていたものの、今回改めて一連の話を聞き、中村先生が一人で始めた『小さな波紋』が、いかに大きく広がっているかを実感した。現在では米国なども注目するほどに成長し、世界にも影響を与えようとしている段階にある。さらに、最後に上坂委員長が述べたように、この活動は単なる教育実践に留まらず、一つの新たな学問分野、すなわち「新たな教育学」を創出していく歴史的な瞬間を、我々が今まさに目の当たりにしているのではないかとの感想を抱いた」
そして中島名誉教授は、これまでは中村助教個人が主導し、一部の高校と連携するローカルな活動であったが、今回、広く公の場で国として共有されたことは大きな転換点であると指摘。これまで文部科学省も関与してきたが、特に原子力に携わる人間としては、国の原子力行政の中核を担う原子力委員会がこの取り組みを「オーソライズ(公認)」した意義は非常に大きいとしたうえで、この公認により、プロジェクトの信頼性と影響力が格段に高まったとの見解を示した。
社会はどう受け止めたのか
学術界から「新たな教育学が立ち上がる瞬間」と評されたNプロジェクトは、同時に、社会の側からも明確な応答を引き出していた。
原子力委員会での発表を傍聴した地方議員や教育関係者の言葉からは、この取り組みが「原子力の理解促進」という枠を超え、教育のあり方そのものを問い直すものとして受け止められていることが浮かび上がる。
「千人に一人でいい」――人材育成の再定義
大阪府議会議員の広野瑞穂氏は、発表を振り返りながら、次のように語った。
「中村助教が接してきた千人、二千人の生徒すべてが、同じ進路や価値観を持つ必要はない。しかし、その中から一人でも二人でも、科学や社会課題に主体的な関心を持つ人が育つのであれば、それ自体がすでに大きな成果だと思う」
「全員が右向け右になる必要はない」という言葉は、Nプロジェクトが目指す人材育成の本質を端的に表している。量ではなく、“きっかけを生み出すこと”に価値を置く姿勢である。
広野氏は、議員としての立場から、この取り組みを今後どのように大阪の教育に生かせるのか、とくに公立学校での展開の可能性について、本格的に検討していきたいとも述べた。
「原子力の話だと思っていた」――教育学への昇華
吹田市議会議員の井口直美氏は、発表を聞く前後で印象が大きく変わったと明かす。当初は、原子力分野の理解を広げるための活動だと思っていた。しかし、委員や有識者の議論を通じて、それが単なる専門分野の話ではなく、教育学そのものの領域に踏み込んでいることに気づかされたという。
ディベート力や対話力が重視される時代において、日本の教育もまた転換を迫られている。Nプロジェクトは、その転換点に位置する取り組みとして、国の場で真正面から受け止められた。
「国もちゃんと見ている」―― そう実感できたこと自体が、大きな意味を持ったと井口氏は語った。
保護者・地域の視点から見た可能性
同じく吹田市議で、佐竹台小学校のPTA会長も務める林恭広氏は、より生活者に近い立場からNプロジェクトを見つめる。
吹田市で開催された中村助教の講演を聞き、率直に「ファンになった」と語る林氏は、今回の発表を通じて、この取り組みが国のレベルで評価されていることを強く実感したという。地元・吹田にとどめておきたいという思いはある。しかし同時に、これは全国、さらには世界へと広がるべき教育モデルだとも感じたと熱く語る林氏。
高校生だけでなく、中学生や小学生、さらには幼稚園にまで広げていくことで、日本にとどまらず、世界に羽ばたく人材が育っていく―― そんな未来像を林氏は描く。
校務分掌に刻まれた「現場の判断」
こうした広がりの出発点にあったのが、教育現場での決断である。Nプロジェクト発足当時、大阪高校の校長としてこの取り組みを支え、校務分掌に位置づける決断を下したのが、岩本信久氏だ。岩本氏は、校長の権限で一方的に進めることもできたが、それでは学校は本当の意味で動かないと振り返る。生徒が先に動き、その姿を見て教員が動き始めた。だからこそ、校務分掌という学校運営の中核に明記する判断ができた。
この制度化によって、Nプロジェクトは個人の挑戦から、学校全体で担う教育活動へと変わった。
「N」は何を意味するのか
そして最後に、Nプロジェクトを率いる中村助教は、今回の原子力委員会での議論を率直に喜びとともに受け止めている。
吉橋委員より「Nプロジェクトの“N”は何か」と問われ、自身でも驚いたという中村助教。いまは「ニッポン」を意味する「N」だと感じているという。
文系・理系という枠を超え、科学について自分の言葉で語れる人が一人でも増える社会。社会的に敏感な出来事が起きたとき、それを自ら判断できる土壌を広げたい。論文化に向けたデータはすでに揃っており、世界で初めてとなる教育効果の検証として、インパクトのある形で発表する構えだ。
大阪にとどまらず、他府県、さらには海外へ――。
Nプロジェクトは、次の段階へと歩みを進めようとしている。