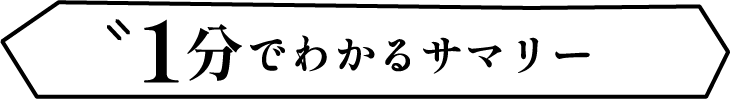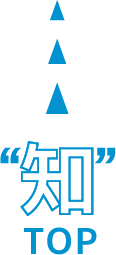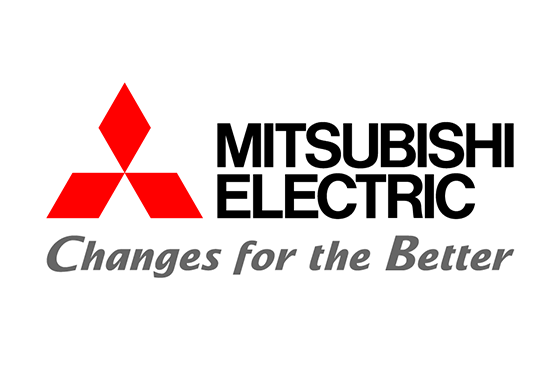2026.02.09
2月8日の衆院選で再選を果たした奥下剛光衆議院議員に独占取材。奥下議員は、当選後に力を入れたい分野として「子育て・教育」を挙げ、選挙前の政策アンケートでは重要政策として「NプロジェクトのようなSTEAM教育の導入」と言及している。
万博で高校生が社会に向けて発信する活動を知り、調べていく中で吹田発のNプロジェクトに強い関心を持った奥下議員。原子力や放射線を題材に、対話や発信を通じて「考え、疑い、語る力」を育てる点を高く評価。そして、原子力委員会で教育学の先進的研究として位置づけられたことを受け、制度化や予算措置、さらには国会での議論へとつなぐ必要性を訴え、「国を変えるチャンスだ」と語った。
奥下剛光衆議院議員(大阪選出・日本維新の会)がNプロジェクトに関心を持つようになった最初のきっかけは、万博の場で高校生が社会に向けて発信している活動を知ったことだった。
当初は、数ある若者の取り組みの一つとして目に留めたにすぎなかったという。しかし、その内容が気になり、どのような活動なのかを調べていくうちに、そこで発信していたのが吹田の高校生であることを知った。
地元・吹田の若者たちが、原子力や放射線といった、決して扱いやすいとは言えないテーマについて、自分たちの言葉で社会と対話している――。その事実は、奥下議員の関心を一気に引き寄せた。さらに調べる中で、この活動を主導しているのが、京都大学の中村秀仁助教であり、しかも吹田出身であると知ったことも、強い印象を残したという。
外から持ち込まれたプロジェクトではなく、地元にルーツを持つ研究者と、地元の高校生たちが中心となって展開している。その構図に、奥下議員は単なる教育イベントを超えた「持続性」や「広がり」の可能性を感じ取った。
万博という国際的な舞台で生まれた関心が、地元・吹田という足元の現場へと結びつき、さらに国の場での議論へとつながっていく。この出会いのプロセスそのものが、後に奥下議員がNプロジェクトを「一過性の取り組みでは終わらせてはならない」と考えるようになる原点だった。
「原子力教育」ではなく「教育そのもの」
奥下議員が、Nプロジェクトについて繰り返し強調するのは、これを単なる「原子力や放射線を教える活動」として捉えるのは、本質を見誤るという点である。Nプロジェクトの核心にあるのは、特定の専門知識をどれだけ覚えたかではなく、学んだことをどう整理し、どのように他者に伝え、相手の反応を踏まえて考え直すかというプロセスそのものだという。
高校生たちが身につけているのは、教科書的な正解ではない。自ら問いを立て、情報を調べ、それを自分の言葉で説明しながら、対話を通じて理解を深めていく力である。奥下議員は、この一連の過程こそが、「教育の本質」ではないかと受け止めている。
特に印象的だったのは、高校生が社会に向けて発信することで、聞き手である大人たちの態度が変わる点だという。政治家や専門家が説明する場合、どうしても立場や肩書きが先に立ち、聞き手が身構えてしまう場面が少なくない。一方で、高校生が前に立ち、自分なりに理解した内容を語ると、「まずは聞いてみよう」という空気が生まれる。完璧な説明でなくても、率直な言葉で語られるからこそ、対話が成立しやすくなる。
奥下議員は、動画などを通じて高校生たちの発信を見た際、「これは大人がやるよりも、よほど人の心に届く」と感じたという。それは、高校生の説明が優れているというよりも、聞き手との距離が近く、同じ社会を生きる存在として言葉が受け取られているからだと分析する。Nプロジェクトは、原子力や放射線を入口にしながら、結果として、社会と向き合い、他者と対話し、自分の考えを更新していく力を育てている。奥下議員は、その点において、この取り組みは「原子力教育」ではなく、まさに「教育そのもの」を問い直す実践だと評価している。
「これが、やりたかったSTEAM教育だ」
奥下議員は、Nプロジェクトを見て感じたこととして、「これまで自分が思い描いてきたSTEAM教育と重なる部分が大きい」と語っている。
これまでにも、STEAM教育を掲げた取り組みは数多く存在してきた。奥下議員自身も、過去に大阪府に対して、システム教育や探究型学習の導入を提案した経験があるという。しかし当時は、コンテンツが十分に整わなかったり、現場に落とし込むための仕組みが見えなかったりと、思い描いた形では実現できなかった。理解を得ることの難しさや、制度と現場の間にある壁を、強く感じた時期でもあったと振り返る。そうした経験があるからこそ、Nプロジェクトの活動を見たとき、単なる新しい試みではなく、「自分が本当にやりたかったことに近い」と感じたという。
原子力や放射線という具体的なテーマを起点にしながら、知識の習得で終わらせず、対話や発信を通じて学びを深めていく。さらに、高校生が主体となって社会と向き合い、自分の言葉で語る構造が組み込まれている点に、これまでのSTEAM教育にはなかった手応えを感じたと述べた。奥下議員にとってNプロジェクトは、理想論として語られてきたSTEAM教育を、現場で機能する形に落とし込んだ数少ない実例の一つだった。
誤情報の時代に必要な「疑う力」
奥下議員が、Nプロジェクトの意義として繰り返し言及したのが、誤情報や断片的な情報が氾濫する時代において、「疑う力」「考え直す力」をいかに育てるかという点である。
国会議員として日々情報に向き合う中で、ネット上では、事実関係が十分に確認されないまま、刺激的な言葉や映像だけが瞬時に拡散していく現実を強く感じているという。本来であれば、少し調べれば裏付けを取れる情報であっても、多くの人がそれを確認しないまま受け取り、感情的な反応が先行してしまう。奥下議員は、そうした情報環境そのものが、社会に分断や不信を生みやすくしているとの認識を示した。
こうした状況に対して必要なのは、特定の答えを教え込むことではなく、物事を一方向からではなく、複数の視点から捉え直す姿勢を身につけることだという。そのためには、「本当にそうなのか」「別の見方はないのか」と立ち止まって考える習慣が欠かせない。
奥下議員は、Nプロジェクトで高校生たちが行っている活動に、まさにその力が表れていると見る。高校生たちは、一方的に説明するのではなく、相手の反応や疑問に耳を傾けながら、自分の言葉を調整し、考えを深めていく。このプロセスを通じて育まれるのが、ディベート力や対話力、そして判断力である。それは、原子力や放射線というテーマに限らず、政治、環境、経済、国際問題など、あらゆる分野に通じる基礎的な素養だと評価する。
奥下議員は、誤情報が拡散しやすい時代だからこそ、若い世代が「疑うこと」「考え直すこと」を恐れずに実践できる環境を整える必要があると指摘する。Nプロジェクトは、そうした力を、教室の中だけでなく、社会との対話を通じて鍛える点に、大きな意義があるとの認識を示した。
「あの時、高校生が説明してくれていたら」
インタビューの中で、奥下議員が特に具体的な例として挙げたのが、東日本大震災後の出来事である。
震災後、大阪府は、被災地で発生した瓦礫の受け入れを表明した。復興を支えるという観点からの判断だったが、一方で社会には強い反対の声が広がった。放射線への不安が先行し、「安全なのか」「本当に大丈夫なのか」という疑念が、十分な説明や理解を伴わないまま拡散していった。当時の状況について奥下議員は、冷静な議論が成立しにくい空気が社会全体を覆っていたと振り返る。
行政や政治の側は、専門家の知見をもとに説明を重ねていたが、その言葉が必ずしも生活者の感覚に届いていたとは言い難かった。肩書きのある大人が語るほど、かえって身構えられてしまう場面も少なくなかったという。
奥下議員は、その経験を踏まえ、もしあの時、Nプロジェクトのような取り組みに参加した高校生たちが、前に立って説明していたら、状況は違っていたかもしれないとの思いを語った。
高校生が、自分なりに調べ、理解した内容を自分の言葉で語る。放射線の性質やリスクについて、「怖い」「危険だ」という感情だけでなく、どういう点に注意が必要で、どこまでが分かっているのかを、等身大の目線で伝える。政治家や専門家の説明では届かなくても、高校生の言葉であれば、「まず聞いてみよう」と感じた人は多かったのではないか。奥下議員は、そうしたコミュニケーションの違いが、社会の受け止め方を左右する可能性を持っていたと指摘する。
この発言は、Nプロジェクトが単なる教育活動にとどまらず、社会の中で分断や不安が生じたときに、対話の回路を作りうる存在であることを示唆している。高校生が社会と向き合い、自らの言葉で語るという行為そのものが、社会的課題に対する理解の土台を形づくる。奥下議員の言葉からは、Nプロジェクトが持つ「社会との接点としての力」が、極めて現実的な文脈の中で語られていた。
原子力委員会での評価をどう受け止めたか
奥下議員は、原子力委員会での評価について、内閣府や文部科学省から報告を受けた際の印象として、行政側、いわゆる役人がここまで踏み込んで価値を認める例は、決して多くないとの認識を示した。事務方からの説明自体は、これまでも折に触れて受けてきたが、今回のように、活動の意義や将来性について、明確な言葉で評価が示されたことは異例だったという。
とりわけ、教育学の先進的研究として位置づけられ、「大学・大学院の一講座として成立しうる」とまで言及された点は、現場発の教育実践が、学術と制度の両面で到達しうる水準に達したことを示すものとして、非常に重い意味を持つと受け止めている。
奥下議員は、そこまで踏み込んだ評価がなされた以上、Nプロジェクトを単なる先進事例や好事例として扱うのではなく、次の段階へ進める責任が、政治の側にも生じたとの認識を示した。具体的には、制度の枠組みに位置づけることに加え、活動を継続させ、広げていくための予算措置をどう講じるかが、避けて通れない論点になるという考えだ。
現場発の教育実践は、関係者の熱意や善意だけに依存する形では長続きしない。国として正式に評価するのであれば、それに見合った形で、人材、活動の場、運営体制を支えるための財源を確保し、持続可能な仕組みとして整えていく必要があると述べた。
奥下議員は、少子高齢化が進む中で、各省庁が人材育成や教育分野への投資を強めつつある現状にも触れ、Nプロジェクトのような取り組みは、そうした政策的な流れの中で、具体的な支援対象として検討しうる位置にあるとの見方を示した。国の審議会での評価は、予算を伴う施策へと展開していくための一つの前提条件であり、また、関係者の間で共通理解を形成する上での重要な拠り所にもなる。
奥下議員は、その意味でも、今回の原子力委員会での位置づけは、Nプロジェクトの将来を左右する重要な転換点であり、政治の側としても、真剣に向き合う必要があると強調した。
「総理に問う」段階へ
奥下議員は、Nプロジェクトをめぐる議論について、国会の場で総理に直接問いを投げかける可能性にも言及した。原子力委員会という専門的な審議会の場で、教育学の先進的研究として評価された以上、この取り組みを、一部の専門家や関係者の間にとどめるのではなく、国のトップに対して「どう位置づけ、どう育てていくのか」を正面から問う必要があるという認識だ。
奥下議員は、現場から生まれた教育実践が、国の審議会で正式に評価された事例は決して多くないとした上で、だからこそ、総理を含む国政の中枢において、その意義を共有することに意味があると述べた。Nプロジェクトを通じて示されたのは、原子力や放射線といった政策テーマに限らず、科学を共通言語として社会と対話する教育の可能性である。奥下議員は、こうした取り組みをどう国として支え、将来世代につないでいくのかを、国会の場で議論していく意義は大きいとの考えを示した。
原子力委員会での評価、制度化や予算措置の検討、そして国会での問題提起。Nプロジェクトは、教育現場の実践から、国政の議論へと射程を広げつつある。
次の舞台をどう用意するか
奥下議員は、万博での経験を一過性のものとして終わらせてはならないとも強調する。大規模な国際イベントで若者が発信する機会を得た以上、その後も継続的に挑戦できる「次の舞台」を用意することが重要だという。
具体例として奥下議員が言及したのが、2027年、横浜で開催が予定されている花博である。花博は、環境や持続可能性といったテーマを掲げており、SDGsなどの文脈と合致する形であれば、Nプロジェクトが参加できる余地は大いにあるとの考えを示した。
実際、花や植物の研究、環境技術、資源リサイクルなどの分野には、放射線利用の知見が関わる場面が多い。科学を通じて社会課題を考え、発信するというNプロジェクトの姿勢は、花博のテーマとも親和性が高く、十分に接続しうるとの見解も示された。そして、吹田発の挑戦をその新たな舞台へと繋ぐ動きは、すでに静かに歩みを進めていた。
また奥下議員は、万博のような国際舞台に限らず、地域のイベントや公民館といった身近な場も含め、規模の大小を問わず、若者が発信し、試行錯誤できる機会を数多く用意することが大切だと述べた。人が集まること自体が制限された時期を経て、子どもたちが意見を述べたり、発表したりする場は大きく減った。だからこそ、場数を踏みながら学び直し、失敗を恐れずに挑戦できる環境を整えることを、政治として支えていきたいとの考えを示した。
「Nプロを広める役割を担いたい」
インタビューの終盤、奥下議員の語り口は、次第に「評価」や「制度」の話から離れ、自らがどう関わり、どう動くのかという個人的な決意へと移っていった。Nプロジェクトについて、もはや誰かの取り組みを外から眺める立場ではなく、自分自身がその価値を伝える側に回りたい――そんな姿勢が、言葉の端々からにじんだ。
奥下議員は、今後は自らも積極的にNプロジェクトを発信していく考えを示した。選挙の場を含め、あえて「Nプロ」という言葉を口にし、「それは何なのか」と問われる状況をつくること自体に、大きな意味があるという。
人々が関心を持ち、立ち止まって調べ、考え始めるきっかけをつくる。それこそが、政治家として果たしうる最初の役割だとの認識だ。原子力委員会での評価、教育現場で積み重ねられてきた実践、そして社会に向けて語り始めた高校生たちの姿。奥下議員は、それらが点ではなく線としてつながり始めていることを、強く実感している。だからこそ、制度や予算、国会での議論といった政治の言葉に置き換え、次の段階へ橋渡しをする役割を、自分が担うべきではないかと考えるようになったという。
Nプロジェクトは、単なる教育の試みではない。社会が不安や分断に揺れる中で、どうすれば人々が対話を取り戻せるのか、どうすれば次の世代が自分の頭で考え、自分の言葉で語れるようになるのか――その問いを、具体的な形で突きつけている。
奥下議員の言葉から浮かび上がるのは、制度を動かす政治家としての顔と同時に、未来を生きる子どもたちに「考える力を手渡したい」と願う一人の大人の姿だ。
Nプロジェクトを広める。それは、一つの教育プログラムを後押しすることにとどまらない。社会のあり方そのものを問い直し、次の世代へとバトンを渡す営みに、自ら関わっていくという意思表示でもある。
奥下議員の語りからは、その覚悟と熱量が、確かな手応えとして伝わってきた。