キーワード:メディア
-
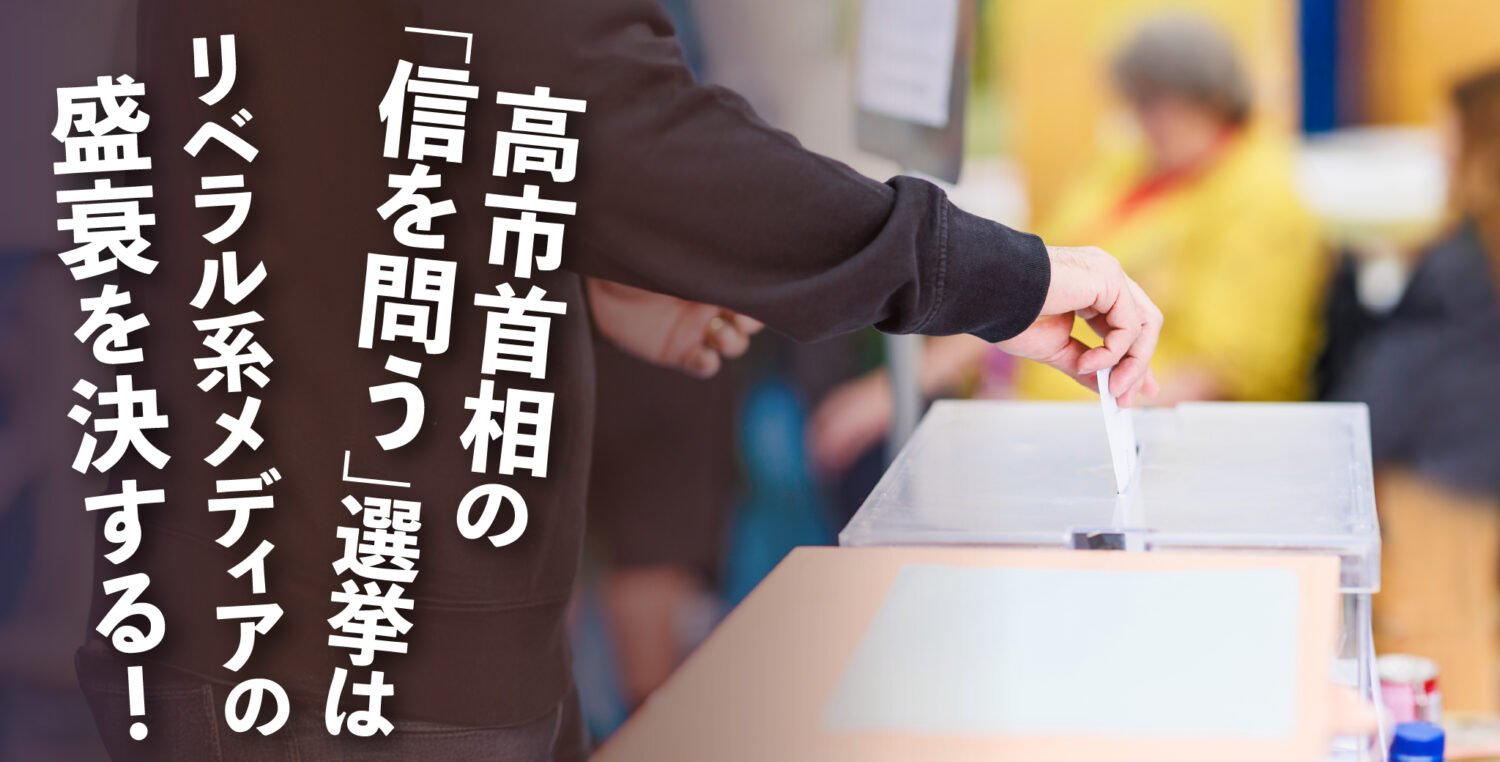
高市首相の「信を問う」選挙は リベラル系メディアの盛衰を決する!
二〇二六年一月十六日 今年も紙媒体のオールドメディアの行方が気になるところだが、昨年から今年にかけて、リベラル系メディアへの信頼を落とす出来事が相次いだ。そこへ、高市早苗首相の「解散」のニュースが飛び込んできた。リベラル系メディアは早くも「党利党略」「自己都合解散」と囃し立てるが、高市氏に批判的なリベラル系メディアは今後、どこまでその力を発揮できるのだろうか。オフレコ破り報道 昨年12月、メディアと政治の関係で大きな注目を集めたのが、高市政権で安全保障政策を担当する官邸関係者の「日本は核保有をすべきだ」との発言をめぐるオフレコ破り報道だ。取材時のオフレコ(off the record)とは、「この話はここだけにとどめ、報道・公表は控えてください」という意味だ。 毎日新聞社で記者をしていた私も何度かオフレコ取材を経験したが、それを破ったことはない。破れば、取材相手との信頼関係が完全に崩れてしまうからだ。ただ後日、報道したい場合は「これこれの内容で報じたい」と事前に了解をとった上で報じていた。了解なしにいきなり報じることが許されないのは、記者だからというよりも個人のモラルとして当たり前だからだ。 核保有発言のオフレコ破りの経過は新聞やテレビを見ていてもよく分からないが、まず最初に報じたのは朝日新聞(12月19日付朝刊)だ。「官邸幹部『日本は核保有すべきだ』との3段見出しで「首相官邸の幹部は18日、報道陣に対して、日本を取り巻く厳しい安全保障環境を踏まえ、個人の見解としつつ、『日本は核兵器を保有すべきだ』との考えを示した」と報じた。残念なのは、どこを読んでも、この記事がオフレコを破っての報道だとは書かれていないことだ。翌日の各紙を見て初めて、オフレコ破りの記事だと知った。個人の内面を断罪してよいのか? オフレコを破るからにはそれ相当の理由があるはずなので、その理由も含めて、発言の全文を載せて、「オフレコを前提とした非公式のやりとりだったが、これこれの理由でオフレコを破ってでも報じた」と書くのなら、読者への信頼も高くなるだろう。だが、記事を見る限り、発言の一部を切り取って、特ダネ的な意識で報じたような印象を受ける。 産経新聞だけは中国やロシアの脅威が迫る中、「議論に一石を投じた一面もある」(12月20日付朝刊)と発言を肯定的に書いたが、他紙はみな発言に批判的だ。ただ、オフレコ破りは、記者そのものへの不信感を高めたことは間違いない。 特に理解に苦しむのは、非公式な場でやりとりされた個人的な意見を記者が問題視したことだ。個人が心の中でどんな思想、信条、価値観をもっていようが、だれにも責める権利はない。ある思想、価値観をもっているだけでその人を断罪するのは旧ソ連のスターリン時代の粛清か、戦前の治安維持法下の取り締まりを思わせる。そういう個人的な内面を問題にしてはいけないという寛容な自由(リベラリズム)の大切さを熟知しているのがリベラル系メディアだと思っていたが、その思想、信条が高市政権を批判する手段(武器)となると見るや、リベラリズムの原則を自ら放棄してしまったという印象はぬぐえない。結果的に見ても、このオフレコ破り報道は日本への圧力を強める中国政府への援護射撃となった。東京新聞がコラムを削除 そんな矢先、朝日新聞と似た者同士の東京新聞が1月9日付紙面で1月1日に載せたコラムを削除するというビッグニュースが入ってきた。東京新聞は1日の紙面で西田義洋特別報道部長が「『熱狂』に歯止めを」と題して、「『中国なにするものぞ』『進め一億火の玉だ』『日本国民よ特攻隊になれ』。ネット上には、威勢のいい言葉があふれている」と書き、高市首相の存立危機事態発言に批判的な記事を載せた。 ところが、読者の指摘から、8日たった9日、「中国なにするものぞ」といった冒頭部分は誤りだったとする謝罪文を載せた。この謝罪文を見て、私は思った。熱狂をつくって不安を煽っているのは東京新聞だと。 この東京新聞の失態(謝罪文掲載)を朝日新聞と読売新聞はベタ記事(重要度が低いと判断される1段扱いの短い記事の俗称)で報じたが、詳細な記述はなく、新聞読者の中にはいまなお東京新聞の誤報を知らない人が多いのではないか。 この問題については、弁護士でジャーナリストの楊井人文氏は、紙面での謝罪やコメントだけでいいのかと鋭く切り込み、以下のように述べている。 「・・・考えられる一つの方法は記者会見だ。不祥事や疑惑があった際、報道機関から厳しい質問を受け、社会的な説明責任が求められるのが一般的だ。ところが、逆のパターン(報道機関の不祥事や疑惑)での会見が行われることは滅多にない。大抵、官僚的な短いコメントで済ます。こうした慣行が人々を伝統メディアから遠ざけている要因の一つだと思う」(Yahoo!ニュース1月9日)。 全く同感である。メディアは責められる立場になると途端に門を閉ざす。オフレコ破り報道も、事後の説明はなく、読者は置き去りにされたままだ。紙媒体の報道が一方通行なのがこれでよく分かる。これでは読者の信頼をつなぎとめることは無理だろう。このままでは紙媒体の衰退は必至だ。ぶら下がり取材の減少 そういう政治とメディアの流れの中で珍しい現象が起きている。高市首相の「ぶら下がり取材」が激減しているという現象だ。ぶら下がり取材とは、首相が官邸などで記者団の質問に短く答えるやりとりだ。北海道新聞(25年12月22日のYahoo!ニュース)は、高市首相が就任以来、記者団の取材に応じたのは17回しかなく、石破首相の31回、岸田首相の42回に比べて、極端に少ないと報じた。朝日新聞と似た傾向をもつ北海道新聞はこの現象について、「首相に都合の悪い情報が国民に伝えられないリスクをはらむ」とネガティブに報じた。 私の見方は全く逆だ。首相側がようやくメディア側と対等の立場に立ったのだ。これまで首相側(政権側)はメディアというフィルターを通じてしか国民に語りかける術がなかった。そのメディアが信頼できるならよいが、過去のオフレコ破り報道に見られるように、首相の言葉が勝手に都合よく切り取られ、「編集の独立」という名目でときに中国に利するような形で報じられてきた。 しかし、いまや既存のメディアが情報伝達を独占する時代ではなくなった。不確かな記者団のぶら下がり取材に頼らなくても、首相は自ら主張したいことを「X」(旧ツイッター)などで直接国民に語ることができるようになった。現に高市首相はXで語り始めている。Xなら首相の全発言が読める。Xで誤報が判明 しかも、Xを通じて報道の誤りが明かされる効用もある。昨年12月下旬、高市首相夫妻(夫は山本拓元衆院議員・脳梗塞でリハビリ中)が公邸へ転居した際、「バリアフリー対応の改修が実施された」と日本経済新聞や時事通信などが報じた。ところが、高市氏は1月9日のXで「私達の公邸への転居に関する報道を目にした夫は、落ち込んでいる様子でした。それは、大手報道機関も含めて、転居を前に公邸はバリアフリー対応の改修も実施されたという誤った報道を目にしたからです」などと報道の誤りを指摘した(ちなみにネットではバリアフリー工事はどんどん進めたほうがよいというコメントが多かった)。 この誤報の判明は明らかに高市首相が自らXで語り始めた成果だ。 これらの事例を見てもわかるように、12月から1月にかけて、高市首相のぶら下がり取材がめっきり減ったのは、高市首相のメディアへの不信感の表れのように思える。リベラル系メディアは安倍総理を徹底して批判してきたが、安倍氏を引き継ぐ高市首相へのスタンスも変わらない。処理水の放出時と似た空気が醸成 こうした中で中国政府は観光客の渡航自粛要請やレアアース(イットリウムなど希土類元素)の輸出規制などを通じて、日本への圧力を強めている。この光景はどこかですでに見た既視感がある。そう、福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出が始まった23年8月の光景だ。 当時、中国は日本からの水産物輸入を全面的に禁止する理不尽な措置をとった。このとき日本の空気は不穏になるかと思いきや、懸念された風評被害は生まれず、逆に日本の中に連帯精神が生まれたことをご記憶の方もいるだろう。リベラル系メディアが中国寄りの報道をしても、日本の空気はそれに引きずられなかったのだ。 それと似た空気がいま生まれようとしている気がする。立憲民主党と公明党が新党を結成して波乱にみえるが、どちらも親中国のスタンスなので、高市政権とリベラル系メディアの対決構図は変わらない。次の総選挙の結果はリベラル系メディアの盛衰を決するのではないか。
- 16 Jan 2026
- COLUMN
-
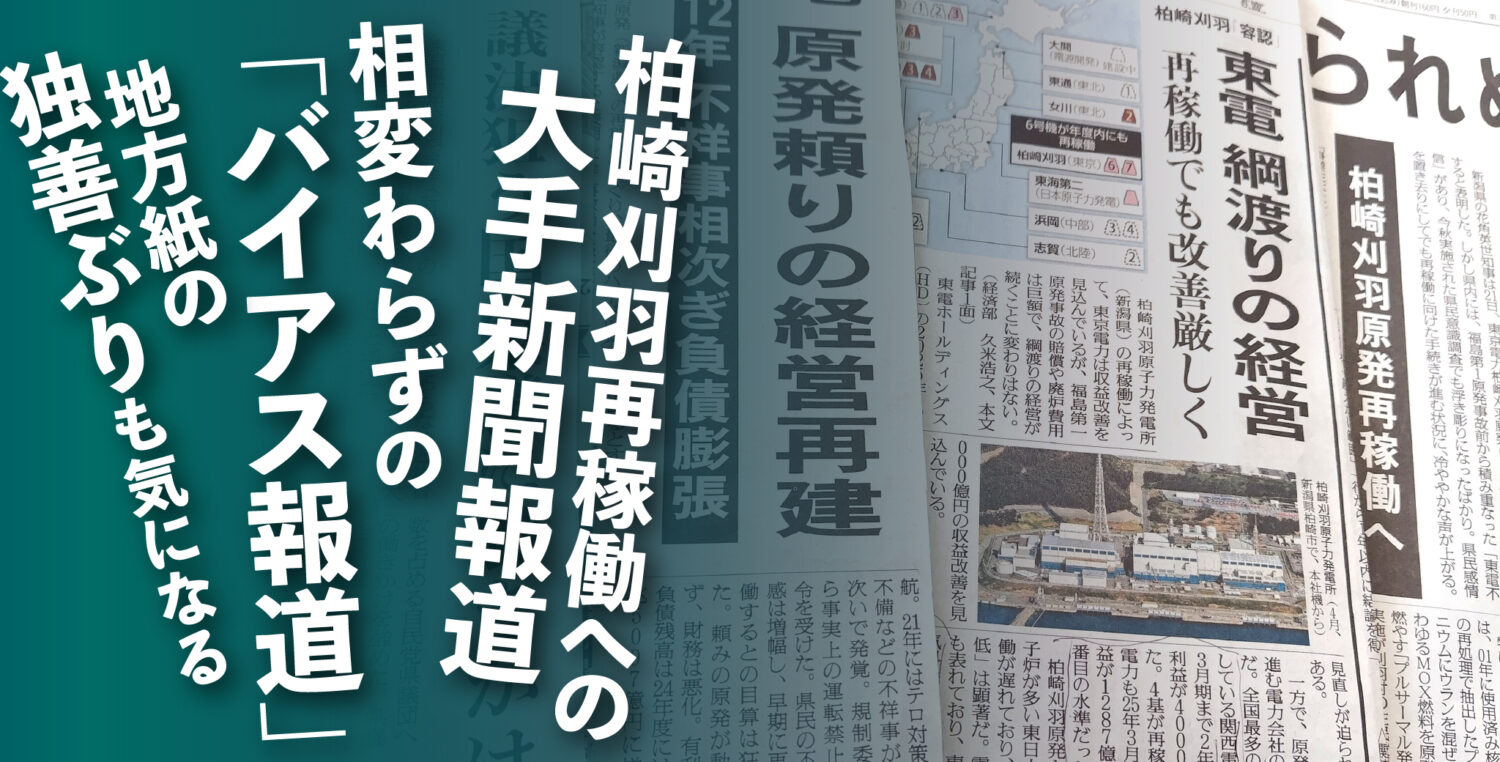
柏崎刈羽再稼働への大手新聞報道 相変わらずの「バイアス報道」 地方紙の独善ぶりも気になる
二〇二五年十二月二日 新潟県の花角英世知事が11月21日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所6~7号機(出力各135万kW)の再稼働を容認する考えを表明した。この判断に対して、大手新聞社はどう報じたのだろうか。やはりリベラル系新聞(朝日、毎日、東京新聞)と保守系新聞(読売、産経新聞)ではかなりの「差」が見られた。いつものことだが、地元紙がネガティブニュースで不安を増長させていることも分かった。産経新聞はAI需要を強調 新聞記事の中身を判断するのに一番適しているのは見出しだ。見出しを見れば、新聞社の姿勢がよく分かる。再稼働を最も肯定的にとらえていたのは産経新聞(11月22日付)だ。1面で「柏崎刈羽再稼働容認 AI需要 脱炭素の安定電源」とうたい、3面で「東電 経営再建へ前進 1基1000億円の収支改善」の文字が躍った。 日本は今後、人工知能(AI)向けデータセンターの増加で電力需要の拡大が見込まれる。その観点から原発の再稼働は安定電源となり、国から見ても悲願だったと見出しに「AI需要 脱炭素の安定電源」を入れたのが特色だ。3面で不祥事が続く東電に対する県民の不信があることにも触れたが、見出しに取るほどの内容にはなっていない。 一方、読売新聞(11月22日付)は記事全体では肯定的だが、「東電綱渡りの経営 再稼働でも改善厳しく」と産経に比べると厳しい眼差しを向ける。再稼働で1基1000億円の収益改善が見込めるが、福島第一原発事故の賠償や廃炉費用が巨額なため、再建は厳しいと断じた。ただ、社会面ではほぼ一面を費やし「地元 経済安定に期待」との見出しで、東電への透明性のある運営を求めつつも、地元経済の活性化に期待する声をひろった。20日付記事でも「再稼働で首都圏の電力需給が緩和する」と報じ、根強い東電不信に対しても、「知事、時間かけ判断」との見出しで徹底した安全対策と経済振興策が再稼働を後押ししたと書いた。 この二紙は、東電の問題点にも触れつつ、原発のメリットも伝え、バランスよく報じたと言えるだろう。毎日新聞は東電への不信を強調 これに対し、毎日新聞(11月22日付)は1面の見出しは「柏崎刈羽再稼働へ 新潟知事容認表明」と通常の見出しだが、3面では一転「原発回帰 国に同調」「政府再三要請に知事決断 東電問われる適格性」と批判的になり、社会面では「東電が信じられぬ 不祥事山積 県民忘れず 福島避難者あきれた」と東電への不信に満ちた内容をくどいほど並べ、県民感情を置き去りにしたと厳しい。同日付の社説でも「解消されぬ東電への疑念」と題し、「東電の安全軽視の体質が改まっていない。新潟県民の不信を置き去りすることは許されない」ときっぱり。「再稼働に反対だ」と社自体が明確に主張しているわけではないが、県民の不安を楯に、再稼働は暴挙だというニュアンスがひしひしと伝わってくる。朝日は5ページにわたり批判を展開 朝日新聞(11月22日付)は5ページにわたり、批判的なトーンを展開した。2面で「再稼働 県民の信待たず 議決狙う国、県議に働きかけ 福島への責任・東電適格性は」と不祥事続きの東電に「原発を動かす資格はあるのか」と相当に手厳しい。解説欄でも「東電が原発を運転することに県民の69%が心配だと答えている。電力は首都圏に送られ、新潟県民にはメリットがないとの見方も根強い」と地元にもメリットがないことを強調した。社説でも「疑念ぬぐえないままの容認。原発回帰に向けた重い判断を立地自治体に押しつけ、地元同意の手続きの不条理がまたも繰り返された」と地元同意が不条理だと一喝した。 国が主体的に再稼働を決めれば、「地元の同意を無視した暴政だ」と批判し、地元の同意を重視すれば、今度は「地元に判断を押しつける不条理だ」と批判する。どちらにせよ、朝日新聞は批判したいのだというトーンが強く伝わってくる。 東電の経営に関しても、「不祥事相次ぎ負債膨張、事故の責任重く いばらの道」と再建は極めて困難と断じた。社会面では福島の被災者を取り上げ、「福島を知るから複雑 『同じ経験してほしくない』 私たちの犠牲、なかったことにされるのか」と、柏崎刈羽原発が近くまた事故を起こすかのような書きぶりだ。 朝日、毎日とも東電の「適格性」を大きく取り上げ、事故を起こした当事者が再稼働させる資格はあるのかと問う。二紙とも、反原発路線に沿った論調なのが改めて分かる。東京新聞はさらに過激 朝日新聞以上に過激なのは、毎度のことながら、東京新聞(11月22日付)だ。1面の見出しに「県民の『東電不信』耳かさず」を入れ、2面で「『再稼働ありき』のシナリオ、柏崎刈羽『信問う』知事選択せず」とし、社会面では「被災者怒り『事故究明が先』 都民は賛否『電力安定』『安全不安』」とネガティブ情報が圧倒する。電力の需給面でも「原発の必要性は薄れている」と書き、23日付からは「見切り発車柏崎刈羽 東電再稼働を問う」と題した計三回の連載記事を載せた。どういうわけか再稼働に怒りをぶつける市民の名前は実名で登場するが、電力が安定すると肯定的な意見を述べる弁護士や講師の名前は匿名だ。 再稼働の経済効果については「柏崎刈羽原発の6、7号機が再稼働したときの経済波及効果は10年で4396億円と試算されているが、単年度では440億円に過ぎず、新潟県の総生産額の8兆9000億円の0・5%ほどでしかない」と経済効果にも疑義を示す。東京新聞を読むと、再稼働のメリットは全く感じられない。原発の拡大とリベラル系新聞の拮抗 こうして見ると、やはり新聞はバイアス(偏り)に満ちている。注意深く読まないと洗脳されてしまう。原発への批判度を順番に並べてみると、一番過激な東京新聞を筆頭に、朝日、毎日となる。逆に肯定度の順番は、産経が強く、次に読売が来る。 いま世界を見れば、原発は拡大傾向にあり、AIや半導体の需要拡大で、原発の必要性が高くなることは間違いない。そうなると、リベラル系新聞が原発批判だけで購読者を維持していくことが、どこまで可能なのかが気になるところだ。地方紙も批判勢力として健在 一方、地元の新潟日報はいつものことながら批判的だ。これまでにも原発に批判的な報道を繰り返してきただけに、批判自体は予想の範囲内だが、独自に延べ7142人(なぜ、延べ人数なのか。重複しているとしたら正確といえるのか疑問だが)を対象にアンケート調査を行い、その結果を報じた(11月28日オンライン)のには、ただならぬ執念を感じた。東電が運転することに対し、「83%が不安を感じる」と報じ、「知事の判断を支持しない」が78%に上ったと報じた。まるで市民活動家並みのアクションだ。 そして11月28日には、鈴木直道・北海道知事が、北海道電力・泊原子力発電所3号機(91・2万kW)の再稼働を容認する考えを表明した。待ってましたとばかり、北海道新聞の社説(29日)は「知事の表明は拙速であり、到底受け入れられない。容認ありきでは道民の命と暮らしを守るリーダーとしての責務は果たせない」と反対論をぶちまけた。北海道新聞も新潟日報と似て、原発批判の双璧をなす印象をもつ。 そう言えば、23年8月に福島第一原発の処理水が海洋放出されたときに、地方紙(福島県を除き)の社説の大半は「反対」だった。大手新聞の偏りだけでなく、地方紙の独善ぶりも要注意だと改めて感じる。
- 02 Dec 2025
- COLUMN
-

発行部数の減少に歯止めかからず いよいよ新聞の危機到来か?
二〇二五年十一月十九日 大手新聞の発行部数の減少が止まらない。いくら紙媒体に人気がないとはいえ、一定数の固定読者層は存在するのではと考えていたが、どうやらそれは幻想だったと言えそうだ。以前に「読売新聞の一強時代の到来か?」と書いたが、それも雲行きが怪しくなってきた。日本ABC協会 新聞の発行部数は「一般社団法人 日本ABC協会」の調査で分かるが、その数字は有料の会員向けには発表されているが、ネットでは見られない。新聞社がこの発行部数の調査結果をニュースにしてくれればよいが、残念ながら、ニュースを見たことはない。 このため、私のような非会員は、会員情報を基にネットで公表している個人のブログやサイトを見て判断するしかない。 ちなみに日本ABC協会は、広告主(車、鉄道、銀行、商社など幅広い)、新聞社、テレビ局、広告代理店などが会員となっている会員制組織で、新聞や雑誌などを公正な立場で調べて部数などを公開している。ABCは、Audit=公査(監査)、Bureau=機構、Circulations=部数の略で、もともとは米国で生まれた組織だ。大手新聞は驚くべき減少ぶり この日本ABC協会の公表数字をネットで探したところ、ジャーナリストの黒藪哲哉氏が運営するウェブサイト「MEDIA KOKUSYO」(25年8月7日参照)と、独立系広告プランナー氏のブログ「広告代理店の未来を考えるブログ」(25年11月12日参照)で発行部数を見つけることができた。読売新聞広告局ポータルサイトでも、読売新聞への広告掲載がいかに有利かを示すために各社の発行部数を載せているが、情報がやや古い。 情報が新しい「広告代理店の未来を考えるブログ」を見て、目が飛び出るほど驚いた。読売新聞の発行部数は約五三七万部(25年8月)、朝日新聞が約三二一万部(同)、毎日新聞が約一一八万部(同)、産経新聞が約八〇万部(同)、日本経済新聞が一二八万部(同)だ(同ブログなどを基に筆者が作成した表を参照)。 私は24年8月、「読売新聞の一強時代はオールド左派リベラル層の衰退の兆しか!?」と題した記事をこのコラムで書いた。そのときの読売新聞は六〇七万部だったが、一年経ったいまは約七〇万部も減って、五三七万部に落ちた。二十年前は千万部を誇っていたことを考えると、隔世の感がある。 朝日新聞も一年間で三四九万部から三二一万部へ減ったが、減り方は少ない。日本経済新聞の減り方も少ない。 この発行部数は、あくまで「発行」された部数だ。新聞代を払っている実際の購読者の数ではない。新聞業界では「押し紙」といって、新聞社が販売店に実際の購読部数を超えて新聞を押しつける慣行がある。この発行部数が多いと広告料を高くとることができるメリットがあるからだ。 押し紙が実際にどの程度あるかは分からないが、仮に一割程度をすると、実際の購読部数は各社とも一割ずつ減り、読売は五〇〇万部を割り、朝日も三〇〇万部を割り、毎日は一〇〇万部ぎりぎりとなる。毎日新聞は危機的 毎日新聞の目を覆うほどの減少ぶりは危機的だ。一年間余りで約四〇万部も減り、約一一八万部となった。もはや全国紙とは言いがたいほどの部数だ。個人的な話で恐縮だが、私が毎日新聞の記者(二〇一八年に退職)だったころは、三〇〇万部程度の発行部数があり、いくら紙媒体が減るとはいえ、二〇〇万部程度の固定読者層はいるだろうと勝手に思っていたが、その予想は全く甘かった。 なぜ毎日新聞だけが危機的なのか。これについて、広告代理店での実務経験をもとに「広告業界の今」を発信しているブログである「広告代理店の未来を考えるブログ」は以下のように分析している。 「読者の六割以上が60歳以上で、若年層へブランド力が届いておらず、アプリやSNS上での存在感がない。読売は家庭での接触、朝日は文化層、日経は就活・ビジネスへのアクセス力が残っているが、毎日新聞にはそういう訴求力がない。産経新聞も部数は少ないが、保守系論調で特定層に一定の支持を得ており、接触経路や読者像が明確に残っている点で毎日新聞とは異なる」(筆者で要約)。双方向の新聞があれば この分析は確かに当たっているように思える。自身の経験から言うと、毎日新聞は記者の自由度が高く、のびのびと取材活動ができる。官僚的な組織ではないため、私自身、社論とは異なる記事も堂々と書くことができていた。そういう自由な気風の新聞社が危機的な状況に陥っているのは悲しいが、時代の動きや消費者のニーズに合わせて業態や情報発信のあり方を変えていくしかない。リベラル系と保守系新聞の行方 ただ、歴史的な記録(アーカイブ)を残す点で新聞に勝る媒体はない。ぜひ生き残ってほしいと思うが、いま私が気になるのは、政治の動きとともにリベラル系新聞(朝日・毎日)と保守系新聞(読売・産経)の勢力図がどうなるかだ。 読売新聞の社説(11月13日オンライン)は高市早苗総理の存立危機事態をめぐる発言について「…台湾有事が存立危機事態になり得る、という首相の認識は理解できる。ただ、危機に際しての意思決定に関する発言には慎重さが求められよう。…だが、しつこく首相に見解をただしたのは立憲民主自身だ。答弁を迫った上で、答弁したら撤回を迫るとは、何が目的なのか。とにもかくにも批判の材料を作りたいということだとしても、安保政策を政局に利用しようとするなどもってのほかだ」と立憲民主党にも非を向けた。 一方、朝日新聞の社説(11月18日)は「不毛な対立に区切りを」と題して「…台湾という地名に触れたことで緊張を不用意に高めたと言わざるを得ない。…とはいえ、中国の姿勢にも大いに疑問がある。高市発言への抗議があまりにも執拗だ。…」と中国の姿勢にも疑問を投げかけ、国民から支持率の高い高市人気が頭にあるのか、以前に比べると中国寄りの度合いが弱くなっている印象を受ける。ただ、読み比べると読売新聞のほうは立憲民主党にも批判の矢を向けたといえる。こういう社説を載せる読売新聞が支持されるかどうかは、今後の発行部数にも大きく影響するだろう。 冒頭で示した読売新聞と産経新聞の発行部数を合わせると、六一七万部となり、朝日と毎日を足した四三九万部を大きく上回る。その差は一七八万部だ。現時点ではリベラル系新聞のほうが劣勢だ。この差が今後、開くのか縮むのか。立憲民主党や共産党を支持する層が減っていけば、リベラル系の朝日、毎日の発行部数も比例して減っていくだろう。高市人気が持続するかどうかはやはり大きなカギを握るように思える。
- 19 Nov 2025
- COLUMN
-
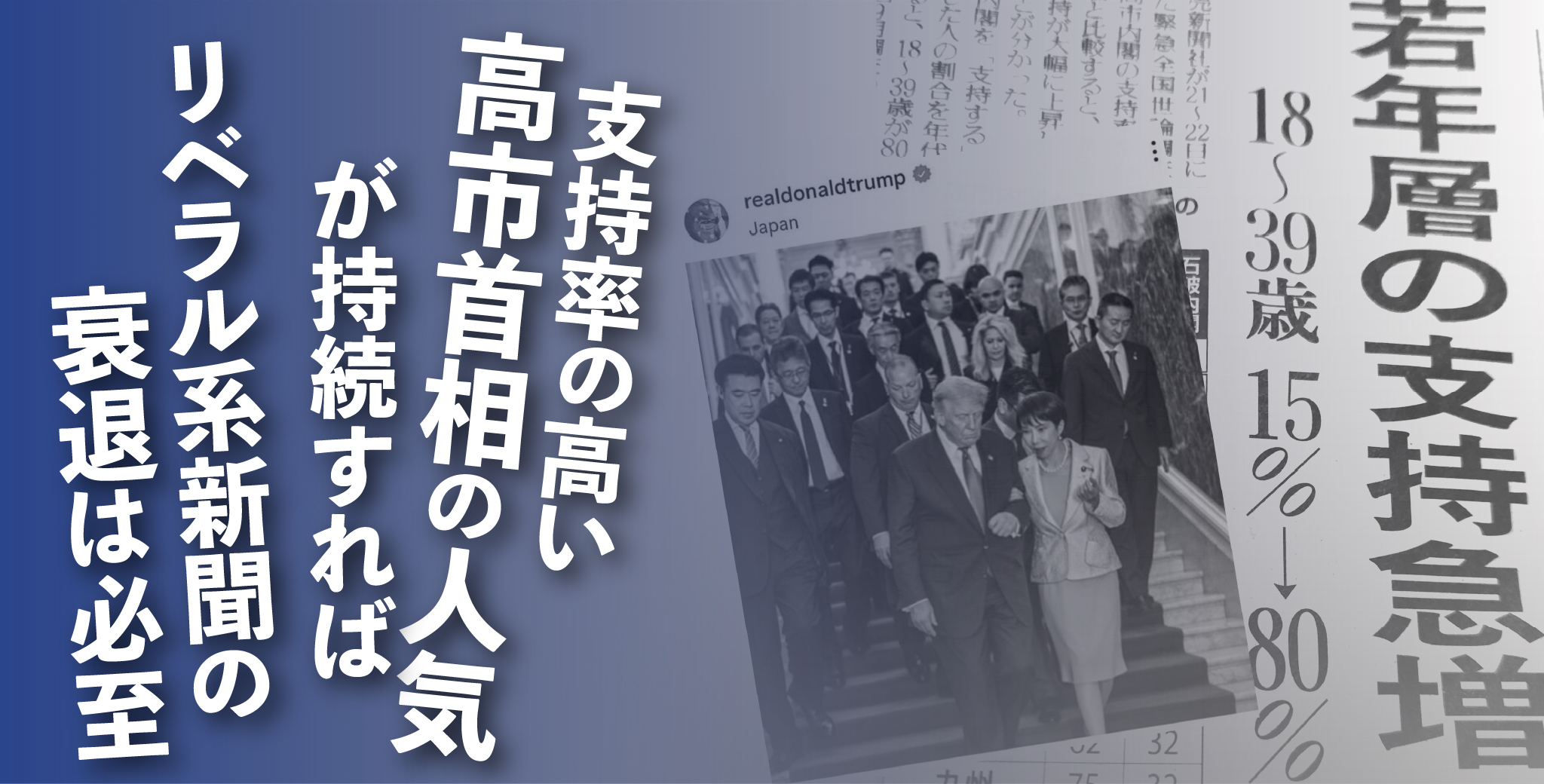
支持率の高い高市首相の人気が持続すれば リベラル系新聞の衰退は必至
二〇二五年十一月七日 自民党の高市早苗氏が憲政史上初の女性首相(第一〇四代)として、着々と独自の経済・外交政治を展開し始めた。高市氏が保守派だけに、今後、大手新聞の二極化(朝日・毎日と読売・産経陣営)が急激に進むことが予想される。エネルギー政策でもリベラル系新聞は高市氏に批判的だが、高市政治の人気が続けば、リベラル系新聞はますます衰退していくのではないか。驚異的な支持率71% 高市内閣が発足したのは10月21日。その二日後の10月23日付け読売新聞の朝刊一面(読売新聞社の緊急全国世論調査の記事)を見て驚いた人が多いのではないか。「高市内閣支持率 71%」という大きな見出しの数字が目に飛び込んできた。正直ここまで高いとは思っていなかっただけに、これはオールドメディア(特に朝日、毎日のような大手リベラル系新聞)の終焉を思わせる予兆だと感じた。 リベラル系新聞の論調やテレビ局の一部番組(特にテレビ朝日やTBS)のリベラル系評論家のコメントを見ていると、高市氏への評価は総じて低い。「高市氏は夫婦別姓に反対する急先鋒であり、国家の安全保障や歴史認識で中国や韓国を敵視し、国家主義的な思想の持主であり、女性の代表とはとても言えない」といった論調だ。 しかし、読売新聞の世論調査の中身を見ると、18歳~39歳の若い層の支持率は80%と驚異的に高い(写真1)。同じ年齢層の石橋内閣の支持率が15%だったのに比べると驚くべき数字だ。しかも男性の支持率が71%なのに対し、女性の支持率は72%と女性からの支持率も高い。「高市氏は女性に人気がない」とリベラル系評論家はテレビなどで言っているが、全く事実と異なる。 確かに朝日新聞や毎日新聞にいる女性記者の間では「高市氏は全くの不人気」だろうが、一般社会では高市氏の人気は高いことが世論調査からうかがえる。こういう場面でもリベラル系新聞と一般社会の意識の乖離が垣間見える。写真1オールドメディアの影響力は低下 つまり、高市首相は若い層の心をつかんでいるのだ。その背景にはSNSを通じた影響力があるのだろうと察する。個人的な興味から高市氏を応援する動画チャンネルを登録して、いくつかを立て続けに見たところ、SNSの世界では「高市氏は日本が誇る最高の女性首相」という印象が強く伝わってくる。オールドメディアの記事を批判する動画もけっこう目立つ。 リベラル系メディアがいくら高市首相に批判的な言論を展開しても、若い層には大した影響を与えていないことが分かる。他の新聞社の世論調査でも高市首相の支持率は約60~70%と高い。そもそも若い層のほとんどは新聞を購読していない。人口構成的に見れば、高市氏に批判的な高齢(60歳以上)のリベラル層はいずれ、この世の中から消えていく。それに比例して、リベラル系新聞の購読者も減っていくだろう。そういう状況の中でこのまま高市人気が続けば、リベラル系新聞の影響力はますます衰えていくことが予想される。「太陽光は中国依存でも普及すべき」? リベラル系新聞では、原子力やエネルギー政策に関する記事にも高市嫌いが見られる。毎日新聞(10月26日)は「高市氏 原子力前向き 資源国に頭下げる外交終わらせたい」との見出しで高市氏のエネルギー政策を論じた。記事では、高市氏の「これ以上、私たちの美しい国土を外国製の太陽光パネルで埋め尽くすっことには猛反対」との極めてまっとうな意見を載せていながら、最後の締めで「太陽光パネルの国産化重視はコストに跳ね返ることになる。そこで勝負をせずに普及に軸足を置くべきではないか」という識者の主張を載せて記事を締めくくった。 どうやら毎日新聞社は「パネルの大半を中国に依存してでも普及すべきだ」という考えをもっていることが分かる。しかし、この記事を裏から読めば、「国産のパネルを使えば、太陽光発電のコスト(電気代)は高くなる」と言っているのと同じだ。とすれば、太陽光発電など再生可能エネルギーの補助政策に「ノー」を突きつけている高市氏(記事ではこのことを批判的に書いている)の主張のほうが的確だと読めてしまう。高市氏のエネルギー政策をなんとしても批判したいという意図は強く読み取れるが、残念ながらその意図に説得力は感じられない。「長期脱炭素電源オークション」を歪曲して報道 高市政権が生まれる前の記事ではあるが、8月13日付け毎日新聞の記事は印象操作記事の悪い見本のようなものだった。見出しは「原発支援 電気代上乗せ 建設費高騰に政府対応」。前文を読むと「政府が原発の建設費や維持費を電気料金に上乗せして支援する仕組みを拡充しようとしている。原発の建設費が想定を上回った場合も電気料金で消費者に負担を求める仕組みで、国際的な環境NGOなどが反対を表明している」とある。 一読しただけで、政府が原発を推進するためにまたまた悪巧みを企てているという印象が伝わってくる。記事中にある仕組みかが何かと言えば、24年1月にスタートした「長期脱炭素電源オークション」のことだ。記事によると、このオークション方式だと、電力会社が原発の建設費を示してオークションに参加し、落札すれば、消費者が支払う電気料金を通じて、建設費の大半を契約金として受け取ることができる。原発をもたない新電力の契約者も原発の建設費などを負担することになるという。オークションは脱炭素のための仕組み このオークションのことをあまり知らない読者は、政府が原発を支援するためにオークションという悪巧みの計画を始めたというふうに受け取ったに違いない。 記事を読むと確かにそういう印象をもつが、そもそも「長期脱炭素電源オークション」(管理者は電力広域的運営推進機関=OCCTO)は脱炭素を実現するために考えられた仕組みである。オークションで落札すれば、脱炭素電源の建設費などを原則20年間得られる仕組みなのだが、その対象電源は原子力のほか、太陽光、風力、水力、蓄電池、地熱、バイオマス、LNG、水素専焼、アンモニア20%以上の混焼にするための既設火力発電所の改修など、電源は幅広い。 このオークションは、自由化が進展し、供給力の確保が難しい中でいかに脱炭素と必要な供給力確保を実現していくか、という差し迫った中で生まれたのであり、決して原発だけを支援するために生まれた制度ではない(詳しくはOCCTOのウェブサイトを読んでほしい)。 にもかかわらず、そういう基本的な解説をせずに消費者の負担を増やして原発を拡充する仕組みかのごとく報じるのは、読者を一方向に誘導しようとするバイアス記事の典型である。 確かに原発をもたない新電力の契約者も負担することになるが、それを言うなら、リベラル系メディアが称賛する太陽光発電も同じである。太陽光発電などは固定価格買取制度に基づき、電力会社が買い取る費用の一部を再エネ賦課金という形ですべての電気利用者に負担を強いている。その再エネ賦課金は年間約二~三兆円にも膨らんでいる。この巨額な負担に比べたら、脱炭素電源オークションによる負担は極めて少ない。朝日新聞も同じ論調 実は、毎日新聞が報じた記事の内容は、朝日新聞がすでに報じていた(6月26日オンライン参照)。どちらも捉え方は同じだ。朝日新聞の記事は「経済産業省は原発の建設費が増えた分を電気料金に上乗せして回収できるようにする支援策の詳細をまとめた。巨費がかかる原発への投資に二の足を踏む大手電力を後押しするねらいだ」と書いた。 新聞社として原発に反対する姿勢があってもよいが、記事の中身は正確に書いてほしい。こういう偏った記事を届けていけば、やがて読者は逃げていくだろう。高市人気はリベラル系新聞の衰退を促す。そんな予感がする。
- 07 Nov 2025
- COLUMN
-
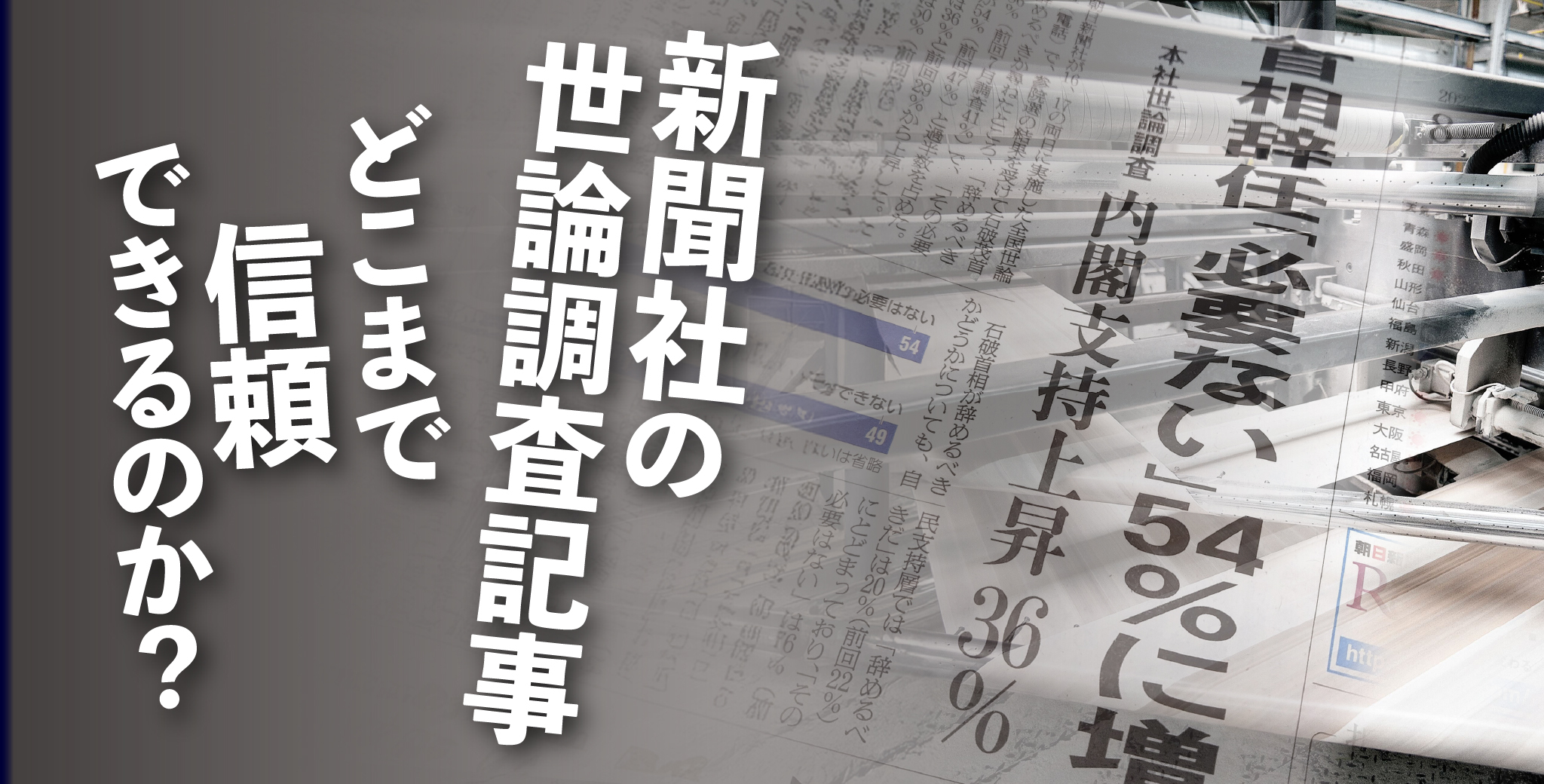
新聞社の世論調査記事 どこまで信頼できるのか?
二〇二五年九月五日 「石破茂首相は辞める必要はない」。八月下旬、こんな見出しの記事が大手新聞を中心に目立ったが、これは本当に世論の反映なのだろうか?大手新聞社は定期的に政党の支持率調査結果を記事にしているが、媒体によって大きな差が出ることが多い。なぜ、媒体ごとに差が出るのか。新聞社の世論調査には「ゆがみ」(バイアス)があることを知っておきたい。朝日新聞が一面トップで石破首相推し! ご存じのように自由民主党は、衆議院選挙(二四年秋)、東京都議選(二五年六月)、参議院選挙(二五年七月)の三つの選挙で大敗した。企業が三期連続で赤字を出せば、トップが経営責任を問われるように、自民党のトップである石破首相が責任を問われて当然だという空気がみなぎる中、八月十八日、朝日新聞が一面トップで「首相辞任『必要ない』54%に増」、「本社世論調査 内閣支持上昇36%」という大見出しの記事(写真参照)を報じた。 この見出しを見て、朝日新聞社はこの世論調査結果に小躍りし、痛くご満悦の様子だと直感した。その小躍りぶりは記事の文章の書き方に現れている。冒頭でいきなり「自民党内では参院選の大敗以降、石破首相に退陣を求める『石破おろし』の動きが続いている。こうした自民内の動きに『納得できない』との意見が49%と半数近くを占め、『納得できる』37%を上回った」と書いた。 この書き出しぶりを見ると、国民の半数を超える54%が「石破首相は辞める必要がない」と考えていることに対して、朝日新聞社は国民の気持ち以上に感激し、さらに「石破首相がんばれ」と朝日新聞の購読者にエールを送り返しているように思えた。その裏には、高市早苗氏(衆議院議員・元経済安全保障担当大臣)が次期首相になり、参政党などと手を結んだら大変なことになる、という思惑が透けてみえる。有効回答がどれくらいあったかを見ることが大事 新聞社が実施する世論調査記事を読むときには、その世論調査が本当に国民の平均的な声を反映しているかどうかを疑う必要がある。つまり、調査対象となった人たちのうち、何人が答えたかを知る必要がある。残念ながら一面トップ記事には、この大事な点が書かれていない。三面を見たら、目立たない隅っこに調査方法が書かれていた。 「コンピューターで無作為に電話番号を作成し、八月十六、十七の両日に固定電話と携帯電話に調査員が電話をかけるRDD方式で行った。固定電話では有権者がいると判明した九百十七世帯のうち四百五十二人(回答率49%)、携帯は有権者につながった千八百七十二件のうち、七百五十九件(回答率41%)、合計で千二百十一人の有効回答を得た」という。 ランダム(無作為)に選んだのはよいが、回答率が50%以下なのがまず気にかかる。いったい、どんな人が回答を拒否し、どんな人が回答を進んで引き受けたのだろうか。これは想像するしかないが、もしあなたが調査対象に当たり、朝日新聞社から電話があった場合、どうするか。あなたが朝日新聞を好きなら進んで答え、大嫌いな場合は拒否する可能性があるのではないだろうか。朝日新聞が行う世論調査では多くの場合、自民党の支持率が低くなるケースが多い。これに対し、読売新聞や産経新聞が世論調査を行うと自民党の支持率が高くなるケースが多い。 つまり、新聞社の世論調査には「ゆがみ」が伴うことを常に警戒する必要がある。読売新聞の携帯電話の回答率は33% 朝日新聞の報道から一週間後、読売新聞は八月二十五日、一面二番手で「内閣支持急上昇39% 首相辞任を42% 思わぬ50%」と報じた。朝日新聞と同様の結果となったが、四面を見たら、「次の総裁 高市氏1位」「総裁前倒し『賛成』52%」の見出しが躍り、石破首相は早く辞めるべきだというニュアンスが伝わってきた。「石破首相辞任へ」という号外まで出した読売新聞としては、石破首相に早く退場してもらいたいのだろう。その意図が記事ににじみ出ている。 読売新聞も、調査方法に関する扱いは九面に小さく載っていた。固定電話では七百七十三世帯から四百六人(回答率55%)、携帯電話では千七百七十四人のうち五百八十五人(回答率33%)が回答したというが、携帯電話での回答率の33%は低すぎる。無作為に選んで三割しか回答がなければ、どこまで日本の有権者(母集団)の真の姿を反映しているのか疑問がわく。毎日新聞は「辞任すべき」が上回る 一方、毎日新聞社は七月二十八日付け一面二番手で「内閣支持上昇29% 首相『辞任すべきだ』42%」と報じた。この記事では「首相は辞任すべきだ」(42%)が「辞任する必要はない」(33%)を上回った。七月下旬の時点ではまだ辞任すべきだという声のほうが強かった様子がうかがえる。 問題は調査方法である。毎日新聞の場合も、二面に小さく調査方法の解説が載っていた。それによると、全国約七千四百万人(18歳以上)の母集団から対象者を無作為に選び、調査への協力を依頼するメールを配信し、二千四十五人から有効回答を得たという。NTTドコモの協力を得たインターネット調査だが、無作為に選んだ人が何人で、そのうち何人が回答したかの数字は記されていない。これでは調査の信頼度は低い。世論調査は調査方法こそが肝 新聞社の世論調査で警戒すべきことは、その世論調査に応じた人たちはそもそも、母集団(日本国民)の代表的なサンプルといえるかどうかを見極めることである。世論調査は調査方法こそが肝なのだ。その調査方法をもっと大きく分かりやすく解説すべきなのに、その解説はいつも小さな扱いで目立たない。一面で世論調査を報じるなら、有効回答率を本文の中で解説するなど、統計的な検証に堪える科学的な記事にしてほしいものだ。読売新聞はあくまで「辞意」を強調 こういう「ゆがみ」は石破首相の動向をめぐる記事にも反映する。 七月下旬から八月上旬、首相官邸前に約二百~千二百人が集まり、「石破首相辞めるな」と石破首相を推すデモがたびたびあった。このデモはリベラル系の大手新聞(特に朝日、毎日、東京)やテレビを中心に幾度も報じられた。記事を読むと「(石破首相は)近年の自民党にはまれな言葉が通じる政治家だ」と石破首相を持ち上げる声もあり、「高市早苗氏と参政党が組んだら最悪の政治になる」といったデモ参加者の本音が読み取れる記事もあった。 興味深いのは、八月末になり、「石破首相は辞めろ」という逆のデモが起きたときだ。産経新聞(九月一日オンライン記事)によると、石破首相の退陣を求める「石破辞めろデモ」が八月三十一日、首相官邸前で行われ、四千人(主催者発表)が駆けつけたという。七月下旬に「石破辞めるな」デモが官邸前で行われたときは、最大でも約千二百人(主催者発表)だった。エッと思ったのは、四千人ものデモ隊が「石破首相は辞めろ」と糾弾しているのに、こちらはほとんどニュースになっていない。デモの規模で比べれば、「辞めろ」デモのほうが大規模なのに、報道は少ない。 自民党が九月二日に開いた両院議員総会で石破首相は、「地位に恋々とするものではない」などと述べたが、それに対し、朝日新聞は一面で「首相は続投姿勢」と報じ、読売新聞も「続投を表明」と報じたものの、同じ一面で「首相『辞める』明言」と書き、七月二十二日に石破首相が「日米交渉が合意に達した場合には記者会見を開いて辞意を表明する」と明言していたことを明かした。やはり朝日と読売の論調はかなり異なる。 どんなニュースも、そして世論調査も、媒体(新聞社やテレビ)のフィルター(社論、スタンス、好み)によって選別され、届くのは歪んだ情報だということを今一度知っておきたい。
- 05 Sep 2025
- COLUMN
-
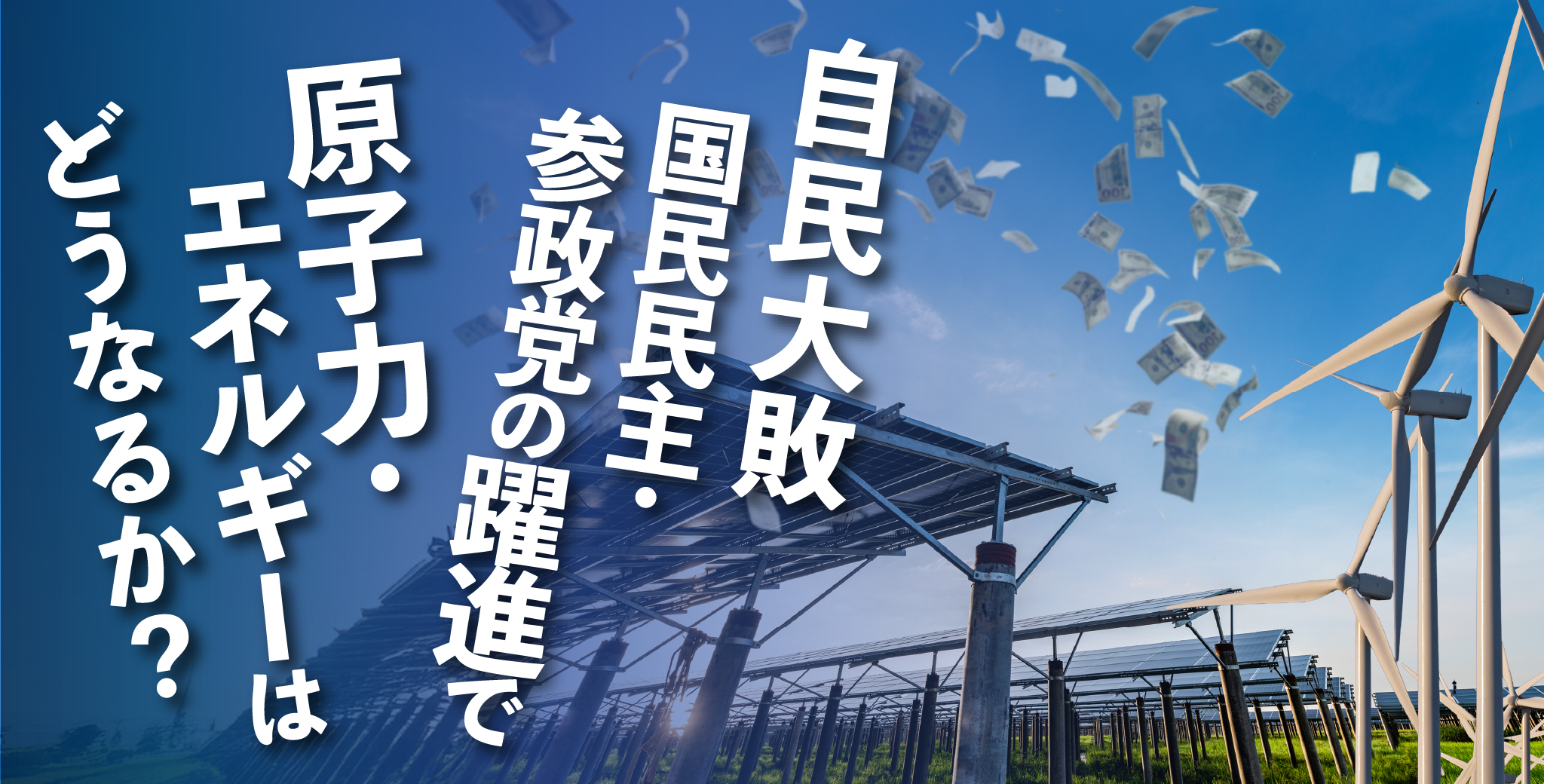
自民大敗 国民民主・参政党の躍進で原子力・エネルギーはどうなるか?
二〇二五年八月十二日 七月の参議院議員選挙で自民党が大敗し、国民民主党と参政党が大きく躍進した。この結果は原子力や太陽光など再生可能エネルギー問題にどう影響するのだろうか。「原子力を最大限活用する」としていた自民党が負けたことで原子力に逆風が吹くかと思いきや、意外にも原子力には追い風が吹いたといえる。その理由は?原発賛成の政党が約七割の票を獲得 参院選で最も躍進したのは、一議席から十四議席(選挙区七人、比例区七人)に急伸した参政党だろう。その急伸ぶりを見せつけたのが比例区での得票数だ。自民党(約一二八一万票)、国民民主党(約七六二万票)に次ぎ、第三位の約七四三万票を獲得した。前回(二〇二二年の参院選では約一七七万票)に比べ、四倍以上の伸びだ。この約七四三万票は立憲民主党(約七四〇万票)をも上回り、公明党(約五二二万票)、日本維新の会(約四三八万票)を大きく引き離した。 どの政党が原子力の必要性を認めているかについては、前回のコラムでも述べたように、自民党、公明党、国民民主党、参政党、維新、日本保守党の六党は原子力の推進に理解を示す(公明党は自民党に比べると消極的な賛成だが)。これに対し、立憲民主、れいわ新選組(約三八八万票)、共産党(約二八六万票)、社民党(約一二二万票)の四党は原発の推進に反対だ。そこで、今回の比例区の政党別の得票数を足して、原発推進派と反対派の割合を比べてみた。すると、原発推進の六党の合計得票数は約七割、反対の政党は約三割となった。もちろん、有権者がどこまで原子力を意識して一票を投じたかは分からないが、結果的にみれば、約七割の有権者が原発を推進する政党を選んだことになる。参政党は再エネ賦課金廃止 あらためて原子力・エネルギー関係に関する参政党の公約を見てみよう。公約は主に二つあり、ひとつは「次世代型小型原発や核融合など新たな原子力活用技術の研究開発を推進する」。もうひとつは「高コストの再生可能エネルギーを縮小し、FIT(電気の固定価格買取制度)、再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金=再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が買い取るときの費用を国民が一部負担するもの)を廃止する」。この公約を私なりに解釈すると、電気代が高くつく太陽光や風力発電を縮小し、年間二兆円以上もの国民負担を強いている再エネ賦課金を廃止する。そして、原子力の再稼働を早め、原子力の利点を活用していこうという政策だ。 七月の選挙戦では原子力やエネルギー問題はほとんど争点にならなかったが、参政党の議員は以前から国会の質問で再エネ賦課金の廃止を訴えてきた。このスタンスは、再生可能エネルギーの推進を訴えてきた反原発の立憲民主党とはかなり異なる。参政党に一票を投じた有権者が参政党の原子力政策をどこまで理解していたかは分からない。だが、参議院で得た十四議席は、予算を伴わない法案を単独で提出することを可能にするだけに、今後の政策展開は大きな関心を浴びるだろう。参政党は大手メディアの批判をはねのけて躍進 参政党の躍進で特筆すべきことは、大手新聞やテレビの批判をかわして勢力を拡大したことだ。たとえば、参政党の神谷宗幣代表は参議院選挙の第一声の街頭演説で「高齢の女性は子どもは産めない」と発言し、リベラル系新聞やテレビから一斉に批判を受けた。 また、選挙戦中の七月十二日、TBS「報道特集」は参政党の主張は外国人排斥運動やヘイトスピーチを誘発していると批判。さらに同番組ではアナウンサーが「これまで以上に想像力をもって、投票しなければいけないと感じています」と参政党の勢いをけん制するかのような主張を述べた。これに対し、参政党は「公平性、中立性を欠く」と強く抗議し、TBSも「有権者に判断材料を示すという高い公共性、公益性がある」と反論するなど、双方の対立はいまも続いている(デイリー新潮・七月三十一日オンライン参照)。 これまでなら、大手マスコミから猛批判を受ければ、有権者の支持を失い、選挙では不利になるはずだが、そうはならなかった。参政党は次々にSNSで動画を発信し、「マスコミは事実を切り取って報じている。日本の六〇〇兆円のGDPをまず日本国民のために使う。これが自国民ファーストだ。そこの何が問題なのか」と切り返していった。SNSを見る限り、参政党を推す声のほうが圧倒的に強いと感じた。ここで強調したいのは、リベラル系の大手テレビや新聞(番組によってはNHKも)が一斉に参政党への批判を繰り広げたにもかかわらず。参政党がその批判をはねのけて躍進したことだ。既存の大手メディアの影響力が低下していることをまざまざと見せつけられた一幕だった。国民民主党は原発推進で勝利 一方、十七議席を獲得した国民民主党は二〇二二年参院選の二倍を超す七六二万票を得て自民党に次ぐ二位の躍進を見せた。その結果、非改選と合わせて、二十二議席を確保、予算をともなう法案(参議院では二十議席が必要)を単独で提出する力を得た。 すでに多くの方がご存じのように、国民民主党は二四年秋の衆議院選挙のときから原発の積極的な推進を公約に掲げているが、有権者からの支持は増えている。以前は選挙で「原発を推進します」と言うと票が減ってしまうため、「原発推進」は選挙に不利な言葉として定着していたが、それを見事にひっくり返したのが国民民主党である。その存在意義は大きい。 一方、日本保守党はエネルギー関連で「再エネ賦課金の廃止」「エネルギー分野への外国資本の参入を禁止する法整備」「わが国の持つ優れた火力発電技術の有効活用」を公約にし、二議席を獲得した。 日本保守党の島田洋一・衆議院議員(福井県立大学名誉教授・国際政治学者)は二四年十二月に提出した石破内閣のエネルギー政策に対する質問主意書で「原子力発電所は発電量当たりの人命リスクがもっとも低い電源であり、燃料の輸入が途絶えた場合でも約三年にわたり発電を続けることができ、エネルギーの安全保障として重要だ」などと述べており、日本の高効率の石炭火力発電所の持続・発展にも高い理解を示している。 興味深いのは、国民民主党、参政党、日本保守党の3党とも「再エネ賦課金の廃止」を訴えていることだ。私はこれまでにも太陽光や風力への過剰な期待(幻想)が反原発運動を支えていると書いてきたが、新たに国会の舞台にニューフェイスとして登場してきた国民民主党、参政党、日本保守党は再生可能エネルギーに過剰な期待を寄せていない。これに対し、自民党には「再生可能エネルギー普及拡大議員連盟」(柴山昌彦会長)があり、太陽光や風力などへの期待を抱く議員たちがたくさんいる。しかも洋上風力発電事業をめぐる汚職事件で秋本真利元衆院議員が起訴(秋本氏は無罪を主張)されるなど、議員と事業者に利権がらみのイメージもあるせいか、国民に良い印象を与えているとはいいがたい。原発はより推進されるのか? 日本経済新聞は選挙が終わった七月二十一日、「与党が大敗し、自公政権の土台は揺らぐが、原子力発電の推進策は維持されるとみられる。議席を伸ばした国民民主党は原発の新増設、参政党は次世代型原発への研究開発を掲げており、原発の推進には前向きな姿勢を示す」と報じた。 自民党が負けたものの、原発推進の国民民主党と参政党が躍進したことで原子力発電の推進策は維持されるという判断だろうが、「維持される」というよりも、むしろ「より推進力が増した」と解したい。原発を推進する力は、再生可能エネルギーに過剰な期待を抱いていない国民民主党、参政党、日本保守党の三党のほうが強いからだ。 今後、三党が国会の場で、原子力政策と再生可能エネルギー政策でどのような言動を見せてくれるのか、注視していきたい。
- 12 Aug 2025
- COLUMN
-

関西電力 次世代型革新炉建設へ
関西電力は7月22日、美浜発電所1号機の後継機(次世代型原子炉へのリプレース)設置の可能性検討に係る現地調査を開始すると発表した。この調査は、2010年に開始していたが、2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、一時的に見合わせとなっていた。国内での新たな原子力発電所の建設は、2009年に運転開始した北海道電力泊発電所3号機(PWR、91.2万kWe)が最後で、実現すれば、2011年の事故以降初となる。政府は、今年2月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画にて、原子力の最大限活用を掲げ、既存サイト内での次世代革新炉へのリプレースを進める方針を明記していた。現地調査では、新規制基準への適合性の観点から、地形や地質等の特性を把握し、後継機設置の可能性の有無を検討する。また、調査結果に加え、革新軽水炉の開発状況や規制の方針、投資判断を行う上での事業環境整備の状況を総合的に考慮するため、「同調査の結果のみをもって後継機設置を判断するものではない」と、同社はコメントしている。美浜発電所は、2015年4月に1、2号機の廃止が決定し、現在は、3号機(PWR、82.6万kWe)のみ稼働している。関西電力の森望社長は「データセンターや半導体産業の急成長を背景に、今後も電力需要は伸びていく。資源の乏しい日本において、S+3Eの観点から、原子力は将来的にわたって役割を果たすことが重要」と述べたうえで、新増設やリプレースに関しては「投資回収の見通しを確保することが重要で、国の政策に基づく事業環境整備などが必要となる」と強調した。同社はウェブ上で「地域の皆様のご理解をいただきながら、安全を最優先に原子力事業を推進していく」とコメントしている。
- 22 Jul 2025
- NEWS
-
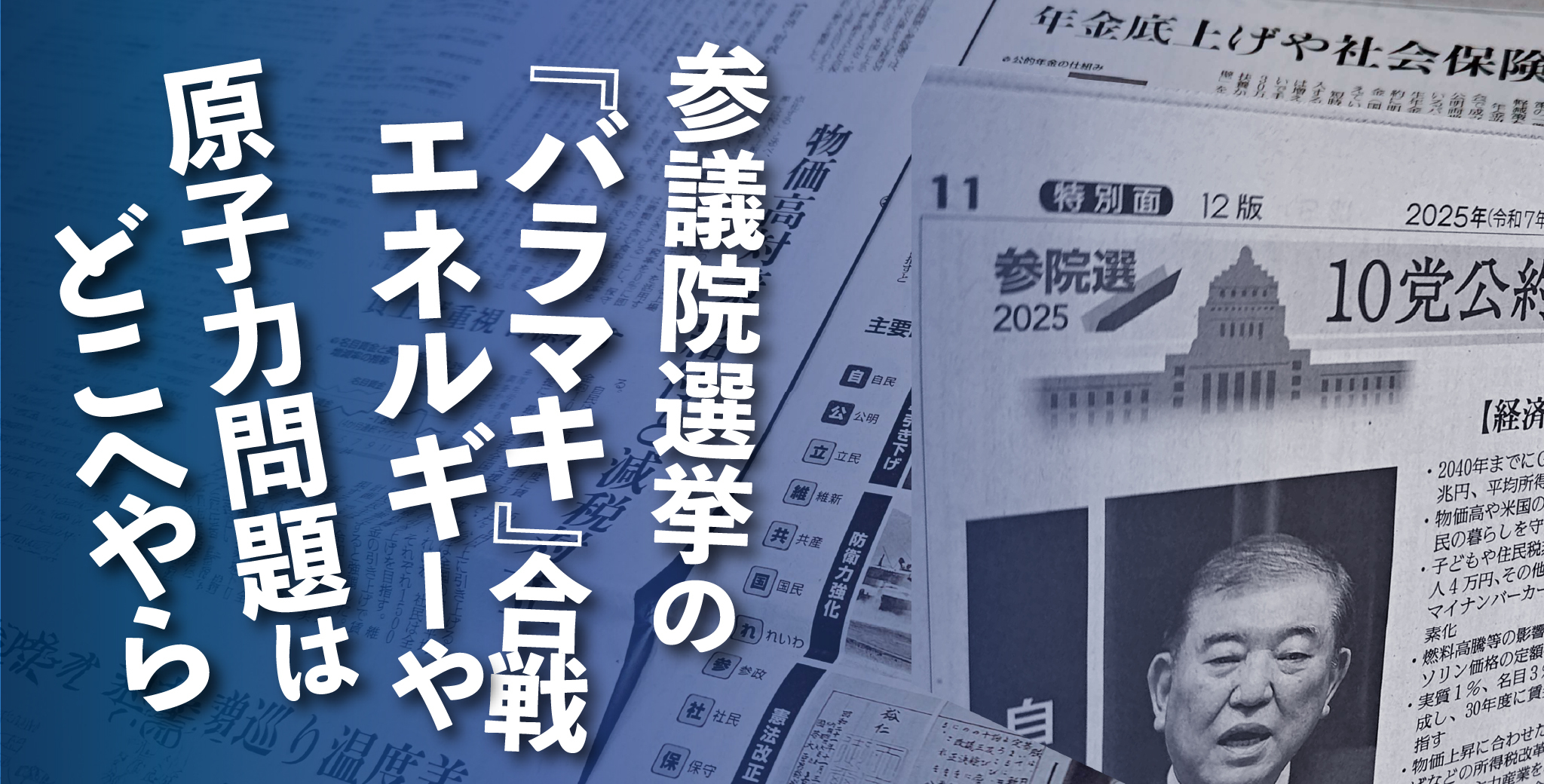
参議院選挙の「バラマキ」合戦 エネルギーや原子力問題はどこへやら
二〇二五年七月十一日 参議院選挙が華やかに繰り広げられている。ただ、三年前の参議院選挙ではエネルギー問題や原子力が大きな争点になっていたが、今回はその様相は全く見られない。各党とも国民の生活向上を訴えているが、そのためには電気、エネルギー、半導体、車など主要産業の確立・強化が不可欠だ。バラマキでは産業は育たない。どの党もバラマキ政策合戦 参議院選挙(七月二十日投開票)が始まってから、大手新聞やテレビをできるだけ見るようにしているが、どの党も手法は異なるものの、長引く物価高で打撃を受けている家計への支援を強調している。自民党と公明党は一人あたり二万円の給付(ただし住民税非課税世帯は一人四万円)、立憲民主党は食卓応援給付金として、一人あたり二万円の即時給付、日本維新の会は食料品の消費税を二年間ゼロ%、共産党は消費税を緊急に一律五%への引き下げ、れいわ新選組は消費税の全面廃止と現金十万円の即時給付、といった具合に聞こえのよいバラマキばかりだ(読売新聞七月二日の記事「10党公約比較」参照)。 三年前の参議院選挙ではロシアのウクライナ侵攻の影響もあってか、原子力やエネルギー政策が大きな争点になっていたが、今回は通常のテレビニュースや新聞記事を見ている限り、エネルギー問題はほとんど顔を出さない。国民民主は原発再稼働を強調 その証拠に、読売新聞の各党公約比較記事(七月二日)を見ても、自民党の公約には「原子力」の文字が見えない。これに対し、日本維新の会は「再生可能エネルギーの導入拡大、次世代原子力発電の推進」をうたい、国民民主党は「安全基準を満たした原発の早期再稼働に向け、規制機関の体制強化」と訴える。自民党と対照的だ。 一方、立憲民主党は「原子力の新増設は認めない」と明記、共産党も「すみやかに原発ゼロとし、石炭火力からの計画的撤退を進め、二〇三〇年度にゼロ」と反原発を鮮明にする。最近、勢いづいている参政党や保守党は同記事では原子力に関する記載がない。原子力に対する各党の立ち位置 では、原子力に対する各党の立ち位置はどうなっているのだろうか。その参考になるのが七月二日の読売新聞だ。たとえば、防衛力の強化では、共産党、れいわ、社民党が同じ位置で慎重な立場をとるのに対し、自民、維新、参政党、保守党、公明党、国民民主党はほぼ同じ位置にいる(写真1参照)。写真1 これと同じように、原子力に対する各党の立ち位置を知りたいところだが、この読売新聞には載っていない。ネットで探したところ、環境問題に取り組む国際的な環境団体「FoEジャパン」が二四年十月に作成した立ち位置図が見つかった(図1参照)。環境団体から見た立ち位置図とはいえ、非常に分かりやすい。自民党、国民民主党、参政党、日本維新の会が原発に賛成、立憲民主党、共産党、れいわ、社民党が原発にブレーキをかける位置にいることが分かる。FOEジャパンによる原子力に対する各党の立ち位置国民民主党がやはりカギか この立ち位置図から分かる通り、立憲民主党、共産党、れいわ、社民党の議席(勢力)が伸びると原子力政策の推進にとっては大きなマイナスとなる。今回の参議院選挙の行方について、毎日新聞は七月七日付け一面記事で世論調査結果を基に「自公苦戦 1人区野党系優位 立憲堅調 国民、参政勢い」と報じた。立憲民主党が堅調で、国民民主党と参政党に勢いが見られるという内容だ。 岸田文雄前首相が決めた「原発の最大限活用」をうたう自民党が衰退し、立憲民主党が伸びれば、確かに原発にとっては逆風となる。しかし、国民民主党と参政党が自民党の劣勢を補う形で伸びれば、原発自体には逆風は吹かないことになる。日本保守党も原発には肯定的だ。保守勢力が割れているとはいえ、原子力自体を否定する政党が勢いを増しているわけではないことが分かる。その意味では、原発推進に積極的な国民民主党の勢力が伸びるかどうかが大きなカギを握るように思える。政治と柏崎刈羽原子力発電所の再稼働 原発の再稼働で気になるのが、東京電力・柏崎刈羽原子力発電所をかかえている新潟県(1人区)の動向だ。新聞を見る限り、自民党新人の中村真衣氏と立憲民主党現職の打越さく良氏の接戦のようだ。中村氏はシドニー五輪銀メダリストの元競泳選手だ。 皆さんもご存じのように、二四年十月の衆議院選挙の新潟小選挙区(五人)で自民党は全敗(比例復活で一人当選したが)し、立憲民主党が五つの小選挙区で全議席を獲得した。 柏崎刈羽原子力発電所の6号機と7号機はいまだに再稼働していないが、政治の影響を受けることは必至だ。今回の選挙で立憲民主党が議席を守るのか注目したいが、そうした中でおもしろい記事をYahoo!ニュースで見つけた。反原発の新聞シェアは約八〇% 最年少で経済誌「プレジデント」編集部編集長を経験した作家、小倉健一氏の「『もはやプロパガンダ』新潟日報」という刺激的なタイトルの記事だ。新潟日報の過去の一連の記事が読者に、「原発は危険で東電は信用できない」という印象を植え付けている、という内容だ。 小倉氏は「日本の未来のために、国益のためにと歯を食いしばり、柏崎刈羽原発の再稼働に向けて奮闘している人々がいることを忘れてはならない。我々は、彼らの努力を正当に評価し、その背中を力強く後押しすべきではないか」と熱く語る。 新潟日報が原発に厳しい記事を書いているという印象は私も抱いているが、それは朝日新聞や毎日新聞、東京新聞にも言え、一民間企業の新聞社がどんな路線の記事(商品)を書こうと自由である。私が興味を抱くのはその新聞社の客観的な影響力である。 日本ABC協会によると、新潟日報の発行部数は約三十四万部(二四年八月現在)。新潟県内の新聞読者に占めるシェアは約七一%と非常に高い。ほぼ一強の状態だ。このほか同県では、読売新聞が約七万三千部、朝日新聞が約二万八千部、日経新聞が約一万八千部、毎日新聞が約一万千部、産経新聞が約五千二百部だ。 この状況を原子力への風当たり指数として見ると、朝日、毎日新聞も反原発路線なので、新潟日報と合わせるとその合計部数は三十七万九千部となる。つまり、新潟県内の新聞読者の約八〇%は反原発かそれに近い記事を読んでいることになる。 それら約八割の読者のすべてが反原発を支持しているとはいえないだろうが、日々接しているニュースが何かしら原発に否定的な印象を与えていることは確かだろう。原発の再稼働がなかなか前進しない背景には、こういうメディア的状況もある気がする。 株式会社マイナビによると、新潟日報の年間売上は約百四十一億円(二三年十二月期)、従業員は五百十九人(二四年四月現在)。会社の規模としては決して大企業と言えるほどの会社ではない。いや小さな会社といってよい。しかし、情報を通じた影響力では七割のシェアを誇り、新潟県民の気持ちを支配する印象操作力をもっている。地元紙の力、恐るべしである。強固な産業の確立こそが重要 選挙では生活支援が争点になっているが、電気やエネルギーも含め、モノやサービスを国民に安く、かつ安定して供給できるのは主力産業の基盤がしっかりと確立され、生産性が上がったときの話だ。かつて岸田文雄前首相は「原発一基の再稼働で百万トンの天然ガスの輸入が節約できる」と訴えていた。LNG(液化天然ガス)一トンあたりの輸入価格はおおよそ九~十万円なので、再稼働で約千億円の国富の流失を防ぐことができる。いま重要なのは「富」を創り出すことであり、ばらまくことではない。メディアは批判することは得意だが、富を生み出すことには関心が低いことをつくづくと感じる。
- 11 Jul 2025
- COLUMN
-

新聞記事の影響力は「拡散不可」でますます縮小か
二〇二五年五月二十七日 新築戸建て住宅への太陽光パネルの設置を義務付ける東京都の改正条例が今年四月から施行された。「太陽光は環境にやさしく、電気代が節約できる」といったミスリード記事が多い中、産経新聞(四月六日付)に「再エネ賦課金 家計にずしり」と題したおもしろい記事が載った。こういう記事こそ拡散を期待したいが、大手新聞の記事はほとんど拡散しない。そこがSNSと比べた場合の最大の弱点かもしれない。再エネ賦課金の累計は二十五兆円 原子力発電への風当たりが依然として強い背景には、太陽光発電を全国くまなく拡大すれば、原子力がなくても電気エネルギーがまかなえるという幻想があるからだと、私は常々考えている。太陽光に関する大手メディアの記事の多くは「再生可能エネルギーの切り札といえる太陽光発電」といった根拠なき称賛の表現が目立つ。 そうしたメディア空間に慣れきっていたところ、四月六日付産経新聞の1面トップに「太陽光未稼働8万件失効 高額買い取り認定分 政府『国民負担4兆円抑制』」との見出しの記事が目に飛び込んできた。同じ紙面の3面には「再エネ賦課金 家計にずしり 電気料金の1割超 月1600円上乗せ」との解説記事が載った。 太陽光発電や風力発電などの事業者が発電した電気を電力会社が一定の価格で長期間、買い取ることを義務づけた「固定価格買い取り制度」(FIT)は二〇一二年にスタートした。電力会社がその一定の価格で買い取るときに上乗せされているのが「再エネ賦課金」(正式名称は「再生可能エネルギー発電促進賦課金」)だ。電気を使うすべての人がこの賦課金を負担する。言ってみれば、国民全員が負担する税金のようなものだ。 この賦課金の単価は二〇一二年以来上昇し続け、二五年度の賦課金単価は一キロワット時あたり三・九八円と過去最高になった。標準家庭で見ると月額千六百円程度の負担増となるが、制度が始まってからの累計額を見ると、なんと約二十五兆円にもなる。太陽光の普及で電気代が安くなっているかと思いきや、現実は逆で、国民の負担は重くなっている。二十五兆円もあれば、国民のためにいろいろな社会的事業ができたのにと思うのは私だけだろうか。旧民主党政権の負の遺産 そもそもは当初の買い取り価格が高過ぎたのだ。確かに太陽光発電の事業者には利益が転がり込むだろうが、日本経済全体でみれば、電気代のコストはどんどん上がっていく。太陽光発電が原子力の代替にならないのは設備利用率が二〇%以下と低いからだ。欧州諸国は太陽光や風力発電の先進国といえるが、実は、太陽光と風力が普及している国ほど家庭の電気料金は高い(杉山大志著『データが語る気候変動問題のホントとウソ』参照)。だが、メディアの中に太陽光幻想が続くせいか、こんな当たり前のことが意外に知られていない。 この賦課金制度は旧民主党政権時代の「負の遺産」として末永く語り継ぎたいが、すでに制度として定着している以上、今それを言っても仕方がない。こうした中、この非合理な制度を解消しようと必死になっているのが国民民主党だ。前述の産経新聞記事によると、再エネ賦課金の一時停止や見直しを主張する国民民主党は昨年三月、「再エネ賦課金停止法案」を提出したという。今後の活動に期待したいが、国会での関心は低いようだ。二〇四〇年代に五十万トンのパネル廃棄物 太陽光発電に関する記事といえば、毎日新聞が五月十四日に報じた「太陽光再資源化見送りへ 費用負担誰が 推進偏重ツケ」との見出しの記事もよかった。太陽光パネルを全国に広めていけば、いずれ寿命が来て廃棄される。二〇四〇年代前半には最大で五十万トンもの廃棄物が発生する見込みだという。環境省と経産省はパネルの所有者に解体費用を、製造者にリサイクル費用を第三者機関に納めさせ、リサイクルを促す法案を用意したのだが、内閣法制局から修正要求があり、法案の提出が見送られたという。 太陽光パネルが増えれば、いずれ大量廃棄がやってくるのはだれにも分かっていることだが、毎日新聞の記事は、冒頭の「脱炭素エネルギーの切り札として導入が広がる太陽光発電」との枕詞を除けば、その課題を分かりやすく解説した良い記事だといえる。新聞記事は著作権法の著作物 今回は、太陽光発電の課題を突く記事を二つ紹介したわけだが、残念なのは、こういう良い記事を見つけても、その内容を拡散できないもどかしさだ。上記の産経新聞の記事はネットでもほぼ公表しており、だれでも読めるが、記事自体を勝手に広めることは難しい。記事は有料の商品だからだ。 そもそもメディアの目的は何だろうか。それは自社の報じた記事(ニュース)を少しでも多くの人に知ってもらうことだろう。しかし、残念ながら、新聞の記事を他の人に届けようと思っても、記事は新聞社の知的財産とあって、コピーして配ることはできない。記事をコピーして、そのコピーをネットでみなに知らせることもできない。インターネットがあまり普及していなかった時代には、新聞記事を大量にコピーして、仲間に配っても、お咎めはなかったが、今は厳しい。新聞記事は著作権法で保護された著作物であり、著作者の許諾なしに記事を複製して配布することは禁止されているからだ。 しかも、新聞記事の大半はネットでは無料で読めず、多くは有料の情報だ。有料の情報を無料で拡散すれば、商品のタダ売りになってしまい、メディア自体の自殺行為になってしまう。無料で情報を発信すれば、取得するのにかかったコストも回収できない。つまり、新聞社は自社のニュースを拡散させて広く知ってほしいと思っても、その目的を達成できないのである。ニュースの価値は拡散こそにある 大手新聞の購読者が激減している中で、どの新聞社も記事を少しでも有料で売ることに腐心し、職場などでの記事のコピー配布にますます目を光らせている。しかし、そうなるとますます新聞記事は拡散できず、かつてのようなマスコミ的な影響力を行使できなくなる。 つまり、いくら良い新聞記事を見つけても、それを不特定多数の大勢に知らせることができないのだ。かたやSNSの世界では、信頼度の有無はさておき、コピーして知らせると言う意味ではほぼ無限に情報を拡散できる。 昨年秋の兵庫県知事選の情報戦では大手メディア(新聞やテレビ)の発信力(情報の拡散力)が、無数の人たちがプレーヤーとなるSNSの発信力(情報の拡散力)に負けた事例だ。大手メディアはもはや昔のように、何百万人もの読者に一度に情報を届けるマスメディアではなくなってきている。 米国を拠点に活躍する新進気鋭の現代美術家、松山智一氏がテレビ番組で次のようなニュアンスのことを言っていた。作品を作っただけでは何の影響力も感化力もない。その作品に共感する人がいて、その共感の輪がくまなく広がっていって初めて、作品の影響力が生まれる。周囲の反応と拡散という関係性こそが作品の価値を広めていく。 それを聞いていて、新聞の記事も同じではないかと思った。記者が記事を書いただけではその価値はまだ低い。拡散して、人の心に突き刺さったときに初めて大きな価値が生まれる。そう、拡散こそが価値を生み出すのだ。 兵庫県知事選でSNSが発揮したパワーはまさに「拡散力」にあった。大手新聞社が自社記事をもっと国民に読んでほしいのであれば、課金なしで拡散させるビジネスモデルを考えないとその影響力はますます低下していくだろう。((編集部注:原子力産業新聞は、どなたでも登録なしで、全ての記事が無料でご覧になれます。))
- 27 May 2025
- COLUMN
-

「正しいことはすごくつまらない」にメディアは迫れるか
二〇二五年五月七日 気候危機を煽るニュースが毎日のように流れているが、今回は「それって本当にエビデンス(科学的根拠)があるのですか」と真摯に問いかける書籍を紹介したい。世の中が熱くなっているときこそ、世間の「空気」に抗う冷静な思考が必要だ。メディア関係者や気象関係者にとっては必読のテキストといってもよいだろう。大規模停電でも地球温暖化が関係? 四月二十九日朝に放映されたテレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」を見ていて、びっくり仰天した。スペインで起きた大規模停電の原因について、アナウンサーの羽鳥慎一氏が「これも地球温暖化の影響かな」と言ったのだ。そして、ゲストコメンテーターも「サイバー攻撃かもしれないが、急に暑くなって一斉に電気を使ったのか」とのコメントも流れた。 常識的に考えて、突然の大規模停電が地球の温暖化によって起きたと想像するのは難しい。地球温暖化といっても、百年間で一℃程度の気温上昇でしかない。それが大規模停電を引き起こしたと考えるのはあまりにも論理の飛躍である。にもかかわらず、テレビや新聞のメディア関係者はことあるごとに「温暖化が原因では」という言葉を安易に気軽に使う。 テレビ朝日の『有働Times』(三月三十日放送)でも「世界的に温暖化が進むと山火事が起こりやすくなる」と報じていた。いうまでもなく温暖化があまり進んでいなかったときでも、山林火災は世界で発生していた。「温暖化が原因」という言葉が安易に使われている状況を見ていると、メディア関係者は温暖化による地球規模の影響を正しく(科学的かつ統計的に)見ていないのではないかと思う。台風は激甚化していない そういうメディアのゆがみ(バイアス思考)に対して、うってつけのテキストが登場した。キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の杉山大志氏(物理学)が著した『データが語る気候変動問題のホントとウソ』(電気書院)だ。杉山氏は気候変動問題やエネルギー政策の論客だ。この本は難しいテーマを非常に分かりやすい言葉で解説し、中学生でもスラスラと読める。 杉山氏は温暖化自体を否定しているわけではない。しかし、「温暖化によって山林火災など自然災害が激甚化している」という言説には疑問を呈する。 たとえば、よく「地球温暖化のせいで台風が激甚化し、頻発している」とのニュースが流れるが、杉山氏は「そんな事実はない」と気象庁などのデータを用いて、詳しく反論している。日本のスーパー台風のランキングをみても、一九五〇年~六〇年代に頻発していた。昭和の三大台風(室戸台風、枕崎台風、伊勢湾台風)は一九三〇年代~五〇年代に起きている。私の自宅(愛知県犬山市)は伊勢湾台風(一九五九年)で半壊した。そんな辛い経験をもつ私にとっては、このことはとても実感できる。いまメディアにいる人たちはそのころの台風を知らない。知らなければ疑問の持ちようがない。ホッキョクグマは減っていない 同書によると、メディアが知っておくべき事実はほかにもたくさんある。「ホッキョクグマは減っていない」「気象災害による死亡数は減っている」「豪州最大のサンゴ礁(グレートバリアリーフ)は一時、半分消滅したといわれていたが、いまはV字回復した」(豪州海洋科学研究所は回復したデータを公表しなくなったという)「太平洋の島しょ国は水没の危機にはない」「世界の食料生産は過去五十年間、温暖化が進んだのに増え続けている」「米国の山火事による森林燃焼面積は一九三〇年代のほうがはるかに多かった」「世界の沿岸の陸地面積は拡大している」。メディアは都合のよいデータだけを探す ではなぜ、メディアは気候危機を煽るのか。それは、大しておもしろくもない統計的事実よりも、感情に訴える刺激的な物語(ストーリー)を好むからだ。 台風の激甚化に関して、杉山氏は次のように述べる。「地球温暖化によって台風が激甚化するといったストーリーを決めていて、それに合うデータだけを探し回る。ストーリーに合わない不都合なデータは無視する」。 全くその通りだ。森林火災や大洪水が起きると、メディアは勝手に温暖化のせいだと決め込んで物語(記事やテレビ番組)を作る。そういうメディア(特にNHKの特集番組はひどい)のバイアスぶりに関しては、私を含め十三人で執筆した「SDGsエコバブルの終焉」(宝島社)の第4章に書いたので、重複は避けたいが、ひと言でいえば、メディアの記者たちは温暖化が進んでいなかった時代にも、同様の大災害が起きていたのではないか、という記者なら常識的な想像力を全く働かせていない。 もうひとつ、杉山氏の本から例を挙げれば、東京では寒さによる死亡(呼吸器疾患や心臓まひなど)は暑さによる死亡(熱中症など)よりも三〇倍も多い。だが、メディアは暑いときに死亡した例を大きくニュースにする傾向がある。東京の例以外でも、「インドで熱波によって一〇〇人が死亡した」といった具合に、温暖化にかかわる事件となるとビッグニュースになりやすいバイアスがある。太陽光や風力への幻想 「エネルギー政策」と題した4章も一読に値する。朝日新聞、毎日新聞をはじめとするリベラル系メディアは依然として反原子力のスタンスだが、その背景には太陽光や風力発電を拡大すれば、化石燃料や原子力がなくても豊かな経済は維持できるという前提(思い込み)があるように思える。しかし、これは幻想である。 よく太陽光で電気代が安くなるといわれるが、これは太陽光パネルが夜や雨などで止まっているときに火力発電や原子力発電などの支援を受けているトータルコストが計算に含まれていないからだ。西欧を見れば分かるように、太陽光や風力が増えた国ほど電気代は高い。しかも太陽光パネルの約八割は中国でつくられる。これだけ中国依存が高いと、むしろそのほうが危機的だと私は思うが、メディアはそういう事実にほとんど触れない。世間の空気に抗う勇気を どうしたら、メディアのバイアスが食い止められるのかと思っていたところ、毎日新聞が四月二十五日付紙面で戦後80年を振り返る特集記事(専門家を交えた座談会)を組んだ。その中で作家の温又柔(おん・ゆうじゅう)さんは、SNS(交流サイト)では正しくない話のほうが波及するという見方に対して、「正しいことはすごくつまらない。だからこそ、こうしたつまらなさに耐えるのが今とても重要だ」と述べた。確かにそうだ。 それに対し、毎日新聞主筆の前田浩智氏は、「『空気』に抗する勇気」と題した総括的コメントとして、戦争反対を唱える国民の声はかき消されたという過去を踏まえ、「つまらない正しさがゆがんだ空気に水を差す。改めてかみしめたいポイントです」と書いた。 これを気候変動問題に置き換えてみる。統計的事実を無視して、温暖化の危機を散々煽るメディアの刺激的な空気に対して、「台風は激甚化していない」「ホッキョクグマは減っていない」といった事実は、大して興味をそそらず、つまらないほどの正しさだ。 だが、はたして、いまになってメディアはその「つまらない正しさ」に耐えられるのだろうか。メディアの使命は事実を突きつけることだ。少なくとも空気に抗う勇気を見せてほしい。
- 07 May 2025
- COLUMN
-

原文財団「原子力に関する世論調査」の最新版を発表
日本原子力文化財団はこのほど、2024年の10月に実施した「原子力に関する世論調査」の調査結果を発表した。18回目となるこの調査は、原子力に関する世論の動向や情報の受け手の意識を正確に把握することを目的として実施している。なお、同財団のウェブサイトでは、2010年度以降の報告書データを全て公開している。今回の調査で、「原子力発電を増やしていくべきだ」または「東日本大震災以前の原子力発電の状況を維持していくべきだ」と回答した割合は合わせて18.3%となった。一方、「しばらく利用するが、徐々に廃止していくべきだ」との回答が39.8%となり、両者を合わせると原子力の利用に肯定的な意見は過半数(58.1%)を超えた。このことから、現状においては、原子力発電が利用すべき発電方法と認識されていることが確認できる。一方、「わからない」と回答した割合が過去最大の33.1%に達し、10年前から12.5ポイントも増加していることが明らかになった。「わからない」と回答した理由を問うたところ、「どの情報を信じてよいかわからない」が33.5%、「情報が多すぎるので決められない」が27.0%、「情報が足りないので決められない」が25.9%、「考えるのが難しい、面倒くさい、考えたくない」が20.9%となっている。この「わからない」と回答した割合はすべての年代で増加しているが、特に若年世代(24歳以下)の間で増加傾向が高かった。また、同調査は、「原子力やエネルギー、放射線に関する情報源」についても分析を行っている。その結果、若年世代(24歳以下)は、「小・中・高等学校の教員」(27.2%)を主な情報源として挙げており、また、SNSを通じて情報を得る割合が、他の年代と比較して高いことがわかった。原文財団では、若年世代には、学校での情報提供とともに、SNS・インターネット経由で情報を得るための情報体系の整備が重要だと分析している。また、テレビニュースは年代を問わず、日頃の情報源として定着しているが、高齢世代(65歳以上)においても、ここ数年でインターネット関連の回答が増加している。「原子力という言葉を聞いたときに、どのようなイメージを思い浮かべるか」との問いには、「必要」(26.8%)、「役に立つ」(24.8%)との回答が2018年度から安定的に推移している。「今後利用すべきエネルギー」については、2011年以降、再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力・地熱)が上位を占めているものの、原子力発電利用の意見は高水準だった2022年の割合を今も維持していることがわかった。再稼働については、「電力の安定供給」「地球温暖化対策」「日本経済への影響」「新規制基準への適合」などの観点から、肯定的な意見が優勢だった。しかし、再稼働推進への国民理解という観点では否定的な意見が多く、再稼働を進めるためには理解促進に向けた取り組みが必要であることが浮き彫りとなった。また、高レベル放射性廃棄物の処分についての認知は全体的に低く、「どの項目も聞いたことがない」と回答した割合が51.9%に上った。4年前と比較しても、多くの項目で認知が低下傾向にあり、原文財団では、国民全体でこの問題を考えていくためにも、同情報をいかに全国へ届けるかが重要だと分析している。
- 28 Mar 2025
- NEWS
-
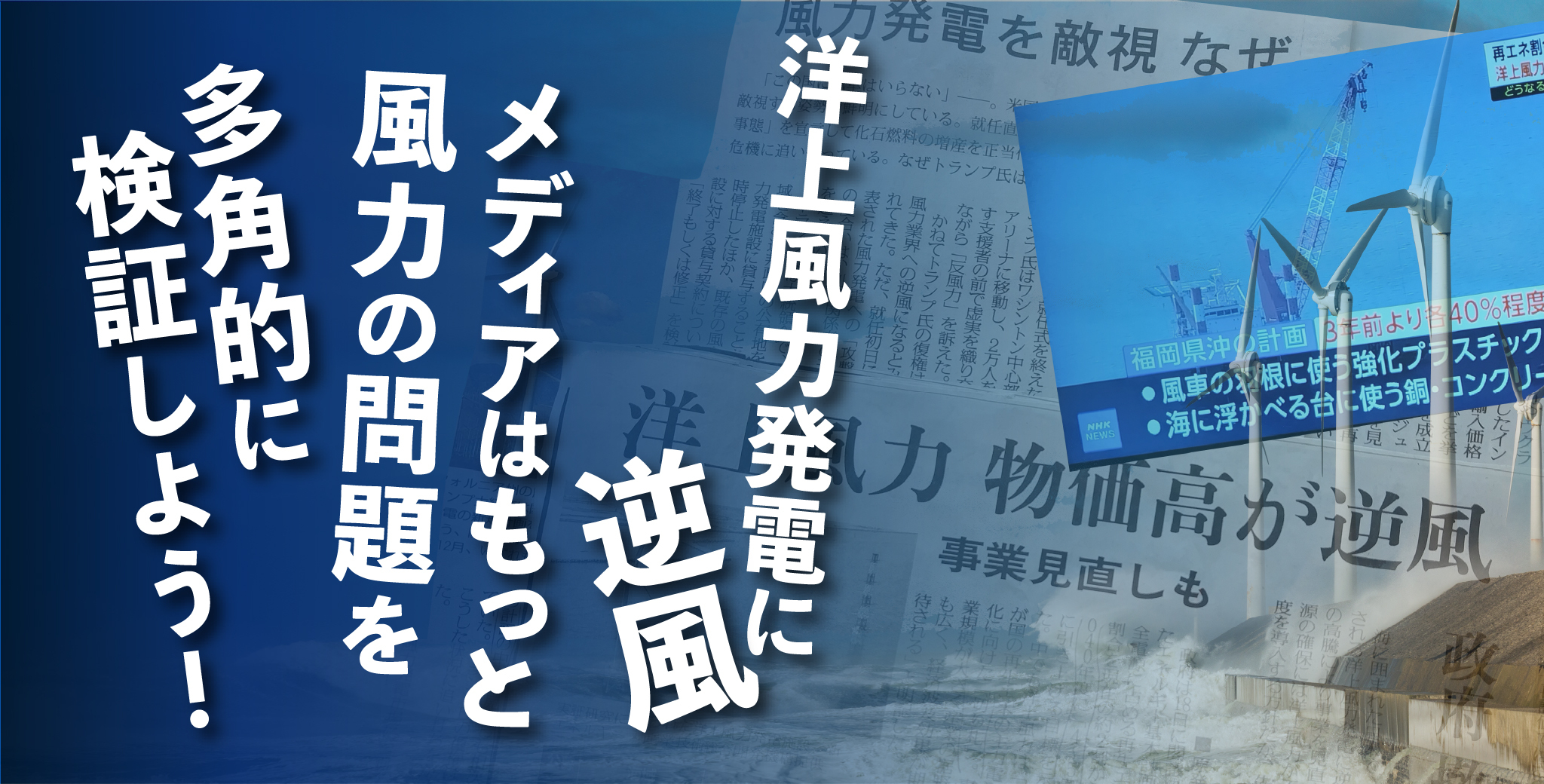
洋上風力発電に逆風 メディアはもっと風力の問題を多角的に検証しよう!
二〇二五年三月三日 風力発電に逆風が吹き始めたというニュースが目立ってきた。米国のトランプ大統領が風力を敵視しているのも逆風になっているようだ。ただ、よくよく考えてみれば当たり前の風が吹いているに過ぎない。大手メディアはもっと風力の限界を定量的にしっかりと検証してほしい。NHKのニュースウオッチ9 「洋上風力発電に逆風」と題して報じられたNHKの「ニュースウオッチ9」(二〇二五年二月十八日放送)を見た人は、日本各地の沖合で計画されている洋上風力発電事業がコスト高で暗礁に乗り上げているとの印象をもったのではないか。私も見ていて、そう思った。 同ニュースによると、卸電力大手の電源開発(J-POWER)が福岡県沖で工事を進める洋上風力発電事業において、風車の羽根に使う強化プラスチックやコンクリートなどの資材費が三年前に比べて約四〇%も上がり、黒字が確保できるのか先行きに不安が広がっているという。同社幹部の「お金の使い方として本当にいいのかと悩み、逡巡している」との悲観的なコメントまで流れた。 NHKは翌十九日にも水野倫之解説委員の「洋上風力に逆風 再エネの切り札に何が?」と題した解説記事をオンラインで公開した。その内容の一部はこうだ。 「洋上風力の先行きが見通せなくなってきている。 三菱商事と、中部電力の子会社などでつくる企業グループは、秋田と千葉県沖の三つの一般海域で、四年前に国の選定を受け洋上風力発電事業を進めており、大規模事業の先駆けとして注目されてきた。しかし今月、三菱商事が五百二十二億円、中部電力が百七十九億円の損失を計上し、『事業をゼロから見直す』と発表。トランプ大統領が風力に批判的なこともあり、すでに米国では事業見直しが相次いでいる」(一部要約)大手新聞も「逆風」を報道 NHKだけではない。読売新聞(二月六日付千葉版)は銚子市沖で進む洋上風力発電事業に関して「着工めど立たず 資材高騰で事業再評価へ」と報じた。翌七日付では全国版でも秋田県と千葉県銚子市沖の三海域で進む洋上風力事業について「洋上風力五百二十二億円減損 三菱商事 資材高騰 事業見直し」と報じた。さらに二月二十日付では全国版経済面で「洋上風力物価高が逆風 政府 撤退防止へ対策導入」との見出しで「政府は二〇四〇年度に再エネの割合を四~五割に引き上げる目標を示したが、政府目標に暗雲が漂い始めている」と長文の記事を載せた。 朝日新聞(二月六日夜オンライン)も三菱商事が洋上風力発電で「五百二十二億円の減損」と報じた。日本経済新聞(二月十九日)も「先行事業者の三菱商事が巨額の損失計上に追い込まれるなど逆風も吹き始めた」と報じた。 また、毎日新聞(二月十八日付)はトランプ大統領の「風車は鳥を殺し、美しい風景を台無しにする。大きく醜い風車はあなたの近所を破壊する」など過激な発言を紹介し、風力を敵視している状況を伝えた。記事自体はトランプ大統領を批判する内容だが、米国でも風力発電は資材費の高騰や金利の上昇などで計画の中止や見直しが相次いでいるとの内容も報じた。風力はバックアップ電源が必要 これらのニュースで分かるように、これまで洋上風力発電は再生可能エネルギーの切り札としてたたえられてきたが、もはやその名称にふさわしくない状況がうかがえる。 しかし、考えてみれば当たり前である。風力はそもそも風まかせの発電である。一年中、常に風が吹いているわけではない。雨や雪、夜に稼働しない太陽光発電よりはややましとはいえ、経済産業省によると、風力の平均的な設備利用率は陸上風力で約二〇%、洋上風力でも約三〇%しかない。 これは、風車が動いていないときは、火力発電や原子力発電などのバックアップ電源が必要になるという意味で根本的な弱点である。風力発電事業に関わる商社マンの知人の話では、「風力を導入する場合は、バックアップ電源として液化天然ガス(LNG)の火力発電所をセットで導入する必要がある。このことが一般市民にほとんど知られていない。それを言っちゃうと風力の魅力がなくなっちゃうからね」と話していた。 つまり、風力発電への投資はマクロ経済的に見れば、二重投資なのだ。バックアップ電源や電気を送るための送電網費用などを含めると、風力発電のコストはさらに高くなる。 大手メディアのニュースを読んでいて、何か物足りなさを感じるのは、風力発電に伴うバックアップ電源の必要性に関する検証内容が、ほとんど出てこないからだ。洋上風力のメリット これまでメディアでは洋上風力発電のメリットとして、①発電時にCO2を排出しない②発電コストが安い③化石燃料に依存せず、自国のエネルギー安全保障につながる④地域の雇用確保と地域経済の振興に寄与する⑤陸上風車よりも設置しやすく、騒音や景観問題が少ない⑥沖合では強い風が持続的に吹く──などが言われてきたが、どれも大きなメリットとは言い難いことが露呈してきたのではないか。 経産省によると、欧米での洋上風力発電(着床式)の発電コストはkWhあたり約九円といわれるが、その欧米でさえ、資材の高騰などで発電事業への入札が成立せず、事業の撤退や縮小が相次いでいる。 秋田県沖の二海域と千葉県銚子市沖での洋上風力発電事業で三菱商事が落札した価格はkWhあたり約十二円~十六円だった。この額は政府の想定を大幅に下回る額だった(読売新聞二月七日付)。コストを極力抑えようとした企業努力は評価したいが、事業の見直しが進めば、結局、電気料金の跳ね上がりとなって庶民の財布を直撃することになるのではと危惧する。自前の技術をもたない悲しさ いくら風力発電を増やしても、自国のエネルギー安全保障の強化につながるかが見通せないことも気がかりである。 かつては日本にも風力発電機メーカーが存在したが、いまでは二MW(二千kW)以上の大型風力発電機メーカーは存在しない(二〇二四年七月八日朝日新聞SDGs ACTION!)。つまり、日本が大型の風力発電機を導入したとしても、欧米のメーカーに頼らざるを得ないのが現状である。自前の技術者がいなければ、普段の維持運用だけでなく、何か故障が起きたときにも自前では復旧できないことを物語る。これではとてもエネルギーの安全保障が確保できるとは思えない。大手メディアは洋上風力の検証記事を 国が経済的な採算を度外視してまで洋上風力を推し進めるのは「脱炭素」という不可侵の目的があるからに他ならない。合理的な経済計算で判断すれば、コストの高い洋上風力よりも、いまは原子力の再稼働を一日も早く進めることが一番理にかなっているといえるが、大手メディアはそこまで踏み込めない。 洋上風力の舞台となっている秋田県能代市のホームページを見ていたら、次のような解説があった。 「洋上風力発電は一基二万点もの部品が必要で、事業規模も大きいため、関連産業への経済波及効果は大きいものがあります。風車設置後も設備メンテナンスや風車部品の供給など、地域活性化につながる産業となります。」 その通りになってくれればうれしいが、願望のように思える。大手メディアは、こうした洋上風力のメリットが本当に実現するかも含め、多角的な検証作業をしてほしい。
- 03 Mar 2025
- COLUMN
-

アツイタマシイ Vol.9 クリスティン&ザイツ
ディアブロキャニオンの延長を勝ち取る運転期間延長を勝ち取りましたね。20年でしたか?クリスティンありがとうございます。ディアブロキャニオン原子力発電所を所有するパシフィック・ガス&エレクトリック(PG&E)社が、運転期間の20年延長を申請し、米原子力規制委員会(NRC)が受理しましたので、いずれライセンスが更新されることは間違いありません。ですが発電所の運転期間に関してはカリフォルニア州にも決定権があるのです。今のところ州政府は、5年の延長が妥当だと考えているようです。私たちMothers for Nuclear(MfN)は、その期間をもっと延長するよう、州政府に働きかけているところです。運転期間延長が決まり、MfNはより幅広い活動を展開するようになったのですか?ハザーそれは違います。2016年にMfNを始めたとき、カリフォルニア州における原子力発電所は非常に厳しい状況に置かれていました。ディアブロキャニオンの閉鎖は既にPG&Eによって決定されていたので、MfNは他の州や国で、原子力を支持する活動を行っていたのです。ですがここ数年間で、カリフォルニア州の状況は大きく変わりました。州政府は、停電を回避するには原子力が必要であることを認識したようです。そのためMfNも、ディアブロキャニオンを護る活動に力を入れ、原子力の重要性についてのコミュニケーションを展開しています。他の地域でも引き続き活動を続けているので、活動の幅が広がったように見えるのでしょうね(笑)カリフォルニアの現在のエネルギー構成は?クリスティンカリフォルニア州には多くの再生可能エネルギーがありますが、既存の原子力発電所を閉鎖するとエネルギー不足に陥ります。原子力はカリフォルニアのエネルギーミックスの欠かせない一部なのです。カリフォルニアの世論はどうですか?クリスティン2016年に始めたとき、全米で原子力の支持率は低下していました。しかし、最近では、電力供給の現実を直視するようになり、原子力が必要だという意識が高まってきています。2024年には、カリフォルニア州民の大多数が原子力を必要だと考えているという驚くべき数字が出ました。カリフォルニアの人々はシュワルツェネッガーのように、太陽光や風力が好きだと思っていました(笑)クリスティンはい。私たちは再生可能エネルギーを愛していますが、再生可能エネルギーと原子力は両立できるものだとも思っています。再生可能エネルギーだけでは限界があるので、原子力も重要な役割を果たすべきです。ハザーカリフォルニア州はすでにかなり多くの再エネ電源を持っていますが、そろそろ限界に近づきつつあります。再生可能エネルギーは特定の時間帯にしか電力を生産できないため、貯蔵設備を作らなければならず、そのためのコストもかかります。そのため、カリフォルニア州の電力は米国で最も高いレベルとなっています。この現実が、私たちの議論を原子力という選択肢にシフトさせる要因となっているのです。また、私たちの電力供給の半分は天然ガス火力であり、30%は他州から輸入しています。つまり、まだ多くの課題が残っており、あらゆる選択肢が必要だと実感しています。クリスティン実は、日本と似た状況なのだと思います。カリフォルニアもエネルギーを輸入しています。日本はもっと多くを輸入しているかもしれませんが。一方でカリフォルニアは隣の州から電力を送ることができるという利点がありますが、日本は島国なのでそのような選択肢がありませんね。そのため、カリフォルニアは日本よりも少し長い間、現実から目を背けていられるような形です。日本はその地理的制約から、早く現実と向き合わなければならないと思いますよ。カリフォルニアの反原子力運動は少数派MfNを始めた理由は?クリスティン私たちがMfNを始めた理由の一つは、カリフォルニアにも原子力に反対する活動家グループがあり、メディアの注目を集めていたからです。彼らは非常に声が大きく、コミュニティ全体が原子力に反対しているという印象を与えますが、実際には少数派なのです。だからこそ、MfNとして活動し、その“ナラティブ”に対抗することが重要だと思いました。反原子力の活動家は決して人々の声を代表していません。しかし、残念ながらメディアはそのように取り上げています。ハザーもう一つ、MfNを始めた理由は、会社(PG&E)が言わないことや言えないことを言いたかったからです。幸いにも、会社は私たちがそれを行うことを許してくれました。私たちが会社を代表していないこと、会社とは別の組織であることを明確にする限り、非常にうまくいっています。ソーシャルメディアが企業にとってリスクがあることを、私たちは認識しています。企業は将来的な経営を見据えて、常に保守的なメッセージを発信しますが、私たちがそれを損なうようなことをしたくありません。ですから、会社が懸念を持った場合は、常に私たちに連絡するように伝えています。私たちからも、私たちが何をしているのか、なぜそれをしているのかを伝え、常に透明性を持って会社と話し合っています。MfNのメインでのコミュニケーション活動は、対面での対話集会でしょうか?ソーシャルメディアを使った活動も多いようですが。クリスティン対面でもSNSでも、あらゆる機会をとらえて活動しています。最近は原子力産業界を対象に、どのようにコミュニケーションをしていくべきかをお話ししています。より多くの人が原子力の価値を共有し、それを地域社会に持ち込むことで、さらに加速的に広がるのです。原子力業界のイベントでお話することもありますが、原子力を支持しないグループや政治団体、学校などでもお話します。もちろん、SNSやウェブサイトも活用しています。ハザーSNSは、対面のイベントでは届かない広い範囲にリーチすることができます。クリスティン対面イベントは素晴らしい機会なのですが、どうしても限定的になります。十分な人々に届きません。ですから、もっといろいろな方法でコミュニケーションを図る必要があります。STEM分野に女性を対面でのコミュニケーションは限定的とはいえ、効果が絶大で強力なツールなのではないでしょうか?昨春JAIFは米国からグレース・スタンケさんを招聘し、日本の中学生や大学生たちとディスカッションする場を設けました。ハザー素晴らしい。若い人同士のディスカッションは盛り上がったのではないですか?特に女学生たちが大いに影響を受けていたようです。日本では、STEM分野(科学、技術、工学、数学の4分野)の女性が少ないことが問題になっているのですが、その理由の一つに、ご家族がSTEM分野へ進むことに反対しているということがあるのです。クリスティン興味深いですね。ご家族はSTEM分野全体に反対しているのですか?それとも原子力に反対しているのですか?私も驚いたのですが、ご家族は娘さんがSTEM分野に進むこと自体に反対しているそうです。もちろん、原子力なんてもってのほかかもしれません。クリスティンSTEMという分野では、時には危険なこともありますからね。スタンケさんのようなSTEM分野で活躍する女性たちは、後に続く女性たちにとって大変良いモデルケースになります。特に日本の女学生にとっては、大きな励みになると思います。クリスティンそうですね。私たちも、もっと多くの女性たちがSTEM分野に進み、特に原子力業界に関わってくれることを強く望んでいます。女性が増えることでチーム全体が強くなり、より良い仕事ができると思うのです。ハザー私は原子力発電所のオペレーターとして、男性たちとチームを組んで仕事をしていますが、自分の貢献は少しばかり特別で、ユニークだと感じています(笑)コミュニケーションの方法が違いますし、気に掛ける点も違います。こうした「違い」がチームを強くし、どんなに異常事態にも対応できるようになるのです。そのためにも女性の力が必要です。もっと多くの女学生にSTEM分野に関心を持ってもらいたいですね。原子力コミュニティが大きく成長COPにも参加されたそうですね。クリスティンはい。ドバイのCOP29に参加しました。11歳の娘と一緒に。とても特別な経験でした。エネルギッシュな会議でしたね。原子力に対する世界的な支持を見るのは本当に励みになりました。またドバイでは、「エコ・ニュークリア」というスペインのNPO団体と知り合いました。スペインで原子力発電プラントを閉鎖の危機から救うために非常に努力しているグループです。彼らはMfNがカリフォルニアで経験したのと同じような課題に直面しています。ですから、私たちはそのことに多くの共感を感じました。MfNは最初、二人の個人から始まりました。原子力の価値を強く信じて活動を開始したのです。自分たちの国が間違った方向に進んでいると感じ、それを正すために声を上げました。ハザー私たちはこうした原子力の支援活動を、世界中にもっと拡大していこうと考えています。世間の人々はこうした活動に従事するメンバーの真摯な姿勢を見て、共感し、信頼するものです。自分たちだけでできることは限られていますが、同様の活動を行っている他のNPOグループをサポートし、互いに協力して使命を達成することを目指しています。クリスティン2016年に活動を開始したとき、私たちはとても孤独を感じていました。原子力を支持するグループは、ほとんど存在しませんでした。私たちは多くのネガティブな反応を受けました。原子力産業界からお金をもらっていると言われたり、悪意があると非難されたりしました。しかし現在では、原子力を支持するコミュニティがソーシャルメディア等を通して成長し、同じような活動をするグループも出てきました。MfNとしては他のグループをサポートし、より効果的な活動ができるよう連携しています。ハザー今では、米国内のみならず世界中に原子力を支持するグループが増えてきています。私たちはその活動をサポートしています。クリスティンハザーと私がMfNを始めた2016年には、原子力を支持する声はほとんどなく、企業からのメッセージだけがありました。少なくとも米国では、企業のメッセージには警戒感を持つ人が多かったので、私たちはそれとは異なるアプローチを取ることが必要だと感じました。ハザー多くの人が企業や政府に対して懐疑的ですから、異なるコミュニティグループからの声が重要です。ですから、さまざまなコミュニティグループが、さまざまな理由から原子力を支持するような、社会全体に広がるような支援の輪を作っていきたいと思っています。クリスティンもし企業がすべてをコントロールしようとすると、それが逆に広がりを妨げることがあります。私たちは、企業が何を言っているのかに加えて、私たち自身がどんな活動をしているのか、そして私たちが何を伝えたいのかをしっかりと示すことが大切だと思います。私たちは個人的に原子力を支持するようになったからこそ、この活動を始めました。原子力が私たちの生活をどれだけ向上させるかを学んだとき、私は母親として、これが私の子供たちの未来のために必要なことだと感じたのです。次世代層は原子力にオープン他の環境系のグループと対面で議論する機会があると思いますが、原子力についての誤解を解くこともあるのでしょうか?クリスティン環境グループのリーダー層とは理解し合うことは難しいですが、メンバーや地域のオーガナイザーとは話しやすいです。学校を訪問すると非常に励みになります。特に高校や大学では、若い人たちは気候変動について多くのことを聞いていますが、実際の解決策についてはあまり学んでいません。原子力について聞くと、ほとんどの学生が興奮するんです。私は彼らに原子力についての正確な情報を提供し、あとは自分で判断してもらいます。若い人たちは心が開かれており、非常に励みになります。ハザー若い人たちは気候変動についてただ論じるだけでなく、自分たちが行動することで、何かを達成することができると信じています。自分たちの未来に希望を持ちたいのです。若い学生たちと会う機会がたくさんあるでしょうが、彼らは原子力をエネルギーの選択肢としてどう見ているのでしょうか?クリスティン現在のカリフォルニア州におけるエネルギー教育には多くの課題があります。現在のカリフォルニアの教育カリキュラムでは再生可能エネルギーに重点が置かれていますが、私たちはその教育をもっと正確にし、エネルギーの現実と課題を伝えていく必要があると感じています。しかし、実際に学校で1コマ(45分間)話すだけで、多くの学生たちは原子力の必要性を理解してくれます。ハザー若い学生たちは、原子力について学ぶと、非常に支持的な姿勢を見せてくれます。しかし問題に思うのは、彼らがそもそも原子力という選択肢があることをこれまで学んでこなかったことです。私たちは、他のグループと協力して、教科書に原子力についてもっと公平に載せるよう求める運動に取り組んでいます。米国やカナダでSMR(小型モジュール炉)がブームになり、多くの若者に人気があるようですが。一方で大型軽水炉への関心はどうでしょうか?クリスティン確かにSMR開発は進展しています。しかし、実際に商業化されて運転される段階には至っていません。ゴールまでかなり近づいている企業もあるようですが、私たちの大きな課題は、より多くの電力が必要だという現実に直面していることです。ジョージア州のA.W.ボーグル原子力発電所4号機が、2024年4月に営業運転を開始しました。これは出力が125万kWの大型炉「AP-1000」です。私たちはもっと多くの電力が必要なのです。ハザーもちろん、小型炉から大型炉までさまざまなタイプの原子力発電プラントが効率良く建設され、地理的な条件に応じてさまざまな用途に導入されるようになれば、気候変動への対応にも有効だと思います。クリスティン大型の軽水炉は本当にワクワクするテクノロジーなんですよ。私とハザーは20年以上ディアブロキャニオン発電所で働いていますが、毎日そのテクノロジーの数々に新鮮な驚きを覚えています(笑)ハザー大きくて迫力のあるクールな機器に囲まれることを想像してみてください。大型炉も最高ですよ(笑)
- 23 Jan 2025
- FEATURE
-
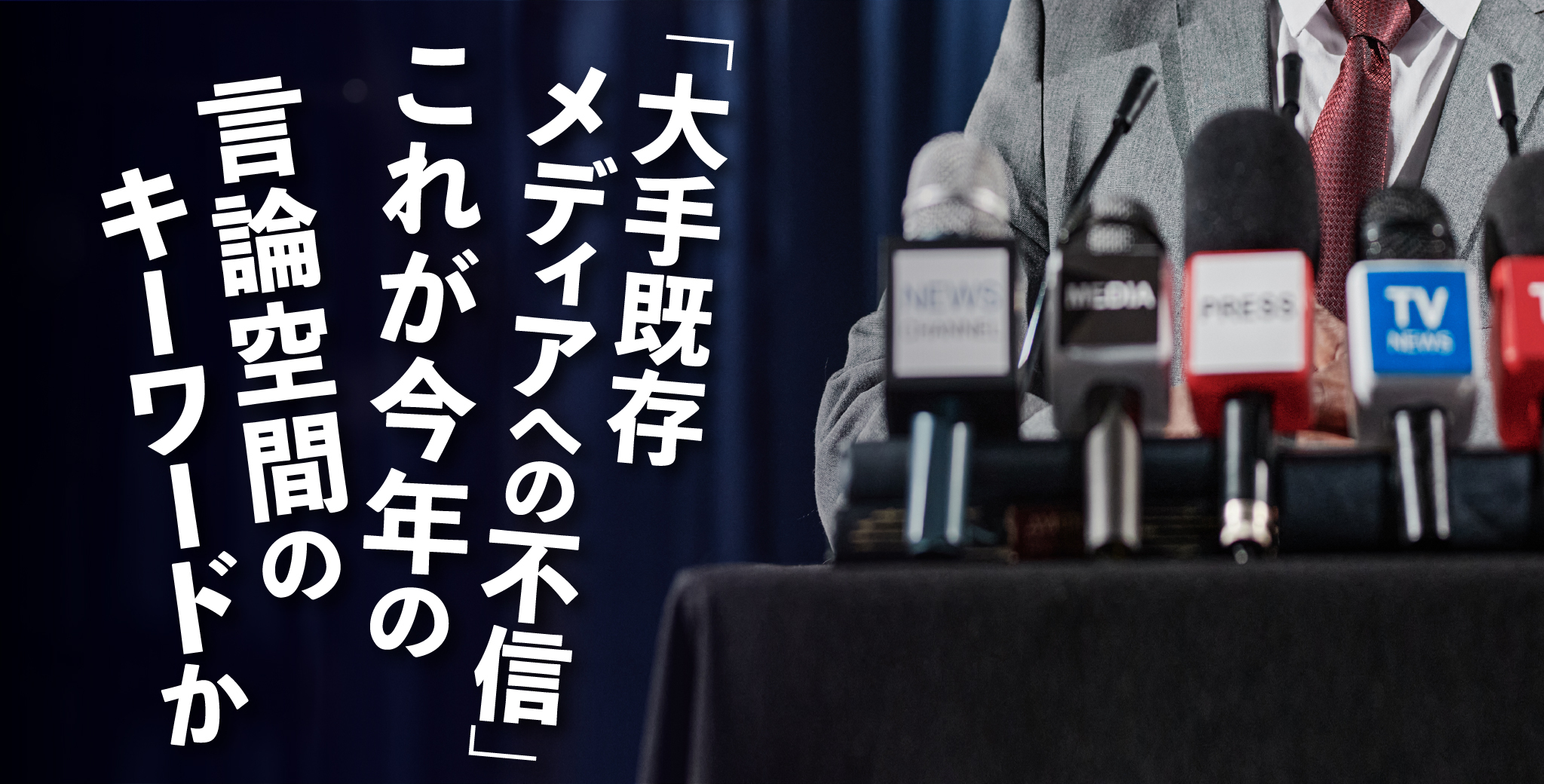
「大手既存メディアへの不信」これが今年の言論空間のキーワードか
二〇二五年一月十四日 二〇二五年を特徴づけるキーワードは何だろうか。最近の米国大統領選や兵庫県知事選を見ていて、「大手既存メディアへの不信」がキーワードのひとつのように思えてきた。特にリベラルメディアへの不信感とその影響力の低下が確実に起きているような気がする。原子力の話題も交えて、その背景を論じてみたい。大手既存メディアへの不信が根底に みなさんもすでにご存じのように昨年十一月の兵庫県知事選で前知事の斎藤元彦氏が再選された。斎藤氏は議会の不信任決議を受けて失職したあと知事選に臨んだ。当時、どのテレビ番組や新聞を見ても、斎藤氏を批判するニュースばかりだった。そのような言論空間で斎藤氏が勝つ見込みはなく、落選の可能性が強かった。ところが、ふたをあけてみたら、斎藤氏が快勝した。 その背景の分析については、いろいろな媒体で取り上げられているが、私なりにひと言で言えば、大手既存メディアへの「不信感」が間違いなく根底にあった。知事選前、既存メディアはどのニュースでも、斎藤氏の「パワハラやおねだり疑惑」を表面的におもしろおかしく報じ、内部告発のどこが本質的な問題かを報じたニュースは少なかった。そういう言論空間を見る限り、選挙前の斎藤氏のイメージは限りなく「悪」=(知事にふさわしくない人物)に近かった。大手メディアが報じない情報をSNSが補完 ところが、大手メディアが報じない裏の世界では斎藤氏側のSNS戦略が功を奏し、さらに斎藤氏の当選を目指すという奇抜でウルトラC的な出馬をした立花孝志党首(NHKから国民を守る党)の動きもあって、既存メディアよりもSNSの情報のほうが県民の心をとらえていた。 では、なぜSNSのほうが県民の心をつかんだのか。私流の解釈では、SNSのほうが玉石混交とはいえ、ニュースの中身が豊富(選べる材料が多い)だったからだ。 大手既存メディアは知っていても書かない(または書けない)ことが多々ある。プライバシーもあって、タテマエしか報道できないためだ。自死したとされる県民局長の公用パソコンに残っていた私的な情報に関しても、具体的にはほとんど報じない。しかし、アウトサイダー的な週刊誌やSNSなら、そういうタテマエ(世間体的思慮)に気を遣うことなく、ニュースを発信できる。 兵庫知事選のそのあたりの事情は「斎藤氏への世論『批判から熱狂』に変わった本質」(東洋経済オンライン・安積明子ジャーナリストの記事(二〇二四年十一月の上・下)を読むとよく分かる。この東洋経済の記事も、大手メディアだとまず書けない。大手メディアの影響力は低下したのか? ここで私が強調したいのは、もはや既存の大手新聞とテレビ局が流す情報(ニュース)は諸現象のごく一面でしかないことを皆が知ってしまったということだ。NHK党の立花氏が「斎藤氏は悪くないですよ」と具体的な例を挙げて自信ありげに演説するのを聞いた多くの人は「えー、そうなのか。大手新聞やテレビは本当のことを報じないのか」と立花氏の新鮮な内容を信じたに違いない。 そう信じてしまうのは、その根底に大手既存メディアへの不信感があるからだ。斎藤氏が当選した昨年十一月十七日、フジテレビ系「Mr.サンデー」(日曜午後十時)のキャスターを務める宮根誠司氏は選挙戦の結果に対して、真顔で「大手メディアの敗北」だと語った。おそらく宮根氏の心の中には「これだけ我々テレビ側の人間が来る日も来る日も斎藤氏を批判的に報じてきたのに、その威力は通じなかったのか。もはやテレビの影響力は想像以上に小さいのかもしれない」といった苦い思いがあったのだろうと推測する。 私もちょうどその宮根氏の言葉をテレビで聞いていて、確かにその通りだとうなづいたのを覚えている。 もはや大手メディア(新聞とテレビ)がどんなニュースを流そうが、SNS(インフルエンサーのブログ的ニュースも含む)で情報を見たり、確認している人たちにとっては、大きな影響力を持たなくなったということを実感した瞬間だった。 兵庫県知事選の検証記事を載せた毎日新聞(十一月二十四日付)でインタビューを受けた西田亮介・日本大学教授は「斎藤氏や知事選について、有権者がネットで検索しても、有権者が知りたいことはマスメディアの記事には出てこない。その代わりに斎藤氏の陣営や支援者らが発信する『切り抜き動画』など大量の情報が目に触れた」と述べている。知事選という特殊なケースだった要因もあるだろうが、大手メディアが発信する情報はもはや読み手の期待に応えていないことが分かる。大手メディアの情報発信は一方通行 そもそも大手既存メディアが流すニュースは、読者の期待とは関係なく、一方通行である。どんなニュースが流れてくるかは、ニュースが出てくるまで分からない。しかも読み手が知りたいと思ったニュースが流れてくる確率は非常に低い。さらに、期待したニュースが流れてきたとしても、そのニュースは記者やその媒体のフィルターを通じたゆがんだ情報であり、多様性に欠けることは否めない。 さらに言えば、大手既存メディアへ「こんなニュースを書いてほしい」とアクセスする手段は限られている。いやほとんどアクセスする手段はないといってもよい。テレビ番組を見ていて、「これはおかしい」と思っても、黙認するしかなく、それを伝える手段はない。仮に取材を受けても、期待した内容のニュースが作られるとは限らない。つまり、既存メディアは国民の手の届かないところにある。そういう疎外感がある中でSNSの世界なら、自ら発信もできるし、ニュースへのコメントもできる。SNSの世界には記者よりも知識の豊富な専門家がたくさんいる。そういう専門家とつながれば、大手メディアよりもSNSのほうがはるかに頼りがいがあり、親近感が感じられるはずだ。トランプ大統領の誕生と酷似するメディア空間 みなさんも薄々感じておられるだろうが、兵庫知事選の構図は、ちょうど同じ時期に誕生した米国のトランプ大統領の誕生と似ている。むろん斎藤知事とトランプ大統領は思想も政治的背景も異なるが、私から見て酷似していると思われるのはメディア空間である。 よく知られているように米国のメディアの大半(ワシントンポスト、ニューヨークタイムズ、テレビのCNNなど)はジョー・バイデン氏の率いる民主党を支持し、共和党に対しては批判的な記事を普段から発信している。共和党の支持者にとっては、米国のメディアはリベラル派に寄り過ぎており、フェイクニュースばかりを流していると映る。つまり、米国の言論界を牛耳っている民主党寄りのリベラルメディアへの反感である。 トランプ大統領はリベラルメディアのニュースを常に「フェイク」だと口にしていた。これは、トランプ大統領の支持者から見ると、「リベラルメディアは真実を報道していない」と映る。NHK国際部の辻浩平記者がホワイトハウスを取材(二〇二〇年~二三年)した第一級レポートといえる「トランプ再熱狂の正体」(新潮社)を読むと、リベラルメディアへの不信がトランプ支持者たちの心をとらえたことは間違いない。 いったん強固なトランプ支持者になると、いくらリベラルメディアが共和党やトランプ大統領を批判しても、そのニュースはフェイクだと認識され、びくともしない構図ができあがる。トランプ支持者の心境は「どうせアメリカの主要メディアはオレたち(私たち)の声を聞いてくれない」だろう。その結果、トランプ支持者たちは、大手メディアを信用せず、共和党サイドの交流サイト(SNS)やユーチューブで情報を入手するようになる。原発推進の国民民主党はなぜ躍進したのか 日本でも米国でも、大手既存メディアへの不信感は以前からあったのだろうが、最近になってその傾向がより露わになった気がする。 日本新聞協会によると、二〇二三年の一世帯当たりの新聞の発行部数は〇・四九部だ。もはや半分の世帯が新聞を購読していない。私のような新聞愛好者にとっては悲しいことではあるが、今後も大手新聞の影響力はますます低下するだろう。確かに新聞を読んでいれば、世の中の政治や経済に関する全般的な動きは良く分かる。しかし、新聞を読まない人にとっては、SNSだけが情報源であり、私とは全く異なる世界を見ていることになる。 しかし、そのことはマイナスばかりではない。昨年秋の衆議院議員選挙で国民民主党は七議席から二十八議席へと大躍進した。これは大手メディアが国民民主党を紙面で応援したからではない。国民民主党の玉木雄一郎代表は昨年十一月二十七日、石破茂首相を訪ね、原子力発電所の新増設を要望した。これまで「原発の推進」を口にすれば、マイナスイメージが響いて選挙では不利だとされてきた。それでも国民民主党は議席を増やした。大手メディアがつくり出す言論空間とは異なる、もうひとつの言論空間がいよいよ生まれつつある。
- 14 Jan 2025
- COLUMN
-

令和七(2025)年は元旦の社説読み比べから
昨年は新聞への不信や衰退論が盛んに聞かれた。それでも元論説委員の筆者としては新聞力を信じたい。そこで今年の初仕事は、朝日、毎日、読売、日経、産経5紙の元旦社説の読み比べ。なお元旦社説は通常の2本ではなく、全紙1本である。まずは見出しから。『不確実さ増す時代に 政治を凝視し 強い社会築く』▼『戦後80年 混迷する世界と日本 「人道第一」の秩序構築を』▼『平和と民主主義を立て直す時 協調の理念掲げ日本が先頭に』▼『変革に挑み次世代に希望つなごう』▼『未来と過去を守る日本に』となる。社名を全部正解出来たら、お年玉モノだ(正解は朝毎読日産の順)。中身に入ろう。朝日は不確実さの主因を米大統領に返り咲くD.トランプ氏に求め、昨年のノーベル経済学賞受賞者、D.アセモグル氏と19世紀の米詩人W.ホイットマンを援用し、時代を読み解く。両者は市民の力を強調する点で共通する。《放置すれば「国家」は市民を圧しにかかる。「社会」の側が国家を監視し、足枷をはめる必要がある》(アセモグル氏)も《堅実な民衆ならもっと強く政治に介入せよ》(ホイットマン)も、新聞の使命を「権力の監視」としてきた朝日らしい。不確実な時代こそ、有権者はしっかり声を上げ強靭な社会を築けと説く。とは言え国家と社会の線引きはそう単純ではない。国家は悪とばかりに、何ら期待しない点も気になる。アセモグル氏については「社会制度が国家の繁栄に与える影響の研究」との授賞理由に言及した方が親切だったろう。毎日は世界の現状分析から始め、ウクライナ、トランプ、国連、ガザなどを暗澹たる状況と見る。新たな国際秩序の青写真にも悲観的だ。それゆえ《戦後80年間、平和国家として不戦を貫いてきた日本は秩序作りで役割を果たすべきだ》とし、「自国第一」から「人道第一」の世界へ軌道修正する外交努力を日本に求め、《日本は『人間の安全保障』を行動指針にすべきだ》(長有紀枝・立教大学教授)との見解を紹介している。日本の役割を明示することは社説の重要な要素だ。後段の市民活動家たちの紹介も悪くはないが、『人間の安全保障』をもっと掘り下げるとか、外交努力を具体的に論じた方が社説により相応しいと感じた。読売は世界が歴史の変動期のただ中にあるとし、3つの危機――「平和の危機」「民主主義の危機」「自由の危機」が同時進行していると警告した。そして《新しい秩序作りに向けて、日本こそがその先頭に立たねばならない》と主張。ここまでは毎日と同じ。続く《危機の中に希望の芽を探し出そう》から違いが出てくる。「自分なら停戦させられる」と豪語するトランプ氏を活用しようと提案し、そのためには世界が侵略も殺戮も許されないと声を一つにする必要があるとする。世界の声を圧力にトランプ氏を有効利用するわけだ。ナルシストと言われるトランプ氏のこと。それもアリかもしれない。成功は保証の限りではないが、トランプ対策が世界だけでなく各国にとっても喫緊の課題であるのは確かだ。日経も冒頭は《不確実性という霧につつまれた2025年が始まった》と朝日と似ているが、《すくんでいるだけでは未来は開けない。危機は変革の生みの親だ。より良い秩序作りに挑み、次世代に希望をつなぐ道筋を付けたい》と、終始プラグマティックなところに同紙の特徴が出ている。また民主主義と選挙に関する文脈で、《新聞などのメディアが正確で信頼される情報をいかに発信するか。わたしたちも変革を肝に銘じる必要がある》と自省した。メディアへの言及が日経だけなのは残念だが、皆無でなくて良かった。産経はへそ曲がりの読者なら見出しを見て「現在はどうなのだ」なんて言いそうだが、《戦後80年である。大東亜戦争(太平洋戦争)について中国や朝鮮半島、左派からの史実を踏まえない誹謗は増すだろう。気概を以って反論しなければ国民精神は縮こまり、日本の歴史や当時懸命に生きた日本人の名誉は守れない》の一文に見るように、現在つまり今年は、過去と未来を守る年との位置づけだろう。自衛隊制服組トップ、統合幕僚長の「国際社会の分断と対立は深まり、情勢は悪化の一途をたどり、自由で開かれた国際秩序は維持できるか否かのまさに瀬戸際にある」(年末記者会見)など有事への危機感溢れる言辞を引用しながら、政治と国民に情勢への備えはあるかと問いかける。情勢認識には異論もあるだろう。当然だ。社説は熟議への土台でもあるのである。ところで産経は「年のはじめに」と題して唯一論説委員長の署名入りだ。無記名より書き手への注目度もプレッシャーも上る。実は筆者も経験者で、テーマは、題材は、と毎回試行錯誤し、読者の反応にドキドキ、ハラハラしたものだ。SNS隆盛の今は、署名の有無を問わず、反応は昔と大違いだろう。分断や対立を煽らず、真っ当で活力ある議論にチャレンジする新聞人にエールを送りたい。
- 07 Jan 2025
- COLUMN
-

敦賀2号機の不許可理由 「可能性を否定できない」は科学的な判断か?
二〇二四年十二月二十五日 原子力関連で令和六年(二〇二四年)最大のニュースと言えば、福井県の敦賀2号機の再稼働の不許可だろう。「不許可」自体もビッグニュースだが、それを決めた原子力規制委員会の「活断層の可能性は否定できない」という主観的な判断理由も、歴史に残るだろう。ただ何か釈然としない気持ちがわいてくるのはなぜだろうか。 原子力規制委員会(山中伸介委員長・委員五人)は十一月十三日、定例の会合で日本原子力発電株式会社が所有する敦賀原子力発電所(福井県敦賀市)の2号機(PWR・百十六万kW)の再稼働申請を不許可(不合格)とすることを全会一致で決めた。二〇一二年に原子力規制委員会が発足して以来、初めての審査不合格だ。2号機は一九八七年に運転を開始したが、二〇一一年にトラブルで停止したあと、二〇一五年十一月、新規制基準への適合性審査を同規制委に申請していた。不許可の理由は「活断層の可能性を否定できず」 私は原子力問題の専門家ではない。この問題を大手新聞や雑誌がどう報じたかに関心がある。どんな理由で不許可になったかを知るために当時の新聞を読んでみた。 審査の主な焦点となったのは、2号機から北へ約三〇〇mのところにある「K断層」が将来、地震を起こす活断層かどうか、そしてその活断層が原子炉直下まで延びている(連動もしくは連続している)かどうかの二点だ。 まずは各紙を見てみよう。朝日新聞(十一月十四日付)は「活断層否定できず」の見出しで「規制委は活断層の可能性は否定できないと判断した」と報じ、さらに「原電の説明が十分な根拠をもって受け入れられなかった」という理由を挙げた。毎日新聞(十一月十四日付)は「原子炉直下に活断層があることを否定できず新規制基準に適合しない」と報じた。東京新聞(十一月十四日付)も「原子炉直下に活断層がある可能性を否定できない」とした。さらに読売新聞(十一月十四日付)は「規制委の審査チームは『活断層の活動性、連続性とも否定できない』と判断した」と報じ、産経新聞(十一月十四日付)も「原子炉直下に活断層が走る可能性を否定できない」と報じた。 つまり、どの新聞も「活断層の可能性を否定できない」という理由を挙げて報じたことが分かる。処理水に反対した地方紙はおおむね不許可を称賛 この不許可の決定に対し、予想通り、反原発路線の朝日、毎日、東京は「否定できない以上、不許可は当然である」と断じた。念のため、地方紙の社説をネットで見つけて読んでみた。おもしろいことに気づいた。どういうことかといえば、福島第一原発の処理水の海洋放出に反対する社説を載せていた地方紙(神戸新聞、中国新聞、北海道新聞、信濃毎日新聞、西日本新聞、京都新聞など)は、今回も「不許可」に対して、「再稼働を認めないのは当然だ」「妥当な判断だ」と称賛していることだ。 要するに、原発に否定的な新聞社は「可能性を否定できない」という、私から言わせれば、極めて科学から程遠い判断理由に対して疑問を呈していないことだ。科学的なデータを突き詰めて解析した結果、不許可はやむを得ないといった論調なら科学的な匂いを感じ取ることができるが、そういう論調ではない。「悪魔の証明」は危うい論理 地方紙の社説を読むといとも簡単に「可能性を否定できないなら、廃炉は当然だ」と主張している。世の中に「可能性を否定できる」現象などない。どんなテクノロジーでも「良くない出来事が決して起きないことを証明せよ」と言われたら、それを事前に証明することは不可能である。これはよく「悪魔の証明」と言われる。 そういう危うい論理にもかかわらず、いとも簡単に「不許可は当然だ」と堂々と主張しているところを見ると、最初から結論は決まっているように思える。なにしろ、ほぼ環境や人体へのリスクがゼロに近い処理水の放出にも反対したくらいだから、「どうみても活断層が動く可能性を否定することは無理だよね」という判断に傾くのは自然の流れである。そもそも原発自体に否定的なのだから、どんな証拠を突きつけられても、活断層の恐れがあるから再稼働は認めないという判断に行く着くのは理の当然である。産経新聞だけは果敢に反対の論陣を張る 大手各紙を見ていて、つくづく感じたのは主要な新聞を読んでいても、細かい科学的な議論が分からないということだ。ただ、産経新聞だけは「悪魔の証明は禁じ手だ」(七月十七日付)、「規制委の偏向審査 強引な幕引きは許されぬ」(八月七日付)、「効率性と対等性の新風を」(九月二十六日付)と一貫して審査の偏向ぶりを指摘していた。 真骨頂は、長辻象平・産経新聞論説委員の書いた「『悪魔の証明』を求める原子力規制委 敦賀2号機の受難」と題した八ページにわたる論稿(月刊「正論」二十四年十月号)だ。長辻氏は「K断層は両側からの圧縮力で生じる逆断層だが、ぐにゃぐにゃで左右に湾曲し、しかも、とぎれとぎれでふらついて息も絶え絶えという代物だ」と形容して、「2号機に脅威を及ぼす断層の姿からはほど遠い」と指摘する。 そして、各紙が「原電による審査資料の無断書き換えと誤記」((筆者注 「無断書き換え」という表現は、原電が意図的にデータを改ざんした、と読める。))と報じた点に関しても、長辻氏は「規制委の審査官が『ここが変わったとかではなく、きちんとした形で更新して最新の形で審査資料として提出するよう』指示したのを受けて更新したところ、『説明なしの書き換え』ととがめられた」と書いている。誤記に関しても「肉眼で観察したものを、新たに顕微鏡で詳細に確認した結果を修正したものだ。そこに悪意はなかったとされて、審査は再開されたが、規制委はその間に原電本店への立ち入り検査を行った。印象操作と批判されても仕方あるまい」と書いている。 ついでに言うと、天野健作氏(大和大学社会学部教授・元産経新聞)が書いた「敦賀原発『不合格』にみる公正審査の疑わしさ」と題した論稿(十一月十四日「国際環境経済研究所」のウェブサイトに掲載)も非常に参考になる。 長辻氏や天野氏の論考を読むと、ことの真相の一端を知ることになるが、これに対する反論も当然あるだろう。私としては、真実に少しでも迫る論争記事を読みたいのだが、残念なことにそういう論争的な記事を大手新聞は載せてくれない。 やはり現状では真相(深層も含め)を知るには、主要各紙を丹念に読み比べることしかなさそうだ。「予防原則の乱用」が怖い 最後にひと言。今回の不許可報道で私が危惧の念を抱くのは「予防原則の乱用」が広がる恐れだ。「良くないことが起きる可能性が否定できない」という論理がまかり通れば、どんなテクノロジーも為政者の思うままに規制できてしまう。現に敦賀2号機の再稼働に対しても、「疑わしきは安全な側に判断すべきだ」(朝日新聞七月二十七日付)という主張が見られる。この主張は、少しでも疑わしき点があれば、あるテクノロジーや化学物質の使用、化学工場の運転などを止めるということを意味する。 一般に「予防原則」は、科学的な因果関係が十分証明されていなくても、規制措置を可能にする考え方を指す。この論理は「可能性を否定できないときは、安全側に立つ」という論理とほぼ同じである。こういう論理がまかり通ると石炭や天然ガス火力は廃止になり、原発の稼働も中止になるだろう。すでに約三十年間、世界で流通している遺伝子組み換え作物にしても、「将来何か良くないことが起きる可能性を否定することは難しい」という判断を為政者がくだせば、いとも簡単に流通や栽培を禁止することも可能になってしまう。これを機に「可能性を否定できない」という論理の適用を限定させる科学的な議論が必要だろう。 もう一言。原発を動かすかどうかは、日本全体の未来を左右する極めて社会経済的な問題である。原子力規制委員会(五人の委員)に経済学やエネルギー、社会心理学など社会工学的な専門家がいないのはどうにも腑に落ちない。国民の代表である政治の側からの参戦をもっと期待したい。
- 25 Dec 2024
- COLUMN
-

リニア中央新幹線と原子力 同じ巨大プロジェクトでも何が違うのか?
二〇二四年十一月十八日 東京と名古屋を四十分で結ぶリニア中央新幹線に関するニュースが最近になって増えてきた。ちょうど十月半ば、山梨のリニア実験線の体験試乗会に参加した。時速五〇〇kmを実感しながら、同じ巨大プロジェクトの原子力との「差」を考えてみた。時速五〇〇kmを実感 私が体験乗車したのは十月十六日。JR東海がメディア関係者を招いて行った。現在、山梨県笛吹市から上野原市までの約43kmの路線が完成している。この実験線は東京~名古屋間の路線の一部であり、完成したあとはそのまま利用される。 ワクワク気分でさっそく乗ってみた。リニアは超電導磁石を用いた浮上走行だ。最初のうちはレールの上を走るが、まもなく浮上走行に替わる。加速して浮上するときは飛行機に乗って離陸するときのような感覚だ。ほとんどがトンネル内を走るため、窓を見ても、宇宙空間を走っているような感じだ。時速五〇〇kmに達したとき(写真1)は、さすがに記者たちも歓声を上げ、時速五〇〇kmの文字を示す速度計の前に立ち、記念写真をパチパチ撮っていた(写真2)。私もミーハー気分で記念撮影に収まった。写真1 思ったよりも揺れは少ない。飛行機に乗っているときのような轟音というか雑音はするが、飛行機ほどではない。座席のテーブルにコーヒーカップを置いても、コーヒーの液体がこぼれ落ちることはないという。これなら、仮に東京から名古屋までリニアに乗り、40分間で着くとしたら、新聞や本を読んだり、コーヒーを飲んでいるうちに到着し、疲れることはないだろうと感じた。写真2 今の予想では、完成は早くても10年後と言われているだけに、未来の科学技術空間をいち早く体験できたのはとても貴重だった。リニア自体を否定するニュースはなし リニアに体験試乗したせいか、リニアに関するニュースが以前よりも目に止まるようになった。私にとって興味があるのは原子力に関するニュースとの相違である。 十一月八日のNHKニュースでは、リニア中央新幹線の地下のトンネル工事が行われている東京都町田市の住宅で水と気泡が湧き出て、JR東海が掘削機による工事を中断しているというニュースが流れた。同様のニュースは十一月十一日朝、フジテレビの「めざまし8」でも流れた。同番組はこの問題を意外に詳しく報じ、気泡剤と水がボーリング跡から漏れ出したのではという指摘もしていた。 ついでに最近の新聞記事もネット検索で読んでみたが、原子力との大きな違いに気づいた。私が見た限り、どのニュースを読んでも、リニア自体を否定する内容がないことだ。原子力発電所の場合は反対派のコメントが記事中に載り、原発反対の大きな見出しも踊るが、リニアにはそれが見られない。もちろん住民による反対運動はあるし、リニア工事の認可取り消しを求める訴訟も起きているが、原子力のような反対の嵐はない。 巨大工事にともなって地下水が枯れたり、住民や工場の立ち退き問題が起きるというニュースはローカル的に流れているが、それらの問題が連鎖反応を起こし、「リニアを止めろ!」という一大合唱にはなっていないようだ。朝日新聞、毎日新聞とも否定的ニュアンスなし 朝日新聞は十月五日付け経済面で「リニア開業遅れ 突きつけられた『延命』」との見出しで記事を載せたが、否定的な論調ではない。「リニアには圧倒的な速度による輸送力と並んで、東海道新幹線の『バイパス』の役目を期待する声がある。しかし、その全線開業の時期がいまだ見通せない」とある。記事の最後は「完成から61年目に突入した新幹線は、さらなる完成への途上にあるのかもしれない」と結んだ。どう見てもリニア自体に否定的なニュアンスは読み取れない。 毎日新聞も十月三日付け記事で「進む移転 迫られる決断」との見出しで、長野県飯田市で明治時代から染色業を営む職人の工場がリニア工事で移転を迫られる苦境を伝えていたが、リニア自体を止めろ、という文言や住民の声は出てこない。 リニア工事に伴う問題点とメリットを詳しく報じたフジテレビの「めざまし8」が、これらのニュースを象徴するかのように思えた。女性のコメンテーターは「人口が減っているのに必要なの?」とコメントしたのに対し、コメンテーターの橋下徹弁護士は「リニアについては賛否両論あるが、リニアは国家戦略上必要だ。高速道路など過去の工事でも問題点を乗り越えて私たちは利益を得てきた。何か問題があるからやめろ、では将来の世代に利益を与えることができない。問題があるからといって工事自体を止めるべきではない」(筆者で要約)と述べた。原子力発電所の問題だと、こういう歯切れのよいコメントは期待できない。移動時間は短いほうが疲れは少ない 私が気になるのは採算だ。JR東海によると工事費は全額自己負担で東京~名古屋間で七兆円以上かかるという。今後の工事の進展いかんでは社会的な補償費用がかさみ、コストが増えていく恐れがある。なんとか10年後には開業にこぎつけてほしいものだ。 最後にひと言。よく「そんなに速く移動する必要があるのか。いまのままで十分だ」という批判を聞く。こういう物言いは、戦後の高度経済成長の真っただ中で「これ以上、経済成長は必要なのか」という議論があったが、これと似ている。いくら「ゆっくりズム」がいいからといって、いまどきあえて東京~名古屋間を移動するのに「こだま」号か在来線の列車に乗る人はいない。だれしも早く目的地に着きたいのだ。日頃「ゆっくりがいい」と言っている人も、間違いなく「こだま」ではなく、「のぞみ」に乗っているはずだ。 また、アメリカへ行くのにあえて船を利用する人はいないだろう。脱炭素を訴えている人でも、みなごく普通に飛行機に乗って世界を駆けまわっている。 移動を目的とした列車や飛行機の旅は、けっこう疲れる。移動時間は短いほうが疲れは少なく済む。口先だけの観念論(理想論)にはくれぐれも要注意だ。リニアの魅力は分かりやすい。原子力のメリットとしては、電力の安定供給(エネルギーの安全保障)をもっと見える化する形で伝えていくことが必要だと、リニア試乗体験から感じた。
- 18 Nov 2024
- COLUMN
-
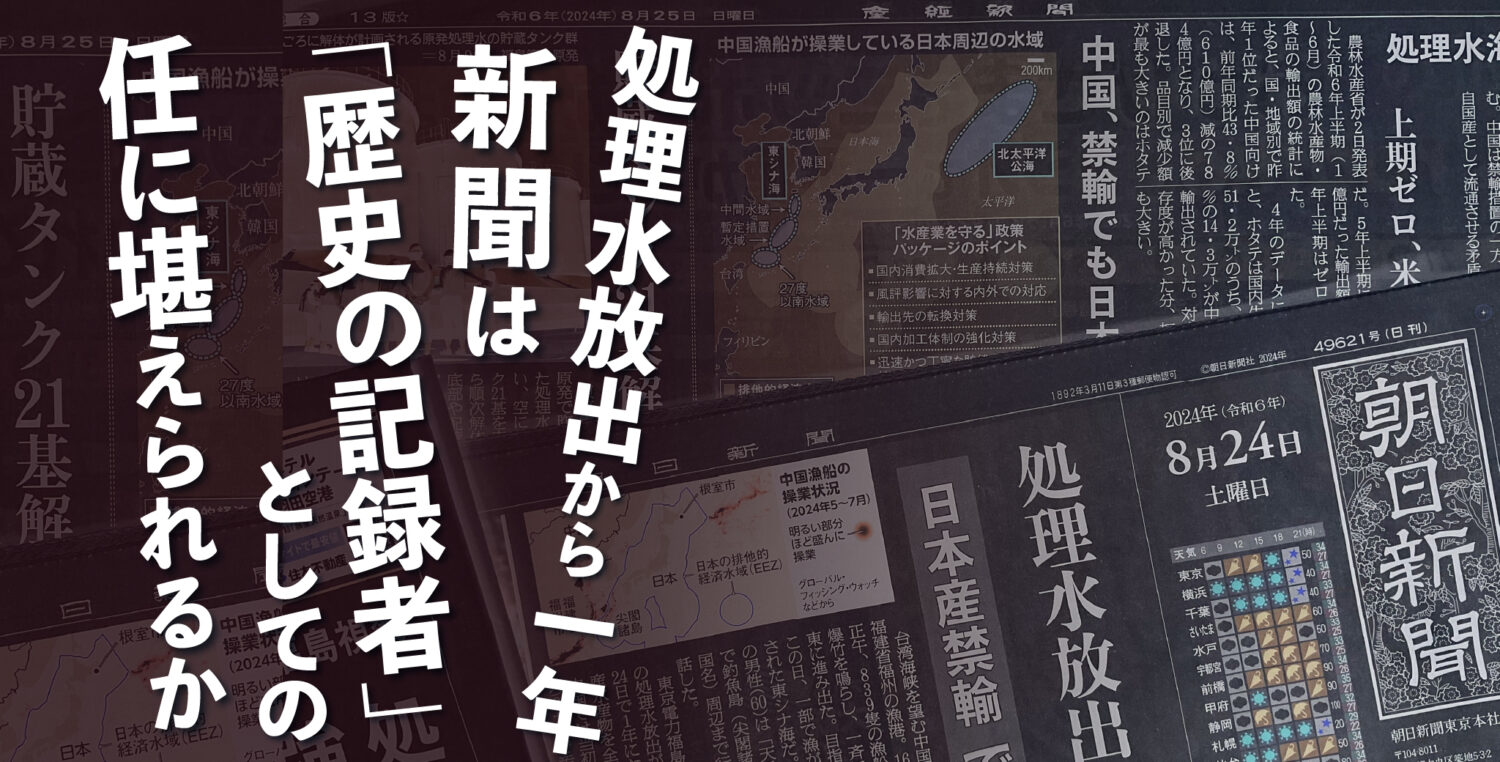
処理水放出から一年 新聞は「歴史の記録者」としての任に堪えられるか
二〇二四年九月二十日 新聞の役割とは何だろうか。世の中で起きている数々の現象を伝えることが主な役割であることは間違いない。だが、もうひとつ重要な使命として、歴史的な記録資料を残すことが挙げられる。三十年前の日本がどんな状況だったかを知ろうとすると、やはり新聞が筆頭に上がるだろう。では、福島第一原発の処理水放出から一年経ったいまを記録する資料として、新聞はその任に堪えているだろうか。 処理水の放出から一年が経った八月下旬、どの新聞社も特集を組んだ。中国が日本産水産物の輸入を禁止したことによって、その後、日本の水産物がどうなったかは誰もが知りたい情報だろう。そして福島の漁業がどうなったかも知りたいはずだ。そういう観点から、新聞を読んでみた。福島の漁業に活気は戻っていない? 毎日新聞の社会面(八月二十三日付)を読んだ。主見出しは「福島の海 活気返して」で、副見出しは「操業制限 漁師、東電へ不信なお」。地元の漁師を登場させ、「放出への不安や東電への不信感を拭えずにいる。いまも操業制限が続いており、かつてのような活気は戻っていない」と処理水の放出から一年経っても、活気は戻っていないと極めて悲観的なストーリーを載せた。 その一方で、福島の水産物の価格は高い水準を維持し、放出前より高値を付けることもあり、風評被害は出なかったと書く。ならば福島の水産物の明るい部分もあるはずだが、そのレポートはない。逆に、国と東電は「関係者の理解なしに、いかなる処分も行わない」と約束したのに、海へ放出し、いまも県漁連は反対の姿勢を崩していないと書き、国や東電への不信感を強く印象づける記事を載せた。 さらに三面では、東京電力は二三年十月から風評被害を受けた漁業者や水産加工業者などに賠償手続きを開始したが、約五五〇件の請求のうち、支払いが決まったのは約一八〇件(約三二〇億円)しかなく、賠償が滞っている様子を強く訴えた。しかも、大半は門前払いで泣き寝入りだという大学教授のコメントも載せた。同じ三面の別の記事では水処理をめぐるトラブルを取り上げ、見出しで「後絶たぬトラブル 東電に疑念」と形容するなど東電への批判を繰り返した。 かなり偏った内容(歴史的記録)に思えるが、同じ毎日新聞でも千葉支局の記者がルポした千葉版の記事(八月二十七日付)は違った。こちらは見出しが「福島原発でヒラメ飼育 1号機『普通の服装』で見学 処理水の安全、魚でテスト」と、敷地内の様子を極めて素直な目線でレポートしていた。これを読む限り、処理水の放出と廃炉作業は少しずつではあるが、前進している印象を与える。 ただ、毎日新聞からは水産物のその後の全体像はつかめず、一紙だけでは歴史的記録としては不十分なのが分かる。東京新聞はネガティブな印象を強調 毎日新聞の記事は全体として悲観的なトーンだが、東京新聞はさらにネガティブだ。一面で「七回で五・五万トン 収まらぬ漁業被害」「今も反対、政府は責任を」「首相近く退陣 漁師不安」と不安を強調し、二面では「汚泥 待ち受ける難題 タンク解体」「過酷作業 被ばくの不安」と、今度はタンクの「解体」や汚染水の処理過程で発生する「汚泥」の保管・処分をどうするかという難題が立ちはだかると厳しい内容を載せた。記事からは課題は分かるものの、前進している材料は全く見えない。これも歴史的記録の一面しか伝えていないように思える。読売・産経はホタテの脱中国に着目 毎日新聞と東京新聞を読む限り、暗い気持ちになるが、読売新聞(八月二十五日付)を読むと、一面で「処理水放出一年異常なし」、社会面では「処理水放出 不屈の漁業」「国内消費拡大・輸出『脱中国』へ」との見出しで明るい面を強調した。社会面の記事では「風評被害の拡大も懸念されたが、好調な国内消費や支援の声に支えられ、漁業関係者らは踏みとどまってきた」と書き、希望を持たせる印象を与えた。 社会面記事は、北海道湧別町のホタテ漁の写真を載せ、「今の湧別町には活気がある。官民挙げて取り組んだ消費拡大キャンペーンの結果、国内消費が好調であるためだ」と書いた。ホタテはふるさと納税の返礼品としても人気があり、別海町は二三年度の寄付額が百三十九億三百万円と前年度の二倍になったという内容も載せ、脱中国に向けて欧米への輸出にも取り組む様子を力強く伝えた。 三面では「政府、水産業支援を継続」という文言を見出しにし、「タンク解体、来年にも開始」とほぼ計画通りに進む様子を伝えた。 読売新聞の記事を読むと、毎日新聞や東京新聞とは全く逆の印象を受ける。毎日新聞に登場する漁業関係者は東電への批判を口にするが、読売新聞では漁業関係者が以前の日常に向けて頑張っている様子が伝わってくる。 産経新聞(八月二十五日付)は三面で「ホタテ輸出 脱中国進む、上期ゼロ、米向けなど急増」との見出しでホタテの輸出が増えている様子を伝えた。ホタテに着目した点は、読売新聞と同じであり、内容も読売新聞と似ている。朝日は意外に穏当か では、朝日新聞はホタテの状況をどう報じたのだろうか。八月二十四日付の社会面を見ると、「ホタテ『王様』復活なるか 国内消費上向き 中国への輸出見通せず」との見出しで「(中国への輸出の)主役だったホタテは行き場を失い危機的な状況に一時陥ったが、国内消費は上向きで回復に向かっている」と明るい要素もあることを報じた。国は基金や予備費を使い、約一千億円を投入、北海道の森町などは水産加工業者からホタテを買い取り、全国の学校給食に無償提供したと書き、自治体の奮闘ぶりを紹介した。また、ホタテの輸出量は減ったものの、米国、ベトナム、タイの三か国が中国の禁輸で行き場を失った分の約五割をカバーしたとも書いた。「楽観はできない」と書きつつも、朝日の記事は読売のトーンに近く、意外に穏当な内容だ。歴史的な記録は全紙が揃って初めて成立? これまでの記事を読み、みなさんは新聞の歴史的な記録を残す価値をどう思われただろうか。同じ現象を報じた歴史的な記録と言いながら、中身は新聞によってかなり異なることが分かるだろう。どの新聞も現象の一断面を切り取って記録していることがよく分かる。 つまり、一紙や二紙では歴史の記録者としての任は果たせない。裏返せば、新聞社の数(記者の数)が多いほど、歴史の多面的な現象を後世に伝えることが可能になる。そういう意味では、いま新聞の販売部数(記者の数も)が減少の一途をたどり、新聞社がつぶれそうな状況になっているのは、多様な歴史的な記録物を残す観点からみると極めて由々しき事態だといえる。 では、新聞社を残す方法はあるのだろうか。提案したいのは、読売新聞の読者はたまには産経新聞を読む、そして朝日新聞の読者はたまには毎日新聞や東京新聞を読むといった「交互購読」で大手五紙を共存させる方法だ。新聞社が減れば、いまの歴史の真実を後世に残す手立てが消えることに通じる。処理水から一年経った各紙の記事を読み比べてみて、そのことに気づいた。前回のコラムの最後に「重大なことに気づいた」と書いたのは、このことである。
- 20 Sep 2024
- COLUMN
-

「宇宙開発フォーラム」宇宙と原子力の関わりを議論
9月6日より3日間、学生団体「宇宙開発フォーラム実行委員会」(SDF)が主催する「宇宙開発フォーラム2024」が日本科学未来館(東京都江東区)で開催された。7日に開催されたパネルセッションでは、石井敬之氏(原子力産業新聞・編集長)ら4名のパネリストが登壇し、「宇宙開発と市民理解(宇宙における原子力利用を例に)」について議論を交わした。同フォーラムは、宇宙開発の現状や今後の展望について、業界内外に広く発信することを目的としており、今年で22回目の開催。原子力利用をテーマとして取り上げるのは今回が初めての試みだったという。議論に先立ち、セッションの企画者であり、モデレーターを務めるSDFの山口雪乃氏(国際基督教大学2年)が、企画の趣旨を説明。「原子力」や「核エネルギー」という言葉に抱くネガティブな印象から、宇宙での原子力利用にも反射的に拒否感を示す人々がいる現状を紹介し、新しい技術への市民理解を促すためにはどのような伝え方ができるか、と問題提起した。宇宙原子力の開発は、1977年に宇宙探査機ボイジャー1号に原子力電池が搭載されるなど、米国で先行して取り組まれてきた。日本でもようやく、今年4月に発表された文部科学省による宇宙戦略基金事業に原子力電池の要素技術の開発が組み込まれたが、高木直行氏(東京都市大学理工学部・教授)は、同事業で「原子力電池」が「半永久電源システム」と称されていることを指摘。国の事業においても、「原子力」という言葉の使用が避けられている現状を強調した。石井氏は「現代の宇宙エンジニアたちと同じく、かつての原子力エンジニアたちも未来に夢を描いていた」とした上で、今後の宇宙開発においても、社会から理解を得られなくなる事態になることが十分予想できると指摘。放射線照射によって誕生した「あきたこまちR」への風評被害や、食品添加物に対する誤解を例に挙げ、科学面でのリテラシー不足こそが、新しい科学技術への市民理解を得る上で最大の課題だと懸念を示した。また同氏は、ゼロリスクの追求が社会を歪めているとの見解を示し、「安全ならば安心する、という正しい感覚を持つべきであり、『安全だけど安心じゃない』が通用する社会を許してはいけない」と、強く訴えた。「未知、または未来の技術への市民理解を促進する上で必要なことは何か」との問いに石井氏は、業界の垣根を越えて「科学リテラシー全体の底上げ」に取り組むことであると主張。ニーメラーの警句を引用し、「『世間が宇宙業界を叩いた時、宇宙業界のために声を上げるものは一人もいなかった』とならないよう、日頃からアンテナを高く伸ばし、宇宙分野以外にも広く意識を向けて、積極的に発言してほしい」と学生たちに呼びかけた。
- 12 Sep 2024
- NEWS
-
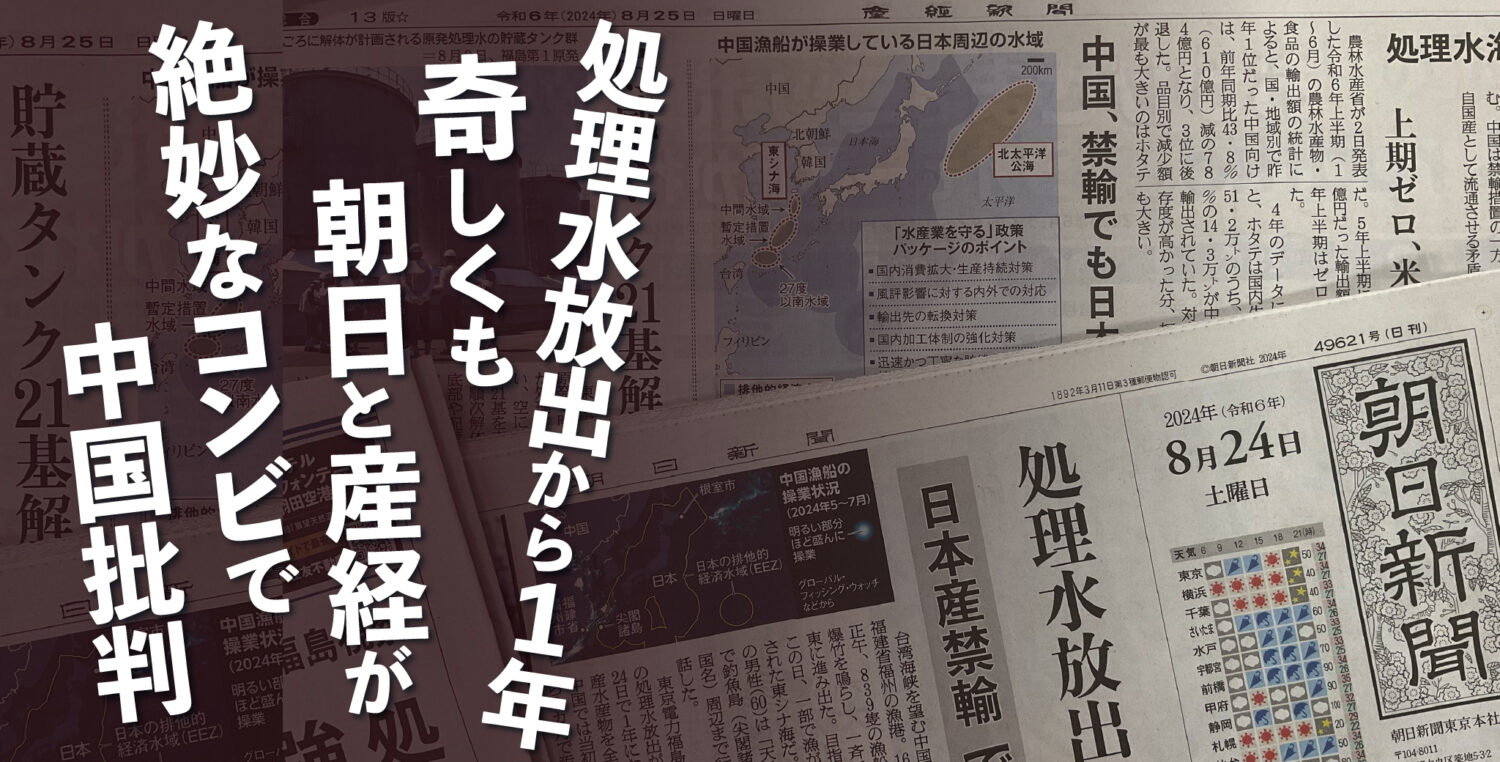
処理水放出から一年 奇しくも朝日と産経が 絶妙なコンビで中国批判
二〇二四年九月六日 福島第一原発の処理水の海洋放出が始まって、一年がたった。大手新聞がどんな報道をしたかを読み比べしたところ、驚愕の事実を発見した。なんと朝日、毎日、産経の各新聞が足並みを揃えたかのように、中国の日本産禁輸を批判する内容を載せた。特に朝日と産経が似た論調を載せたのは極めて異例だ。いったいどんな論調なのか。最大の武器は「自己矛盾」を突くこと だれかを批判するときに最も効果的な武器は、相手の言い分の「自己矛盾」を鋭く突くことである。相手に「痛いところを突かれた。勘弁してくれ」と言わしめる急所を突く論法である。 では、処理水の自己矛盾とは何だろうか。 中国政府は処理水を「核汚染水」と呼び、国民の健康と食品の安全を守るためと称して日本からの水産物の輸入を禁止した。これは言い換えると「日本の沖合で取れた魚介類は核汚染水で汚染されていて危ないから、中国の消費者には食べさせない」という国家の意思表示である。 ところが、中国の漁船は日本の沖合に堂々と来て、魚介類を取り、中国で販売している。同じ太平洋の海で捕獲しながら、日本の漁船が取って、日本に持ち帰った魚は危ないが、中国の漁船が取って、中国の港に持ち帰った魚は安全だという中国の論理は、どうみても自己矛盾の極みである。 中国の禁輸措置を批判する場合、いろいろな言い方はあるだろが、私は、大手新聞がこの自己矛盾をどう報じたかに注目した。朝日新聞は地図入りで矛盾を指摘 すると、なんと朝日新聞は八月二十四日付朝刊の一面トップで「処理水放出 漁続ける中国 日本産禁輸でも近海で操業」という大見出しで中国の自己矛盾を大きく報じた。 記事によると、当初、中国は日本の汚染水は放出から八か月で中国の沿海に届くと言っていた。この通りだとすれば、中国の漁船が中国の沿海で漁をすることは不可能になる。ところが、そんな事情にお構いなく、中国の沿海では八百隻を超える漁船が漁を続けている。中国の漁師は「もし汚染があれば、国(中国政府)は我々に漁をさせない」と意に介さない様子だ。福建省全体からは日本沖の太平洋に向かう漁船が毎日出漁している。 さらに日本の近海でも中国の漁船が多数出漁し、北海道の東方沖の公海にはサンマ、サバ、イワシなどの中国漁船が活発に活動している。そうした中国漁船の操業状況がひと目で分かるよう、朝日新聞は「明るい部分ほど盛んに操業」との解説を入れた日本周辺の海図を載せた。この記事を読んだ朝日新聞の読者はきっとこう思ったに違いない。 「中国は言っていることと、やっていることが全く矛盾している。日本産水産物の輸入を禁止したのは、食の安全とは全く関係ないことがこれで分かった」。 この朝日新聞の記事は、中国の矛盾した態度を鋭く突く、拍手喝采ものの傑作だろう。産経新聞も朝日新聞と同様に鋭く突いた 驚いたのは、産経新聞の八月二十五日付朝刊の一面トップ記事と、三面の特集記事を見たときだ。朝日新聞とそっくりの内容なのだ。三面の見出しは「中国、禁輸でも日本沖で操業」と、朝日新聞の「日本産禁輸でも近海で操業」とほぼ同じ内容だ。 産経新聞の三面記事の前文の締め言葉は、「中国は禁輸措置の一方、中国漁船が日本沖で取った海産物を自国産として流通させる矛盾した対応を取り続けている」と厳しく断じた。 そして、産経新聞も朝日新聞と同様に、「中国漁船が操業している日本周辺の水域」と題した地図まで載せた。そのうえで、はっきりと「中国漁船が福島県や北海道の東方沖の北太平洋でサンマやサバの漁を続けている。同じ海域で日本漁船が取ったサンマは日本産として輸入を認めない半面、中国漁船が中国の港に水揚げすれば、中国産として国内で流通させている。日本政府関係者は不合理としか思えないと批判する」と書いた。 言わんとしていることは産経も朝日と同じである。おそらく新聞の題字(ロゴ)を隠して記事を読み比べたら、どちらが産経か朝日か見分けにくいだろう。毎日新聞も社説で矛盾を指摘 おもしろいことに、毎日新聞も八月二十四日付社説で中国の矛盾した態度を指摘した。社説は後半で「中国政府は『食品の安全と国民の健康を守る』と禁輸を正当化しながら、中国漁船による三陸沖の公海などでの操業は規制していない。これでは矛盾していると言わざるを得ない」ときっぱりと言い放った。 朝日、毎日、産経が横並びで中国の禁輸措置を「矛盾」と形容して批判する記事は、そうそうお目にかかれない。朝日新聞の記事を喜ばない読者もいる! 最後に、この一連の報道に関する、私のちょっとした考察を述べてみたい。 普段は真逆の朝日と産経が的確な記事を報じたわけだが、それぞれの読者層からは、いったいどう評価されているのだろうか。今回の朝日の記事を私は高く評価するが、左派リベラル層はおそらく苦々しく思っていることだろう。 朝日新聞が一年前に中国の禁輸に対して「筋が通らぬ威圧やめよ」と書いたところ、「朝日はおかしくないか。批判すべきは海洋放出を強行した政府ではないか」と主張するネット記事が出た。そう、左派リベラル層が朝日に期待しているのは中国への批判よりも、日本政府や巨大企業への鋭い批判である。だとすると、朝日新聞が地図まで示して中国の矛盾を鋭く突けば突くほど、朝日の読者層は「最近の朝日はおかしくないか」との思いを募らせるであろうことが想像される。一方、産経の論調は首尾一貫しており、読者層は「よくぞ書いた」と喝采を送っていることだろう。 朝日新聞の記者とて、矛盾が明らかな以上、中国の禁輸の矛盾を書かないわけにはいかない。ただ、記者が鋭い記事を書いても、それを喜ばない読者層がいることを思うと、記者の悩ましいジレンマが伝わってくる気がする。 処理水の報道をめぐっては、もうひとつ重大なことに気づいた。それは次回に詳述する。
- 06 Sep 2024
- COLUMN



