キーワード:メディア
-
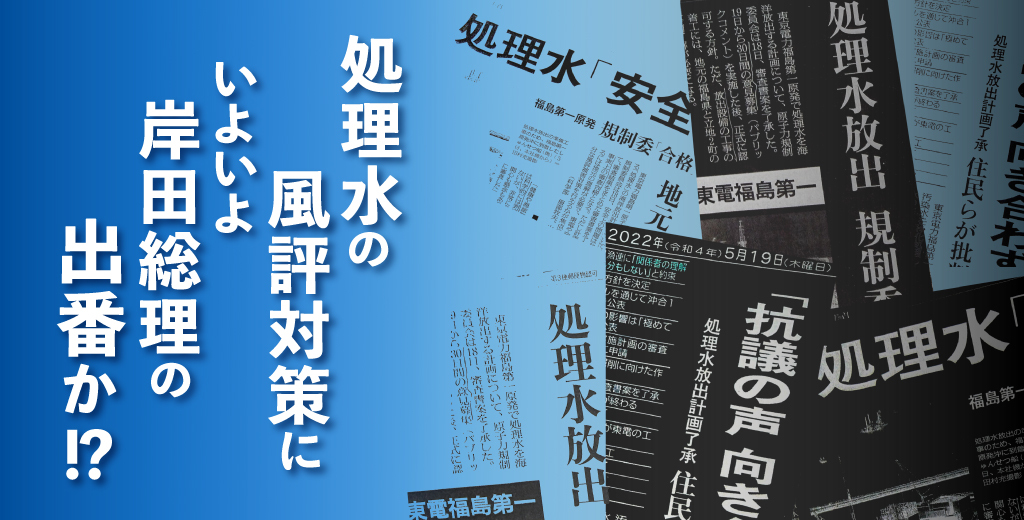
処理水の風評対策に いよいよ岸田総理の出番か!?
二〇二二年六月十五日 原子力規制委員会は五月十八日の定例会合で、福島第一原子力発電所のALPS(アルプス)処理水の海洋放出に、事実上のゴーサインを出した。そこで最近の一連の新聞を読み比べてみたところ、半分の新聞メディアは風評の解消どころか、その拡大に加担していることがあらためてわかった。では、どうすればよいのだろうか?読売新聞は「安全」を強調 五月十九日付の主要六紙(朝日、読売、毎日、産経、東京、日経)を見ると、これまでの流れの通り、朝日、毎日、東京は海洋放出に批判的だ。この三陣営と読売、産経の二陣営が対立する「分断の構図」は間違いなく定着したといってもよいだろう。 読売新聞は二面と三面で扱った。社説横の三面ではほぼ全面を費やし、「海へ処理水『安全』 福島第一原発 規制委『合格』 地元の理解が焦点」と海洋放出の安全と審査合格をアピールした。冒頭の文章では、更田豊志・規制委員会委員長の「健康や海産物への影響は到底考えられないが、非常に多くの人の関心も懸念もあるので丁寧に審査した」とのコメントを載せ、安全性を強調した。 見出しで「安全」という大きな文字が目に飛び込むのは読売だけであった。これは明らかに風評が生じないように意図された記事に思える。産経は一面の二段見出しで「処理水放出計画を了承」とあっさりした内容だった。朝日新聞はあえて「木材への風評」を持ち出した 興味深いのは朝日新聞だ。 五月十九日付に限れば、社会面の四段見出しで「処理水放出 規制委が了承、着工 地元の了解が焦点」と事実関係を中心に報じ、意外に地味だった。しかしこれは、すでに四月十四日付けの新聞で二頁(四面と八面)にわたり大特集を組み、批判的に報じたからに他ならない。 驚いたのはこの四月十四日付総合面(四面)。福島県森林組合連合会の代表理事会長の「反対だ」の声を載せ、「処理水が放出されれば、福島産木材のイメージ低下につながるとの懸念」と、海とは関係ない木材の風評まで持ち出した。 海への放出が、なぜ木材の風評にまで拡大するのか、私は想像したこともない。危険な方向に対して想像力がたくましく働く朝日新聞の記者はあえて木材関係者の声を拾い、「木材への風評が生じるのでは」と小火に火種を放り込むような記事に仕立てた。本人は善意と警告の意図から書いているのだろうが、結果的にはこういう記事が風評を起こすのだというお手本のような記事である。 いったい記者は何を目的に記事を書いているのだろうか。私自身は海洋放出が滞りなく進むことを願っているが、朝日の記者は木材への風評が生じるのをまるで期待しているかのような書きっぷりである。朝日新聞は一月三十一日付でも、一面と二面を割いて特集を組んだ。一面の大見出しは「処理水『来春放出不信なお』で不信を強調していた。これでは風評に火と油を注ぐようなものだ。威勢がよい東京新聞 反原発路線を貫く東京新聞は依然として威勢がよい。一面の見出しは「抗議の声向き合わず 処理水放出計画了承 住民らが批判」。原発被災者訴訟の原告団長の「反対や不安の声が出ているのに、何があっても流そうという強硬な姿勢を感じる」とのコメントを載せ、海洋放出が反対の動きを押し切る形で強行される事態を強調した。毎日新聞の社説はまるで他人事の論調 毎日新聞は五月十九日付の一面では「処理水放出『計画』了承」と事実関係をあっさりと報じたが、風評に向き合う傍観者的姿勢がより鮮明に分かったのは五月二十九日付社説だった。 同社説はいきなり「政府や東電には地元や国内外に対して説明を尽くそうという姿勢が見えない」と書いた。私から見れば、国民にわかりやすい説明を尽くそうとしないのは新聞の方に思える。 この社説はさらに「政府は三〇〇億円の基金を新設し、風評で海産物の価格が下がった場合に買い取ったり、販路の拡大を支援したりする方針を示している。被害対策を講じるだけでは、関係者の不安は解消されまい。風評そのものが生じないように努めることが欠かせない」と書く。そして「何よりも重要なのは、正確な情報の発信に力を入れることだ」と強調するが、一体誰に向けて言っているのだろうか。重ねて言うが、風評そのものが生じないように正確な情報の発信に力を入れるべきなのは新聞の方である。 なぜそう言えるのか、説明しよう。五〇〇回説明してもまだ足りないのか? その証拠のような記事が朝日新聞の一月三十一日付朝刊だった。「政府は昨年四月から約五〇〇回の説明会や意見交換会を開いてきた」と書いている。しかし、五〇〇回開いても、「対象者は農林漁業者、観光業者、自治体職員と限られ、学校など若い世代への説明は少ない」と批判した。 政府が学校にチラシを配ろうとすると、それを阻もうとしたのは自治体やメディアである((『処理水のチラシ配布に見る国の「ひ弱さ」とメディアの傍観主義の行く末は?』))。 政府が五〇〇回もの説明会を開いても、なお説明が行き届かず、なおかつ風評が収まらないというのであれば、それを補う形でメディアがしっかりと正確な記事を書けばよいはずだと思うが、朝日新聞にはそうした問題解決を指向する情報発信に努める意識は低いようだ。 仮に政府が一〇〇〇回の説明会を開いても、それと同時並行して、新聞が反対や不安をもつ人たちの異議ばかりを報じれば、説明会の努力は無に帰すだろう。 そこに見られるのは、風評を鎮めるのは政府の役目であり、われわれメディアは高みの見物(よく言えば客観的な観察者)といこうとの構図だ。このようなメディアの姿勢で風評が収まるわけがない。高みの見物だけならまだしも、その高みから世間の諍いに向けて火の玉を投げているのが実情である。記者は国の報告書をもっと分かりやすく解説を 原子力規制庁は五月十八日にALPS処理水の海洋放出関連に係る「審査書案の取りまとめ」(全一一〇頁)と題した詳細な報告書を公表している。そこには海や海の生物、人などへの影響が細かく解説されている。風評を抑えたいと思うなら、記者はそれをじっくりと読み込んだ上で、その内容を国民に伝えればよい。こうした解説記事を書くなら、 風評の軽減に少しは貢献できるはずだ。 ところが、朝日、毎日、東京の記事のパターンは、政府の決定に対して、異を唱える人達のコメントをメインに掲げ、「計画通りに放出できるかは不透明だ」「地元との調整が難航しそうだ」「風評対策の基金をつくっても、地元の理解の醸成につながるかは未知数だ」といったワンパターン記事を繰り返す。政府の対策への言及は五~六行で終わりだ。岸田総理は記者会見で直接、国民に語ろう ではどうすればよいか。岸田総理が風評対策に絞った記者会見を何度か開き、一回の会見で少なくとも三〇分間にわたり、処理水に関する科学的な説明を行えばよい。ジャーナリストの池上彰氏のような感覚で解説するのだ。こうすれば、記者も書かざるを得ないだろう。 その会見で威力を発揮するのが前回のコラム((『原子力の再稼働に向け、岸田首相が名サウンドバイトを放つ!』))で書いた「サウンドバイト術」である。 「トリチウムを含む処理水は世界中で放出されている」「海産物に蓄積することはない」「トリチウムは川や飲み水など自然界にも存在する」などの基本的な事実を総理がしっかりと伝えれば、一定の伝達効果はあるはずだ。 イラストや図をふんだんに使って、岸田総理が肉声で解説を行えば、テレビは「総理自らの異例の解説とメッセージ」と生放送で流してくれるだろう。新聞も会見内容を無視することは難しいだろう。サウンドバイト術を駆使した会見をぜひ見たいものだ。
- 15 Jun 2022
- COLUMN
-
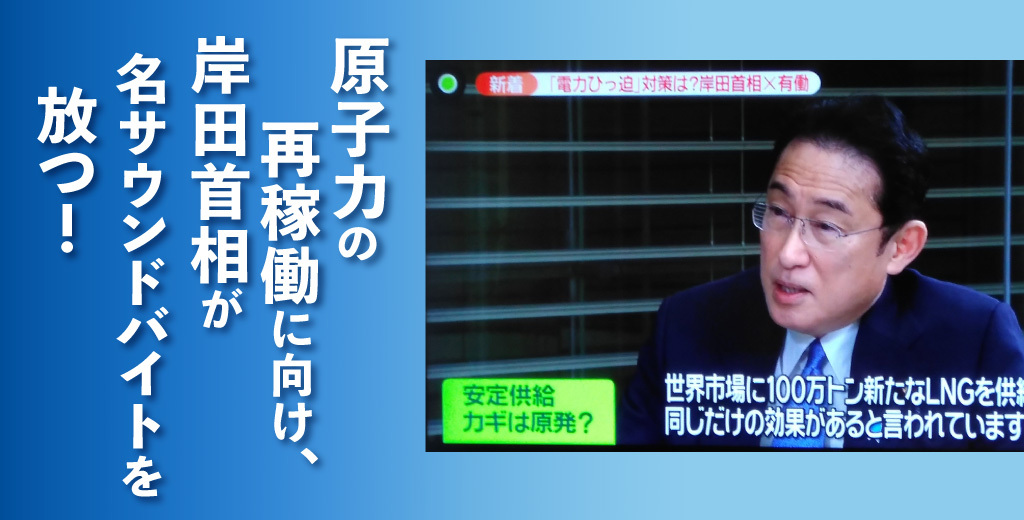
原子力の再稼働に向け、岸田首相が名サウンドバイトを放つ!
二〇二二年五月二十四日 エネルギー価格の高騰で原子力の再稼働に注目が集まる中、その再稼働に向けて、岸田文雄首相が短い言葉で的確なメッセージを伝える「サウンドバイト術」のお手本ともいえる大ヒットを放った。来年に予想される福島第一でのALPS処理水の海洋放出についても同様に、ホームラン級のサウンドバイトを期待したい。テレビ番組「ZERO」で明言 五月十三日夜に放映された日本テレビのニュース番組「ZERO」に出演した岸田総理(=写真)は有働由美子アナウンサーのインタビューに答えて「原発一基の再稼働で 一〇〇万トンの新たなLNG(液化天然ガス)を供給する効果がある」と自信に満ちた表情で述べた。たまたまテレビを見ていて、「この言い方は、事の本質をズバリと伝えるサウンドバイトのお手本だ」と思い、心の中で喝采を送った。 サウンドバイト(sound bite)とは、政治家や識者などの発言や映像が放送などで短く切り取られて伝えられることを指す。簡単に言えば、発言のカケラ(biteは「ひとかじり」の意)のことだ。多くの人が経験する通り、テレビのインタビューを受けて、三十分間とうとうと話しても、実際に放送されるのは、発言の一部だけで、たいていは10~20秒程度の長さの発言が視聴者に届くだけだ。 ならば、最初からテレビのインタビューを受けるときは、10~20秒に収まるような発言を用意しておいて、そのフレーズを何度も強調することが「サウンドバイト術」となる。政治家やテレビのコメンテーターは、たとえどんなテーマであっても、常にこのサウンドバイト術を身に着け、事の本質をとことん考え抜いた上で、視聴者の心に響く短い言葉を編み出しておく必要がある。「一〇〇万トン」の数字にインパクト だれもが知る通り、ロシアのウクライナ侵攻で天然ガスをはじめ、さまざまな原料の価格が高騰している。電力を生み出すエネルギー価格、そして電気代も上昇中だ。この悲惨な現状を見れば、電気代の抑制につながる原子力の再稼働が当然議論されるべきであり、原子力の再稼働に向けた強力なメッセージが必要になる。識者でも政治家でもよいから、原子力の再稼働をプッシュする的確な言葉を、このタイミングでズバッと言ってくれないものかと個人的に思っていた。 私なら、どういう言い方をするのだろうかと思案していた矢先に、岸田総理の発言を聞いた。原子力の再稼働は「LNG一〇〇万トンの経済価値」という数字を聞いたとき、「なるほど」と感心した。 日本は海外から石炭、石油、天然ガスを大量に輸入している。その価格が跳ね上がれば、巨額の国富が海外に消えていく。この国富の流失は、言ってみれば、海外の資源国に巨額の税金を払っているようなものだ。その国民負担を抑えてくれるのが原子力の再稼働である。 この窮状を打破する言葉が岸田総理の「一〇〇万トン」だった。原子力発電所一基の再稼働でLNGが一〇〇万トンも節約されると聞けば、相当な量だというイメージが誰にでも伝わる。それこそが、私が大ヒットと形容した理由である。 翌日の毎日新聞はこの発言をニュースにした。 朝日は「一〇〇万トン」という言葉を入れずにニュースにした。一〇〇万トンという数字を入れると、いかにも原子力の再稼働に有利な数字に見えるので、あえてインパクトのある数字を外したとしたら、さすが朝日新聞らしいなぁと感心する。サウンドバイトは繰り返しが重要 実は、岸田総理の同様の発言は四月二十六日に放送されたテレビ東京の「WBS(ワールドビジネスサテライト)」でも見られた。このときも「一〇〇万トン」という数字を出していた。東京電力の株価が一時急騰したくらいだから、世間に対する影響力はあったといえる。 サウンドバイト術の大事な点は、一回言ったら終わりというわけではないことだ。良いフレーズは、どの媒体でも、何度でも繰り返す。これが肝要である。テレビでも、ラジオでも、新聞でも、視聴者や読者はいつも同じ層が見たり、読んだりしているわけではない。一回言ったところで全国民に伝わることはない。その観点からも、岸田総理の複数回にわたる「一〇〇万トン」発言はサウンドバイト術にぴったりとかなっている。金額を示せば、ホームラン ただし、一〇〇点とは言えない。一〇〇万トンの節約に相当する金額がどれくらいかが分からないからだ。 LNGの輸入価格は相場の変動で上下するが、一トン当たりおよそ十万円となっているようだ。とすると一〇〇万トン×十万円で一千億円となる。つまり、原発一基の再稼働でおよそ一千億円の国富を食い止めることができる。コロナ禍で経済的に苦しむ人たちへの給付金に換算するならば、十万円を一〇〇万人に配れる額である。 こういう身近な例を挙げて、一千億円という金額も同時に示せば、サウンドバイト評価ではホームランだった。一千億円という言葉を追加するだけなら、二秒もあれば十分だ。次に発言するときには、ぜひとも金額を加えてほしい。 来年はいよいよ福島第一のALPS処理水の海洋放出が始まる。処理水のリスクの大きさをしっかりと伝え、なおかつ風評被害を抑えるために、政府関係者は20秒以内で伝える言葉と映像を今から考えておく必要があるだろう。
- 24 May 2022
- COLUMN
-
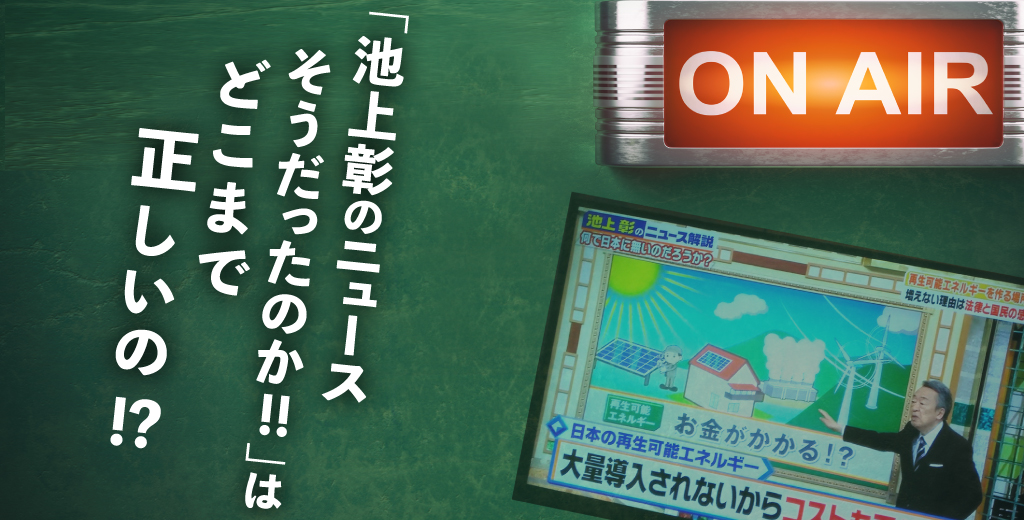
「池上彰のニュースそうだったのか!!」はどこまで正しいの!?
気候変動を防ぐ国際会議COP26(第26回気候変動枠組条約締約国会議)の開催やガソリン代などの高騰で再生可能エネルギー問題を取り上げるテレビ番組が増えている。しかし、分かりやすさを強調するあまり、偏った内容が多い気がする。その最たる例が「池上彰のニュースそうだったのか!!」だ。たいていの視聴者は池上彰氏の解説なら、信じてしまうだろう。テレビ番組を検証するファクトチェックが必要だ。その番組は11月13日に放映された。そのシナリオは「先進国の中でなぜ、日本の再生可能エネルギーは、世界に比べて遅れているか」という設定だ。ドイツの大地に広がる無数の風力プロペラ映像を見せながら、日本は温暖化対策に後ろ向きで、市民団体から不名誉な「化石賞」をもらったと解説し、化石賞がさも重要な意味をもつかのような内容も流した。蛇足ながら、化石賞は、メディア受けを狙った環境団体が恣意的な基準で決めた一種のプロパガンダであり、そこに科学的な意味合いはない。同番組で池上彰氏は、太陽光発電などが日本で進まないのはなぜかと問い、その理由について、「日本では技術開発は進んでいたが、大量に導入しないから建設コストが下がらない」「農地につくろうとしても、農地法にひっかかる」「太陽光の導入で電気代が上がると国民の反発を招くので、先送りしてきた」「日本国民の環境意識は海外とちがう」といった事情を挙げた。そういう説明で特に興味をそそったのは、「ドイツでは再生可能エネルギーを拡大してきた結果、電気代が2倍になった。しかし、ドイツの人たちは環境意識が高いので、温暖化対策になるならば、電気代が上がっても、払ってくれる人が多い」という解説だった。まるでドイツの人たちは地球を守るために犠牲的精神を発揮しているかのような解説には目を疑う。日本は世界でトップクラスの太陽光発電大国番組を見ていて、一番疑問(ミスリードと言い換えてもよい)を感じたのは、日本では太陽光発電が少しも進んでいないという誤ったメッセージを伝えたことだ。事実は全く逆である。日本はドイツよりも太陽光発電の導入容量は多い。資源エネルギー庁によると、日本の太陽光発電導入容量は、中国、米国に次いで3位(2018年実績で5,600万kW)だ。ドイツは4位(同4,500万kW)、インドは5位と続く。この導入量は単純に導入容量を比較したものだ。いうまでもなく太陽光発電は広大な面積を必要とする。日本よりはるかに広い面積を誇る中国や米国で太陽光発電が多いのはある意味であたり前である。そこで、国土面積あたりの太陽光設備容量を比べると、なんと日本は1位に躍り出る。2位はドイツで、英国、フランス、中国、インド、米国と続く。さらに平地面積(1平方km)あたりの設備容量で比べると、日本は426kWでダントツの1位(図参照)。2位のドイツ(184kW)よりもはるかに多い。中国(24kW)や米国(10kW)よりも20~40倍も多いのだ。つまり、日本の平地は、他国に比べるとすでに太陽光発電パネルがひしめき合っている状態なのだ。これ以上増やせば、農地や宅地が狭くなり、国内の食料生産自給率を悪化させる要因にもなりうる。国民に巨額の負担を強いる「固定価格買取制度」には触れずこういう厳然たる事実があるにもかかわらず、番組の構成が「なぜ、日本の太陽光発電は増えないのか」というシナリオになるのか不思議である。全く視聴者を小バカにしたミスリードである。すでによく知られているように、日本の太陽光発電がここまで急激に増えたのは、太陽光など再生可能エネルギーが生み出した電気を電力会社が20年間(産業用)にわたり、一定の固定価格で買い取る「固定価格買取制度」(FIT、2012年開始)のせいだ。事業者にとって確実に利益が出る価格で国民が太陽光電力を買い支えるわけだから、増えていくのは当然である。この買い支え額が「再エネ賦課金」だ。この再エネ賦課金は年々高くなり、2021年5月からは、1kWhあたり3.36円となり、2012年当初の15倍近くにもはね上がった。電気料金の上昇は電気を大量に使う日本の産業競争力を低下させる。電気料金が跳ね上がったドイツでは産業向けの料金を下げる優遇措置を講じている。こういう事実こそ放映してほしいが、全く触れていない。また、再エネ賦課金は、所得の低い人でも負担を強いられる。太陽光を導入する所得層はどちらかと言えば、高所得層なので、この固定価格買取制度は、低所得層から高所得層への所得移転ともいえる。国民全体で見ると、年間約2~4兆円ものお金が太陽光発電の買い支えに費やされているのだ。この太陽光発電の負の部分こそが、視聴者に知らせるべきポイントのはずだ。太陽光の買い支え額はクーポンの比ではない2兆円といえば、10万円を2000万人に配ることができる巨額だ。コロナ対策で5万円のクーポン券を配るのに約1000億円(10万円を100万人に配れる額)の事務的経費がかかると批判されているが、太陽光の買い支えはその20倍の2兆円である。2兆円あれば、コロナ禍で経済的に困った人たちをたちどころに解消できる額だ。おそらく池上氏ほどの勉強家であれば、こういう制度の仕組みと問題点を熟知していたはずだ。なのに肝心な解説がなかったのは本当に残念である。結局、あの番組を見て、多くの視聴者の心に残った印象は「環境意識の高いドイツ人は地球温暖化を防ぐために高い電気代を払ってまで太陽光発電などを進めている。これに対し、日本は遅れている」という、相変わらずのワンパターン思考だ。つい最近、テレビ朝日の羽鳥慎一モーニングショーでも、ゲストコメンテーターが「デンマークの人々は風力発電などで電気代が高くなっても、それを受け入れている。私は電気代の負担が高いという実感はない」と話していた。ここでも西欧は進んでいて、日本は遅れているという図式が見られた。日本の知識人の頭脳はいまも西欧の植民地支配状態どうやら、新聞やテレビのメディアの頭の中には、いまなお「西欧が進んでいて、日本が遅れている」という明治以来の西欧信仰が脈々と生きているようだ。良き規範となるお手本は常に欧米諸国である。このことは、脱炭素や脱石炭、車の電動化(EV化)にもあてはまる。悲しいことに日本政府の頭脳までもが西欧の植民地と化している。北京五輪の外交的ボイコット問題を見ていても、欧米に従うかどうかが議論になっている。同じ西欧でも、さすが原子力大国のフランスだけは「スポーツを政治問題化してはいけない」とカッコよく一線を画している。全く同感である。話はテレビ番組にもどる。SNSが普及したとはいえ、テレビ番組は世論に大きな影響を与える。テレビ番組の内容を科学と事実の観点から検証するサイトがぜひとも必要だ。「池上彰のニュースそうだったのか!!」の中身を検証するサイト「池上彰のニュースは、そうだったのか!!」を開設したい気持ちだ。
- 16 Dec 2021
- COLUMN
-
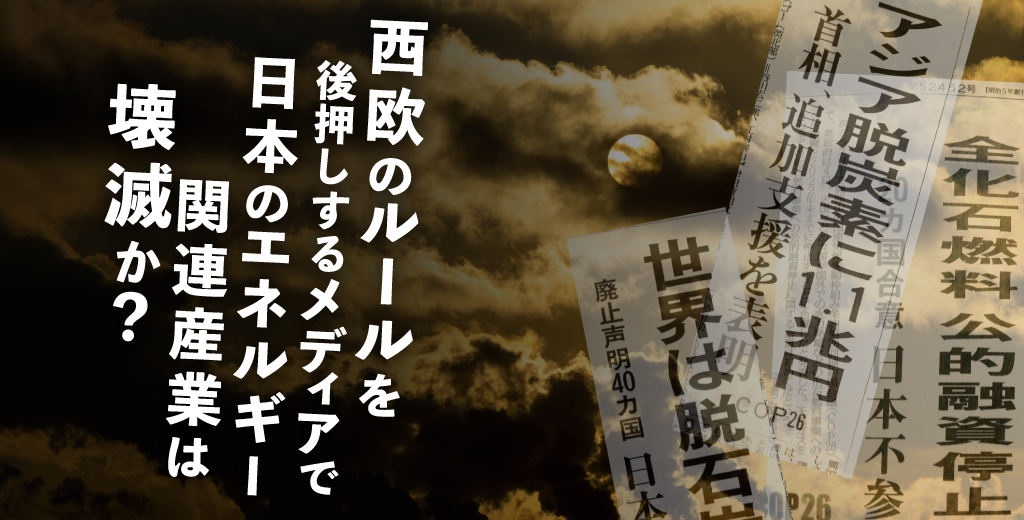
西欧のルールを後押しするメディアで 日本のエネルギー関連産業は壊滅か?
みなさんにビッグな朗報をお伝えしよう。日本政府が11月2日、COP26で環境団体「気候行動ネットワーク」(CAN)から、名誉ある「化石賞」を受賞した。もちろん皮肉を込めて言っているのだが、この種の環境団体から称賛されたら、そのときこそ日本の産業が危機を迎えるときだ。それにしても日本の主要新聞はなぜ、こうも西欧を崇拝し、日本を貶める論調を好むのだろうか。英国グラスゴーで開かれている「国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議」(COP26、10月31日~11月12日)で、岸田文雄首相はアジア全体の温室効果ガスの削減を掲げ、気候対策に最大100億ドル(1兆1,000億円)の追加拠出を表明した。そして、パリ協定に基づく2050年実質ゼロを目指し、水素やアンモニア発電、CO2の貯蔵・回収技術の推進などを表明した。日本なりの貢献を示す至極まっとうな政策である。これに対し、環境団体「気候行動ネットワーク」は待ってましたとばかり、日本に「化石賞」を授与した。理由は「石炭火力の段階的廃止がCOP26の優先課題なのに、日本は未知の技術に頼って、2030年以降も石炭火力を使い続けようとしている」(11月4日付毎日新聞1面)ことらしい。このこと自体は想定内で、環境団体がどんなアクションを起こそうと自由である。日本の主要新聞は環境団体や西欧に迎合!問題なのは、こういう動きに対する日本の新聞の論調である。毎日新聞(4日付)は1面トップの大見出しで「火力に固執日本逆風」と報じた。 サブ見出しは「脱炭素へ『新技術を積極活用』 NGO批判『化石賞』」だ。そして、7面(4日付)の解説記事を見ると、見出しは「『火力大国』日本に外圧 脱石炭合意 政策変更迫られる恐れ」と日本への批判一色である。朝日新聞も負けていない。「首相演説に『化石賞』 COP26環境NGOから批判アジア支援に火力発電『アンモニアや水素妄信』との見出しで、環境団体の抗議風景を写真入りで報じた(11月4日付3面)。石炭融資に関する記事(11月5日付2面)でも「世界は脱石炭火力 廃止声明40カ国 日本賛同せず」の大見出しだ。どちらの論調も、石炭火力を簡単に手放そうとしない日本を「世界の潮流とかけ離れた国」または「悪い国」と断じている。日本経済新聞ですら「日本はめまぐるしく動く脱炭素の議論で後手に回り、存在感が薄れている」(11月8日付)といった論調である。西欧目線で日本を批判するおなじみの「日本遅れてる論」である。一方、読売新聞は「アジア脱炭素に1.1兆円 首相、追加支援を表明」と同じ1面トップ記事ながら、西欧目線の批判的な表現はない。産経新聞も「森林保護・メタン削減合意 温暖化対策へ交渉本格化」(11月4日1面トップ)と日本の姿勢を貶めるような表現は見当たらない。同じ新聞でもかなり異なることが分かる(写真参照)とはいえ、朝日や毎日新聞を読む限り、まるで西欧だけが正しいかのような錯覚を生む。石炭の利用は国によってみな違うどの新聞を読んでも、すっきりしないのは、日本のエネルギー事情の特殊性を詳しく報じていないからだろう。いうまでもなく、エネルギー事情はどの国もみな違う。電源構成に占める石炭火力の割合ひとつをとっても、日本が約30%なのに対し、英国は2%、フランスは1%、スウエーデンに至ってはゼロ%である。そして、中国とインドは約60%台と非常に高く、ドイツと米国では約2割とまだ高い。これだけ大きな差があれば、同じルールを一律に押し付けるほうが非合理なのは小学生でも分かるはずだ。石炭火力が少ない英国(COP26の議長国)なら、石炭を全廃しても自国産業に大きな打撃はないだろう。しかし、日本は2030年にも約2割を石炭火力でまかなう計画である。中国やインドなどの新興国にとっては、しばらくは、石炭火力は安くて安定した電力源である。こうした現実を考えれば、いずれ世界的に石炭火力を縮小させていくことは必要だとしても、すべての国が西欧ルールに合わせることが不条理なのは明らかである。中国や米国も脱石炭宣言に不参加ここで大事なことは、主要新聞やテレビの論調だけが世論ではないことをしっかりと胸に刻むことである。別の言い方をすると、政府はメディアに振り回されることなく、しっかりと自国の利益を世界に向けて主張することである。幸い、英国が提案した「化石燃料事業への公的融資を2022年末までに廃止」に日本は参加しなかった。これは称賛すべき決断だ。ところが、毎日新聞(11月5日付)は一面トップで「全化石燃料 公的融資停止へ 20カ国合意 日本不参加」と報じた。まるで合意した20カ国が正義で、不参加の日本は悪役みたいな扱いである。堂々と自国の利益を主張し、安易な妥協をしなかった日本を称賛する新聞がないのが悲しい。この公的融資の廃止については、中国や韓国も不参加だ。脱石炭宣言に至っては、米国や中国も加わらなかった。当然である。これらの国は、自国の産業を犠牲にしてでも、西欧の一方的なルールについていくほど愚かではないことを教えてくれる。中国は言論の自由がない独裁国家ではあるが、欧米にひるむことなく、堂々と自分の意見を押し通す姿勢だけは見倣ってよいだろう。日本が、自由と民主主義を共通の価値とするEUや米国と足並みをそろえていくことは重要だが、だからといって、西欧主導のルールがどの国にとっても正しいわけではない。今後、化石燃料の高騰が日本を襲う化石燃料事業への公的融資の廃止の広がりは、決して他人事ではない。この化石燃料事業には石炭だけでなく、天然ガスも含まれる。化石燃料事業への融資が止まれば、今後、化石燃料を採掘することはますます難しくなる。そうなれば、今後、石炭やガス、石油などの化石燃料価格が高騰するのは必至である。すでに日本でガソリンなど化石燃料の価格が高騰しているのはその兆しである。にもかかわらず、日本の新聞にはそういう危機感覚がまるでない。環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんの住むスウェーデンは、原子力と再生可能エネルギー(水力など)だけでほぼ100%の電力を賄っている。化石燃料事業がなくなっても、さして困らないだろう。そういう事情にもかかわらず、日本の新聞の多くはグレタさんの「化石燃料事業が環境を破壊し、人々の命を危機にさらしている」という現実無視のコメントをしょっちゅう載せている。資源のない日本の特殊なエネルギー事情を西欧に紹介し、日本独自の戦略を西欧の人たちに理解してもらうのも、日本のメディアの役割だと思うが、そういう気概は全く感じられない。この点で興味を引いたのが毎日新聞(4日付7面)の記事だ。「ルール作りに長じた欧州主導の脱化石燃料の動きが世界の主流になれば、『脱炭素火力』を目指す日本は国際的にさらに孤立する懸念もある」。せっかく欧州主導のルールだと気づいたならば、そのルールがいかに他国の事情を無視した独善的ルールかを解説してくれればよいのに、「西欧主導のルールが主流になれば、日本は孤立する」と書いて終わりだ。西欧のルールに従えば、日本のエネルギー産業に幸せがやってくるとでも思っているのだろうか。総じて日本の新聞やテレビは、国民の生活や命を支えている日本の自動車産業やエネルギー産業が危機的な状況になろうとしていることに冷淡である。環境団体が主張するようなことを真に受けて実践すると、とんでもないことになるのは、すでに旧民主党政権で体験済みである。西欧が「世界のため、地球のため」と称しながら、実は西欧の利益のために動いていることをもっと知るべきだろう。いったい日本の新聞は、日本の何を守ろうとしているのだろうか。いま西欧の味方をしておけば、いずれ日本の産業がつぶれて困ったときに、西欧が助けてくれるのだろうか。そんな幻想を抱かせるようなメディア報道に振り回されてはいけないとつくづく感じる。
- 11 Nov 2021
- COLUMN
-
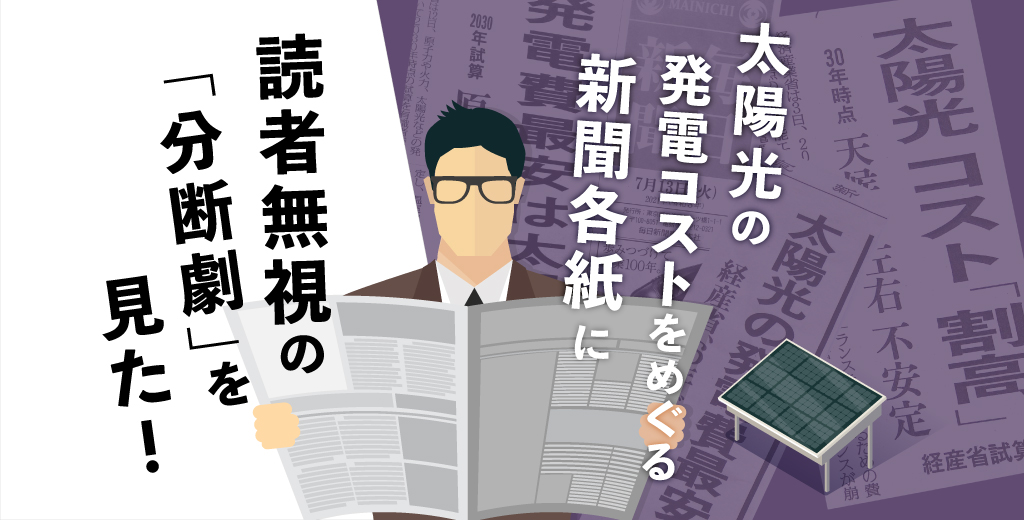
太陽光の発電コストをめぐる新聞各紙に
読者無視の「分断劇」を見た!太陽光と原子力の発電コストをめぐる7月と8月の新聞報道をご覧になっただろうか。新聞の世界が自然礼賛派と現実重視派に「分断」された模様が手に取るようにわかるドタバタ劇だったのではないか。記者たちは、国の思惑に沿った報道ではなく、もっと事実をしっかりと掘り下げてほしい。写真1「発電費最安は太陽光 2030年試算 原発優位崩れる」。7月13日の毎日新聞の1面トップの見出しだ(写真1)。そして2面では「政府 割高でも原発延命」の見出しで、これまでコストが安いと言われてきた原発神話が崩れたと解説した。朝日新聞も一面で「発電コスト最安 原子力→太陽光 経産省試算」の見出しだった。原子力発電に理解のある読売新聞も経済面で「発電コスト『太陽光最安』 経産省試算 原子力を逆転」の見出しで経産省の試算を報じた。読売と同様に原子力発電に肯定的な産経新聞も1面で「発電コスト最安『太陽光』 原発は安全対策費増」と報じた。ただ産経は2面で「太陽光 安定供給に不安」との見出しで太陽光の問題点も指摘した。日本経済新聞も1面で「太陽光発電費 原発より安く」と報じたが、5面の記事では、太陽光発電を拡大するには送電網接続費などのコストがかかり、「主力電源へ壁厚く」との見出しで太陽光発電の課題も詳しく解説していた。新聞を見るとき、読者はまず見出しで出来事の重要性を判断する。本文を批判的にじっくりと読み解く読者が少ないことを考えると、7月13日の新聞各紙の見出しは大半の読者に対して、「いよいよ原発優位の時代が終わり、太陽光発電が主役になる時代が来る」との印象を届けたと思う。どの新聞も経産省の試算を素直に報じたといえば、それまでだが、雨の日や夜に発電できず、常にバックアップ電源を必要とする太陽光発電がそんなに安くなるはずはないと思っている私から見ると、実に不思議な報道ばかりだった。そこには、太陽光の発電コストが最も安いのだと、何が何でも言いたい経産省の思惑が透けて見えた。案の定、4日後の7月17日、各紙は2030年の電源構成で「太陽光などの再生エネルギーが36~38%に拡大する」との政府のエネルギー基本計画の原案を報じた。これまでの計画では、太陽光などの再生可能エネルギーの比率は22~24%だった。これら一連の新聞報道の流れを追っていた読者は、太陽光発電のコストが最安なのであれば、再生可能エネルギーの比率を引き上げるのは当然だと思ったに違いない。ここまでは、国の描いた筋書き通りの展開に見えた。「太陽光コストは割高」の見出しに仰天ところが、8月4日の新聞各紙を見て、目が回るほど仰天した(写真2)。写真2読売新聞の見出し(2面)は「太陽光コスト『割高』 30年時点 天候が左右 不安定」だった。太陽光のコストは1kWhあたり18.9円なのに対し、原子力は14.4円と明らかに原子力のほうが安いことを示す数字も載せた。7月13日の記事とは真逆の内容に面食らった読者もいただろう。そして、産経新聞を見ると、読売新聞と同様に見出しは「太陽光、一転割高に 経産省 発電コスト再試算」だった。産経も統合的な発電コストとして、原子力14.4円、太陽光(事業用)18.9円という数字を載せていた。今回の数値は「バックアップ電源の費用も含めたより実態に近い統合的な発電コストを試算した」結果なのだという。統合的な発電コストとは、太陽光が休止しているときに応援に駆り出される他の電源コストなども含めたトータルのコストのことだ。たった20日前の報道では「太陽光が最安」だったのに、一転、「太陽光は割高」という報道に対して、本当か!?と疑った読者もいたに違いない。そこへ、NHKも8月4日のニュース報道で「太陽光はコスト高に 経産省試算」と報じた。割高になる理由として、NHKは経産省の説明として「太陽光や風力は天候により発電量が大きく変動するため、出力を抑制したり、バックアップ用の火力発電を確保したりするコストが加わったためだ」と解説した。3つの媒体が報じれば、どうやら本当らしいと分かる。読売新聞の記事をよく読むと、さらに驚くべきことが書かれていた。「今回の試算には、(太陽光の設置などで)山林などを造成する費用や再生可能エネルギーの増加に合わせた送電網の増強費などは含まれていない。実際には再生可能エネルギーのコストはさらに高くなる可能性もある(経産省幹部)という」。実際に運用が始まると太陽光が少しも安くないことがこれで分かる。朝日、毎日は過去の記事との整合性を優先一方、毎日新聞や朝日新聞はどう報じたのだろうか。これまたびっくり仰天だ。毎日新聞は8月4日の記事でも依然として「太陽光8.2円最安 経産省2030年発電費用を試算」と報じた。記事では「この試算には送電網強化などの費用は含まれていない。実際の運用時のコストは試算よりも高くなる可能性がある」と書いているが、太陽光のコストとして、経産省が示した18.9円を隠したままだ。朝日新聞も「発電コスト原発11.7円以上 国2030年試算 太陽光が下回る見通し」と報じ、原発よりも太陽光が優位だという論調を繰り返した。記事を読むと、「事業用太陽光は『18.9円』と原発より高くなるとの参考値も経産省は示した」との記述も出てくるが、あっさり触れて終わりだ。やはり「太陽光が最安」を伝えたいようだ。過去に「太陽光が最安」と書いておいて、急に「太陽光が割高に」と書いては、過去との整合性が保てないのだろう。東京新聞(共同通信の配信記事の可能性が強い)は「太陽光の発電費最安」との見出しを載せ、毎日新聞と同様の数字を示して、「太陽光が最も安い」との印象を与える記事を伝えた。これらの論調を見て分かるように、もはや朝日、毎日、東京は何が何でも「原発のコストは優位性を失った」ということを主張したいことが分かる。それに対し、読売、産経は実際の運用では太陽光のコストはまだ高く、原発の優位は揺るがないという路線を肯定的に報じている。これがよく言われる新聞界の分断だ。朝日、毎日、東京新聞を読んでいる限り、太陽光は夢のような自然エネルギーであり続ける。この例だけでも、1紙だけを読み続けるとバイアスに満ちた情報に洗脳されることがわかるだろう。朝日、毎日、東京に至っては「太陽光が地球を救う」という記者の思い込み、社論が「正確な事実を読者に届ける」という目的を妨げていることも分かる。最後に私の見方を伝えよう。太陽光発電が増えた先進国で、太陽光が増えるにつれてトータルの電気代が安くなったケースがはたしてあるだろうか。すでにNHKなどが伝えたように、太陽光の最大の欠点は天候に左右されるため、必要なときに必要な電気を生み出せないことだ。その足りない必要を満たすために、追加的に火力発電や原子力発電が応援に回らねばならない。そうなると、太陽光が増えるほど、その不安定さに振り回されて、火力発電は稼働率を上げたり、下げたり、設備は消耗する。いったい何のための応援なのか。それなら最初から火力発電だけで済むはずだ。これが、太陽光と火力の二重投資によるコストアップの実態だ。太陽光や風力が増える国で電気代が高くなっていくのは理の当然である。記者たちは7月13日の時点で国の試算を素直に報じるだけでなく、太陽光がかかえる統合コストの問題について、もっと詳しく解説すべきだった。
- 17 Aug 2021
- COLUMN
-
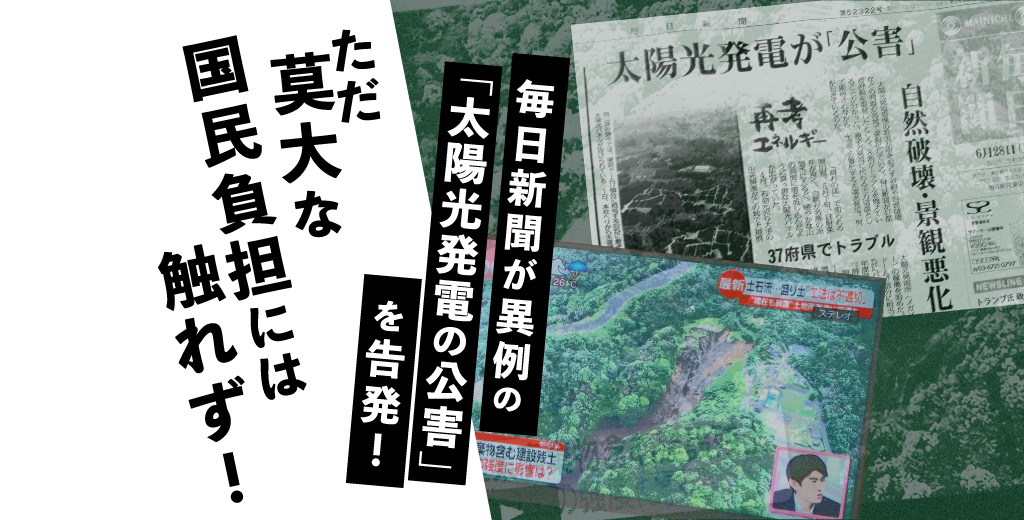
毎日新聞が異例の「太陽光発電の公害」を告発! ただ莫大な国民負担には触れず!
脱炭素社会に向かう手段として太陽光発電が期待されている中、毎日新聞が6月28日付けの一面トップで「太陽光発電が『公害』 自然破壊・景観の悪化 37府県でトラブル」との大見出しで特集記事を載せた。記事は3面にも載る特集だった。私の知る限り、主要新聞の中で太陽光発電の自然破壊ぶりをここまで大きく取り上げた例はない。「ようやく目覚めたか」と遅きに失した感もあるが、問題を提起した意義は高い。ただし、太陽光発電を支えるために莫大な国民負担が強いられていること、そして太陽光発電が真に自立したエネルギー源になりうるのかという大事な視点は抜けていた。■トラブルは「土砂崩れ」「景観悪化」「自然破壊」毎日新聞が伝えたのは各地で起きている太陽光発電の設置をめぐるトラブルだ。岡山県赤磐(あかいわ)市の山では、面積82ヘクタールにパネル32万枚が設置されたが、その後、山の斜面で土砂崩れが起き、地元の水田が土砂で埋まる被害が起きた。奈良県平群町では今年3月、住民約1,000人が「土砂災害の危険がある」として、太陽光発電の事業者を相手取り、事業の差し止めを求める集団訴訟を奈良地裁に起こした。森林の伐採で山は丸裸になり、土砂崩れが心配だという。事業者が当初の契約事業者と代わり、発電事業者の実態が分からないのも問題だとの地元住民の声も伝えている。土砂崩れと太陽光発電といえば、ちょうど7月上旬に起きた静岡県熱海市の土砂崩れ災害を連想する。土砂が崩れた急斜面の起点のすぐ近くの山頂に太陽光パネルがずらりと並ぶ光景がテレビで何度も放映されたのを覚えている人もいるだろう。太陽光パネルの設置が今度の土砂崩れと関係があるかどうかは不明だが、緑の多い山頂に忽然と現れる太陽光パネルの醜い光景に驚いた人も多いはずだ。光をはね返す人工的な太陽光パネルの絨毯はどう見ても自然の光景になじまない。毎日新聞が47都道府県にアンケートしたところ、8割が太陽光発電でトラブルをかかえていた。トラブルの中身は「土砂災害」が29府県で最も多く、次いで「景観の悪化」(28府県)、「自然破壊」(23府県)だった。■太陽光発電は地域に雇用を生み出さない太陽光発電の中でもメガソーラーといわれる大規模発電は広大な場所を必要とするため、山肌を削ることが多く、トラブルが多発していることが分かる。ここまでの記事の内容は、「言われてみればそうか」という想定内のトラブルだ。だが、毎日新聞は記事の後半でさらに踏み込んで「太陽光発電が設置されても、固定資産税以外の税収は見込めない。原発や火力発電所のように雇用を生み出すこともほとんどない。通常、発電した電気の売却先は大手の電力会社。そのため、非常時に地域独自の電源として用いることもできない」と書いている。要するに、太陽光発電を地域に設置しても地方の経済振興に貢献する度合いは乏しく、発電の利益は外部の事業者にもっていかれる植民地型ビジネスモデルだという批判を展開した。これまで太陽光発電に関する記事の多くでは、地域分散型電源で地域の経済に役立つという理想論ばかりを聞かされてきたが、ようやく、ここまで踏み込んだ記事が出てきたわけだ。それだけ太陽光発電の公害が露わになってきた現実があるのだろう。個人的な注文をつければ、「10年~20年後に巨大な量の太陽光パネルがごみとしてたまり、山野に放置される可能性が高い。その撤去で再び住民の貴重な税金が無駄に使われる恐れが高い」という事実も加えてほしかった。■固定価格買取制度で今後10年間で40兆円の負担このように高く評価する記事ではあるが、その一方で限界も見えた。太陽光発電の実力がそもそもどれだけのものなのかに関する踏み込んだ解説がなかったことだ。記事(新聞の3ページ目)には、2012年7月から、太陽光の電気を固定価格で買い取る制度(FIT)がスタートし、これまでに買い取られた累積導入量が一目で分かる棒グラフ(風力やバイオマスも含む)も載っていた。グラフを載せたのはよいが、長期間にわたり、固定価格で買い取られてきた国民の莫大な負担(毎年約2~3兆円)については、全く触れていない。仮に太陽光発電のせいで自然が少々破壊されても、その発電コストが他の電力に比べて、はるかに安ければ、自然破壊も我慢できようが、事実は全く逆だ。太陽光や風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーの普及を支えるために、私たち国民は莫大な金額を電気料金の上乗せとして負担している。これがよく知られる「再エネ賦課金」だ。その金額は導入当初の2012年は1kWhあたり0.22円だったが、2021年は3.36円と約15倍にもはね上がった。家庭用太陽光発電の買取期間は10年だが、10kW以上の産業用太陽光発電は20年もの間、固定価格での買い取りが保証されている。外資系企業が参入しても、確実にもうかる仕組みなのだ。電力中央研究所社会経済研究所の試算によると、2021年度の国民全体の負担額は約3.84兆円にもなる。負担は今後も増えていくため、2030年度は約4.57兆円の予想だ。つまり、今後10年間だけでも40兆円近くが主に太陽光発電を支えるために国民の負担が続くわけだ。その負担は国内の事業者も背負っているため、電気を大量に使う産業界の競争力を弱くする要因にもなる。自然を破壊し、しかも地域の経済振興に対して貢献度の低い太陽光発電の普及に、なぜ、40兆円もの負担を国民に強いる価値があるのか。その核心部分に関する解説が毎日新聞には一切ない。ただ、Q&Aの解説(3面)で「(太陽光は)夜間や悪天候の時は発電できない。太陽光発電の出力が変動しても問題ないように一定量のバックアップ電源を用意しておく必要があります。結果として余ってしまうこともあるため、コストがかかります」とのミニ解説はあった。 バックアップ電源が必要だという点はまさに太陽光発電の最大の弱みだが、肝心な点については、さらっと触れて終わりだ。そこを詳しく突っ込んでいくと、石炭などの火力発電所や原子力発電所の再稼働問題に踏み込まざるを得なくなる。反原発路線で記事を書いてきた毎日新聞の限界が、ここで露呈する。原子力発電所の再稼働は貴重なバックアップ電源になるはずなのに、そこには触れたがらない。結局、毎日新聞は太陽光発電の開発と環境保護の両立が必要だという極めて凡庸な論調で締めくくった。■脱炭素は中国依存を深めていくリスクが高い産業的に見ても、太陽光発電をめぐる国内の状況は厳しい。パナソニックは今年2月1日、マレーシアと島根県にあった工場を閉鎖させ、2021年度中に太陽電池(太陽光発電パネル)の生産から撤退することを公表した。これに象徴されるように、太陽電池生産の分野ではいまや中国系企業が世界の上位を独占している。日本で設置されるパネルの多くは中国製である。パネルだけならまだしも、中国系資本が福島県などにメガソーラーをつくるなど、太陽光の発電分野でも支配の度を強めていく。車に目を転じると、日本が世界をリードしてきたガソリン車やハイブリッド車が目の敵にされている。代って今後、電気自動車が増えていけば、ここでもいち早く車の電動化を進めてきた中国系資本が米国とともに世界の市場を牛耳ることになるだろう。一方、日本では石炭火力までが敵視され、日本の金融機関が次々に石炭火力への融資を止めようとしている。このままでは日本にとって、もっとも安定した電源といえる石炭火力もいずれ消えゆく運命にある。残念なことに、その間隙を縫って、中国が石炭火力を一手に請け負い、途上国の石炭火力建設で覇権を握る。こういう緊迫した世界状況を見るにつけ、太陽光発電を主力電源と位置付ける日本のカーボンニュートラル政策が、いかに日本の基幹産業を破壊していくかが分かるはずだ。そういう未来の革新的な部分を掘り下げる記事にはまだほとんど出会っていない。今回の毎日新聞の記事の限界もそこにある。太陽光発電も含め、自然エネルギーは所詮、自然を犠牲にして初めて成り立つ密度の薄いエネルギーである。ここ数年の自然災害を見ていると、太陽光発電というものはいくら蓄電池とセットで稼働しても、地震や台風、水害などに弱く、バックアップ電源が常に必要なことが明白になった。かつて江戸時代から明治にかけて、木材という自然資源を伐採し過ぎて、あちこちの山が丸裸になった。その自然破壊を救ったのは石油や石炭、原子力発電などだ。似たような過ちが再び繰り返されようとしている。聞こえのよい自然エネルギーが日本のふるさとを破壊していく光景をこれ以上許してよいのだろうか。いまこそ原子力発電所の再稼働に関する議論をもっと起こすべきだろう。
- 15 Jul 2021
- COLUMN
-
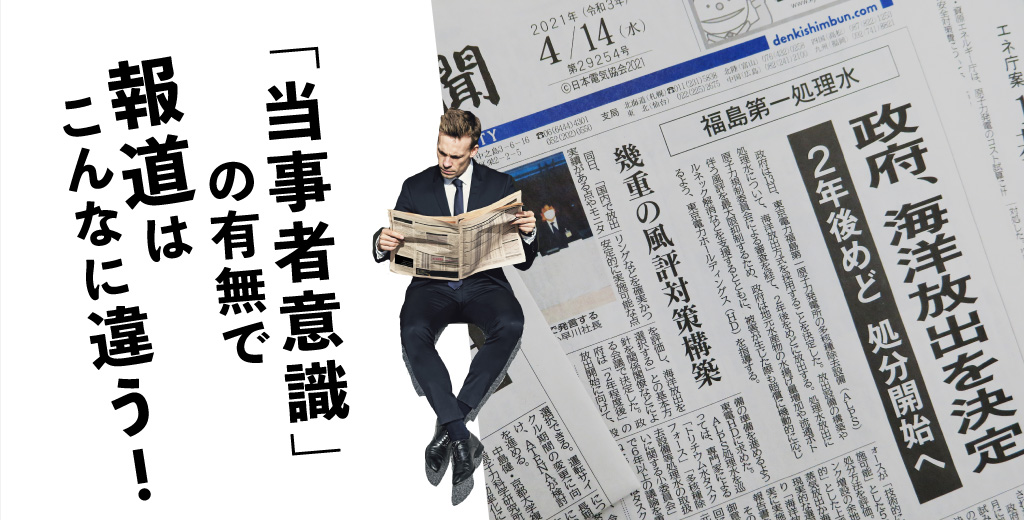
「当事者意識」の有無で報道はこんなに違う!
東京電力福島第一原子力発電所の敷地内にたまる「ALPS(アルプス)処理水」の海洋放出が今年4月13日、決まった。廃炉作業に向けて、大きな一歩を踏み出したといえるが、政権の動向次第では決定が覆される可能性もあり、予断を許さない。カギとなるのはやはり今後の報道だろう。今回は、事態をなんとか前進させようとする「当事者意識」をもっているかどうかで、新聞記事のトーンが大きく異なることを指摘したい。 最初に「当事者意識」を定義しておきたい。ある事柄に直接かかわっているという自覚をもつことを当事者意識というが、もっと言えば、傍観者(評論家)のようにならず、自分の問題として事態を良くしようとするスタンスのことだ。この当事者意識の観点から、政府の海洋放出決定を受けた4月14日付けの朝日新聞と読売新聞を読み比べてみた。どの新聞でもそうだが、論調の違いはまず見出しに表れる。朝日の一面トップの見出しは「処理水 海洋放出へ 風評被害、適切に対応」「政府方針決定2年後めど開始」。さらに同じ一面に載った解説の見出しは「唐突な政治判断 地元反対押し切り」だった。一方、読売の一面トップは「福島第一 処理水23年めど海洋放出 飲料基準以下に希釈」で、副見出しは「政府決定『風評』東電が賠償」だ。朝日と読売で決定的に異なるのは、読売が見出しに大きな文字で「飲料基準以下に希釈」という言葉を入れたことだ。朝日では地元の反対を押し切ったというニュアンスが強く伝わるのに対し、読売はあえて処理水について「飲料基準以下に希釈」をうたい、安全性を強調した。どちらが安心感を醸成するかはいうまでもなかろう。この差は一面トップ記事の冒頭の前文からもうかがえる。朝日の一面トップの冒頭の文章は「菅政権は13日、海洋放出する処分方針を決めた。風評被害を懸念する声は根強く、放出が終わる時期の見通しは立っていない。先行きが見えないまま、処理済み汚染水の保管を続けてきた対策は大きな方針転換を迎えた」(一部省略)とある。まるで他人事のように冷めた目で事態を見ていて、「先行きが見えない」と事態を突き放すかのような印象を与える内容だ。これに対し、読売は「政府は13日、海洋放出を正式に決めた。事前に大量の海水で薄め、放射性物質の濃度を飲んでも健康に影響がないとされる国際基準よりもさらに引き下げる。東電は2023年をめどに放出を開始し、期間は30年以上の長期に及ぶ見通し」。読売も放出が長期に及ぶとしているが、「先行きが見えない」という他人事的な言葉は使っていない。それどころか、短い文字数の前文であえて「飲んでも健康に影響がないレベルにしてから海洋に放出する」という事実を強調している。この処理水問題では、海洋放出によって人体や環境にどのような影響が及ぶかが世間の最大の関心事である。このことにどう応えるかが注目されるが、読売は「飲んでも健康に影響がない国際基準よりもさらに低いレベル」を強調し、世間の不安に応えようとしていることが分かる。■海外でのトリチウム放出をどう伝えるかがポイント政府の決定に対して、朝日と読売がいかに異なったスタンス(政治姿勢)で記事を書いているかの差は2面、3面にも表れる。読売は「海洋放出 世界の通例」との見出しで韓国や英国、フランス、中国、国内の他の原子力発電所でもトリチウムを含む処理水を流している状況を詳しく報じた。「海洋放出は国内外で実績が多く、安全管理の方法は蓄積されている。住民の健康や環境への悪影響は考えられず、・・」と書き、各国の放出量の数値を一覧表にして掲載した。海洋放出は日本だけの特別な事例ではなく、これまで長期間にわたり国内外で放出されてきたという事実を国民に伝えれば、安心感が生まれるはずだというニュアンスが伝わる内容だ。一方、朝日は「いちから わかる!」という解説コラムでトリチウムの放出リスクについて触れている。「日本に限らず、海外でも原発1施設あたり、年間数兆~数十兆ベクレルを排水している。国(日本)の放出基準は1リットルあたり6万ベクレル。基準の40分の1まで薄めるそうだ」と他国でも放出している様子に触れているが、すぐそのあとに「でもやっぱり不安もあるなあ」と書く。読売がWHOの飲料水ガイドライン(1リットルあたり1万ベクレル)よりもはるかに低い濃度で放出すると書いたことに対して、朝日は数字を記した表を載せ、そこに「WHOの飲料水ガイドラインは1リットルあたり10000ベクレル、東京電力の放出時は1500ベクレル」と載せ、よく見れば、飲料水のガイドラインよりも低く放出することが分かるが、あえて読売のような記述的な解説をしていない。■もっと建設的な提言ニュースを期待したいさらに、朝日は「処分方針への態度をあいまいにし、決断を先延ばしし続けてきた」と書き、「風評対策 効果見通せず」と批判的なトーンを展開。それに加え、「中国が『深刻懸念』 韓国『強い遺憾』 米は決定を評価」(※筆者注:「米は決定を評価」の文字が小さい)との見出しで中国や韓国の言い分を載せている。中国や韓国も海へトリチウムを放出しているという事実をしっかりと詳しく書いてほしいところだが、その誠意は見られない。また、朝日は決断の先延ばしを特に問題視しているが、では仮に、5年前に政府が海洋放出を決定していたら、「よくぞ決断した。評価したい」と政府を後押ししただろうか。それはまずありえない。5年前に決断していれば、間違いなく「国民との議論を十分にせず、熟議を経ないまま海洋放出した」と非難しただろう。政府の決断が早ければ、「議論を打ち切った」と非難し、決断が遅ければ「先延ばし」と批判する。私はこういう報道スタンスを「評論家的」と呼びたい。いずれは必ず実行せねばならない課題に対して、自分は高見の見物に位置して、批評を繰り返すような報道スタンスに、はたして国民は共感するだろうか。もし先延ばしが許されないなら、新聞社自らが政府の決断を促すような建設的な記事(情報)を流し、事態を前進させようと頑張ればよいのに、この処理水問題を見る限り、そういう事態を打開するような当事者意識が朝日には見られない。もちろん朝日新聞のこうした批判的な姿勢を評価する人が多いことも承知しているし、朝日新聞が政権の問題点をただすうえで数々の良い記事を書いていることも分かっているが、それでも、この種の「避けて通れない難題」に対してはもっと建設的な提言記事を期待したいところだ。処理水の海洋放出に対して国民が抱くイメージは報道次第で良くも悪くもなる。報道機関が「当事者意識」をもって処理水問題を報じてくれれば、事態はもっと良い方向に向かうのになあ、と今回の読み比べで認識した次第である。同じテーマを追いながら、2紙を比べるだけでもこれだけの差がある。やはり新聞は1紙だけに頼るとその1紙の色に染まってしまう。新聞はできるだけたくさんあったほうが民主主義にとって健全である。1紙だけを長く購読するのではなく、主要な新聞を半年ごとに交互購読するのがよい。ふとそんなことも感じた。
- 17 May 2021
- COLUMN
-
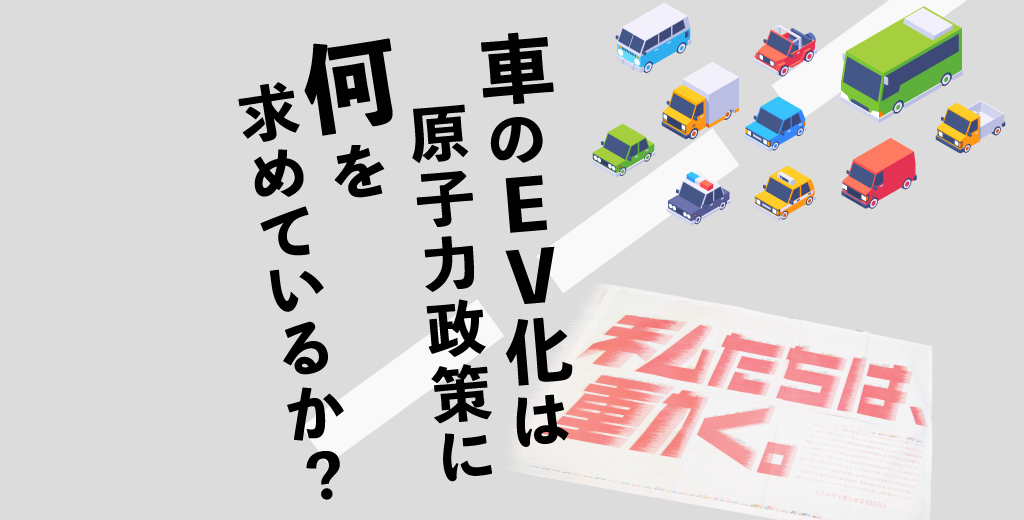
車のEV化は原子力政策に何を求めているか?
最近の新聞を見ていると、電気自動車(EV)の販売が世界で加速しているというニュースがよく目につく。そこで思い出すのが、2020年12月に行われた豊田章男日本自動車工業会会長(トヨタ自動車社長)の会見内容だ。豊田氏はそこで重大な発言をした。日本中に電気自動車が普及したら、大量に必要となる電気をどう賄うのかという問いかけだった。その問いかけにメディアはまだ応えていない。電気で走る電気自動車は一見環境に良いように見える。確かに走っているときには二酸化炭素などを含む排気ガスを出さない。だが、少し考えればわかる通り、その車が走るのに必要な蓄電池(バッテリー)の電気が、石油や石炭、ガスなどの化石燃料を使った火力発電所で生み出されていれば、トータルで見て、二酸化炭素を排出していることになる。言うまでもなく車を生産する工場でも二酸化炭素は排出される。では、電気自動車が再生可能エネルギーの代表格である太陽光発電で生み出された電気を使うなら、二酸化炭素を出してないと言えるかというと、そうでもない。太陽光発電は1年中、昼夜を問わず電気を生み出してくれるわけではない。夜になれば休むし、雨や雪が降ったり、曇るだけでも小休止する。なんと太陽光発電の平均的な稼働率は、日本では20%前後しかない。となると、太陽光発電が休むときに備えて、バックアップとして別の火力発電所を用意しておかねばならない。もちろん水力発電や原子力発電でもバックアップできるが、現実には化石燃料を使う火力発電なしでのバックアップは難しいのが実情である。つまり、太陽光はいまだ自立したエネルギーではない。電気自動車がいくら「太陽光発電の電気で走りました」といっても、間接的には化石燃料に頼っていることになる。言い換えると、電気自動車だけを見ても、それが二酸化炭素の削減に貢献したかどうかは分からず、電気自動車の電気がどういう手段で生み出されたかを考える必要が出てくる。たとえば、原子力発電が多いフランスと、いまだ火力発電が多いドイツでは、同じ電気自動車が走っていても、その自動車はエコにも非エコにもなるわけだ。ここまでは、ごく常識的な話だが、では、今後、世界中で加速する車のEV化にどう対処すればよいのだろうか。そういう中、菅義偉総理は2020年10月、「2050年までに二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を実質ゼロにする」とのカーボンニュートラル政策を宣言した。はたしてどこまで実現できるのか、個人的には冷ややかに見ているが、どちらにせよ、温室効果ガスの排出を実質ゼロにするためには、電気自動車の普及は絶対に欠かせない。しかし、問題は、その電気自動車の電気をどういう方法で調達するかである。EV化で日本の車関連産業は壊滅する!そこで思い出すのが豊田氏の記者会見である。豊田氏は次のように述べた。「カーボンニュートラルは国家のエネルギー政策の大変化なしには達成できない。このまま車のEV化が急激に進めば、日本では車が作れなくなってしまう。仮に400万台の車をすべてEV化したら、夏の電力の使用ピークのときは、電力不足に陥り、その解消には原発だと10基分の電気が必要になる。充電インフラの整備には約14~37兆円かかる」(筆者で要約)豊田氏は他にも重要な指摘をいくつかしている。興味のある方はぜひYouTube(※テレビ東京にて視聴可能)を見てほしいが、残念だったのは翌日の新聞だった。毎日新聞だけは大きく取り上げ、「『脱ガソリン』反対 トヨタ社長、政府批判」との大見出しで報じた。報じたのはよかったが、見出しの言葉には「違うでしょ!」と思った。会見を聞く限り、政府に反対したというよりも、政府の性急なカーボンニュートラル政策によって、日本の基幹産業である自動車産業が壊滅的な影響を受けることへの憂慮を表明したと私には思えた。共同通信は「急速なEV普及推進に懸念」との見出しで配信したが、小さな記事だった。他紙には総じて目立つような記事はなかった。豊田氏は、このまま車のEV化を進めていけば、エネルギー政策の大変革が起きることを訴えたわけだが、そういう真意を深く汲み取った含蓄に富む記事はなかった。日本自動車工業会によると、日本には約7,600万台の車(バスやトラックも含む)がある。これらがいずれすべてEV化していく流れを考えると、いますぐにでも、原子力発電所の新設をもっと増やすのか、原子力発電所の再稼働をもっと進めるのか、または原則として40年という稼働を60年に延ばすのか、という真剣な議論を巻き起こす必要があるが、そういう白熱した議論は見られない。トヨタが世界のEV化戦争で勝ち抜けるかどうかは、私たち日本人にとって決して他人事ではない。案の定、2021年1月1日、日本自動車工業会などは驚くべき広告を主要紙に載せた。見開き2ページにわたり、「私たちは、動く。」との赤い文字が躍る斬新な広告だ(写真)。その中に「日本の自動車業界には、550万の人たちが働いている」と書いてあった。EV化を慎重に進めないと、550万人が路頭に迷う可能性があることを印象づける内容だ。それだけ危機感が強いのだろう。EV化の方向いかんでは、車関連産業に依存する愛知県や群馬県、静岡県などは壊滅的な影響を被る可能性がある。車のEV化はそれくらい日本経済に大きな変革を迫る動きなのだ。いずれは、GoogleやAmazonなどの海外の巨大IT企業が車の製造販売市場に参入してくるだろう。欧米はもはや「ハイブリッドカーではトヨタに勝てない。今後、トヨタに打ち勝つには電気自動車しかない」という戦略で車のEV化を強力に推し進めているようにみえる。「地球を守るため」という美しい文句は、うわべの宣伝であり、本心は自国に有利な産業を育成するのが狙いのはずだ。政府は2030年の電源構成で原子力の比率を20~22%との計画をつくり、推進している。しかし、原子力の再稼働でさえ思ったほど進まない中、このままでは、この比率の達成はほぼ不可能だろう。まして車のEV化を同時に進めようとしているならば、たとえ世間から批判があろうとも、原子力による電気の調達をどうするかの議論をもっと巻き起こす必要がある。政治の側にも豊田氏の憂慮に応える決断と覚悟が求められる。
- 19 Mar 2021
- COLUMN
-
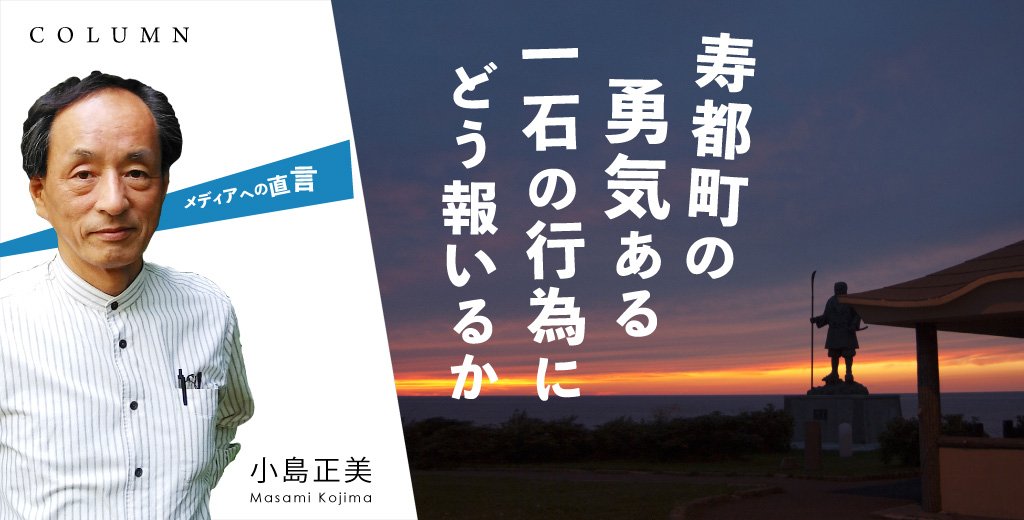
寿都町の勇気ある一石の行為にどう報いるか
日本の原子力発電所から発生する高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場の選定をめぐって、北海道の寿都町と神恵内(かもえない)村が名乗りを上げた。だれもが避けて通れない難題に、寿都町が果敢な一石を投じたといえるが、新聞をはじめメディアの反応は冷ややかだ。誠に不思議である。だれもが引き受けることを忌み嫌う国家的なプロジェクトに協力の姿勢を見せた人への感謝の念として、20億円はあまりにも少な過ぎる。100億円でもまだ少ない。寿都町町長が投げかけた一石の意義をしっかりと考えたい。いまそこにある危機をどう打開するか核のごみ問題の本質とは何だろうか? それは、だれかがいつかは必ずやらねばならない難題(一大国家プロジェクト)にどう立ち向かうかということだ。今後、原子力発電所の増設をゼロにするかどうか、再稼働を認めるかどうかという政策的な選択の問題ではない。たとえ今後、原発の建設をゼロにしたとしても、すでに発生している放射性廃棄物が消えてなくなるわけではない。いまそこにある危機をどう解決するかという哲学的難題(アポリア)だという認識がまず必要である。いま全国には1718の市町村(2019年1月1日時点)がある。この小さな国で放射性廃棄物をどう解決すべきかという設定で考えると理解しやすい。日本は民主主義と自由の国なので、処分場の受け入れをだれかに強制させることはできない。そこで一国の議長はこう提案する。「長きにわたり、みなが原子力発電所の恩恵を受けてきましたが、そのエネルギーの副産物を国内のどこかに捨てねばならなくなりました。まず、国内で処分することに賛成ですか、反対ですか」。すると、予想通り全員が「国内処分に賛成」と手を挙げる。そこで、次のステップに進み、議長は「分かりました。では、自分の住む場所に処分場を引き受けてもよいと考える人は手を挙げてください。公共的な視点に立って、市民的な義務を果たしてもよいと考える人はぜひ手を挙げてください」と提案する。ところが、議場に集まった1718人の代表者は一言も声を発せず、場内は沈黙の空気が続く。来る日も来る日もだれも手を挙げない。とうとう13年たっても、手を挙げる人は出てこない。どの人も、だれかが手を挙げるだろうと他人の利他的精神を期待したが、その期待はかなわなかった。この状況は、だれもが総論では賛成するが、各論では反対するという古くて新しい政治哲学的な難題である。どのような形で感謝するのが妥当なのかこの難題がもはや暗礁に乗り上げたかに見えたそのとき、日本の中心部から遠く離れた寿都町の代表者が手を挙げた。だれも引き受けたがらない仕事を、あえて引き受けようという勇気ある挙手だった。文献調査応募書を手渡す片岡町長(左)その人が寿都町の片岡春雄町長だ。「日本は核のごみに関してあまりにも無責任だ。一石を投じたい」(朝日新聞デジタル 9月3日付)と力強く言い放った。1718人の中でだれ一人、公共的な視点に立って責任ある行動を示そうとしなかった中で、片岡町長は貴重な一石を投じたといえるが、共感を示す声は少ない(ように思える)。この行き詰まりを打開する行為に対しては、まずもって、敬意を払うのがこの国の住人のモラルだと私は思う。傍観者だった人が、名乗り上げた人を非難することなど、できようはずはない。もちろんこの国は言論の自由が保障されているので、どんな反対意見を言っても自由だし、どんな思想を訴えようとかまわないけれど、まずは「よく手を挙げてくれました」と労いと感謝の言葉を発するのが市民的義務を分かち合う人としての礼儀というものだろう。「礼」とは思いやりを、みなに見える形で表す礼儀作法のことだ。メディアは冷ややかで無責任な論調ばかりしかし、メディアの論調はどうだろう。「自治体を多額の補助金で誘導するような方法で安全で国民が納得できる最終処分場を選べるとは思えない」(河北新報 10月14日)。「交付金で誘導するような手法は見直すべきだ。財政難に苦しむ自治体には、現実の地域課題に対応した交付金や政策で支援するのが筋ではないか」(京都新聞 8月18日)。「鈴木北海道知事は『ほおを札束ではたくようなやりかた』と疑問を呈する」(朝日新聞 9月21日)と報じている。何という温かみに欠ける反応だろう。みなが忌み嫌う国家プロジェクトに対し、初期段階の文献調査とはいえ、協力してもよいと勇気ある決断を下した人に対して、あまりにも冷た過ぎるのではないか。感謝の気持ちは100億円でも少ないでは、どういう感謝の表し方がよいのだろうか。仮に、将来処分場になるとしたら、みなで拠出したお金を「処分場を引き受けていただき、ありがとうございます」とその当人に渡すのは理にかなったことだ。第一段階の文献調査に応じただけなので、その拠出額は20億円だというが、この難題に一石を投じた人がだれ一人現れなかったことを考えると、20億円はあまりにも安すぎる。橋脚を一つつくれば、なくなってしまう額である。あまり役に立ったとは思えないコロナ禍のマスク配布でさえ466億円の税金を費やしたことを考慮すると、だれもやりたがらない一大国家プロジェクトを引き受ける価値は100億円でも安いはずだ。寿都のまちづくりを支援するのがよい寿都の人々に対して、私たち国民は次のように言うべきではないだろうか。「傍観者だった私たち国民は何もできませんが、せめて寿都町のみなさんがその町で末永く安心して暮らせるような町づくりの実現にお手伝いしたいと思います。そのために今後100年間にわたり、私たちの税金から、毎年20億円をお使いください。これは町づくりへの支援です。痛みの分かち合いであり、決して札束でほおをはたくのではありません。せめてもの私たちの感謝の印です」。寿都町の弁慶岬哲学者のマイケル・サンデル氏は「これから『正義』の話をしよう」(早川書房 15ページ)で「良い社会は困難な時期に団結するものだ」と言っている。つまり、公益のために犠牲を分かち合う正義(道徳)が称賛される社会が良い社会だというわけだ。私は片岡町長と会ったことはないし、どういう人かは知らない。それでも、世に議論の一石を投じた行為を高く評価したいと思う。いまのメディアの論調に欠けているのは、こういう倫理的、市民的な公共精神のあり方を問いかける視点ではないだろうか。
- 01 Dec 2020
- COLUMN
-

「脱石炭」は日本経済の破滅への入り口だ(下)
「みんなちがってみんないい」童謡詩人、金子みすゞ(1903-1930年)が作った「私と小鳥と鈴と」に出てくる有名な一節。いま脱石炭火力問題を考えるうえで大事なのは、この一節である。子育てや人材育成にかかわる人なら、だれしも「そうだ」「そうだ」とうなづくはずだ。国のエネルギー政策にも同じことが言えるはずだ。それぞれの国がそれぞれの地政学的な特徴や条件に応じて、それぞれ自国の利益にかなうエネルギーの組み合わせ(ベストミックス)を選択すればよいという考えに対して、おそらく大半の人は同意するだろう。フランス、ドイツ、英国、米国、中国、ロシアの6国のエネルギー政策を見みてみよう。どの国も自国の利益に従い、「みんなちがってみんないい」を実践している。世界で猛威を振るう新型コロナに置き換えてみれば、都市封鎖を行わず、経済を優先させたスウェーデンのような国があってもよい。同じようなことをエネルギー分野で日本が実行できないはずはない。しかしながら、こと石炭の話になるとメディアや政治の世界はまるで一色の論調がはびこる。新聞やテレビを見る限り、その背景には「石炭火力をやめても、太陽光や風力など自然エネルギーでなんとか賄える」という再生可能エネルギーへの過度の期待、楽観視があるのではと思う。自然エネルギーは「火力寄生」と呼びたい政府の第5次エネルギー基本計画では再生可能エネルギーを主力電源にすることが明記されている。だが、そもそも太陽光や風力は天候次第で稼働したり、休んだりで自立したエネルギーとはとても言えない。石炭やガスなど火力発電をあてにした寄生的な電源だということだ。再生可能エネルギーという言葉ではその本質は伝わらず、「火力寄生エネルギー」と呼んだほうがより事実に近い。この寄生性が国民に正しく伝わっていないために、石炭火力を全廃しても大丈夫といったイメージが流布しているように思う。また、太陽光や風力は需要に応じて出力を自在に制御できない欠点をもつ。このため、太陽光や風力が増えれば増えるほど、そのしわ寄せを食う火力発電は無理な調整運転を強いられる。そのことが火力発電所の経済性を悪化させ、火力発電所の寿命を短くするというような話は非常に重要なことではあるが、専門紙を除き、一般の報道ではほとんど報じられない。世界を見渡せば、再生可能エネルギーが普及している国ほど電気料金は高い。一般家庭にとっては、電気料金が多少上がっても、節約でやりくりできるだろうが、電力をたくさん使う化学や鉄鋼産業にとっては、電気料金の高騰は国際競争力を維持するうえで致命的な弱みとなる。そういう大事な側面も一般の人には意外に知られていない。世界が石炭火力から撤退するなら、むしろチャンスださらに気になるのは、脱石炭火力に関する新聞やテレビの論調で、脱石炭を加速させる欧州に対して、日本は出遅れているという言い方が目立つことだ。新型コロナの死者数を見れば分かるように、欧州が常にお手本とは限らない。エネルギー問題で欧州路線が正しいという保証はどこにもない。経産省の脱石炭方針の公表に対して、日経ビジネス(7月20日)は「『石炭火力休廃止』宣言の真意、エネルギー専門家の橘川氏が読む」と題したインタビュー記事で、橘川武郎氏の「高効率の石炭火力維持が本質ではないかとみています」との声を載せた。どのみち、環境市民団体も専門家も「日本は石炭火力維持だ」とみているのだから、堂々と「日本は、長期的には脱炭素社会を目指していくが、しばらくは日本が世界に誇る高効率の石炭火力をこれからも維持していきます。それが日本の国民の命、経済を守るエネルギー政策だ」と宣言すればよいのに、なぜ、そうしないのか。表向きは「脱石炭に向かっています」と言いながら、実は「高効率の石炭火力を維持する路線です」という言い方は、石炭火力の重要性を伝える点でリスクコミュニケーションの失敗である。石炭火力の重要性を強調する専門家は多くいるのだから、世間に媚を売る必要はなく、市民団体から批判されたら、逆に石炭火力の重要性を訴えるチャンスだと、なぜ思えないのだろうか。国やエネルギー産業界は論戦で勝つ自信がないのだろうか?と勘繰ってしまう。暴論と言われそうだが、欧米が石炭火力から手を引くならば、それはむしろ日本にとっては、高性能の石炭火力を世界に広めるチャンスでもある。他国と同じことをやっていては、世界の競争には勝てない。「みんなちがってみんないい」路線は最新高性能の石炭火力で勝負するチャンスでもある。中国が漁夫の利このまま安易に欧州の流れに乗って石炭火力を全廃してしまえば、中国が漁夫の利を得るのは火を見るよりも明らかだ。高性能の石炭火力の輸出に対して「東南アジアでは日本が建設を協力する発電所の地元住民から、環境汚染への不安から反対運動をしている例もある。政府に求められているのは、完全な撤退である」(一部要約・朝日新聞・7月12日の社説)という他人事的な論調もあるが、それを言うなら、ぜひ中国政府にも強く言ってほしいものだ。今後、原子力の十分な再稼働が見通せない中で何か危機的な状況が発生したときには石炭火力の出番(東日本大震災後に活躍したように)が十分に考えられる。にもかかわらず、日本の金融機関までが石炭火力への融資から手を引く動きを見ていると、いよいよ日本経済も破滅の入り口ではないかと素人ながら悲観的予感がよぎる。これが私の妄想でなければよいがと祈る。「あのとき石炭火力を残せばよかった」で済むか最後にもうひとつ、異論が出そうな見方かもしれないが、世の中は「人為的なCO2(二酸化炭素)の排出が地球温暖化の最大の原因だ」という大前提で石炭火力を廃止する方向で動いているが、もしCO2が温暖化の主因でなかったらとしたら、という別のシナリオも考えたうえで、石炭火力を残すかどうかも議論したほうがよいように思う。未来は常に不確定だからだ。石炭は石油と異なり、複数の国から安定して確保でき、熱量あたりの輸入価格も化石燃料の中ではもっとも安い(資源エネルギー庁ウェブサイト)という事実をもっと国民に知らせることが必要だろう。私が言うよりも、エネルギー問題の基本的なことは資源エネルギー庁のウェブサイトに書かれている。食のリスクや健康の問題を科学的に知るうえで食品安全委員会や厚生労働省、農林水産省、国立医薬品食品衛生研究所など公的機関のウェブサイトが欠かせないように、資源エネルギー庁のウェブサイトをもっと国民に読んでもらうよう広報活動を強化することも必要だろう。エネルギー問題の専門家でもない私があえて大仰な見出しで石炭火力問題に触れた訳は、石炭火力を全廃するかどうかが、日本の将来を左右する天下分け目の戦さだと直感したからだ。
- 25 Sep 2020
- COLUMN
-

「脱石炭」は日本経済の破滅への入り口だ(上)
日本の石炭火力発電を取り巻く状況が厳しくなっている。その象徴的な出来事が昨年12月に日本が受賞した「化石賞」。新聞やテレビの報道では不名誉な賞とされたが、私は「名誉ある賞」だと強く言いたい。これは私の偏見だろうが、環境市民団体から賞賛されたら、むしろそのほうが危うい状況だと思っている。「エネルギー自給率が極めて低く、資源もない日本にとって、石炭火力は絶対に必要だ」との独自の戦略、姿勢を日本国民だけでなく、海外にも向けて訴えていくべきだろう。なぜ中国を批判しないのか不思議なぜ、こんな世論を逆なでするようなことを言うかといえば、長く毎日新聞の記者として取材してきた経験からの直感(皮膚感覚)だ。遺伝子組み換え作物や農薬などの問題で環境保護団体と政府、企業、専門家との議論、交渉、確執を見てきた結果、気づいたことが2つある。ひとつは、EU(欧州連合)の政策が正しく、米国や日本は悪という構図だ。もうひとつは、中国の悪口を言わないことだ。この2つは、環境市民団体(幅広く言えば消費者団体)の「思考の癖」といってもよい。国際NGO「気候行動ネットワーク」(CAN)は昨年12月、スペインで開かれたCOP25(気候変動枠組条約第25回締約国会議)で、脱石炭を示さない日本に「化石賞」を贈った。政府を批判することに使命感をもつマスメディアはすぐさま不名誉な賞として報じた。化石賞はロシア、豪州、カナダ、米国、ブラジルなども受賞している。EU(欧州連合)も一度、受賞しているが、受賞の回数(米国6回、豪州5回、ブラジル3回、日本やカナダ2回など)から見て、脱石炭を打ち出すEU諸国の政策が正しく、米国や日本は温暖化問題の解決に消極的だというイメージをマスメディアはふりまいている。いくら中国が石炭火力を増やし、二酸化炭素を大量に出そうが、中国に化石賞を贈ることはない。なぜなのか本当に不思議である。このことを見るだけでも、化石賞はどこかイデオロギー臭のするうさん臭さを感じる。中国をかばう賞なら、むしろ名誉ある賞だと思ったほうがよいと皮肉を言いたくなる気持ちもお分かりいただけるだろう。EUの政策が正しいお手本?この2つの思考癖については、もちろん、細かく見れば、例外的な現象は多々あるだろうが、ことあるごとに環境市民団体は「EUでは遺伝子組み換え作物の表示に厳しい」「EU並みにゲノム編集食品も遺伝子組み換えとみなすべきだ」「日本もEU並みに残留農薬の基準値を厳しくすべきだ」「EUはホルモン剤を使用した米国産牛肉の輸入を認めていない。日本も見倣うべきだ」「EUは家畜の福祉に熱心だ」などとEUの政策、価値観を正しい基準とみなして、日本や米国を批判している。農業の世界でも同様の癖が見える。日本の生産者(国や県の研究機関も含む)が知的財産権をもつ高級ブドウやイチゴが知らぬ間に中国や韓国で無断栽培される事件が相次いだ。韓国のイチゴの9割近くは日本の品種がもとになっているというから驚く。そこで農水省は今年、種苗法を改正して、生産者の自家増殖に対し開発者の許諾を必要とし、開発者の知的財産権をより守ろうとしたが、環境市民団体は「海外の巨大企業に日本の種子が支配される」などの理由で反対し、今年夏、法案改正は先送りになった。市民団体は中国や韓国を非難するのではなく、日本政府や米国の多国籍巨大企業を批判するという妄想に近い反対運動がマスメディアを賑わした。こういうEU理想主義、反米反日の特徴はゲノム編集など農業の世界だけかと思いきや、最近のエネルギー報道を見ていると、脱石炭を打ち出し、太陽光や風力など再生可能エネルギーを積極的に増やしているEUが正しく、それに比べて日本は遅れているという論調ばかりが目立つことに気づく。日本とEUは地政学的に異なる存在エネルギー問題に詳しくない私でさえ、少し考えれば分かるように、日本とEUの置かれた状況は地政学的に全く異なる。環境市民団体がほめそやすような政策を日本が真に受けて実施していけば、おそらく日本の国益が損なわれ、いずれエネルギー危機に襲われる経済的地獄が待っているだけだろう。資源のない日本の国民(もしくは国家)にとって、絶対にはずせないエネルギー供給の大原則がある。それは以下の5つの原則だ。エネルギーの安定供給エネルギーの安全保障(供給が途絶しないような安全保障政策の確立)コストの低いエネルギー資源の確保環境に大きな負荷を与えないエネルギーの組み合わせの確保世論の支持が得られるようなエネルギーの安定確保策この原則は、どの国も生きていくうえで必要な糧なので、EUにもあてはまるだろう。しかし、EUが脱石炭を進めるのは自国の利益にかなうからであり、また自国の産業を育成するためでもある。決してEUは地球の問題を解決するために犠牲的精神で脱石炭を進めているわけではない。脱石炭火力を進めても、さほど自国経済に打撃がなければ、再生可能エネルギーによる発電を進めていくだろう。EUは陸続きゆえに変動の激しい太陽光や風力エネルギーが余った場合には、お互いに余剰電力を融通し合うことが可能だ。しかし、海に囲まれた日本はそうはいかない。マスメディアは何かとドイツのエネルギー政策を理想視するが、中国に大量の車を輸出するドイツは、中国経済に極めて強く依存しているだけに、中国の悪口を言わない。中国を忖度しながら、自国の利益に沿ったエネルギー政策を進めているだけであり、ドイツと日本は置かれた地政学的な状況は全く違うことを知っておきたい。情けない新聞の社説今年7月3日、経済産業省は「旧式の石炭火力発電所の9割に相当する100基を2030年までに休廃止する」と発表した。この発表に関する主要新聞の見出しを見た人の多くは、「ついに日本も世界の流れにのって、脱石炭に向かうのか」と思ったに違いない。ところが、これに対し、環境市民団体「気候ネットワーク」(日本)は7月6日、「脱石炭にはほど遠い『石炭の長期延命策』であることが鮮明に」との見出しで反論をホームページに載せた。この気候ネットワークの分析結果を見て、私はむしろホッとした。日本ではこれからも石炭火力が生き残っていくのだという方向性が見えたからだ。この点に関して情けないのは各種新聞の社説だ。「気候ネットワーク」の代理弁護人かと思われるほどのオウム返しだ。読売新聞と産経新聞を除き、ほとんどの社説は共同通信社も含め、「石炭依存をやめられない日本は世界で厳しい批判を浴びてきた」「石炭火力の全廃が国際社会の一員としての務めである」「石炭火力の輸出から早急に手を引かねばならない」といった調子だ。要するに「世界の潮流に乗り遅れるな」というEU迎合的な評論家的スタンスだ。こういうスローガンだけのきれいごと社説を見ていると、かつての民主党政権のスローガン政治を思い出す。理想やスローガンを掲げれば、エネルギーが天から降ってくるとでもいうのだろうか。こういう社説は一種の念仏論だ。エネルギーの安全保障、安定供給には、そのエネルギーを海外から調達する(莫大な外貨がいる)ための涙ぐましい民間産業の育成、競争力の維持が必要である。石炭は石油と異なり、中東に依存していない。政治的にも安定した豪州をはじめ、インドネシア、ロシア、カナダなどから輸入できる。資源確保のうえでリスク分散は基本中の基本である。日本の産業や市民の生活にエネルギーを供給する構成も、石炭、石油、ガス、水力、原子力、自然エネルギー(太陽光や風力、バイオマス)を分散して確保していくのが、これまた基本中の基本である。特定のエネルギー源に依存し過ぎると、いざというときの備えに弱い。マスメディアと環境市民団体は、仮に日本がエネルギー危機に見舞われてエネルギーが途絶しても、その責任をとってくれるわけではない。環境市民団体やメディアは、国の富を創り出すことにほとんど関心がない。また富を創り出す具体的な政策案にも関心がない。エネルギー供給確保のリスク分散から見て、石炭火力を確保しておくのはごく常識的なことのように思えるが、マスメディアの思考は違うようだ。実は、石炭火力が必要な理由として、まだ触れていない重要なことがある。それが何かを後編で述べてみたい。(次回に続く)
- 02 Sep 2020
- COLUMN
-

コロナ報道に見る「見える死」と「見えない死」
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大の勢いがようやく収まってきたようにみえる。これまでの報道(以下、略してコロナ報道)を見ていて、死が「平等」に報道されていないことに気づく。ある特定の死だけに過大な関心を向け過ぎると、知らぬ間に他の死亡リスクが増えていることもありうる。新型コロナウイルスによる死亡数は他の死亡リスクと比べて、どれくらい多いのだろうか。「子宮頸がん」の死亡者は新型コロナウイルスより多い若い女性で増加傾向にある「子宮頸がん」はウイルス(ヒトパピローマウイルス)感染で起きる。新型コロナウイルスとは異なるウイルスとはいえ、ウイルスによる感染という点では同じだ。その子宮頸がんで毎年約3,000人が死亡している。1日あたり8人だ。しかも毎年、約1万人が子宮頸がんにかかり、子宮を摘出する手術を受けている。1日あたり27人だ。新型コロナウイルスによる死亡者の数は5月17日時点で756人。子宮頸がんの死亡者数のほうがはるかに多い。きょうも明日も、子宮頸がんでだれかが死ぬだろうが、報道はゼロだ。「死」というものがみな平等な価値をもつというなら、そして年間3,000人という死亡者数の多さなら、コロナ報道と同様に報道されてもおかしくないはずだが、なぜか報道はほとんどない。子供の自殺は深刻みなさんは、子供の自殺が年間どれくらいあるか、お分かりだろうか。驚いてはいけない。警察庁と厚生労働省の調査によると、2019年の10~19歳の未成年者の自殺は659人にも上る。新型コロナウイルスによる死亡者数(756人)と大して変わらない。深刻なのは、10代の自殺者数は年々じわじわと増えていることだ。新型コロナウイルスによる死亡者は高齢者が中心なのに対し、これら10代の死亡は日本の未来を担う若い命だ。同じ命とはいえ、その重みは大きい。しかし、10代の自殺が毎日2人程度あっても、その都度報道されることはない。これが見えない死亡だ。報道される死亡は、無数の死のほんの一部に過ぎない。日本国内で起きている「死」は何も子宮頸がんや子供の自殺に限らない。それこそ無数の死が日常的に起きている。「無数の死亡」は全く報道されないでは、どんな死亡がどれくらい発生しているのだろうか。厚生労働省の人口動態統計(2018年)によると、日本全国の死者の総数は男女合わせて約136万人に上る。その内訳をみると、がん(腫瘍)が約38万6,700人(約28%)、次いで心血管・脳血管疾患が約35万2,500人(約26%)だ。驚くのは、新型コロナウイルス感染症と同じ分類に相当する呼吸器系疾患(肺炎、インフルエンザ、急性気管支炎、喘息など)による死亡者が約19万1,356人もいることだ。19万人といえば、1日あたり520人の死だ。新型コロナウイルスによる死亡者数は2月~5月半ばまでの累積で約800人だ。従来の呼吸器系疾患で死ぬ人はたった1日で平均500人もいるから、こちらのほうがはるかに多い。しかし、そのような死亡は報道されない。このほか、ウイルス感染という点では同じのウイルス性肝炎(B型とC型)による死亡者は年間3055人もいる。これも新型コロナ感染の死亡者より多い。いうまでもなく、ウイルス性肝炎による死亡が報道されることはない。しかし、これだって、もし毎日ウイルス性肝炎での死亡者を詳しく報じれば、おそらく人々の関心は高くなるだろう。さらに他の死亡例をみていこう。2018年の1年間の自殺者数は約2万人。1日あたり55人だ。交通事故死は4,595人。驚くべきことに転倒・転落・墜落で9,645人も死んでいる。さらに不慮の溺死だけでも8,021人も死んでいる。自殺、交通事故死、転倒、溺死、どれをとっても、新型コロナウイルス感染による死亡者よりもはるかに多い。しかし、だれも関心を示していない。特殊なケースを除き、報道されることはほとんどないからだ。同じ「死」でも価値は異なるこれらのどの無数の死も、それぞれの当事者、家族にとっては例外なく、痛ましいドラマ、悲嘆、挫折、絶望が伴うだろう。しかし、現実にはどれもニュースにはならず、どの死もみな人知れず忘却に消えていく。では、なぜ新型コロナウイルスの死亡だけはこれほど大きなニュースになるのだろうか。それは、新型コロナウイルスで死んだ場合にはニュース性があるからだ。どの死の価値にも差はないはずだが、報道(ニュース)の世界ではニュース性という視点が加わるため、「死」は偏った形で伝えられる。恐怖が死の価値を高めるでは、なぜコロナ報道ではバランスの良い「死の報道」が存在しないのだろうか。その鍵は「恐怖心」にある。ハーバード大学ロースクールのキャス・サンスティーン教授が著した「命の価値」(勁草書房)がそのヒントを与えてくれる。サンスティーン教授は米国司法省勤務などを経て、2009~2012年、オバマ政権のもとでホワイトハウス情報規制問題局(OIRA: Office of Information and Regulatory Affairs)局長を務めた行政経験豊富な法学者だ。サンスティーン教授は同著「命の価値」(第7章)で人々の「恐怖」がいかに思考停止、確率無視の行動に導くかを述べている。その恐怖状態の心理の特徴を3つ挙げている。ひとつ目は「多く報道された出来事は、非現実的なほどふくれ上がった恐れを引き起こす」という点だ。ある特定の死亡事例(怖い現象)が来る日も来る日も、あらゆるマスコミで報道されれば、人々の恐怖心はいやがうえにも膨れ上がるだろう。2つ目の特徴は、「人々は馴染みのない、コントロールしにくそうなリスクについては、不釣り合いなほどの恐怖を示す」という点だ。3つ目は、人々の間で「感情が強く作用しているときは、人々は確率無視の行為に及ぶ」という点だ。人は感情的になると確率を無視した行動に出るわけだ。国民が極度に感情的になった例は過去にたくさんある。9.11の同時多発テロのあと、新型インフルエンザ(2009年)が大流行したとき、何度かあった大災害や大森林火災のあと、中国産輸入品の残留農薬問題のあと、BSE(牛海綿状脳症)が発生したあと、子宮頸がんなどを予防するHPVワクチン接種後に起きた諸症状の報道のあと、などが思い浮かぶ。そういう大事件・大事故・大災害のあと、人々の恐怖心は頂点に達する。米国の同時多発テロのあと、人々は飛行機を恐れ、車に乗り換えた。その結果、車による事故死の件数が以前より増えたという例はあまりにも有名だ。この副作用ともいえる交通事故死の増加はあとになって統計的な死亡数として分かるまでだれも気付かない。人は恐怖心に怯えると低い確率を無視し、結果的に高いリスクのほうを選んでしまう場合が生じうるということだ。これが死のトレードオフ(何かを得ると別の何かを失う二律背反の関係)である。東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故のあと、放射線による死亡リスクよりも、あわてて避難したことによる死亡リスクのほうがはるかに高かったのも、この例にあたるだろう。同じ死亡でも、「いま見える死」と「今は見えない死」があることが分かる。「恐怖」は世界を一瞬で伝わる確かに新型コロナウイルスによる死亡は恐怖を呼び起こす要素に満ちている。馴染みがなく、コントロールもできず、予測不能な振舞いで有名人をあっという間に死亡させる怖さ。まさに「新奇のニュース性」に富む要素を備えている。しかも、いまはインターネットの時代。世界中の人が恐怖におののく光景を、世界中の人々がリアルタイムで見ている。恐怖はインターネットを通じてウイルスよりも早く伝染する。恐怖心は飛行機よりも速く、そしてウイルスよりも速く伝わることが今回の惨劇で証明された。経済活動の縮小で自殺増加の可能性しかし、冷静に考えてみれば、大切な人を失った家族や友人にしてみれば、ことさら新型コロナウイルス感染による死だけが悲しみや嘆きの対象なわけではない。新型コロナウイルス感染による影響で職を失い、収入の道を絶たれ、だれかが自殺したら、その家族は新型コロナウイルス感染以上の悲しみに暮れるだろう。家族や友人から見れば、どの「死」も等価だからだ。新型コロナウイルスによる死亡だけを減らそうとすると、いつか目に見えない副作用が襲ってくる。4月30日朝、TBS「グッとラック」で藤井聡・京都大学教授は「このままだと1年後にコロナが収束しても、その後の20年間で自殺者が14万人増える」と話していた。経済の悪化で自殺者が増えるという試算だ。現在の年間の自殺者は約2万人。その数に7,000人が加わる計算だ。この7,000人の予測数は、新型コロナウイルスによる死亡者数(756人 5月17日現在)よりはるかに多い。経済悪化による悪影響は自殺に限らない。失業、貧困、盗難や強盗などの犯罪、会社倒産、精神的ストレス、家庭内暴力、虐待、教育格差などさまざまな副作用を生むだろう。人の命を支えているのは医療経済資源(医師関係者や医療器具、病院、医療制度など)だけではない。もろもろの経済活動もまた人の命を支えているという事実を忘れてはいけない。もちろん新型コロナウイルス感染を抑えることは重要だが、メディアの立場としては、今後の10年間も見据えた時系列的な全体の死亡数をいかにして抑えていくか、という視点も忘れないようにしたい。
- 18 May 2020
- COLUMN
-

日本の新聞は科学的な分析よりも政権批判が優先か!
新型コロナウイルスによる感染が国内外で深刻を極めている。この感染問題に対する日本の新聞報道をどう評価したらよいか、あれこれ考えているうちに、ひとつの重大な特徴に気付いた。科学的なリスクを的確に伝えることよりも、安倍政権への批判が優先している点だ。いわば科学と政治の混同だ。いったいどういうことか。安倍首相を「科学軽視」と批判ここでの考察は日頃、安倍政権に批判的なスタンスを貫く毎日新聞と朝日新聞を対象とする。私がまず驚いたのは、安倍首相が2月27日、全国の小中高校の一斉休校を要請したことに対する毎日新聞社の論調だ。毎日新聞社は3月10日付けの社説で「首相は科学的分析尊重を」の見出しで科学的分析という言葉を3回も織り交ぜて科学的分析の重要性を指摘した。その一部を紹介する。「全国の小中高校の一斉休校の要請も、中韓を対象とする入国規制強化も、安倍首相は専門家会議の意見を聞かずに打ち出した。・・科学的分析に基づかない判断は大きな副作用を招く恐れもある。・・政府の対策本部は拙速な判断を避け、科学的分析を踏まえて今後の対応を決めてほしい」日頃、多くの新聞メディアは科学的分析をさほど重視して報道しているとは思っていなかったので、新聞が時の首相に向けて「科学的な分析を尊重せよ」という言論はとても新鮮であり驚きであった。日本が一斉休校を要請した当時、英国は休校措置を取っていなかった。これを受けて、毎日新聞は「英国は入国制限や学校閉鎖の措置を取っていない。科学的な根拠に基づき政策決定しようとする英国とは対照的な(日本の)姿勢に、専門家は『科学が政治に負けた』と憤る」(3月18日付)と書いた。その紙面では英国のジョンソン首相の「スポーツイベントの禁止は、感染拡大防止には効果が小さいというのが科学的助言だ」との言葉も紹介している。メディア自らは科学を重視してきたか?これを読んで、そこまで安倍首相を批判するほど日本の新聞は過去に科学的分析を重視してきたのだろうかと大いに疑問を抱いた。私は毎日新聞の記者(東京本社で1986年〜2018年)として、科学的なリスクにかかわる様々な問題を追いかけてきたが、首相の言説に対して、新聞社が「もっと科学的な分析を尊重せよ」と厳しく迫った論調は記憶にない。この首相への科学軽視批判は、別の言い方をすると「私たちメディアは科学的な分析を重視して報道しているのに、安倍首相は軽視している」という物言いである。では、過去の新聞のリスク報道はどうだったのだろうか。福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質のリスク。BSE(牛海綿状脳症)の感染リスクと全頭検査。子宮頸がんを予防するHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンのリスクとベネフィット(便益)。福島第一原子力発電所のタンクにたまるトリチウム水のリスクと放出問題。遺伝子組み換え食品やゲノム編集食品の安全性に関する問題。放射線を当てて殺菌する照射食品の問題。これら一連の問題を振り返ると、政府がいくら科学的な分析・根拠を尊重したリスクを示しても、新聞メディア(もちろん新聞社によって濃淡はある)は、消費者の不安を持ち出したり、異端的な科学者の声を大きく取り上げたりして、常に政府を批判していた。決して科学的分析を尊重してこなかった。新聞はコミュニケーターの役割を果たしていない例を挙げよう。いくら政府の科学者たちがゲノム編集食品は従来の品種改良と変わりなく安全だと科学的に説明しても、朝日新聞や毎日新聞はどちらかといえば(同じ紙面でも社会面、経済面、生活面、科学面でやや異なるものの)、科学的な側面を軽視して、「それでも消費者は不安だ」「本当に安全か」などと書いてきた。もし本当に新聞社が科学的な分析・根拠を重視する姿勢をもっているなら、そうした分析結果を分かりやすく解説して、消費者にしっかりと理解してもらうのが科学者と市民の間をつなぐコミュニケーターとしてのメディアの役割だろうと思うが、そういうリスクコミュニケ—ションはしていない。日ごろは科学をさほど尊重していないのに、安倍首相を批判するときには「科学的な分析を尊重せよ」とカッコよく言われても面食らってしまう。結局、新型コロナウイルスでも、子宮頸がん予防のHPVワクチンでも、メディアは科学的な事実を正確に伝えようとする姿勢、つまり、科学的なリスクを的確に伝えるコミュニケーターとしての役割を果たしていないことが分かるだろう。これはおそらく政府を批判することが記者の使命、記者の正義だと思い込んでいる意識が多くの記者にあるからだろう。もちろん政治の問題で政府を批判することは大いに必要だが、科学的な分野は別のはずだ。緊急事態宣言では科学を度外視!このメディアの政治と科学を混同する姿勢は、3月14日に緊急事態宣言を可能にする新型インフルエンザ等対策特別措置法改正が参議院本会議で可決されたときにも如実に現れた。朝日新聞はさっそく「新型コロナの蔓延時などに、首相が緊急事態宣言を出し、国民の私権制限もできるようになる」(3月14日付一面トップ)と書き、感染拡大を抑えるリスク削減効果よりも、安倍政権による私権制限に危機感を抱かせるようなトーンに重きを置いた。同じ朝日新聞の3月20日付の「耕論」ではコメディアンの松元ヒロさんを登場させ、「独裁的な首相に、こんな権限を与えて大丈夫でしょうか。歴史を振り返ると戦時に歌舞音曲が禁止されました・・」などの見方を紹介した。リスクの問題がなぜ政治の話になるのだろうか。読売新聞が緊急事態宣言を「都道府県知事の行政権限を強めることが可能になる」(3月14日の一面トップ)と解説したのと対照的だ。いま重要なのは新型コロナウイルスの感染リスク拡大をいかにして食い止めるかである。そのような極めて科学的な判断が真剣に試される究極の場面でも、なお時の政権を批判することに重点を置いた論調を展開する。これでは科学を正しく伝えられないのではないか。読者が知りたいのは緊急事態宣言でどの程度感染リスクが削減されるかだ。感染症に対する緊急事態宣言(※旧民主党政権が新型インフルエンザに対してつくった極めて制限の緩い法律を踏襲した内容であることを知っておきたい)は戦前の治安維持法ではない。国民の健康、安全をどう確保するかという極めて科学的な分析を要するリスクコミュニケーションの問題である。それに徹した科学報道を期待したいが、朝日新聞と毎日新聞はどうも政権への批判が優先しているようだ。もちろん大手2紙にも良いところはたくさんあり、このコロナ報道だけで新聞の良し悪しを判断してはいけないことは承知している。ただ、科学と政治の問題を分けて報道することが大事だと強調したい。一斉休校は良い意味で予防原則だった話題を冒頭の科学的な分析の話にもどそう。毎日新聞が安倍首相を批判した当日の3月18日、ジョンソン首相は20日から学校を休校すると発表した。英国の判断のほうが甘かったのである。この休校問題に限れば、安倍首相の唐突な決断が結果的には、科学無視と批判されるような愚かなものではなかったことになる(もちろん、休校にかかわるさまざまな副作用は発生したが)が、それをフォローする記事は出てこない。「科学的分析を尊重せよ」は一時の首相批判に持ち出された道具に過ぎなかったようだ。「一斉休校」という安倍首相の決断は、善意に解釈すれば、科学的な判断が難しい場合に市民団体や野党の議員たちがよく口にする大好物の「予防原則」にのっとったものだった。しかし、嫌いな安倍政権が予防原則を実行するとメディアは「科学的根拠がない」と批判し、安倍首相が予防原則を実行しないときは逆に「早く予防原則を実行すべきだ」と迫る。結局いつも政権批判である。それほど科学的な分析・根拠が大事だというなら、新聞社自らが多数の専門家の意見を聞き、科学的な分析を駆使して、「感染を食い止めるためにはいまこそ、科学的な意味での緊急事態行動が必要だ」と具体的な対策項目を前面に押し出して国民に訴えればよいだろうと思うが、そういうリスキーなことはしない。政府が何をやっても「後手、後手だ」と批判するような野党的な感覚でリスク報道をされたのでは、読者はいつまでたっても的確な科学的情報を新聞からは得られない。福島第一原子力発電所で増え続けるトリチウム水のタンク。安倍首相に「科学的分析を尊重せよ」と訴えた誇り高き姿勢をこの問題でも示してほしいものだ。緊急事態宣言は6日か7日にも出されそうだ。安倍首相は専門家の意見を尊重して、ぎりぎりまで科学的根拠を重視していた。まさか「遅かった緊急事態宣言」と書かないだろうね!
- 06 Apr 2020
- COLUMN
-

ゴーン被告「甘い国・日本」から「風と共に去りぬ」
コラムsalonのリニューアルで新しいタイトルを頂いたので、第1弾は風にちなんだ話を、と思っていたところに起きたのが、日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告の大脱走だった。これってまさに風、『風とともに去りぬ(Gone With the Wind)』じゃない?ゴーン イズ ゴーン。保釈条件を一方的に破り、財力にあかせて高跳びしたゴーン被告。保身と傲慢ぶりに腹が立つが、もう一つ腹の立つのが、大脱走で炙り出された「甘い国・日本」である。「甘い国」の“戦犯1号”はやっぱり裁判所だ。「人質司法」との非難を気にして保釈するなら、少なくともカナダで拘束された中国・華為技術(ファーウェイ)副会長の孟晩舟被告のように、GPS(衛星利用測位システム)装着が不可欠だった。ゴーン被告の反発を回避したかったのだろうか。昔、「雑音には耳を貸さない」と言って国民の顰蹙[ひんしゅく]を買った最高裁長官がいた。褒められはしないが、よほど毅然としていた。パスポートの所持を鍵付きケースで許可したのも失笑ものだ。鍵などその気になれば壊せる。壊さないと本気で思っていたとしたら、お人好しで甘いと思う。弁護団もいい加減で、これまたパスポートの管理が甘かった。在日外国人はパスポート携行が義務だからというのだが、保釈中や裁判の間は代替証明書を出せばよい。それにゴーン被告なら顔パスポートで十分では? 杓子定規で融通が利かず、逃亡防止への備えが足りないことは、最近、保釈中の脱走事件の多いことでも分かる。保釈金額15億円の判断も甘かった。保釈金は被告の収入や財産、罪の重さを勘案し、「被告人にとって戻ってこないと困る金額」にするという。そうだとすれば富豪ゴーン被告の15億円は安すぎる。検察は100億円を提示したとか。それでも逃亡したかもしれない。しかし没収された保釈金は雑収入として国庫に入るから、15億と100億では大違い。財政厳しき折り、ちょっと損した感じだ。ゴーン被告を箱詰めしたプライベート・ジェットを易々と飛び立たせた関西空港も“戦犯”を免れない。もし「御用」にしていたら、関空は世界にその名を残したものを、実際は不名誉を残した。運び屋たちは何十回と来日し、日本中の空港を調べた上で関空を選んだという。恐らく同程度の甘い空港は他にもあったに違いないが、地方では目立ちすぎるので避けたのだ。胸をなでおろした空港はどこだろうか。さて、これだけ失策を重ねながら、責任論がどこからも上らず、結局ウヤムヤになりそうなのも、いかにも甘い国・日本らしい。不祥事が露見すると、頭だけは下げる最近の謝罪も安易だが、お詫びもなければ、ないことへの追及もないことの不思議。その点でメディアの報道ぶりも甘かった。逃亡先レバノンでのゴーン被告の自己正当化と偏見に満ちた日本批判を鵜呑みにするような欧米メディアもある中、ここは事実を正確に伝えることがメディアの役割だし、ひいては一矢を報いることにもなる。同様に法務省はじめ政府の対応も甘いと思う。日本のメディアは検察が異例の速さで反論したと報じたが、発信の相手は世界、世界基準でも異例の速さだったのかどうか。日本の情報発信と情報戦略の立ち遅れはかねてから指摘されてきたこと。それが百戦錬磨のゴーン被告が相手で一段と浮き彫りになった。これからも本を書き、映画のモデルになり、手段を選ばず自己正当化を続けるのだろう。ここは日本も、中東の有力メディア「アルジャジーラ」の英語・アラビア語両放送を使い、発信力のある日本人(誰だろう?)が日本の立場や逃亡の犯罪性を主張するとか、レバノン政府と徹底的に引き渡し協議をする等攻勢に出ないと、官庁ホームページの反論程度では、限界は明らかだ。ゴーン被告の逃亡事件に限らず、何事も一見厳しそうに見えて実は抜け穴だらけ、というのが「甘い国・日本」の特徴である。「甘える」に相当する言葉が他の言語にはない、日本人特有の感情であることを指摘した『甘えの構造』(土居健郎著)は、代表的な日本人論として世界にも知られるロングセラーである。それは風土と歴史の中で時間をかけて出来上がったものでもあるから、一朝には改まらないし、必ずしも今、ゴーン被告逃亡事件で見てきたような負の側面だけではない。「甘い国・日本」は一面では優しい、思いやりの社会を形成して来た。ただヒト、モノ、カネが世界を自由に行き交い、異なる価値観の人間が共生する今日、「甘さ」が弱点を孕むことをもっと自覚すべきなのだ。関係当局が、ゴーン被告を「絶対に連れ戻す」気概をまずは態度で示すことが第1歩ではないか。
- 31 Jan 2020
- COLUMN
-

危うい「市民ジャーナリズム」 ─ 根拠なき情報に対抗する第三の「プロフェショナル・ジャーナリズム」が必要
ネットの発達で市民が自由にいろいろな意見やニュースを発信する「市民ジャーナリズム」が活発になってきた。しかし、そこには第三者の査読や校閲の機能はほとんど見られない。そういう危うい市民ジャーナリズムに対抗する第三の「プロフェショナル・ジャーナリズム」が必要なときに来ているのではないだろうか。2019年8月、山田正彦・元農水大臣や国会議員の福島瑞穂さんらが集まって、衆議院会館で記者会見が行われた。国会議員を含む29人のうち19人の髪の毛から除草剤のグリホサート(もしくはその代謝物)が検出されたという内容だった。検出された量は0.1 ppm(ppmは100万分の1の単位なので、1グラムの中に1000万分の1グラムの割合)前後の微量だが、議員らは「(水俣病の)メチル水銀と同じように人体に蓄積していく可能性があり、後遺症や障害を起こすという証拠が出ている。禁止すべきだ」と声高に訴えた。検出量は安全な量の1000分の1確かにグリホサートはパンなど一部の食品から検出されるが、これまでの国の調査データ(厚生労働省)によると、日本人が平均的に摂取しているグリホサートの量は、生涯にわたって毎日食べ続けても安全といえる1日許容摂取量(ADI)の1000分の1程度である。安全な量の1000分の1だから、なんら健康上の問題はないと考えられる。しかし、市民団体が標的とする農薬や食品添加物などが、たとえごく微量でも、単に検出されたという事実だけで「危ない」「禁止すべきだ」だと糾弾するのが、こういう「市民ジャーナリズム」の特徴である。こうしたむき出しの情報が、ネット上のブログやヤフーニュースなどで、だれの査読やチェックもなしに拡散しているのがいまのネット時代だ。市民が思うがまま(好き勝手に)に自分のニュースを発信できるのは、ときの権力の横暴を抑える武器となり、自由な言論の象徴とも言える。その意味ではよい面ももっているが、こと科学や医学ににかかわるニュースとなると、おかしな情報を信じた人たちに無益な行動に走らせることにもつながっていく。たとえば、上記の例なら、グリホサートの使用を怖がって、やめてしまう行動がそのひとつである。内閣府食品安全委員会のリスク評価を見てもわかるように、毒性学的に見て、グリホサートほど安全な除草剤(いうまでもなく使用基準を守って使うことが前提)は他にないと思うが、それに怖さを感じた人は、より危ない別の農薬を使うことにもなりかねない。いや現実にそういうことが起きつつある。市民ジャーナリズムは責任なし市民ジャーナリズムは悪く言えば、素人ジャーナリズムだ。間違った情報でだれかに被害を与えても、市民ジャーナリズムは責任をとることはない。そもそも市民は素人なので、科学的に根拠のないことを言っても、その言動によって、責任をとらされることもない。これは考えてみれば不思議な現象だが、いまの市民社会では市民が主人公であり、市民には発言をする権利があり、知る権利があり、自由にものを言う権利がある。それでいて、間違った場合でも、許されるのが市民である。要するに、市民は神様なのである。ある市民(女性)が「長生きしたければ、肉を食べるな」という内容の本を書いてベストセラーになったことがある。食品添加物や白い砂糖などを避ければ、がんを克服できるといった本を書いてベストセラーになった例もある。どちらも根拠なき一個人の主張、体験に過ぎないが、そんなおかしなことをいいふらしても、責任をとらされることは全くない。この本の内容を信じて、まねして、早く死んでも責められることはない。市民ジャーナリズムは無敵なのである。間違っても、非難されないという特権をもっている。その一方、おかしなことを言えば、すぐに世間から悪のレッテルをはられて追放されるのが専門家である。市民は素人ゆえの恐るべきパワーをもっているのだ。原子爆弾はゲノム編集と同じなのか?元農水大臣の山田氏(弁護士)も、一市民であり、科学者ではない。一市民なので自由になんでも言える。山田氏のブログ(9月21日)を見ていたら、インタビューしたカリフォルニア大学のイグナシオ・チャペラ教授の話として、山田氏は最近、注目されているゲノム編集について「100%副作用が出るし、原子爆弾とゲノム編集は全く同じ物です」と書いている。どうみても言論が軽すぎる。人権に配慮するはずの元大臣の発言とは思えない物言いである。自分に都合のよい専門家の話を引用して、ゲノム編集の危険性を広めたい気持ちは分からないでもないが、どうみても原子爆弾を例に挙げるのは原子爆弾の被爆者の心、尊厳を傷つけるものだ。一度に数十万人の生命を奪う原子爆弾と、単なる品種改良のひとつに過ぎないゲノム編集技術を同列に扱うとは、被爆者の生命(いのち)をあまりにも軽く見過ぎる発言にしかみえない。狙った遺伝子を思うように書き換えるゲノム編集技術が、仮に原子爆弾と同じような危険性をかかえているとすれば、医療分野でゲノム編集による治療に取り組んでいる医師や学者は、危険性に全く気付いていない大愚者なのだろうか。ノーベル賞の候補ともいわれるゲノム編集技術で動植物の品種改良に挑んでいる研究者は無学の徒とでもいうのだろうか。このように何を言っても許されるのが市民の強みである。それが市民ジャーナリズムの武器でもある。第三の「専門家ジャーナリズム」が必要これに対し、科学者はそうはいかない。根拠なき言論で市民を惑わせ、市民の気持ちを逆なでしようものなら、「御用学者」「インチキ学者」とレッテルをはられ、世間から追い出される。科学者の世界では査読やピアレビューがあり、おかしな説や根拠なき理論は淘汰されるというメカニズムが働く。だからか、科学者の物言いは慎重になる。「絶対に危ない」とか「100%安全です」とか断定調の言葉を発信することに慎重になるのだ。その結果、なんでも自由にものを言う市民(素人)のパワーに負けてしまう。そして、市民社会では素人が勝ち、専門家が負ける。ゲノム編集や遺伝子組み換え作物、農薬のグリホサート、食品添加物、福島のトリチウム水などに関するネット情報界隈の生態を見ていると、そういう危ういけれど、強い影響力をもつ市民ジャーナリズムの姿がしばしば見える。そうはいっても、市民ジャーナリズムが科学的にどこまで的確なことを言っているかをちゃんと知りたい市民も多いことだろう。しかし、いまのところ、市民ジャーナリズムの言論を厳しくチェックする専門家の集団はほとんど存在しない。専門家による第三のジャーナリズムの出現を期待したい。
- 26 Dec 2019
- COLUMN
-

農薬をめぐるバイアス記事の好例
除草剤グリホサートをめぐる恐るべき事態が勃発 ─ 科学者へ、決して他人事ではありません ─悪意に満ちたバイアス(偏った)記事がいまなお健在だという好例の記事を見つけた。知識層が最も好むとされる大手新聞(8月24日付)の朝刊記事だ。グリホサートという除草剤が発がん性や胎児への影響をもたらすと指摘する記事だが、先進国の公的機関は明確に否定している。こういう記事が続く限り、活字メディアはいよいよ専門家から見放されるだろうとの思いを強くする。記事の冒頭の前文は、記事全体の顔だ。まずは、記事の冒頭を以下に記す。──発がん性や胎児の脳への影響などが指摘され、国際的に問題になっている農薬が、日本では駐車場や道ばたの除草、コバエやゴキブリの駆除、ペットのノミ取りなどに無造作に使われ、使用量が増えている。代表的なのが、グリホサートの除草剤とネオニコチノイド系の殺虫剤だ。海外では規制が強化されつつあるのに、国内の対応が甘いことに、研究者は懸念を抱いている。──この前文を読むと、世界中の科学者がグリホサート(製品名ラウンドアップ)という除草剤が、がんを起こすことを認めているかのような書きっぷりだが、事実は全く違う。さらに、同記事は「国内の対応が甘いことに、研究者は懸念を抱いている」と書いているが、私がこれまでに農薬問題を約30年間取材した経験から言って、この種のリスクの問題で「懸念を抱いている」とみられる研究者は100人の科学者のうち、多くて数人だろう。そのたった数人の研究者の異端的な意見を、さも大多数の研究者が抱く懸念かのごとく、記事の前文で報じることに作為的な悪意を感じる。この前文を読むだけで、この記者は科学的で正確な事実を読者に伝えようと努力していないことが読み取れる。米国で恐るべき訴訟同記事にも出てくるが、いまグリホサートをめぐって、米国では恐るべき訴訟が起きている。科学を重視する科学者にとっては、背筋が寒くなるような訴訟ビジネスの実態だ。──どんな訴訟なのか?グリホサートを使っていた市民たちが「白血球のがんになったのはグリホサートが原因だ」とカリフォルニア州地方裁判所に訴訟を起こしたのだ。これまでの3件(2018年8月~2019年5月)ではいずれも原告側の市民が勝訴している。なんとこの3件で陪審員は補償的損害と懲罰的損害を合わせて、約300億円、約80億円、約2200億円(1ドル100円で換算)もの賠償金の支払いを命じた。のちに判事の裁定でそれぞれ約80億円、約25億、約90億円に減額されたものの、途方もない賠償金に違いはない。被告の農薬メーカーは旧モンサント社(現在はドイツのバイエル)。控訴中でまだ決着はついていないが、恐るべきは、同様の訴訟が米国内で18000件以上も起きていることだ。グループ分類の意味訴訟が起きた背景には、2015年3月に国際がん研究機関(IARC)がグリホサートを発がん性分類で「グループ2A」にしたことが大きく影響している。おそらく陪審員たちは弁護士の巧みな論法に説得され、グループ2Aという印籠にひれ伏してしまったのだろうと推察する。しかし、がんのグループ分類は、実際の危険性やリスクの高低とは、全く関係がない。ちなみに、発がん性分類は「グループ1」(発がん性あり)▽「グループ2A」(おそらく=probably=発がん性がある)▽「グループ2B」(発がん性の可能性あり)▽「グループ3」(発がん性と分類できない)▽「グループ4」(発がん性なし)の5段階ある。いうまでもなく、この分類は発がん性の証拠の強さの順番に並んでおり、グループ1はがんの証拠が十分にそろっているという意味だ。そのグループ1には「ダイオキシン」「たばこ」「ハム・ソーセージなどの加工肉」「アルコール」「カドミウム」「ヒ素」などがある。アルコールを毎日、たくさん20~30年も飲み続ければ、がんになるリスクが高くなるという証拠が十分にそろっているという意味だ。逆に言えば、アルコールをときどき適量に飲んでいれば、がんのリスクはゼロに低い。グループ2Aには「熱い飲み物」もグリホサートに反対する市民グループは、このグループ2Aを盾に「グリホサートは発がん性」と主張しているが、実は、その同じグループ2Aには「肉類(鶏肉を除くレッドミート)」、「アクリルアミド」(ポテトフライやト―ストの茶色く焦げた部分などに含まれる)、「65度以上の熱い飲み物」などがある。言い換えると豚肉や牛肉も、外食産業で食べるポテトフライも、毎日自宅や喫茶店で飲む熱い飲み物も、みなグループ2Aである。ちなみにポテトフライに含まれるアクリルアミドは毒劇物取締法では「劇物」に指定されているのに対し、グリホサートは同じ法律で「普通物」扱いだ。これを知るだけで「グループ2Aだから危ないとは言えない」ことが中学生でも分かるだろう。仮にグリホサートの使用者ががんになって、10億円を超す賠償金を獲得できるならば、毎日ポテトフライを食べていて、がんになった人も、ポテトフライを売る会社を相手取って訴訟を起こせば、10億円を勝ちとれるという理屈になる。熱いコーヒーを出す喫茶店からも高額の賠償金をもぎ取れるだろう。すでに察しがつくように、グループ1はグループ2Aよりも証拠がそろっているのだから、アルコールを売る会社やハムソーセージを売る会社にも訴訟を起こして、莫大な損害賠償を勝ち取ることも可能になるだろう。こういうたとえ話を聞けば、この訴訟のおかしさが分かるはずだが、米国の陪審員は科学者のような思考には慣れていないのだろう。勝訴で勢いづいた弁護側はいまテレビに広告(CM)を流し、「グリホサートを使っていて、がんになった人は訴訟に加わりましょう」と原告を募集している。見たこともない大金がもらえるなら、原告に加わる人も出てくるだろう。がん患者を食いものにする訴訟ビジネスの寂しい一面でもある。この訴訟の背景にはグリホサートに発がん性の警告表示が必要だとするカリフォルニア州特有の「安全飲料水および有害物質施行法(プロポジション65)」がある。そういう意味ではこの種のリスクに敏感な民主党の強いカリフォルニア州特有の動きともいえるが、この恐るべき訴訟がいつ日本に来ないとも限らない。正当な意見は無視さて、上記の大手新聞の記事は、こういうグループ分類の科学的な解説には全くふれず、グリホサートで発達障害や腸内細菌の異常、生殖毒性まで起きているとする海外の団体の偏った主張だけを載せている。市民グループの意見は長々と載せているのに対し、世界中の科学者の多数意見ともいえる欧州食品安全機関(EFSA)や米国環境保護局(EPA)の見解については、「発がん性を否定」しているというたった一言で済ませている。要するに記事の大半は、農薬に反対する市民グループとその市民グループに味方するごくごく一部の研究者の意見や主張だけが占めるという構図だ。こういう記事を書くときは、「私が共感する市民グループの意見だけを紹介する」と前置きして書くべきだろう。記事はいかにも客観性を装う内容にみえるが、単なるプロパガンダに過ぎない。よくあるパターンだと言ってしまえば、それまでだが、週刊誌ならまだしも、日本で最も信頼されているとされる新聞でこの状況である。この米国の訴訟の判決に対して、米国の環境保護局(EPA)は8月8日、「米国政府はグリホサートの発がん性警告表示を全く認めていない。国際がん研究機関よりもはるかに包括的に研究文献を精査した結果、発がん性の根拠はない」とするプレスリリースを出した。こういう重要な動きを記事は全く伝えていない。さらに言えば、IARCは2015年にグリホサートのほか、マラソン(殺虫剤)、ダイアジノン(殺虫剤)もグループ2Aにした。しかし、同じグループながら、マラソンやダイアジノンは全く話題にも上らない。訴訟にもなっていない。なぜかグリホサートだけが攻撃される。市民グループの恰好のターゲットとなっている旧モンサント社がからむからだろう。市民グループの主張だけを取り上げて、よい記事を書いたと自己満足している記者がいまも存在するということをぜひ知っておきたい。ここで強調したいのは、反対運動自体を問題視しているのではなく、科学的な根拠に基づく正確な情報を伝えない報道の目に余る偏りが問題だということだ。こうした海外の動きを受けて、日本の市民グループや国会議員もグリホサートへの反対運動を強めている。次回で続編をレポートしたい。 ※文中に出てくるグリホサートは除草剤の有効成分です。現在、世界で数多くの会社がグリホサートを含む除草剤を製造・販売していますが、米国での訴訟の対象になっているのは旧モンサント(現在はドイツのバイエル)の商品のラウンドアップです。ただ、記事では分かりやすくするため、成分名のグリホサートで統一しました。
- 19 Sep 2019
- COLUMN
-

メディア・ハラスメントの誕生 ─ 今後、メディアの信頼回復策はあるのか
いったいメディアはいま、どんな情報を市民に届ければ、信頼される存在になるのだろうか。新聞やテレビ、週刊誌などのメディアへの信頼性がますます低下する中でメディアの生き残り策はあるのだろうか。私は、読み手に「反論権」をあらかじめ与えるのが生き残り策のひとつだと考える。どういうことかを述べてみよう。一部週刊誌の非科学的言説最近の一部週刊誌の食品のリスクに関する記事を見ていると、もはや言論というよりも、非科学的な言説の一方的な垂れ流しであり、言論の自由の範疇に収まり切れない要素をもっているのではないかと感じることがある。「食べてはいけない国産食品の実名リスト」との派手な見出しで事業者と製品名を挙げて、「これが危ない食品のランキングです」といった週刊誌の記事のことだ。たとえば、「食品添加物が子供の自閉症の原因になっている」とか「うま味調味料のグルタミン酸ナトリウムが脳の障害を起こす」とか「パンに使うイーストフードは体に悪い」とか「アルミニウムは子供の発達障害と関連がある」とか、およそ科学的とは言いがたい言説を平気で記者たちが書いている。この種の記事に登場するコメント諸氏は、私から見れば、いつも偏った評論家か学者、市民活動家ばかりだ。その名前をリストに挙げることは簡単にできる。その数が10人程度と少ないからだ。名指しされた事業者は反論の機会も与えられず、ただただ泣き寝入りするしかないようだ。もちろん、この種の記事に対しても、無添加表示で商売をもくろむ一部の事業者は大喜びだろうし、食品添加物を敵視する一部市民は喝采を送るだろう。しかし、食品の科学に詳しい学者に聞けば、だれ一人として、そうした記事を称賛する人はいない。そうした記事は、科学論文のように第三者のレフリーの目(査読)を経たわけではない。いうなれば、雑誌側の記者たちと一部の評論家諸氏が勝手に作り上げた粗雑な物語といってもよい。では、なぜ、この種のひどい記事がいつまでも存在し続けるのか。モノを売買する市場では、欠陥商品を売る評判の悪い店や会社はいずれ淘汰されてもよいはずだが、なぜか生き残っている。メディア・ハラスメントではないか名指しで非難された事業者からみれば、一方的に書かれっぱなしのままであり、反論する術もない。私はいつしか、これは言論によるハラスメントではないかと思うようになった。相手の言い分を聞くかのようなポーズを見せながら、最初から結論ありきの記事を一方的に書きまくる。言論による「いやがらせ」としか思えないようなスタンスである。これを「メディア・ハラスメント」と呼びたい。そもそもハラスメント(Harassment)とは何か。ネットで検索してみると、分かりやすい大阪医科大学の定義が出てきた。どんな内容かを以下に記してみる。「いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言います。その種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを言う」本人の意図に関係なく、つまり、相手の言い分をよく聞かずに一方的に相手の嫌がることをしたり、不利益を与えたりする行為である。週刊誌による一方的で横暴な言論はどうみても、この定義にあてはまるように思える。勇気をもって行動し、評判をつくるでは、ハラスメントを受けたら、どう対処すればよいのか。大阪医科大学は先ほどの説明のあと、次のような提言をしている。「一人で我慢せず、勇気をもって行動し、はっきりと自分の意思を伝える。受けた日時を記録し、相談窓口に助力を求める」つまり、泣き寝入りせず、勇気をもって行動することが大事だといっている。これは通常のセクシャルハラスメント(セクハラ)などではごく常識的な対処法だろうが、この言論によるハラスメントの世界では、この種の対処法が全く機能していないことに気付く。私と唐木英明・東大名誉教授が共同代表を務めるメディアチェック団体「食品安全情報ネットワーク」(個人で集まったボランティア集団)はこれまでにおかしな記事を見つけたら訂正を申し入れるなどの活動をやってきたが、これからは「この記事は不正確です。ミスリードする内容が多く、信頼性は低い」といったような評価作業を行い、その評価結果を当該メディアに送り、なおかつ他の多数のメディアにも送るというアクションを起こすことを決めた。試験的に、ある新聞の食品添加物に関する記事をみなで読み、「ミスリードする内容で不正確」との評価をくだした。評価する基準は主に「科学的な根拠が適切に示されているか」「大げさに伝える誇大な見出しになっていないか」「事実関係の説明に誤りがあるか」の3つだ。この評価に基づく評判を世間一般に知らせることによって、その評価にふさわしい報いを受けてもらおうという活動である。決して言論を否定するわけではない。目的はあくまで評価を通じた評判作りである。そもそも、この種のメディアチェック活動が必要なのは、当該メディアが読み手に対して「この記事への反論を載せます。ご意見をお寄せください」という反論権を認めていないからだ。メディアが読み手に反論権を与える姿勢に転じれば、その時はそのメディアは市民から信頼され、守るべき市民の代理人としてのメディアに格上げされるだろう。反論を載せることこそが言論メディアの生き残る道だと考える。
- 19 Jul 2019
- COLUMN
-

SNS時代にふさわしいメディアチェックとは ― おかしな記事を評価して、世間に知らせる活動をもっとやろう
おかしな新聞記事やテレビニュースを見つけたときに、まずだれもが思いつくのが「訂正の要求」か「抗議文の送付」だろう。しかし、相手が完全に無視したら、どうすればよいのか。そのひとつが相手の評判を落とすアクションだ。どのメディアも世間の評判には弱い。そのやり方を私なりに考えてみる。私が共同代表を務めるメディアチェック団体「食品安全情報ネットワーク」(もう一人の代表は唐木英明・東大名誉教授)は、科学的な根拠がないか、あるいは乏しい記事を見つけたら、その媒体に訂正を求めたり、意見書を出したりする活動を続けている。学者や記者、企業の品質保証担当者、公的機関の研究者など約50人が集まったボランティア団体である。会費もなく、おかしな記事を見つけたら、みなで手分けして検証して、訂正の内容をメディアに送るという純粋な検証団体である。ボランティアだから、自由にモノが言えるし、どの媒体に対しても等距離に身を置ける利点がある。2008年から活動を続けてきたが、一番の悩みは相手から無視されたときだ。幾度質問を繰り返しても、相手から全く音沙汰なしだとあきらめるしかなかった。そのときの気持ちは、一言で言えば「悔しい」だった。新聞系雑誌は「無視」知名度のない弱小ボランティア団体ゆえに無視されたのだろうと思うと本当に歯がゆい思いを何度も味わった。たとえば、2018年2月、週刊朝日が「健康寿命を延ばす食品選び」というタイトルで、どうみても非科学的な記事を載せた。添加物を避ければ、健康寿命が延びるかのような非科学的な言論を吐く評論家や市民団体は昔からあったが、それが堂々と新聞系の雑誌に載ったとあっては、黙って見過ごすわけにはいかない。さっそく質問状とその理由を書いて編集部に送ったが、全く返事は来なかった。しびれを切らして私たちの担当者が電話したところ、相手からは「特定の相手にだけ時間を割くことはできない・・」などといった冷淡な言葉だった。その後も、別の複数の週刊誌の記事に対して、何度か訂正を求めたが、ここ1、2年は「回答なし」が目立つようになってきた。ニュースの真偽を検証するこのまま敗北するわけにもいかない。どうすればよいかを思案していたときにヒントになったのが、最近、世界で大流行している「ファクトチェック活動」だ。ファクトチェックとは、簡単に言うと記事やニュースの真偽を検証することだ。たとえば、米国のトランプ大統領の発言とそれが掲載された記事がどこまで真実かを検証して、「大統領の発言はフェイクです」などとSNSなどを通じて、みなに知らせる活動である。欧米を中心に100を超えるチェック団体がすでに存在している。検証または評価のやり方はそれぞれ国や団体のカラーで異なる。たとえば、記事の評価を「ねつ造」「不正確」「やや不正確」「正確」と単純に分ける方法もあるだろうし、その一方、「科学的な根拠がなく、嘘に近い」「信じてはいけない真っ赤な嘘」「科学的な根拠があり、信じてもよい」という言い方で評価する方法もあるだろう。評価結果の知らせ方は、これまた国や団体で異なる。ただ基本的には、あらかじめ評価項目とその判断基準を決めておき、それぞれの団体がくだした評価結果を自らのウェブサイトに載せるという点は一致している。その評価結果を当該メディアに送るほか、他のメディア媒体(新聞、テレビ、雑誌など)にも送り、さらにそれぞれの団体会員が個々にSNSに投稿するという形をとれば、影響力は大きいはずだ。欧米では、メディアチェック団体と提携した既存のメディアが評価結果を記事として載せるケースもある。既存メディアが協力すれば、確かに一般の人の目に触れる頻度は高くなる。これが理想的なあり方だろう。「評価結果」は他の媒体にも知らせるここで大事なことは、たとえば、週刊朝日の例なら、週刊朝日の記事に関する評価結果を他のメディア媒体にも送るということだ。実は私たちの団体も2018年から、他の媒体(全部で約20社)にも送っていた。おかしな記事を書いていないAという媒体に「B社の記事は、非科学的です。信じてはいけないという評価がくだりました。SNSにも投稿されています」という評価結果が届けば、他社の出来事とはいえ、おそらく、変な記事を書くブレーキになるのではと思う。この「おかしな記事の評価を他社にも知らせる」というアクションは、実は、ずっと以前に一般社団法人「日本アルミニウム協会」がやっていたことだ。「アルミニウムの摂取がアルツハイマー病の原因になる」といった記事が約20年前にはやっていた。私もそうした記事を書いた記憶がある。いまでは信じられない話だが、台所でアルミ鍋を使っていた主婦たちが恐怖のあまりアルミ鍋を捨てるという行為まで見られた。日本アルミニウム協会は、科学的な根拠の低い記事を見つけるたびに、どの部分が非科学的かの理由を明記して訂正要求リリース文を作り、当該の媒体のほか、他の新聞社にも送っていた。私の記憶では、この活動は10年近く続いた。その地道な活動の要因だけではないだろうが、アルミニウムがアルツハイマー病に関係するという記事は少しずつ減っていったように思う。どのメディアもNHKを除き、客商売なので、世間の評判を気にする。世間の評判が落ちたら、購読数(視聴者数)の減少に直結する。この商の論理は傍若無人ぶりの週刊誌も免れない。いま世界で流行しているフェイクニュースのチェックは、どちらかといえば、大手メディアが流すニュースの真偽よりも、政府要人など有名人の発言が真実かどうかをチェックすることに重きを置いている。個人的な意見では、日本では主要なメディアの流すおかしなニュースに翻弄されているケースのほうがより深刻だと思っている。ぜひ、それぞれの組織の有志たちでメディアチェック団体をつくり、おかしなニュースを見つけたら、その評価結果をあらゆる媒体に知らせていく活動を始めてほしいと思っている。5~10人いれば、できるはずだ。どんなことも、初めの一歩がなければ、成し遂げられない。私たちの団体もまもなく評価活動を始動させる。
- 25 Apr 2019
- COLUMN
-

メディアへの訂正要求は多角度から試してみよう
おかしな記事やニュースを見たとき、だれに、どうやって訂正を求めればよいのか。また、どんな方法で抗議をしたらよいのか。日本のメディア(新聞やテレビなど)には残念ながら、欧米のメディアと異なり、反論を載せてくれるコーナーや番組が存在しない。では、どうすればよいか。狙ったメディア内で、できるだけ多くの人(記者も含め)に周知してもらう作戦がよい。その具体的なやり方を紹介しよう。七つのルート新聞社やテレビ局などに訂正を求める場合、限られたルートしかないようなイメージがあるが、実は案外と多い。思いつくだけでも、以下の七つの方法がある。記事を書いた記者本人に抗議し、訂正を求める。記者の直属の上司(多くは部長か課長クラスのデスク)に訂正を求める。広報を担当する社長室に訂正を求める。社長あてに抗議文を出して訂正を求める。読者センターにメールか手紙で間違いを指摘し、回答を求める。新聞社内で紙面を審査する担当窓口にメールか手紙を出す。新聞社に設置されている外部の第三者委員会にメールか手紙を出す。意外に多いと思った人が多いのではなかろうか。ひと口に抗議や訂正といっても、実は、記事の間違いの程度いかんで対応は異なる。ちょっと表現(言葉)がおかしいとか、記者への説明と記事の内容が少々食い違うといった軽いミス(許容できる間違い)の場合には、記者本人に伝えて、「今回は目をつぶるけれど、次回はちゃんとこちらの言い分を書いてくださいね」とか「もう一度、記事を書いてくださいよ。ただ、今度は正しく書いてくださいね」とか言って、恩を売っておくのもよいだろう。私の経験から言って、記者は「もう一度、記事を書くから、今回は大目に見てほしい。次回の記事では正しく書くから」という受け入れ策を好む傾向がある。訂正記事を出すよりも、そのほうが記者個人の汚点にならないからだ。正直な話、私も記者生活40年間の中で、何度かこの手を使ったことがある。しかし、今回の話は、そういう恩を売っておくという程度で済むような間違いではないケースだ。間違いは全社的な話題にもっていく具体的な例を挙げたほうが分かりやすいので、前回で取り上げた毎日新聞の一面トップ記事の「もんじゅ設計廃炉想定せず ナトリウム搬出困難」(2017年11月29日付)を例に説明したい。前回は事実関係に絞って訂正を求めたほうがよいと書いたが、今回は、だれに、どのような方法で訂正を求めるのがよいかという問題だ。この記事をめぐっては、日本原子力研究開発機構の担当者は、記事を書いた記者の部署の直属上司(部長クラス)と面談して、訂正を申し入れたようだが、結局は、「取材源の秘密」を理由に「記事に間違いはない」と言われ、訂正やおわびを勝ち取ることはできなかった。一般的に言って、外部から訂正要求がくるということは、その記事は間違いだという可能性は高い。どんな人でも、記事が間違ってもいないのに、訂正を求めるようなことはしないからだ。そういう意味で、外部から「この記事は間違いです」と指摘されたメディア担当者(このケースでは部長クラスの上司)は、まずはなんとか自社組織の中で大きな火種にならいよう、ことを丸く収めようと内心で思うはずだ。訂正を求めるときは、その担当者の意識の弱さを突くことを考えたい。つまり、訂正を求める場合は、その間違いを全社的な問題(話題)にもっていくのがよい。一部署との交渉だけでは、その部署だけで問題が終わってしまう可能性があるからだ。外部からの通報で間違い記事に気づいた部長クラスの上司がまず気にするのは「社内にいる他の部長クラスのみんなが知ったら、まずいなあ。立場が弱くなるなあ」という自身への風当たりだ。つまり、その間違い記事が全社的な話題になってしまうことを恐れるのだ。間違いの指摘は社長室か読者センターへということは、訂正を求める場合は、第一段階として、記事を担当した記者や部署ではなく、広報担当の社長室か読者センターに通報するのがベストである。間違い記事に関する回答書を求められた読者センターは、すぐに関係する部署のほか、社長室にも連絡をする。そして、「これこれの間違いが外部から指摘され、訂正を求められている。訂正するかどうかの判断はそちらに任せるが、とりあえずは関係部署の上司と記者の釈明書を書いて、こちらに送ってほしい」と回答書の提出を指示するだろう。こうなると、間違い記事は一部署から一挙に広範囲に知れ渡る。おそらく部長クラスが集まる部長会議の議題にもなるだろう。私の経験からいって、間違い記事を指摘された部署は当然ながら、訂正の掲載に抵抗するだろうが、他の部署は意外に冷静な目で判断する傾向がある。間違ったときは潔く訂正を出したほうが読者の信頼を獲得でき、社会的な信頼度も上がると考える新聞人が最近は増えてきているので、その間違い記事とは関係のない部署の記者たち(部長クラスの記者たち)からは、意外にも訂正を出すことに賛成する意見が出てきやすい。開かれた新聞委員会も活用したいもうひとつの方法は、新聞社内に設けられた第三者委員会にメールか手紙で間違いを指摘し、そこで議論してもらうことだ。第三者委員会はどの新聞社にもあるわけではないが、毎日新聞社の場合は、著名なジャーナリストの池上彰さんら複数の外部識者で構成された「開かれた新聞委員会」がある。紙面に寄せられた抗議や訂正要求などを議論し、その審議内容を紙面に定期的に載せている。その中で「これこれの訂正要求が来ているが、これは訂正に値する間違いだ」といった内容の論評記事が出たりする。これはいわゆる訂正記事ではないものの、識者の意見として「あの記事は裏とりが不十分だった」との記事が載るため、事実上、訂正記事に近いものになる。この論評付きの意見は、簡単な訂正掲載よりも、記者が間違った背景も分かり、読者には親切である。残念なのは、こういう外部の意見を審議する第三者委員会をもっている新聞社がまだ半分にも満たないことだ。その意味で毎日新聞の開かれた新聞委員会は専門家からも高い評価を得ていて、おそらく新聞社の中ではもっとも先進的な例ではないかと思う。そういう意味では、この「もんじゅ設計廃炉想定せず」の記事は、第三者委員会に通報してもよかったケースだと言える。ちなみに第三者委員会の会議には部長クラスの上司はみな出席する。これまで述べてきたように、訂正要求にもいろいろな方法があることが分かるだろう。ただどんな場合でも、少なくとも相手の組織図を知っておくことは最低必要条件である。そしてもうひとつ、確実に実行したいことは、自社のホームページに「○○社の記事は○○の部分が間違いです。この記事は誤報です」といったメッセージを必ず載せることを忘れてはいけない。訂正を求めるという面倒な行為をしなくても、ただホームページに載せるだけでも、だれかがそれに気づいて、その間違い記事を拡散してくれる効果も狙えるからだ。何もしないのが最悪の行為である。次回は、間違いを指摘しても、メディアから無視された場合の対処法を考えてみたい。
- 28 Feb 2019
- COLUMN
-

メディアの間違いにどう対処すればよいか ― 記事の弱点を突き、照準をしぼることが肝要
新聞やテレビをはじめメディアの“誤報”にたびたび苦杯をなめてきた体験をお持ちの方は多いはずだ。しかし、誤報と分かっても、たいていは文句も言えず、泣き寝入りで終わるケースがほとんどだろうと察する。では、どうすればよいか。果敢に訂正を求めるアクションを起こすしかない。ただアクションを起こすからには賢い方法を身に着けておくことが必要だ。どんな方法か?賢い方法のヒントは、日産自動車のカルロス・ゴーン前会長が逮捕された事件にある。東京地検は金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕し、立件を進めている。犯罪を立件するなら、背任や横領のほうがニュース価値は高いが、なぜ、有価証券報告書の虚偽記載という微罪で逮捕したのか。虚偽記載なら、虚偽の記載という厳然たる事実があれば、立件しやすいからだ。まずは相手の確実なエラー、弱点を突き、追い込んでいく。これがメディア対応の基本である。もんじゅ「欠陥」の記事具体的な例をあげよう。2017年11月29日、毎日新聞の一面トップに「もんじゅ設計廃炉想定せず ナトリウム搬出困難」(東京版)との見出しの記事が大きく載った。大阪版の一面は「ナトリウム回収想定せず もんじゅ設計に『欠陥』 廃炉念頭なく」との見出しだった。東京版に比べ、「欠陥」という文字が大きく見出しにとられた。これを受けて、翌30日には福井新聞にも「一次取り出し困難」と題する記事が掲載された。これに対し、日本原子力研究開発機構は11月29日、ホームページに記事解説を載せた。毎日新聞の記事の概要を記したあと、その記事に関する事実関係について、「概ね事実」「一部事実誤認」「誤報」「その他」の4分類のうち、「誤報」に〇印をつけた。そのうえで「・・原子炉容器内のナトリウムの抜き取りについては、原子炉容器の底部まで差し込んであるメンテナンス冷却系の入口配管を活用するなどにより抜き取ることが技術的に可能と考えている・・」などの解説を記し、記事の主要部分が間違いであることを強調した(ちなみに、この記事解説はいまもネットで読める)。さらに、「事実関係を十分に取材せずに掲載されたものであることから、当機構としては甚だ遺憾であります。今後、このようなことが起こらないように強く抗議するとともに善処を求めてまいります」との見解を公表した。その後、同機構側は、記事を載せた関係部署の担当責任者と直接会って、訂正を求めたが、「記事は間違っていない」と言われ、結局、求めた訂正は実現されなかった。明らかな間違いに照準訂正を求めるときの最大の要諦は、記事の中で「明らかな間違い」を見つけることだ。その間違いに照準を定め、「ここは明らかに間違っています。間違った情報を信じた読者に対して、再び、正確な情報を流すのが報道機関の使命と考えます。読者のためにも、訂正をお願いします」と強く主張することだ。もんじゅの一面トップの記事の前文を読むと、「・・液体ナトリウムの抜き取りを想定していない設計になっていると日本原子力研究機構が明らかにした。・・・・廃炉計画には具体的な抜き取り方法を記載できない見通しだ」となっている。私が記事を読んでまず気づくのは、欠陥ともいえる設計になっていることを「同機構が明らかにした」という記述になっている点だ。つまり、「抜き取りが想定されていないことが毎日新聞の調査で分かった」という言い方ではなく、「同機構が明らかにした」という言い方になっている。同機構が公的にそんなことを言うわけはなく、また、そんな見解を述べた文書があるわけでもなく、これは明らかに間違いだと言える。さらに記事を改めてよく読むと、《同機構幹部は取材に対し、「設計当時は廃炉のことは念頭になかった」と、液体ナトリウム抜き取りを想定していないことを認めた》となっている。「ナトリウム抜き取りを想定していないことを認めた」という文章は、記者の地の文であり、幹部が抜き取りを想定していなかったと証言したという文章ではない。つまり、抜き取り想定せずは幹部の言葉ではなく、記者の拡大解釈だ。仮に幹部の一人がそのようなニュアンスを記者にもらしたとしても、それは一意見であり、「機構自体が明らかにした」という断言調の言い方は明らかに間違いだと言える。幹部がだれだったかは「取材源の秘密」で明かせないと言われたそうだが、それは関係ない。機構自体が明らかにしたという事実が全くないことを強く主張すれば、訂正は勝ち取れるはずだ。もうひとつ勝ち取れる点があった。「抜き取り方法を記載できない見通しだ」という表現である。そもそも記載する必要がないから記載していないだけで、記載することは十分に可能なのは明らかなことから、これは「間違いです」と突っ込める。記事には、他にもおかしな点は出てくるが、まずは訂正を勝ち取ることができる部分に絞ることが肝要である。これはゴーン氏の逮捕容疑と同じである。記事に抗議するとか、善処を求めるといった主張は必要ない。あくまで的をしぼって訂正を勝ち取ることを目標にしたい。記者は補助に軌道修正実は、毎日新聞はあのあと、記事の内容を軌道修正している。たとえば、2017年12月7日、もんじゅの廃炉に関する続報を載せた記事を見ると、その見出しは「もんじゅ廃炉課題山積 核燃料回収 複雑な手順」だった。この記事は、「同機構が12月6日、廃炉計画を原子力規制委員会に申請した」という記事の中で改めて解説を加えたもので、11月29日の記事では、「数百トンは抜き取れない構造」と書いていたのに、12月7日の記事では同機構の見解として「技術的には十分可能」との内容を載せた。もし技術的に十分可能なのであれば、そもそもあの一面トップの記事は特ダネとして成立しなかったことになる。最初の記事と8日後の記事には大きな矛盾が生じているが、ほとんどの読者はそんなことには気づかなったに違いない。さらに言えば、2017年12月6日の毎日新聞の朝刊では、同機構が福井県と敦賀市に廃炉計画の概要を示したとの記事が掲載されたが、その記事には欠陥を思わせる記述は全く出てこない。11月29日の記事を書いた記者とは別の記者が書いているからだ。記者たちはやや勢い余って「書き過ぎたかな」と思うと、前に書いた記事のトーンを少しずつ修正していく習性がある。私の見方では、これもその一例である。いったい何が事実なのか。混乱するのは読者だけだろう。メディアという媒体はどこも訂正を出すことを極度に嫌う。記者も嫌う。私も過去に平均して2~3年に一度は訂正記事を出してきたが、訂正のあとはいつも憂鬱な気分になったものだ。しかし、読者にとっては、訂正の掲載は正確な情報の担保条件であり、信頼の証でもある。あとで振り返れば、訂正を出してよかったと思ったのも事実である。訂正を求めるときはこう言おう。「訂正は読者のために必要です。報道機関として、読者に間違った情報を届けたままでよいのでしょうか」。次回のコラムは、メディア対応の次の手を紹介したい。
- 06 Dec 2018
- COLUMN




