キーワード:バイアス記事
-
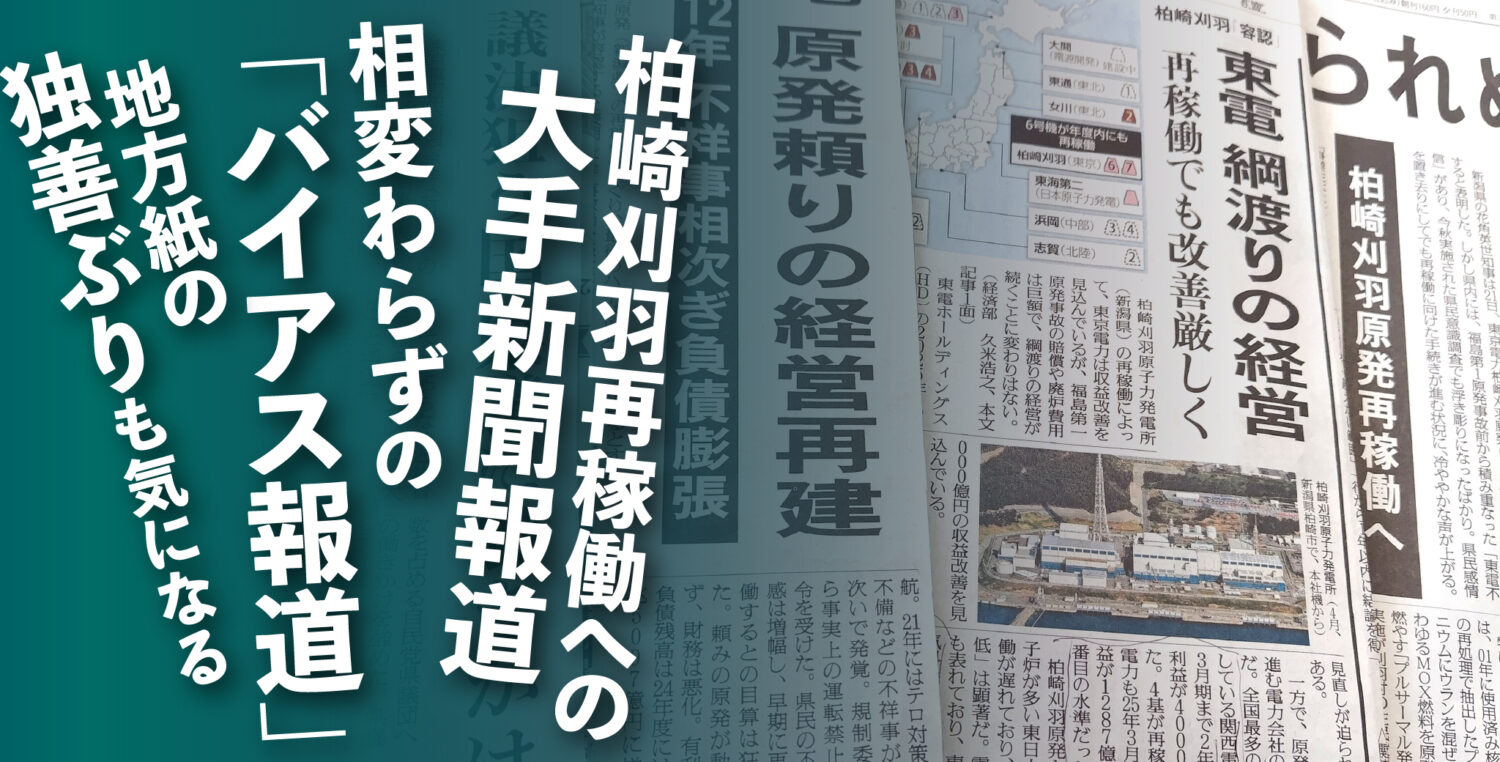
柏崎刈羽再稼働への大手新聞報道 相変わらずの「バイアス報道」 地方紙の独善ぶりも気になる
二〇二五年十二月二日 新潟県の花角英世知事が11月21日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所6~7号機(出力各135万kW)の再稼働を容認する考えを表明した。この判断に対して、大手新聞社はどう報じたのだろうか。やはりリベラル系新聞(朝日、毎日、東京新聞)と保守系新聞(読売、産経新聞)ではかなりの「差」が見られた。いつものことだが、地元紙がネガティブニュースで不安を増長させていることも分かった。産経新聞はAI需要を強調 新聞記事の中身を判断するのに一番適しているのは見出しだ。見出しを見れば、新聞社の姿勢がよく分かる。再稼働を最も肯定的にとらえていたのは産経新聞(11月22日付)だ。1面で「柏崎刈羽再稼働容認 AI需要 脱炭素の安定電源」とうたい、3面で「東電 経営再建へ前進 1基1000億円の収支改善」の文字が躍った。 日本は今後、人工知能(AI)向けデータセンターの増加で電力需要の拡大が見込まれる。その観点から原発の再稼働は安定電源となり、国から見ても悲願だったと見出しに「AI需要 脱炭素の安定電源」を入れたのが特色だ。3面で不祥事が続く東電に対する県民の不信があることにも触れたが、見出しに取るほどの内容にはなっていない。 一方、読売新聞(11月22日付)は記事全体では肯定的だが、「東電綱渡りの経営 再稼働でも改善厳しく」と産経に比べると厳しい眼差しを向ける。再稼働で1基1000億円の収益改善が見込めるが、福島第一原発事故の賠償や廃炉費用が巨額なため、再建は厳しいと断じた。ただ、社会面ではほぼ一面を費やし「地元 経済安定に期待」との見出しで、東電への透明性のある運営を求めつつも、地元経済の活性化に期待する声をひろった。20日付記事でも「再稼働で首都圏の電力需給が緩和する」と報じ、根強い東電不信に対しても、「知事、時間かけ判断」との見出しで徹底した安全対策と経済振興策が再稼働を後押ししたと書いた。 この二紙は、東電の問題点にも触れつつ、原発のメリットも伝え、バランスよく報じたと言えるだろう。毎日新聞は東電への不信を強調 これに対し、毎日新聞(11月22日付)は1面の見出しは「柏崎刈羽再稼働へ 新潟知事容認表明」と通常の見出しだが、3面では一転「原発回帰 国に同調」「政府再三要請に知事決断 東電問われる適格性」と批判的になり、社会面では「東電が信じられぬ 不祥事山積 県民忘れず 福島避難者あきれた」と東電への不信に満ちた内容をくどいほど並べ、県民感情を置き去りにしたと厳しい。同日付の社説でも「解消されぬ東電への疑念」と題し、「東電の安全軽視の体質が改まっていない。新潟県民の不信を置き去りすることは許されない」ときっぱり。「再稼働に反対だ」と社自体が明確に主張しているわけではないが、県民の不安を楯に、再稼働は暴挙だというニュアンスがひしひしと伝わってくる。朝日は5ページにわたり批判を展開 朝日新聞(11月22日付)は5ページにわたり、批判的なトーンを展開した。2面で「再稼働 県民の信待たず 議決狙う国、県議に働きかけ 福島への責任・東電適格性は」と不祥事続きの東電に「原発を動かす資格はあるのか」と相当に手厳しい。解説欄でも「東電が原発を運転することに県民の69%が心配だと答えている。電力は首都圏に送られ、新潟県民にはメリットがないとの見方も根強い」と地元にもメリットがないことを強調した。社説でも「疑念ぬぐえないままの容認。原発回帰に向けた重い判断を立地自治体に押しつけ、地元同意の手続きの不条理がまたも繰り返された」と地元同意が不条理だと一喝した。 国が主体的に再稼働を決めれば、「地元の同意を無視した暴政だ」と批判し、地元の同意を重視すれば、今度は「地元に判断を押しつける不条理だ」と批判する。どちらにせよ、朝日新聞は批判したいのだというトーンが強く伝わってくる。 東電の経営に関しても、「不祥事相次ぎ負債膨張、事故の責任重く いばらの道」と再建は極めて困難と断じた。社会面では福島の被災者を取り上げ、「福島を知るから複雑 『同じ経験してほしくない』 私たちの犠牲、なかったことにされるのか」と、柏崎刈羽原発が近くまた事故を起こすかのような書きぶりだ。 朝日、毎日とも東電の「適格性」を大きく取り上げ、事故を起こした当事者が再稼働させる資格はあるのかと問う。二紙とも、反原発路線に沿った論調なのが改めて分かる。東京新聞はさらに過激 朝日新聞以上に過激なのは、毎度のことながら、東京新聞(11月22日付)だ。1面の見出しに「県民の『東電不信』耳かさず」を入れ、2面で「『再稼働ありき』のシナリオ、柏崎刈羽『信問う』知事選択せず」とし、社会面では「被災者怒り『事故究明が先』 都民は賛否『電力安定』『安全不安』」とネガティブ情報が圧倒する。電力の需給面でも「原発の必要性は薄れている」と書き、23日付からは「見切り発車柏崎刈羽 東電再稼働を問う」と題した計三回の連載記事を載せた。どういうわけか再稼働に怒りをぶつける市民の名前は実名で登場するが、電力が安定すると肯定的な意見を述べる弁護士や講師の名前は匿名だ。 再稼働の経済効果については「柏崎刈羽原発の6、7号機が再稼働したときの経済波及効果は10年で4396億円と試算されているが、単年度では440億円に過ぎず、新潟県の総生産額の8兆9000億円の0・5%ほどでしかない」と経済効果にも疑義を示す。東京新聞を読むと、再稼働のメリットは全く感じられない。原発の拡大とリベラル系新聞の拮抗 こうして見ると、やはり新聞はバイアス(偏り)に満ちている。注意深く読まないと洗脳されてしまう。原発への批判度を順番に並べてみると、一番過激な東京新聞を筆頭に、朝日、毎日となる。逆に肯定度の順番は、産経が強く、次に読売が来る。 いま世界を見れば、原発は拡大傾向にあり、AIや半導体の需要拡大で、原発の必要性が高くなることは間違いない。そうなると、リベラル系新聞が原発批判だけで購読者を維持していくことが、どこまで可能なのかが気になるところだ。地方紙も批判勢力として健在 一方、地元の新潟日報はいつものことながら批判的だ。これまでにも原発に批判的な報道を繰り返してきただけに、批判自体は予想の範囲内だが、独自に延べ7142人(なぜ、延べ人数なのか。重複しているとしたら正確といえるのか疑問だが)を対象にアンケート調査を行い、その結果を報じた(11月28日オンライン)のには、ただならぬ執念を感じた。東電が運転することに対し、「83%が不安を感じる」と報じ、「知事の判断を支持しない」が78%に上ったと報じた。まるで市民活動家並みのアクションだ。 そして11月28日には、鈴木直道・北海道知事が、北海道電力・泊原子力発電所3号機(91・2万kW)の再稼働を容認する考えを表明した。待ってましたとばかり、北海道新聞の社説(29日)は「知事の表明は拙速であり、到底受け入れられない。容認ありきでは道民の命と暮らしを守るリーダーとしての責務は果たせない」と反対論をぶちまけた。北海道新聞も新潟日報と似て、原発批判の双璧をなす印象をもつ。 そう言えば、23年8月に福島第一原発の処理水が海洋放出されたときに、地方紙(福島県を除き)の社説の大半は「反対」だった。大手新聞の偏りだけでなく、地方紙の独善ぶりも要注意だと改めて感じる。
- 02 Dec 2025
- COLUMN
-

発行部数の減少に歯止めかからず いよいよ新聞の危機到来か?
二〇二五年十一月十九日 大手新聞の発行部数の減少が止まらない。いくら紙媒体に人気がないとはいえ、一定数の固定読者層は存在するのではと考えていたが、どうやらそれは幻想だったと言えそうだ。以前に「読売新聞の一強時代の到来か?」と書いたが、それも雲行きが怪しくなってきた。日本ABC協会 新聞の発行部数は「一般社団法人 日本ABC協会」の調査で分かるが、その数字は有料の会員向けには発表されているが、ネットでは見られない。新聞社がこの発行部数の調査結果をニュースにしてくれればよいが、残念ながら、ニュースを見たことはない。 このため、私のような非会員は、会員情報を基にネットで公表している個人のブログやサイトを見て判断するしかない。 ちなみに日本ABC協会は、広告主(車、鉄道、銀行、商社など幅広い)、新聞社、テレビ局、広告代理店などが会員となっている会員制組織で、新聞や雑誌などを公正な立場で調べて部数などを公開している。ABCは、Audit=公査(監査)、Bureau=機構、Circulations=部数の略で、もともとは米国で生まれた組織だ。大手新聞は驚くべき減少ぶり この日本ABC協会の公表数字をネットで探したところ、ジャーナリストの黒藪哲哉氏が運営するウェブサイト「MEDIA KOKUSYO」(25年8月7日参照)と、独立系広告プランナー氏のブログ「広告代理店の未来を考えるブログ」(25年11月12日参照)で発行部数を見つけることができた。読売新聞広告局ポータルサイトでも、読売新聞への広告掲載がいかに有利かを示すために各社の発行部数を載せているが、情報がやや古い。 情報が新しい「広告代理店の未来を考えるブログ」を見て、目が飛び出るほど驚いた。読売新聞の発行部数は約五三七万部(25年8月)、朝日新聞が約三二一万部(同)、毎日新聞が約一一八万部(同)、産経新聞が約八〇万部(同)、日本経済新聞が一二八万部(同)だ(同ブログなどを基に筆者が作成した表を参照)。 私は24年8月、「読売新聞の一強時代はオールド左派リベラル層の衰退の兆しか!?」と題した記事をこのコラムで書いた。そのときの読売新聞は六〇七万部だったが、一年経ったいまは約七〇万部も減って、五三七万部に落ちた。二十年前は千万部を誇っていたことを考えると、隔世の感がある。 朝日新聞も一年間で三四九万部から三二一万部へ減ったが、減り方は少ない。日本経済新聞の減り方も少ない。 この発行部数は、あくまで「発行」された部数だ。新聞代を払っている実際の購読者の数ではない。新聞業界では「押し紙」といって、新聞社が販売店に実際の購読部数を超えて新聞を押しつける慣行がある。この発行部数が多いと広告料を高くとることができるメリットがあるからだ。 押し紙が実際にどの程度あるかは分からないが、仮に一割程度をすると、実際の購読部数は各社とも一割ずつ減り、読売は五〇〇万部を割り、朝日も三〇〇万部を割り、毎日は一〇〇万部ぎりぎりとなる。毎日新聞は危機的 毎日新聞の目を覆うほどの減少ぶりは危機的だ。一年間余りで約四〇万部も減り、約一一八万部となった。もはや全国紙とは言いがたいほどの部数だ。個人的な話で恐縮だが、私が毎日新聞の記者(二〇一八年に退職)だったころは、三〇〇万部程度の発行部数があり、いくら紙媒体が減るとはいえ、二〇〇万部程度の固定読者層はいるだろうと勝手に思っていたが、その予想は全く甘かった。 なぜ毎日新聞だけが危機的なのか。これについて、広告代理店での実務経験をもとに「広告業界の今」を発信しているブログである「広告代理店の未来を考えるブログ」は以下のように分析している。 「読者の六割以上が60歳以上で、若年層へブランド力が届いておらず、アプリやSNS上での存在感がない。読売は家庭での接触、朝日は文化層、日経は就活・ビジネスへのアクセス力が残っているが、毎日新聞にはそういう訴求力がない。産経新聞も部数は少ないが、保守系論調で特定層に一定の支持を得ており、接触経路や読者像が明確に残っている点で毎日新聞とは異なる」(筆者で要約)。双方向の新聞があれば この分析は確かに当たっているように思える。自身の経験から言うと、毎日新聞は記者の自由度が高く、のびのびと取材活動ができる。官僚的な組織ではないため、私自身、社論とは異なる記事も堂々と書くことができていた。そういう自由な気風の新聞社が危機的な状況に陥っているのは悲しいが、時代の動きや消費者のニーズに合わせて業態や情報発信のあり方を変えていくしかない。リベラル系と保守系新聞の行方 ただ、歴史的な記録(アーカイブ)を残す点で新聞に勝る媒体はない。ぜひ生き残ってほしいと思うが、いま私が気になるのは、政治の動きとともにリベラル系新聞(朝日・毎日)と保守系新聞(読売・産経)の勢力図がどうなるかだ。 読売新聞の社説(11月13日オンライン)は高市早苗総理の存立危機事態をめぐる発言について「…台湾有事が存立危機事態になり得る、という首相の認識は理解できる。ただ、危機に際しての意思決定に関する発言には慎重さが求められよう。…だが、しつこく首相に見解をただしたのは立憲民主自身だ。答弁を迫った上で、答弁したら撤回を迫るとは、何が目的なのか。とにもかくにも批判の材料を作りたいということだとしても、安保政策を政局に利用しようとするなどもってのほかだ」と立憲民主党にも非を向けた。 一方、朝日新聞の社説(11月18日)は「不毛な対立に区切りを」と題して「…台湾という地名に触れたことで緊張を不用意に高めたと言わざるを得ない。…とはいえ、中国の姿勢にも大いに疑問がある。高市発言への抗議があまりにも執拗だ。…」と中国の姿勢にも疑問を投げかけ、国民から支持率の高い高市人気が頭にあるのか、以前に比べると中国寄りの度合いが弱くなっている印象を受ける。ただ、読み比べると読売新聞のほうは立憲民主党にも批判の矢を向けたといえる。こういう社説を載せる読売新聞が支持されるかどうかは、今後の発行部数にも大きく影響するだろう。 冒頭で示した読売新聞と産経新聞の発行部数を合わせると、六一七万部となり、朝日と毎日を足した四三九万部を大きく上回る。その差は一七八万部だ。現時点ではリベラル系新聞のほうが劣勢だ。この差が今後、開くのか縮むのか。立憲民主党や共産党を支持する層が減っていけば、リベラル系の朝日、毎日の発行部数も比例して減っていくだろう。高市人気が持続するかどうかはやはり大きなカギを握るように思える。
- 19 Nov 2025
- COLUMN
-
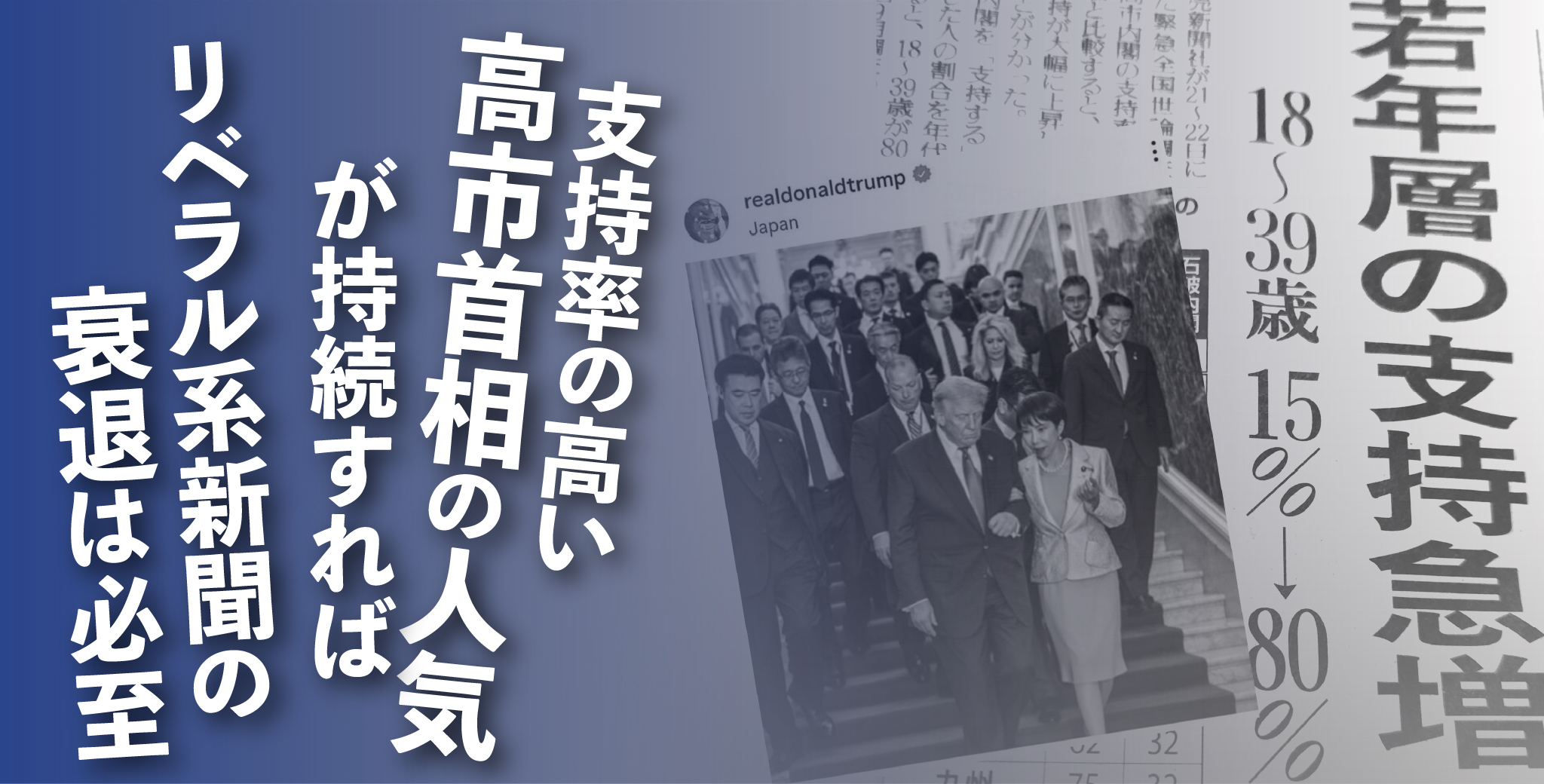
支持率の高い高市首相の人気が持続すれば リベラル系新聞の衰退は必至
二〇二五年十一月七日 自民党の高市早苗氏が憲政史上初の女性首相(第一〇四代)として、着々と独自の経済・外交政治を展開し始めた。高市氏が保守派だけに、今後、大手新聞の二極化(朝日・毎日と読売・産経陣営)が急激に進むことが予想される。エネルギー政策でもリベラル系新聞は高市氏に批判的だが、高市政治の人気が続けば、リベラル系新聞はますます衰退していくのではないか。驚異的な支持率71% 高市内閣が発足したのは10月21日。その二日後の10月23日付け読売新聞の朝刊一面(読売新聞社の緊急全国世論調査の記事)を見て驚いた人が多いのではないか。「高市内閣支持率 71%」という大きな見出しの数字が目に飛び込んできた。正直ここまで高いとは思っていなかっただけに、これはオールドメディア(特に朝日、毎日のような大手リベラル系新聞)の終焉を思わせる予兆だと感じた。 リベラル系新聞の論調やテレビ局の一部番組(特にテレビ朝日やTBS)のリベラル系評論家のコメントを見ていると、高市氏への評価は総じて低い。「高市氏は夫婦別姓に反対する急先鋒であり、国家の安全保障や歴史認識で中国や韓国を敵視し、国家主義的な思想の持主であり、女性の代表とはとても言えない」といった論調だ。 しかし、読売新聞の世論調査の中身を見ると、18歳~39歳の若い層の支持率は80%と驚異的に高い(写真1)。同じ年齢層の石橋内閣の支持率が15%だったのに比べると驚くべき数字だ。しかも男性の支持率が71%なのに対し、女性の支持率は72%と女性からの支持率も高い。「高市氏は女性に人気がない」とリベラル系評論家はテレビなどで言っているが、全く事実と異なる。 確かに朝日新聞や毎日新聞にいる女性記者の間では「高市氏は全くの不人気」だろうが、一般社会では高市氏の人気は高いことが世論調査からうかがえる。こういう場面でもリベラル系新聞と一般社会の意識の乖離が垣間見える。写真1オールドメディアの影響力は低下 つまり、高市首相は若い層の心をつかんでいるのだ。その背景にはSNSを通じた影響力があるのだろうと察する。個人的な興味から高市氏を応援する動画チャンネルを登録して、いくつかを立て続けに見たところ、SNSの世界では「高市氏は日本が誇る最高の女性首相」という印象が強く伝わってくる。オールドメディアの記事を批判する動画もけっこう目立つ。 リベラル系メディアがいくら高市首相に批判的な言論を展開しても、若い層には大した影響を与えていないことが分かる。他の新聞社の世論調査でも高市首相の支持率は約60~70%と高い。そもそも若い層のほとんどは新聞を購読していない。人口構成的に見れば、高市氏に批判的な高齢(60歳以上)のリベラル層はいずれ、この世の中から消えていく。それに比例して、リベラル系新聞の購読者も減っていくだろう。そういう状況の中でこのまま高市人気が続けば、リベラル系新聞の影響力はますます衰えていくことが予想される。「太陽光は中国依存でも普及すべき」? リベラル系新聞では、原子力やエネルギー政策に関する記事にも高市嫌いが見られる。毎日新聞(10月26日)は「高市氏 原子力前向き 資源国に頭下げる外交終わらせたい」との見出しで高市氏のエネルギー政策を論じた。記事では、高市氏の「これ以上、私たちの美しい国土を外国製の太陽光パネルで埋め尽くすっことには猛反対」との極めてまっとうな意見を載せていながら、最後の締めで「太陽光パネルの国産化重視はコストに跳ね返ることになる。そこで勝負をせずに普及に軸足を置くべきではないか」という識者の主張を載せて記事を締めくくった。 どうやら毎日新聞社は「パネルの大半を中国に依存してでも普及すべきだ」という考えをもっていることが分かる。しかし、この記事を裏から読めば、「国産のパネルを使えば、太陽光発電のコスト(電気代)は高くなる」と言っているのと同じだ。とすれば、太陽光発電など再生可能エネルギーの補助政策に「ノー」を突きつけている高市氏(記事ではこのことを批判的に書いている)の主張のほうが的確だと読めてしまう。高市氏のエネルギー政策をなんとしても批判したいという意図は強く読み取れるが、残念ながらその意図に説得力は感じられない。「長期脱炭素電源オークション」を歪曲して報道 高市政権が生まれる前の記事ではあるが、8月13日付け毎日新聞の記事は印象操作記事の悪い見本のようなものだった。見出しは「原発支援 電気代上乗せ 建設費高騰に政府対応」。前文を読むと「政府が原発の建設費や維持費を電気料金に上乗せして支援する仕組みを拡充しようとしている。原発の建設費が想定を上回った場合も電気料金で消費者に負担を求める仕組みで、国際的な環境NGOなどが反対を表明している」とある。 一読しただけで、政府が原発を推進するためにまたまた悪巧みを企てているという印象が伝わってくる。記事中にある仕組みかが何かと言えば、24年1月にスタートした「長期脱炭素電源オークション」のことだ。記事によると、このオークション方式だと、電力会社が原発の建設費を示してオークションに参加し、落札すれば、消費者が支払う電気料金を通じて、建設費の大半を契約金として受け取ることができる。原発をもたない新電力の契約者も原発の建設費などを負担することになるという。オークションは脱炭素のための仕組み このオークションのことをあまり知らない読者は、政府が原発を支援するためにオークションという悪巧みの計画を始めたというふうに受け取ったに違いない。 記事を読むと確かにそういう印象をもつが、そもそも「長期脱炭素電源オークション」(管理者は電力広域的運営推進機関=OCCTO)は脱炭素を実現するために考えられた仕組みである。オークションで落札すれば、脱炭素電源の建設費などを原則20年間得られる仕組みなのだが、その対象電源は原子力のほか、太陽光、風力、水力、蓄電池、地熱、バイオマス、LNG、水素専焼、アンモニア20%以上の混焼にするための既設火力発電所の改修など、電源は幅広い。 このオークションは、自由化が進展し、供給力の確保が難しい中でいかに脱炭素と必要な供給力確保を実現していくか、という差し迫った中で生まれたのであり、決して原発だけを支援するために生まれた制度ではない(詳しくはOCCTOのウェブサイトを読んでほしい)。 にもかかわらず、そういう基本的な解説をせずに消費者の負担を増やして原発を拡充する仕組みかのごとく報じるのは、読者を一方向に誘導しようとするバイアス記事の典型である。 確かに原発をもたない新電力の契約者も負担することになるが、それを言うなら、リベラル系メディアが称賛する太陽光発電も同じである。太陽光発電などは固定価格買取制度に基づき、電力会社が買い取る費用の一部を再エネ賦課金という形ですべての電気利用者に負担を強いている。その再エネ賦課金は年間約二~三兆円にも膨らんでいる。この巨額な負担に比べたら、脱炭素電源オークションによる負担は極めて少ない。朝日新聞も同じ論調 実は、毎日新聞が報じた記事の内容は、朝日新聞がすでに報じていた(6月26日オンライン参照)。どちらも捉え方は同じだ。朝日新聞の記事は「経済産業省は原発の建設費が増えた分を電気料金に上乗せして回収できるようにする支援策の詳細をまとめた。巨費がかかる原発への投資に二の足を踏む大手電力を後押しするねらいだ」と書いた。 新聞社として原発に反対する姿勢があってもよいが、記事の中身は正確に書いてほしい。こういう偏った記事を届けていけば、やがて読者は逃げていくだろう。高市人気はリベラル系新聞の衰退を促す。そんな予感がする。
- 07 Nov 2025
- COLUMN
-
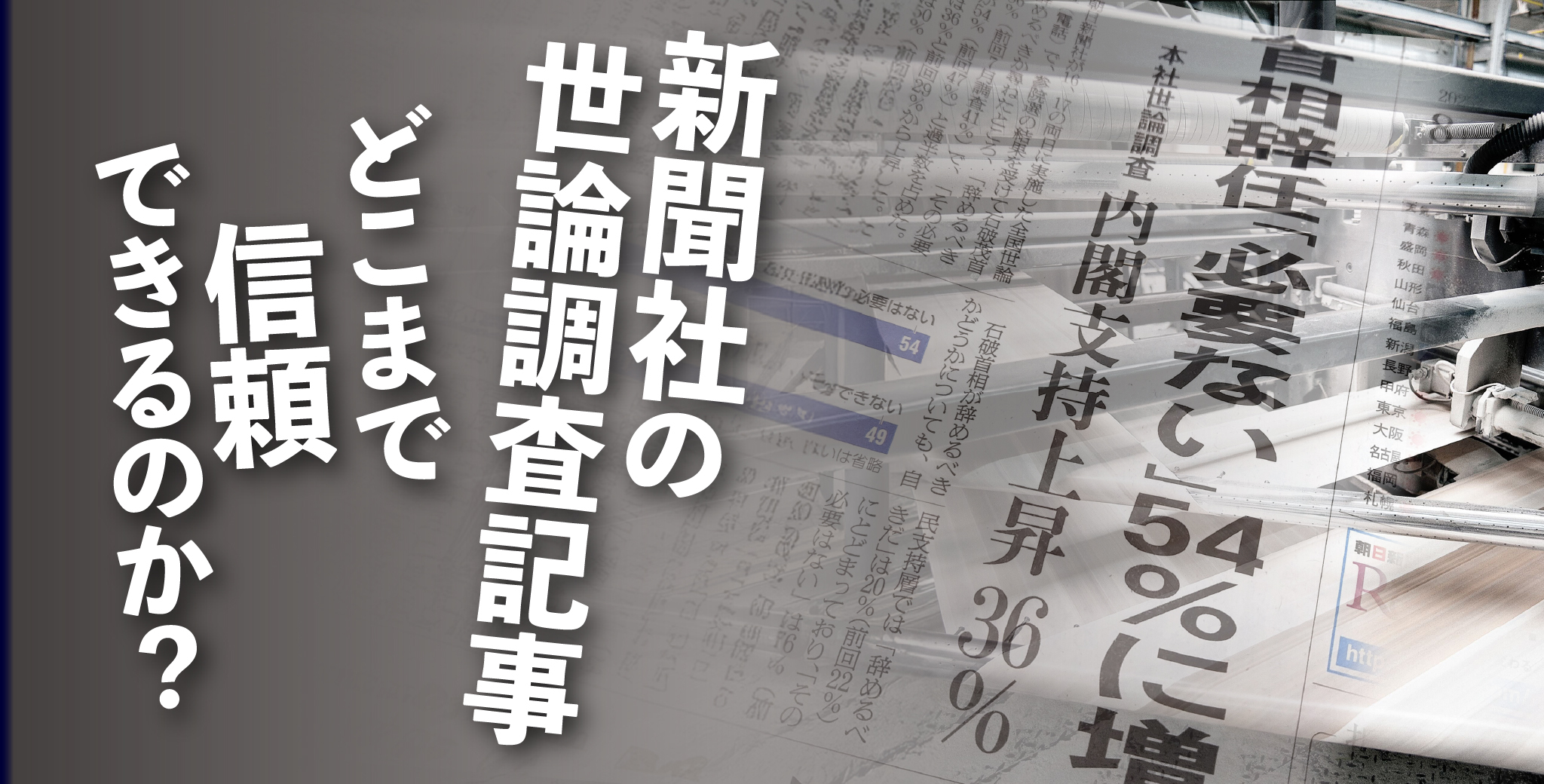
新聞社の世論調査記事 どこまで信頼できるのか?
二〇二五年九月五日 「石破茂首相は辞める必要はない」。八月下旬、こんな見出しの記事が大手新聞を中心に目立ったが、これは本当に世論の反映なのだろうか?大手新聞社は定期的に政党の支持率調査結果を記事にしているが、媒体によって大きな差が出ることが多い。なぜ、媒体ごとに差が出るのか。新聞社の世論調査には「ゆがみ」(バイアス)があることを知っておきたい。朝日新聞が一面トップで石破首相推し! ご存じのように自由民主党は、衆議院選挙(二四年秋)、東京都議選(二五年六月)、参議院選挙(二五年七月)の三つの選挙で大敗した。企業が三期連続で赤字を出せば、トップが経営責任を問われるように、自民党のトップである石破首相が責任を問われて当然だという空気がみなぎる中、八月十八日、朝日新聞が一面トップで「首相辞任『必要ない』54%に増」、「本社世論調査 内閣支持上昇36%」という大見出しの記事(写真参照)を報じた。 この見出しを見て、朝日新聞社はこの世論調査結果に小躍りし、痛くご満悦の様子だと直感した。その小躍りぶりは記事の文章の書き方に現れている。冒頭でいきなり「自民党内では参院選の大敗以降、石破首相に退陣を求める『石破おろし』の動きが続いている。こうした自民内の動きに『納得できない』との意見が49%と半数近くを占め、『納得できる』37%を上回った」と書いた。 この書き出しぶりを見ると、国民の半数を超える54%が「石破首相は辞める必要がない」と考えていることに対して、朝日新聞社は国民の気持ち以上に感激し、さらに「石破首相がんばれ」と朝日新聞の購読者にエールを送り返しているように思えた。その裏には、高市早苗氏(衆議院議員・元経済安全保障担当大臣)が次期首相になり、参政党などと手を結んだら大変なことになる、という思惑が透けてみえる。有効回答がどれくらいあったかを見ることが大事 新聞社が実施する世論調査記事を読むときには、その世論調査が本当に国民の平均的な声を反映しているかどうかを疑う必要がある。つまり、調査対象となった人たちのうち、何人が答えたかを知る必要がある。残念ながら一面トップ記事には、この大事な点が書かれていない。三面を見たら、目立たない隅っこに調査方法が書かれていた。 「コンピューターで無作為に電話番号を作成し、八月十六、十七の両日に固定電話と携帯電話に調査員が電話をかけるRDD方式で行った。固定電話では有権者がいると判明した九百十七世帯のうち四百五十二人(回答率49%)、携帯は有権者につながった千八百七十二件のうち、七百五十九件(回答率41%)、合計で千二百十一人の有効回答を得た」という。 ランダム(無作為)に選んだのはよいが、回答率が50%以下なのがまず気にかかる。いったい、どんな人が回答を拒否し、どんな人が回答を進んで引き受けたのだろうか。これは想像するしかないが、もしあなたが調査対象に当たり、朝日新聞社から電話があった場合、どうするか。あなたが朝日新聞を好きなら進んで答え、大嫌いな場合は拒否する可能性があるのではないだろうか。朝日新聞が行う世論調査では多くの場合、自民党の支持率が低くなるケースが多い。これに対し、読売新聞や産経新聞が世論調査を行うと自民党の支持率が高くなるケースが多い。 つまり、新聞社の世論調査には「ゆがみ」が伴うことを常に警戒する必要がある。読売新聞の携帯電話の回答率は33% 朝日新聞の報道から一週間後、読売新聞は八月二十五日、一面二番手で「内閣支持急上昇39% 首相辞任を42% 思わぬ50%」と報じた。朝日新聞と同様の結果となったが、四面を見たら、「次の総裁 高市氏1位」「総裁前倒し『賛成』52%」の見出しが躍り、石破首相は早く辞めるべきだというニュアンスが伝わってきた。「石破首相辞任へ」という号外まで出した読売新聞としては、石破首相に早く退場してもらいたいのだろう。その意図が記事ににじみ出ている。 読売新聞も、調査方法に関する扱いは九面に小さく載っていた。固定電話では七百七十三世帯から四百六人(回答率55%)、携帯電話では千七百七十四人のうち五百八十五人(回答率33%)が回答したというが、携帯電話での回答率の33%は低すぎる。無作為に選んで三割しか回答がなければ、どこまで日本の有権者(母集団)の真の姿を反映しているのか疑問がわく。毎日新聞は「辞任すべき」が上回る 一方、毎日新聞社は七月二十八日付け一面二番手で「内閣支持上昇29% 首相『辞任すべきだ』42%」と報じた。この記事では「首相は辞任すべきだ」(42%)が「辞任する必要はない」(33%)を上回った。七月下旬の時点ではまだ辞任すべきだという声のほうが強かった様子がうかがえる。 問題は調査方法である。毎日新聞の場合も、二面に小さく調査方法の解説が載っていた。それによると、全国約七千四百万人(18歳以上)の母集団から対象者を無作為に選び、調査への協力を依頼するメールを配信し、二千四十五人から有効回答を得たという。NTTドコモの協力を得たインターネット調査だが、無作為に選んだ人が何人で、そのうち何人が回答したかの数字は記されていない。これでは調査の信頼度は低い。世論調査は調査方法こそが肝 新聞社の世論調査で警戒すべきことは、その世論調査に応じた人たちはそもそも、母集団(日本国民)の代表的なサンプルといえるかどうかを見極めることである。世論調査は調査方法こそが肝なのだ。その調査方法をもっと大きく分かりやすく解説すべきなのに、その解説はいつも小さな扱いで目立たない。一面で世論調査を報じるなら、有効回答率を本文の中で解説するなど、統計的な検証に堪える科学的な記事にしてほしいものだ。読売新聞はあくまで「辞意」を強調 こういう「ゆがみ」は石破首相の動向をめぐる記事にも反映する。 七月下旬から八月上旬、首相官邸前に約二百~千二百人が集まり、「石破首相辞めるな」と石破首相を推すデモがたびたびあった。このデモはリベラル系の大手新聞(特に朝日、毎日、東京)やテレビを中心に幾度も報じられた。記事を読むと「(石破首相は)近年の自民党にはまれな言葉が通じる政治家だ」と石破首相を持ち上げる声もあり、「高市早苗氏と参政党が組んだら最悪の政治になる」といったデモ参加者の本音が読み取れる記事もあった。 興味深いのは、八月末になり、「石破首相は辞めろ」という逆のデモが起きたときだ。産経新聞(九月一日オンライン記事)によると、石破首相の退陣を求める「石破辞めろデモ」が八月三十一日、首相官邸前で行われ、四千人(主催者発表)が駆けつけたという。七月下旬に「石破辞めるな」デモが官邸前で行われたときは、最大でも約千二百人(主催者発表)だった。エッと思ったのは、四千人ものデモ隊が「石破首相は辞めろ」と糾弾しているのに、こちらはほとんどニュースになっていない。デモの規模で比べれば、「辞めろ」デモのほうが大規模なのに、報道は少ない。 自民党が九月二日に開いた両院議員総会で石破首相は、「地位に恋々とするものではない」などと述べたが、それに対し、朝日新聞は一面で「首相は続投姿勢」と報じ、読売新聞も「続投を表明」と報じたものの、同じ一面で「首相『辞める』明言」と書き、七月二十二日に石破首相が「日米交渉が合意に達した場合には記者会見を開いて辞意を表明する」と明言していたことを明かした。やはり朝日と読売の論調はかなり異なる。 どんなニュースも、そして世論調査も、媒体(新聞社やテレビ)のフィルター(社論、スタンス、好み)によって選別され、届くのは歪んだ情報だということを今一度知っておきたい。
- 05 Sep 2025
- COLUMN
-
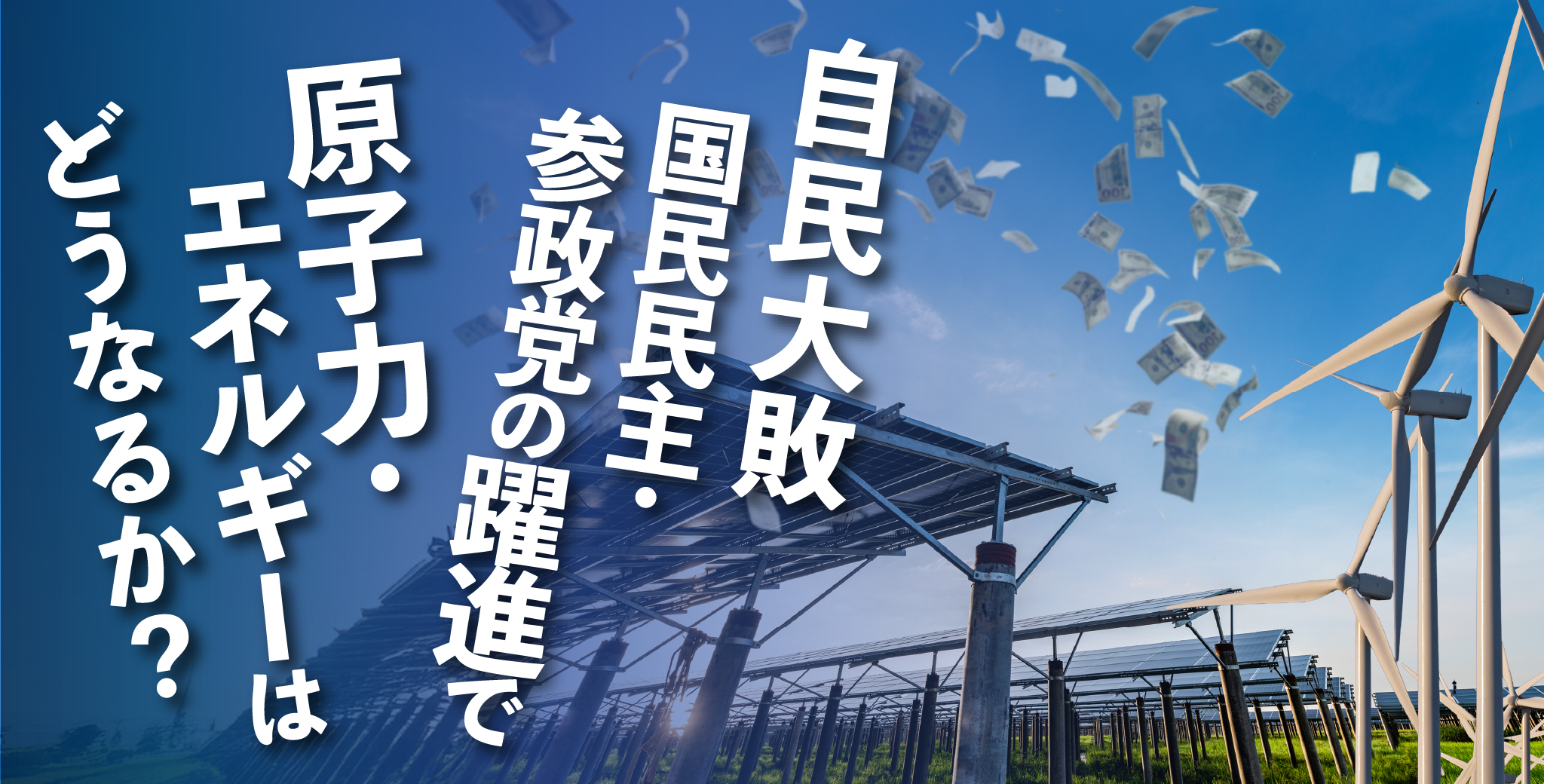
自民大敗 国民民主・参政党の躍進で原子力・エネルギーはどうなるか?
二〇二五年八月十二日 七月の参議院議員選挙で自民党が大敗し、国民民主党と参政党が大きく躍進した。この結果は原子力や太陽光など再生可能エネルギー問題にどう影響するのだろうか。「原子力を最大限活用する」としていた自民党が負けたことで原子力に逆風が吹くかと思いきや、意外にも原子力には追い風が吹いたといえる。その理由は?原発賛成の政党が約七割の票を獲得 参院選で最も躍進したのは、一議席から十四議席(選挙区七人、比例区七人)に急伸した参政党だろう。その急伸ぶりを見せつけたのが比例区での得票数だ。自民党(約一二八一万票)、国民民主党(約七六二万票)に次ぎ、第三位の約七四三万票を獲得した。前回(二〇二二年の参院選では約一七七万票)に比べ、四倍以上の伸びだ。この約七四三万票は立憲民主党(約七四〇万票)をも上回り、公明党(約五二二万票)、日本維新の会(約四三八万票)を大きく引き離した。 どの政党が原子力の必要性を認めているかについては、前回のコラムでも述べたように、自民党、公明党、国民民主党、参政党、維新、日本保守党の六党は原子力の推進に理解を示す(公明党は自民党に比べると消極的な賛成だが)。これに対し、立憲民主、れいわ新選組(約三八八万票)、共産党(約二八六万票)、社民党(約一二二万票)の四党は原発の推進に反対だ。そこで、今回の比例区の政党別の得票数を足して、原発推進派と反対派の割合を比べてみた。すると、原発推進の六党の合計得票数は約七割、反対の政党は約三割となった。もちろん、有権者がどこまで原子力を意識して一票を投じたかは分からないが、結果的にみれば、約七割の有権者が原発を推進する政党を選んだことになる。参政党は再エネ賦課金廃止 あらためて原子力・エネルギー関係に関する参政党の公約を見てみよう。公約は主に二つあり、ひとつは「次世代型小型原発や核融合など新たな原子力活用技術の研究開発を推進する」。もうひとつは「高コストの再生可能エネルギーを縮小し、FIT(電気の固定価格買取制度)、再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金=再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が買い取るときの費用を国民が一部負担するもの)を廃止する」。この公約を私なりに解釈すると、電気代が高くつく太陽光や風力発電を縮小し、年間二兆円以上もの国民負担を強いている再エネ賦課金を廃止する。そして、原子力の再稼働を早め、原子力の利点を活用していこうという政策だ。 七月の選挙戦では原子力やエネルギー問題はほとんど争点にならなかったが、参政党の議員は以前から国会の質問で再エネ賦課金の廃止を訴えてきた。このスタンスは、再生可能エネルギーの推進を訴えてきた反原発の立憲民主党とはかなり異なる。参政党に一票を投じた有権者が参政党の原子力政策をどこまで理解していたかは分からない。だが、参議院で得た十四議席は、予算を伴わない法案を単独で提出することを可能にするだけに、今後の政策展開は大きな関心を浴びるだろう。参政党は大手メディアの批判をはねのけて躍進 参政党の躍進で特筆すべきことは、大手新聞やテレビの批判をかわして勢力を拡大したことだ。たとえば、参政党の神谷宗幣代表は参議院選挙の第一声の街頭演説で「高齢の女性は子どもは産めない」と発言し、リベラル系新聞やテレビから一斉に批判を受けた。 また、選挙戦中の七月十二日、TBS「報道特集」は参政党の主張は外国人排斥運動やヘイトスピーチを誘発していると批判。さらに同番組ではアナウンサーが「これまで以上に想像力をもって、投票しなければいけないと感じています」と参政党の勢いをけん制するかのような主張を述べた。これに対し、参政党は「公平性、中立性を欠く」と強く抗議し、TBSも「有権者に判断材料を示すという高い公共性、公益性がある」と反論するなど、双方の対立はいまも続いている(デイリー新潮・七月三十一日オンライン参照)。 これまでなら、大手マスコミから猛批判を受ければ、有権者の支持を失い、選挙では不利になるはずだが、そうはならなかった。参政党は次々にSNSで動画を発信し、「マスコミは事実を切り取って報じている。日本の六〇〇兆円のGDPをまず日本国民のために使う。これが自国民ファーストだ。そこの何が問題なのか」と切り返していった。SNSを見る限り、参政党を推す声のほうが圧倒的に強いと感じた。ここで強調したいのは、リベラル系の大手テレビや新聞(番組によってはNHKも)が一斉に参政党への批判を繰り広げたにもかかわらず。参政党がその批判をはねのけて躍進したことだ。既存の大手メディアの影響力が低下していることをまざまざと見せつけられた一幕だった。国民民主党は原発推進で勝利 一方、十七議席を獲得した国民民主党は二〇二二年参院選の二倍を超す七六二万票を得て自民党に次ぐ二位の躍進を見せた。その結果、非改選と合わせて、二十二議席を確保、予算をともなう法案(参議院では二十議席が必要)を単独で提出する力を得た。 すでに多くの方がご存じのように、国民民主党は二四年秋の衆議院選挙のときから原発の積極的な推進を公約に掲げているが、有権者からの支持は増えている。以前は選挙で「原発を推進します」と言うと票が減ってしまうため、「原発推進」は選挙に不利な言葉として定着していたが、それを見事にひっくり返したのが国民民主党である。その存在意義は大きい。 一方、日本保守党はエネルギー関連で「再エネ賦課金の廃止」「エネルギー分野への外国資本の参入を禁止する法整備」「わが国の持つ優れた火力発電技術の有効活用」を公約にし、二議席を獲得した。 日本保守党の島田洋一・衆議院議員(福井県立大学名誉教授・国際政治学者)は二四年十二月に提出した石破内閣のエネルギー政策に対する質問主意書で「原子力発電所は発電量当たりの人命リスクがもっとも低い電源であり、燃料の輸入が途絶えた場合でも約三年にわたり発電を続けることができ、エネルギーの安全保障として重要だ」などと述べており、日本の高効率の石炭火力発電所の持続・発展にも高い理解を示している。 興味深いのは、国民民主党、参政党、日本保守党の3党とも「再エネ賦課金の廃止」を訴えていることだ。私はこれまでにも太陽光や風力への過剰な期待(幻想)が反原発運動を支えていると書いてきたが、新たに国会の舞台にニューフェイスとして登場してきた国民民主党、参政党、日本保守党は再生可能エネルギーに過剰な期待を寄せていない。これに対し、自民党には「再生可能エネルギー普及拡大議員連盟」(柴山昌彦会長)があり、太陽光や風力などへの期待を抱く議員たちがたくさんいる。しかも洋上風力発電事業をめぐる汚職事件で秋本真利元衆院議員が起訴(秋本氏は無罪を主張)されるなど、議員と事業者に利権がらみのイメージもあるせいか、国民に良い印象を与えているとはいいがたい。原発はより推進されるのか? 日本経済新聞は選挙が終わった七月二十一日、「与党が大敗し、自公政権の土台は揺らぐが、原子力発電の推進策は維持されるとみられる。議席を伸ばした国民民主党は原発の新増設、参政党は次世代型原発への研究開発を掲げており、原発の推進には前向きな姿勢を示す」と報じた。 自民党が負けたものの、原発推進の国民民主党と参政党が躍進したことで原子力発電の推進策は維持されるという判断だろうが、「維持される」というよりも、むしろ「より推進力が増した」と解したい。原発を推進する力は、再生可能エネルギーに過剰な期待を抱いていない国民民主党、参政党、日本保守党の三党のほうが強いからだ。 今後、三党が国会の場で、原子力政策と再生可能エネルギー政策でどのような言動を見せてくれるのか、注視していきたい。
- 12 Aug 2025
- COLUMN
-
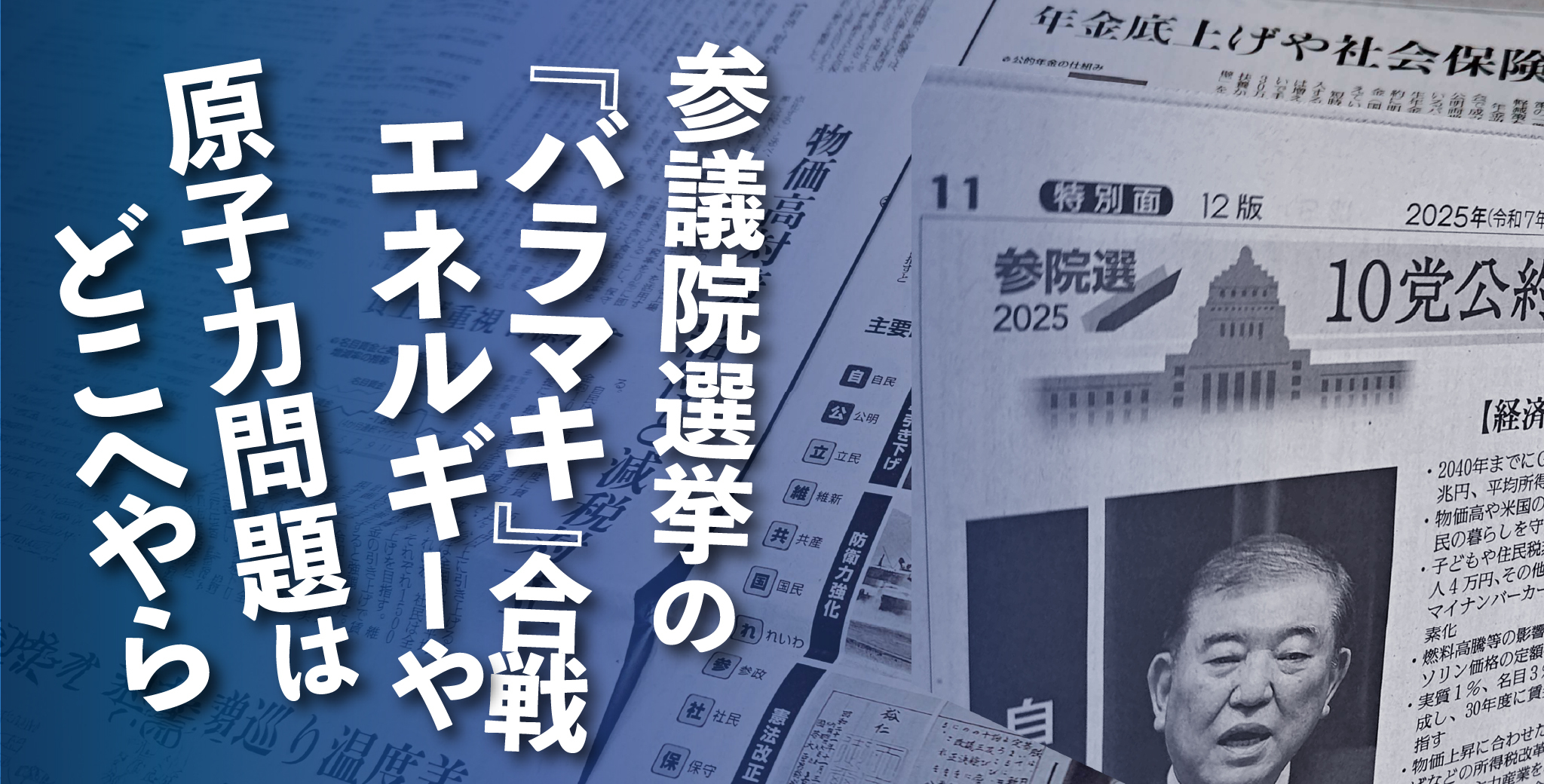
参議院選挙の「バラマキ」合戦 エネルギーや原子力問題はどこへやら
二〇二五年七月十一日 参議院選挙が華やかに繰り広げられている。ただ、三年前の参議院選挙ではエネルギー問題や原子力が大きな争点になっていたが、今回はその様相は全く見られない。各党とも国民の生活向上を訴えているが、そのためには電気、エネルギー、半導体、車など主要産業の確立・強化が不可欠だ。バラマキでは産業は育たない。どの党もバラマキ政策合戦 参議院選挙(七月二十日投開票)が始まってから、大手新聞やテレビをできるだけ見るようにしているが、どの党も手法は異なるものの、長引く物価高で打撃を受けている家計への支援を強調している。自民党と公明党は一人あたり二万円の給付(ただし住民税非課税世帯は一人四万円)、立憲民主党は食卓応援給付金として、一人あたり二万円の即時給付、日本維新の会は食料品の消費税を二年間ゼロ%、共産党は消費税を緊急に一律五%への引き下げ、れいわ新選組は消費税の全面廃止と現金十万円の即時給付、といった具合に聞こえのよいバラマキばかりだ(読売新聞七月二日の記事「10党公約比較」参照)。 三年前の参議院選挙ではロシアのウクライナ侵攻の影響もあってか、原子力やエネルギー政策が大きな争点になっていたが、今回は通常のテレビニュースや新聞記事を見ている限り、エネルギー問題はほとんど顔を出さない。国民民主は原発再稼働を強調 その証拠に、読売新聞の各党公約比較記事(七月二日)を見ても、自民党の公約には「原子力」の文字が見えない。これに対し、日本維新の会は「再生可能エネルギーの導入拡大、次世代原子力発電の推進」をうたい、国民民主党は「安全基準を満たした原発の早期再稼働に向け、規制機関の体制強化」と訴える。自民党と対照的だ。 一方、立憲民主党は「原子力の新増設は認めない」と明記、共産党も「すみやかに原発ゼロとし、石炭火力からの計画的撤退を進め、二〇三〇年度にゼロ」と反原発を鮮明にする。最近、勢いづいている参政党や保守党は同記事では原子力に関する記載がない。原子力に対する各党の立ち位置 では、原子力に対する各党の立ち位置はどうなっているのだろうか。その参考になるのが七月二日の読売新聞だ。たとえば、防衛力の強化では、共産党、れいわ、社民党が同じ位置で慎重な立場をとるのに対し、自民、維新、参政党、保守党、公明党、国民民主党はほぼ同じ位置にいる(写真1参照)。写真1 これと同じように、原子力に対する各党の立ち位置を知りたいところだが、この読売新聞には載っていない。ネットで探したところ、環境問題に取り組む国際的な環境団体「FoEジャパン」が二四年十月に作成した立ち位置図が見つかった(図1参照)。環境団体から見た立ち位置図とはいえ、非常に分かりやすい。自民党、国民民主党、参政党、日本維新の会が原発に賛成、立憲民主党、共産党、れいわ、社民党が原発にブレーキをかける位置にいることが分かる。FOEジャパンによる原子力に対する各党の立ち位置国民民主党がやはりカギか この立ち位置図から分かる通り、立憲民主党、共産党、れいわ、社民党の議席(勢力)が伸びると原子力政策の推進にとっては大きなマイナスとなる。今回の参議院選挙の行方について、毎日新聞は七月七日付け一面記事で世論調査結果を基に「自公苦戦 1人区野党系優位 立憲堅調 国民、参政勢い」と報じた。立憲民主党が堅調で、国民民主党と参政党に勢いが見られるという内容だ。 岸田文雄前首相が決めた「原発の最大限活用」をうたう自民党が衰退し、立憲民主党が伸びれば、確かに原発にとっては逆風となる。しかし、国民民主党と参政党が自民党の劣勢を補う形で伸びれば、原発自体には逆風は吹かないことになる。日本保守党も原発には肯定的だ。保守勢力が割れているとはいえ、原子力自体を否定する政党が勢いを増しているわけではないことが分かる。その意味では、原発推進に積極的な国民民主党の勢力が伸びるかどうかが大きなカギを握るように思える。政治と柏崎刈羽原子力発電所の再稼働 原発の再稼働で気になるのが、東京電力・柏崎刈羽原子力発電所をかかえている新潟県(1人区)の動向だ。新聞を見る限り、自民党新人の中村真衣氏と立憲民主党現職の打越さく良氏の接戦のようだ。中村氏はシドニー五輪銀メダリストの元競泳選手だ。 皆さんもご存じのように、二四年十月の衆議院選挙の新潟小選挙区(五人)で自民党は全敗(比例復活で一人当選したが)し、立憲民主党が五つの小選挙区で全議席を獲得した。 柏崎刈羽原子力発電所の6号機と7号機はいまだに再稼働していないが、政治の影響を受けることは必至だ。今回の選挙で立憲民主党が議席を守るのか注目したいが、そうした中でおもしろい記事をYahoo!ニュースで見つけた。反原発の新聞シェアは約八〇% 最年少で経済誌「プレジデント」編集部編集長を経験した作家、小倉健一氏の「『もはやプロパガンダ』新潟日報」という刺激的なタイトルの記事だ。新潟日報の過去の一連の記事が読者に、「原発は危険で東電は信用できない」という印象を植え付けている、という内容だ。 小倉氏は「日本の未来のために、国益のためにと歯を食いしばり、柏崎刈羽原発の再稼働に向けて奮闘している人々がいることを忘れてはならない。我々は、彼らの努力を正当に評価し、その背中を力強く後押しすべきではないか」と熱く語る。 新潟日報が原発に厳しい記事を書いているという印象は私も抱いているが、それは朝日新聞や毎日新聞、東京新聞にも言え、一民間企業の新聞社がどんな路線の記事(商品)を書こうと自由である。私が興味を抱くのはその新聞社の客観的な影響力である。 日本ABC協会によると、新潟日報の発行部数は約三十四万部(二四年八月現在)。新潟県内の新聞読者に占めるシェアは約七一%と非常に高い。ほぼ一強の状態だ。このほか同県では、読売新聞が約七万三千部、朝日新聞が約二万八千部、日経新聞が約一万八千部、毎日新聞が約一万千部、産経新聞が約五千二百部だ。 この状況を原子力への風当たり指数として見ると、朝日、毎日新聞も反原発路線なので、新潟日報と合わせるとその合計部数は三十七万九千部となる。つまり、新潟県内の新聞読者の約八〇%は反原発かそれに近い記事を読んでいることになる。 それら約八割の読者のすべてが反原発を支持しているとはいえないだろうが、日々接しているニュースが何かしら原発に否定的な印象を与えていることは確かだろう。原発の再稼働がなかなか前進しない背景には、こういうメディア的状況もある気がする。 株式会社マイナビによると、新潟日報の年間売上は約百四十一億円(二三年十二月期)、従業員は五百十九人(二四年四月現在)。会社の規模としては決して大企業と言えるほどの会社ではない。いや小さな会社といってよい。しかし、情報を通じた影響力では七割のシェアを誇り、新潟県民の気持ちを支配する印象操作力をもっている。地元紙の力、恐るべしである。強固な産業の確立こそが重要 選挙では生活支援が争点になっているが、電気やエネルギーも含め、モノやサービスを国民に安く、かつ安定して供給できるのは主力産業の基盤がしっかりと確立され、生産性が上がったときの話だ。かつて岸田文雄前首相は「原発一基の再稼働で百万トンの天然ガスの輸入が節約できる」と訴えていた。LNG(液化天然ガス)一トンあたりの輸入価格はおおよそ九~十万円なので、再稼働で約千億円の国富の流失を防ぐことができる。いま重要なのは「富」を創り出すことであり、ばらまくことではない。メディアは批判することは得意だが、富を生み出すことには関心が低いことをつくづくと感じる。
- 11 Jul 2025
- COLUMN
-

新聞記事の影響力は「拡散不可」でますます縮小か
二〇二五年五月二十七日 新築戸建て住宅への太陽光パネルの設置を義務付ける東京都の改正条例が今年四月から施行された。「太陽光は環境にやさしく、電気代が節約できる」といったミスリード記事が多い中、産経新聞(四月六日付)に「再エネ賦課金 家計にずしり」と題したおもしろい記事が載った。こういう記事こそ拡散を期待したいが、大手新聞の記事はほとんど拡散しない。そこがSNSと比べた場合の最大の弱点かもしれない。再エネ賦課金の累計は二十五兆円 原子力発電への風当たりが依然として強い背景には、太陽光発電を全国くまなく拡大すれば、原子力がなくても電気エネルギーがまかなえるという幻想があるからだと、私は常々考えている。太陽光に関する大手メディアの記事の多くは「再生可能エネルギーの切り札といえる太陽光発電」といった根拠なき称賛の表現が目立つ。 そうしたメディア空間に慣れきっていたところ、四月六日付産経新聞の1面トップに「太陽光未稼働8万件失効 高額買い取り認定分 政府『国民負担4兆円抑制』」との見出しの記事が目に飛び込んできた。同じ紙面の3面には「再エネ賦課金 家計にずしり 電気料金の1割超 月1600円上乗せ」との解説記事が載った。 太陽光発電や風力発電などの事業者が発電した電気を電力会社が一定の価格で長期間、買い取ることを義務づけた「固定価格買い取り制度」(FIT)は二〇一二年にスタートした。電力会社がその一定の価格で買い取るときに上乗せされているのが「再エネ賦課金」(正式名称は「再生可能エネルギー発電促進賦課金」)だ。電気を使うすべての人がこの賦課金を負担する。言ってみれば、国民全員が負担する税金のようなものだ。 この賦課金の単価は二〇一二年以来上昇し続け、二五年度の賦課金単価は一キロワット時あたり三・九八円と過去最高になった。標準家庭で見ると月額千六百円程度の負担増となるが、制度が始まってからの累計額を見ると、なんと約二十五兆円にもなる。太陽光の普及で電気代が安くなっているかと思いきや、現実は逆で、国民の負担は重くなっている。二十五兆円もあれば、国民のためにいろいろな社会的事業ができたのにと思うのは私だけだろうか。旧民主党政権の負の遺産 そもそもは当初の買い取り価格が高過ぎたのだ。確かに太陽光発電の事業者には利益が転がり込むだろうが、日本経済全体でみれば、電気代のコストはどんどん上がっていく。太陽光発電が原子力の代替にならないのは設備利用率が二〇%以下と低いからだ。欧州諸国は太陽光や風力発電の先進国といえるが、実は、太陽光と風力が普及している国ほど家庭の電気料金は高い(杉山大志著『データが語る気候変動問題のホントとウソ』参照)。だが、メディアの中に太陽光幻想が続くせいか、こんな当たり前のことが意外に知られていない。 この賦課金制度は旧民主党政権時代の「負の遺産」として末永く語り継ぎたいが、すでに制度として定着している以上、今それを言っても仕方がない。こうした中、この非合理な制度を解消しようと必死になっているのが国民民主党だ。前述の産経新聞記事によると、再エネ賦課金の一時停止や見直しを主張する国民民主党は昨年三月、「再エネ賦課金停止法案」を提出したという。今後の活動に期待したいが、国会での関心は低いようだ。二〇四〇年代に五十万トンのパネル廃棄物 太陽光発電に関する記事といえば、毎日新聞が五月十四日に報じた「太陽光再資源化見送りへ 費用負担誰が 推進偏重ツケ」との見出しの記事もよかった。太陽光パネルを全国に広めていけば、いずれ寿命が来て廃棄される。二〇四〇年代前半には最大で五十万トンもの廃棄物が発生する見込みだという。環境省と経産省はパネルの所有者に解体費用を、製造者にリサイクル費用を第三者機関に納めさせ、リサイクルを促す法案を用意したのだが、内閣法制局から修正要求があり、法案の提出が見送られたという。 太陽光パネルが増えれば、いずれ大量廃棄がやってくるのはだれにも分かっていることだが、毎日新聞の記事は、冒頭の「脱炭素エネルギーの切り札として導入が広がる太陽光発電」との枕詞を除けば、その課題を分かりやすく解説した良い記事だといえる。新聞記事は著作権法の著作物 今回は、太陽光発電の課題を突く記事を二つ紹介したわけだが、残念なのは、こういう良い記事を見つけても、その内容を拡散できないもどかしさだ。上記の産経新聞の記事はネットでもほぼ公表しており、だれでも読めるが、記事自体を勝手に広めることは難しい。記事は有料の商品だからだ。 そもそもメディアの目的は何だろうか。それは自社の報じた記事(ニュース)を少しでも多くの人に知ってもらうことだろう。しかし、残念ながら、新聞の記事を他の人に届けようと思っても、記事は新聞社の知的財産とあって、コピーして配ることはできない。記事をコピーして、そのコピーをネットでみなに知らせることもできない。インターネットがあまり普及していなかった時代には、新聞記事を大量にコピーして、仲間に配っても、お咎めはなかったが、今は厳しい。新聞記事は著作権法で保護された著作物であり、著作者の許諾なしに記事を複製して配布することは禁止されているからだ。 しかも、新聞記事の大半はネットでは無料で読めず、多くは有料の情報だ。有料の情報を無料で拡散すれば、商品のタダ売りになってしまい、メディア自体の自殺行為になってしまう。無料で情報を発信すれば、取得するのにかかったコストも回収できない。つまり、新聞社は自社のニュースを拡散させて広く知ってほしいと思っても、その目的を達成できないのである。ニュースの価値は拡散こそにある 大手新聞の購読者が激減している中で、どの新聞社も記事を少しでも有料で売ることに腐心し、職場などでの記事のコピー配布にますます目を光らせている。しかし、そうなるとますます新聞記事は拡散できず、かつてのようなマスコミ的な影響力を行使できなくなる。 つまり、いくら良い新聞記事を見つけても、それを不特定多数の大勢に知らせることができないのだ。かたやSNSの世界では、信頼度の有無はさておき、コピーして知らせると言う意味ではほぼ無限に情報を拡散できる。 昨年秋の兵庫県知事選の情報戦では大手メディア(新聞やテレビ)の発信力(情報の拡散力)が、無数の人たちがプレーヤーとなるSNSの発信力(情報の拡散力)に負けた事例だ。大手メディアはもはや昔のように、何百万人もの読者に一度に情報を届けるマスメディアではなくなってきている。 米国を拠点に活躍する新進気鋭の現代美術家、松山智一氏がテレビ番組で次のようなニュアンスのことを言っていた。作品を作っただけでは何の影響力も感化力もない。その作品に共感する人がいて、その共感の輪がくまなく広がっていって初めて、作品の影響力が生まれる。周囲の反応と拡散という関係性こそが作品の価値を広めていく。 それを聞いていて、新聞の記事も同じではないかと思った。記者が記事を書いただけではその価値はまだ低い。拡散して、人の心に突き刺さったときに初めて大きな価値が生まれる。そう、拡散こそが価値を生み出すのだ。 兵庫県知事選でSNSが発揮したパワーはまさに「拡散力」にあった。大手新聞社が自社記事をもっと国民に読んでほしいのであれば、課金なしで拡散させるビジネスモデルを考えないとその影響力はますます低下していくだろう。((編集部注:原子力産業新聞は、どなたでも登録なしで、全ての記事が無料でご覧になれます。))
- 27 May 2025
- COLUMN
-

「正しいことはすごくつまらない」にメディアは迫れるか
二〇二五年五月七日 気候危機を煽るニュースが毎日のように流れているが、今回は「それって本当にエビデンス(科学的根拠)があるのですか」と真摯に問いかける書籍を紹介したい。世の中が熱くなっているときこそ、世間の「空気」に抗う冷静な思考が必要だ。メディア関係者や気象関係者にとっては必読のテキストといってもよいだろう。大規模停電でも地球温暖化が関係? 四月二十九日朝に放映されたテレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」を見ていて、びっくり仰天した。スペインで起きた大規模停電の原因について、アナウンサーの羽鳥慎一氏が「これも地球温暖化の影響かな」と言ったのだ。そして、ゲストコメンテーターも「サイバー攻撃かもしれないが、急に暑くなって一斉に電気を使ったのか」とのコメントも流れた。 常識的に考えて、突然の大規模停電が地球の温暖化によって起きたと想像するのは難しい。地球温暖化といっても、百年間で一℃程度の気温上昇でしかない。それが大規模停電を引き起こしたと考えるのはあまりにも論理の飛躍である。にもかかわらず、テレビや新聞のメディア関係者はことあるごとに「温暖化が原因では」という言葉を安易に気軽に使う。 テレビ朝日の『有働Times』(三月三十日放送)でも「世界的に温暖化が進むと山火事が起こりやすくなる」と報じていた。いうまでもなく温暖化があまり進んでいなかったときでも、山林火災は世界で発生していた。「温暖化が原因」という言葉が安易に使われている状況を見ていると、メディア関係者は温暖化による地球規模の影響を正しく(科学的かつ統計的に)見ていないのではないかと思う。台風は激甚化していない そういうメディアのゆがみ(バイアス思考)に対して、うってつけのテキストが登場した。キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の杉山大志氏(物理学)が著した『データが語る気候変動問題のホントとウソ』(電気書院)だ。杉山氏は気候変動問題やエネルギー政策の論客だ。この本は難しいテーマを非常に分かりやすい言葉で解説し、中学生でもスラスラと読める。 杉山氏は温暖化自体を否定しているわけではない。しかし、「温暖化によって山林火災など自然災害が激甚化している」という言説には疑問を呈する。 たとえば、よく「地球温暖化のせいで台風が激甚化し、頻発している」とのニュースが流れるが、杉山氏は「そんな事実はない」と気象庁などのデータを用いて、詳しく反論している。日本のスーパー台風のランキングをみても、一九五〇年~六〇年代に頻発していた。昭和の三大台風(室戸台風、枕崎台風、伊勢湾台風)は一九三〇年代~五〇年代に起きている。私の自宅(愛知県犬山市)は伊勢湾台風(一九五九年)で半壊した。そんな辛い経験をもつ私にとっては、このことはとても実感できる。いまメディアにいる人たちはそのころの台風を知らない。知らなければ疑問の持ちようがない。ホッキョクグマは減っていない 同書によると、メディアが知っておくべき事実はほかにもたくさんある。「ホッキョクグマは減っていない」「気象災害による死亡数は減っている」「豪州最大のサンゴ礁(グレートバリアリーフ)は一時、半分消滅したといわれていたが、いまはV字回復した」(豪州海洋科学研究所は回復したデータを公表しなくなったという)「太平洋の島しょ国は水没の危機にはない」「世界の食料生産は過去五十年間、温暖化が進んだのに増え続けている」「米国の山火事による森林燃焼面積は一九三〇年代のほうがはるかに多かった」「世界の沿岸の陸地面積は拡大している」。メディアは都合のよいデータだけを探す ではなぜ、メディアは気候危機を煽るのか。それは、大しておもしろくもない統計的事実よりも、感情に訴える刺激的な物語(ストーリー)を好むからだ。 台風の激甚化に関して、杉山氏は次のように述べる。「地球温暖化によって台風が激甚化するといったストーリーを決めていて、それに合うデータだけを探し回る。ストーリーに合わない不都合なデータは無視する」。 全くその通りだ。森林火災や大洪水が起きると、メディアは勝手に温暖化のせいだと決め込んで物語(記事やテレビ番組)を作る。そういうメディア(特にNHKの特集番組はひどい)のバイアスぶりに関しては、私を含め十三人で執筆した「SDGsエコバブルの終焉」(宝島社)の第4章に書いたので、重複は避けたいが、ひと言でいえば、メディアの記者たちは温暖化が進んでいなかった時代にも、同様の大災害が起きていたのではないか、という記者なら常識的な想像力を全く働かせていない。 もうひとつ、杉山氏の本から例を挙げれば、東京では寒さによる死亡(呼吸器疾患や心臓まひなど)は暑さによる死亡(熱中症など)よりも三〇倍も多い。だが、メディアは暑いときに死亡した例を大きくニュースにする傾向がある。東京の例以外でも、「インドで熱波によって一〇〇人が死亡した」といった具合に、温暖化にかかわる事件となるとビッグニュースになりやすいバイアスがある。太陽光や風力への幻想 「エネルギー政策」と題した4章も一読に値する。朝日新聞、毎日新聞をはじめとするリベラル系メディアは依然として反原子力のスタンスだが、その背景には太陽光や風力発電を拡大すれば、化石燃料や原子力がなくても豊かな経済は維持できるという前提(思い込み)があるように思える。しかし、これは幻想である。 よく太陽光で電気代が安くなるといわれるが、これは太陽光パネルが夜や雨などで止まっているときに火力発電や原子力発電などの支援を受けているトータルコストが計算に含まれていないからだ。西欧を見れば分かるように、太陽光や風力が増えた国ほど電気代は高い。しかも太陽光パネルの約八割は中国でつくられる。これだけ中国依存が高いと、むしろそのほうが危機的だと私は思うが、メディアはそういう事実にほとんど触れない。世間の空気に抗う勇気を どうしたら、メディアのバイアスが食い止められるのかと思っていたところ、毎日新聞が四月二十五日付紙面で戦後80年を振り返る特集記事(専門家を交えた座談会)を組んだ。その中で作家の温又柔(おん・ゆうじゅう)さんは、SNS(交流サイト)では正しくない話のほうが波及するという見方に対して、「正しいことはすごくつまらない。だからこそ、こうしたつまらなさに耐えるのが今とても重要だ」と述べた。確かにそうだ。 それに対し、毎日新聞主筆の前田浩智氏は、「『空気』に抗する勇気」と題した総括的コメントとして、戦争反対を唱える国民の声はかき消されたという過去を踏まえ、「つまらない正しさがゆがんだ空気に水を差す。改めてかみしめたいポイントです」と書いた。 これを気候変動問題に置き換えてみる。統計的事実を無視して、温暖化の危機を散々煽るメディアの刺激的な空気に対して、「台風は激甚化していない」「ホッキョクグマは減っていない」といった事実は、大して興味をそそらず、つまらないほどの正しさだ。 だが、はたして、いまになってメディアはその「つまらない正しさ」に耐えられるのだろうか。メディアの使命は事実を突きつけることだ。少なくとも空気に抗う勇気を見せてほしい。
- 07 May 2025
- COLUMN
-
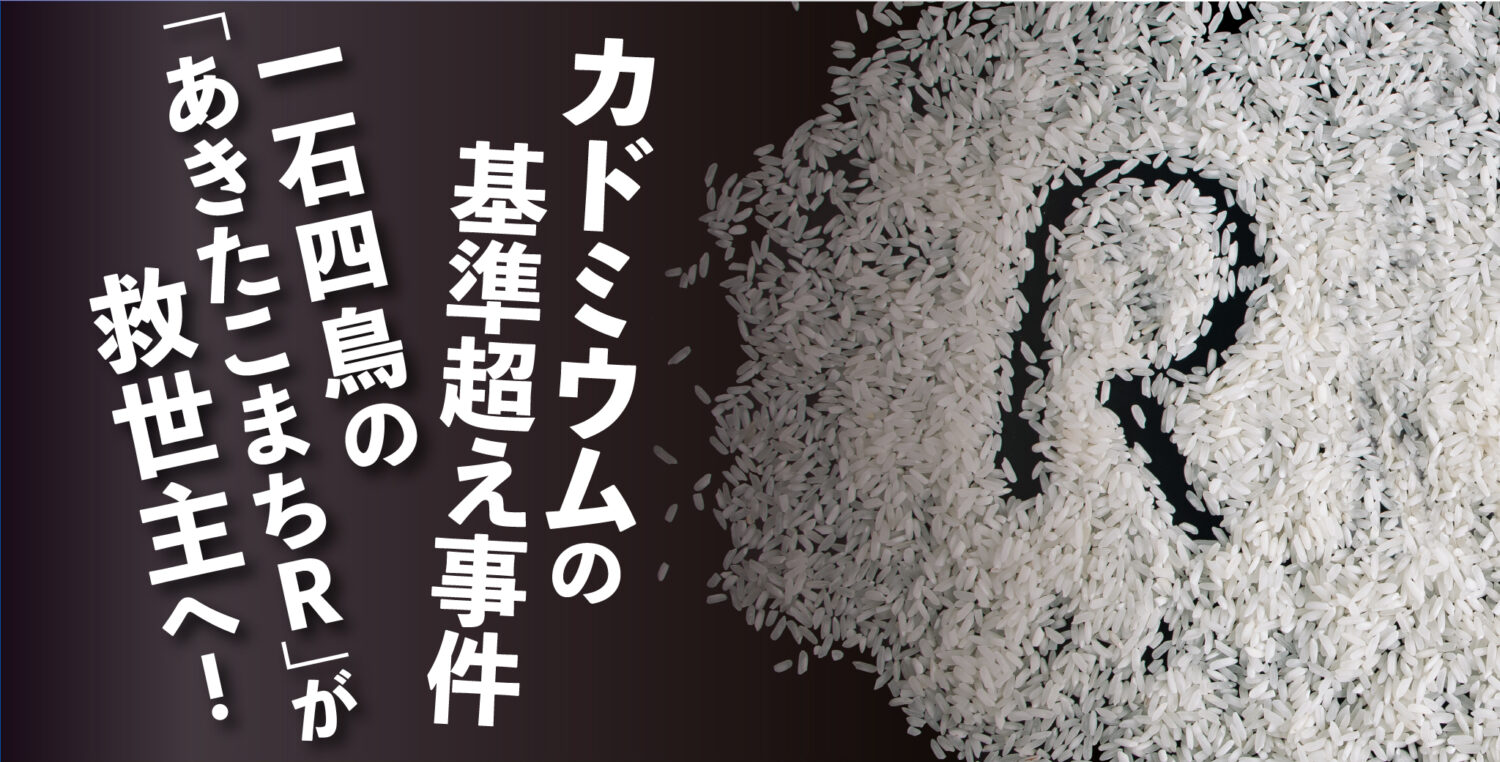
カドミウムの基準超え事件 一石四鳥の「あきたこまちR」が救世主へ!
二〇二五年四月二十一日 四月上旬、秋田県内の農事組合法人が出荷したコメから基準値を超えるカドミウムが検出された。コメは首都圏の広範囲の店で販売され、自主回収が進む。こうした悲劇的事件を避ける救世主が、カドミウムをほとんど含まない画期的な新品種「あきたこまちR」だということを重ねて強調したい。これを大きく報じないのは、メディアの怠慢だろう。基準超えは重大な失態 秋田県が四月四日に公表したリリースによると、農事組合法人・熊谷農進(秋田県小坂町)が出荷した約八六トンのコメの一部から食品衛生法で定められた基準値〇・四ppm(ppmは百万分の一の単位。一ppm=〇・〇〇〇一%)を超える〇・四七~〇・八七ppmのカドミウムが検出された。販売先は加工・卸売業者も含め、青森、茨城、埼玉、東京、神奈川、千葉など広範囲に及んだ。 基準超えのコメを知らずに販売した青森県の老舗米穀会社の社長は「裏切られた。農家の生産者として、全くプロ意識がなく、憤っています」(四月八日の青森朝日放送)と怒った。自主回収の対象となった数多くの販売店も同様の思いだろう。 基準超えのコメを一時的に食べても健康への影響はないが、今回の失態は「あきたこまち」のイメージ悪化につながる重大な事件だと認識したい。小坂町はかつて鉱山の町 不思議なのは、この基準値超えを報じるメディアが、カドミウムをほとんど含まない「あきたこまちR」が登場すれば、今回のような悲劇的事件を避けることができるという事実に触れていない点だ。 コメに含まれるカドミウムは稲が土壌中から吸収したものだ。今回の事件で基準超えのコメを出荷した熊谷農進はカドミウムが高くなった原因について、「去年は水不足が発生し、田んぼに水が入っていない状況が続いた」(四月八日の青森朝日放送)と語っている。どの農家もカドミウムの吸収を抑えるために夏場に水をはるのだが、その湛水管理に失敗したというわけだ。 熊谷農進のある小坂町にはかつて小坂鉱山があり、周辺地域の土壌は他の地域に比べてカドミウムの濃度が高かった。一九七〇年代に土壌汚染対策地域に指定され、九〇年代に対策は完了していた。そうした苦い過去を考えると、生産者はより強い注意深さが求められていたのだが、ちょっとした油断が今回の悲劇を生んだといえる。カドミウムとヒ素はトレードオフ ただ、生産者を責めるには酷な面もある。 首尾よく田んぼに水をはれば、確かにカドミウムの吸収は抑制されるが、逆に無機ヒ素の吸収は促進されてしまう。ヒ素はカドミウムと同様に国際がん研究機関(IARC)によるグループ分類で「発がん性あり」のグループ1に属する重金属だ。仮に湛水管理がうまくいっても、ヒ素が増えてしまうため、カドミウムとヒ素は相反するトレードオフの関係にある。 さらに言えば、田んぼに水をはると地球温暖化の原因となるメタンガスの発生量も増える。つまり、コメのカドミウムを低くしようとすると、ヒ素とメタンガスの両方が増えてしまうのだ。 日本列島を見渡せば、土壌中のカドミウムが高い地域があちこちにある。環境省によると、基準値を超えるおそれのあるカドミウムの土壌中濃度の高い地域(二〇二二年度)は秋田、富山、愛知、群馬、島根、福岡など九十七地域(面積約六七〇九ヘクタール)もある。 ではどうすべきか。結論を先に言えば、それを同時解決するのが「あきたこまちR」なのである。「あきたこまちR」なら、手間のかかる湛水管理が不要となるため、カドミウムが減るだけでなく、ヒ素もメタンも減らすことができる。そして、その先に日本人のコメを通じた健康リスクも低下する。つまり、カドミウムの吸収を抑制する新品種「あきたこまちR」はまさに一石四鳥の救世主なのである。カドミウムとヒ素の相対的リスクは高い では、なぜ日本の記者たちはこのことをあまり報じないのだろうか。それはおそらく、記者たちが日本のカドミウムのリスクの現状をあまり知らないからだろう。この「あきたこまちR」に関しては、このコラムで過去に2回(「放射線を活用したコシヒカリの画期的な育種に反対運動 いまこそ放射線教育を!」、「汚染土の行方にも影響する『あきたこまちR』問題 いまは関ヶ原の戦いなり!」)書いているので重複する説明は省くが、日本人がコメから摂取しているカドミウムとヒ素による健康リスクは、食品中に残留していてよく話題になる農薬や食品添加物のリスクよりもはるかに高いという事実を知っておく必要がある。 もちろんコメを食べて危ないという意味ではない。日本人が平均的にコメから摂取しているカドミウムやヒ素の量は、健康影響の目安とされる耐容摂取量より低い(耐容摂取量の数分の一‘程度)ものの、農薬や食品添加物(許容摂取量の百分の一~千分の一程度)と比べると許容量に近いため、相対的なリスクが高いという意味だ。 日本人はカドミウムの約四~五割をコメから摂取している。天候に左右されず、土壌中のカドミウムをほとんど吸収しない形質をもった「あきたこまちR」の存在意義が高いのは、これでお分かりだろう。自家採種は可能 こういう説明をすれば、どの消費者も「あきたこまちR」を食べたいはずだと思うが、残念ながら、それでも「あきたこまちR」を阻止しようとする反対運動が起きている。栽培意欲のある農家に対して、電話の抗議が来たり、「死ね」といったメールまで送られてくるケースがあるという。 反対派の主張の中に「県は一斉にあきたこまちRに切り替えるのではなく、従来の品種を栽培したいと思う個人の権利を守るべきだ」という声がある。確かに個人の選択を守ることは必要だろう。これに対して、県は「全農家に強制するものではない。従来の品種を希望する農家は自家採種してよい。県外産あきたこまちの種子を購入することも可能だ」と答えている。「あきたこまち」は品種登録されていないため、農家は自分で種子を採種(自家採種)できる。ならば個人の選択は守られているはずだ。難しい表示の問題 二五年産米からは、従来の「あきたこまち」も新しい「あきたこまちR」も、「あきたこまち」として販売される。これに対して、反対派は「従来の品種とあきたこまちRの区別がつかないため、あきたこまちRと表示して販売すべきだ」と訴える。 この表示の問題はちょっと複雑な心境になる。私としては「あきたこまちR」を食べたいので、たとえば「あきたこまちR」が「しんあきたこまち」といったネーミングになれば、「しんあきたこまち」を選んで購入したい。従来の「あきたこまち」を避けたいからだ。 一方、カドミウムやヒ素の含有量が高くても、従来の「あきたこまち」を食べたい人もいるだろう。そういう意味では表示の区別があってもよいと考えるが、消費者に混乱をもたらす恐れもあり、「あきたこまち」(秋田産あきたこまちの大半は「あきたこまちR」なので)という統一表記でもよいかと思う。乾田直播にも最適 今後、「あきたこまちR」が他県にも普及していくことを期待したいが、その理由は日本の稲作農業をさらに強くしたいという思いがあるからだ。カドミウムのコメの国際基準値は〇・四ppmだが、中国や香港、シンガポールは〇・二ppm、EU(欧州連合)は〇・一五ppmと日本より厳しい国もある。そういう国へコメを輸出する場合、カドミウムの基準値クリアーは必須要件だ。その意味からも「あきたこまちR」は優等生である。 さらに今後、日本の稲作では、田んぼに水をはらず、乾いた田んぼに直接、種子をまく乾田直播(かんでんちょくは)が増えていくだろう。この技術は育苗、代掻き、田植えという工程がなくなるため、大幅な省力化や低コストにつながる。そういう未来の稲作に対しても、「あきたこまちR」は大きく貢献できる。 知り合いの大手新聞記者に「なぜ、あきたこまちRの意義を記事にしないのか」と聞いてみた。すると「育種交配など問題が複雑で短めに分かりやすく書くことが難しい」との返答が返ってきた。難しいことを分かりやすく記事にするのが記者の仕事だ。記者の矜持をぜひ見せてほしい。
- 21 Apr 2025
- COLUMN
-
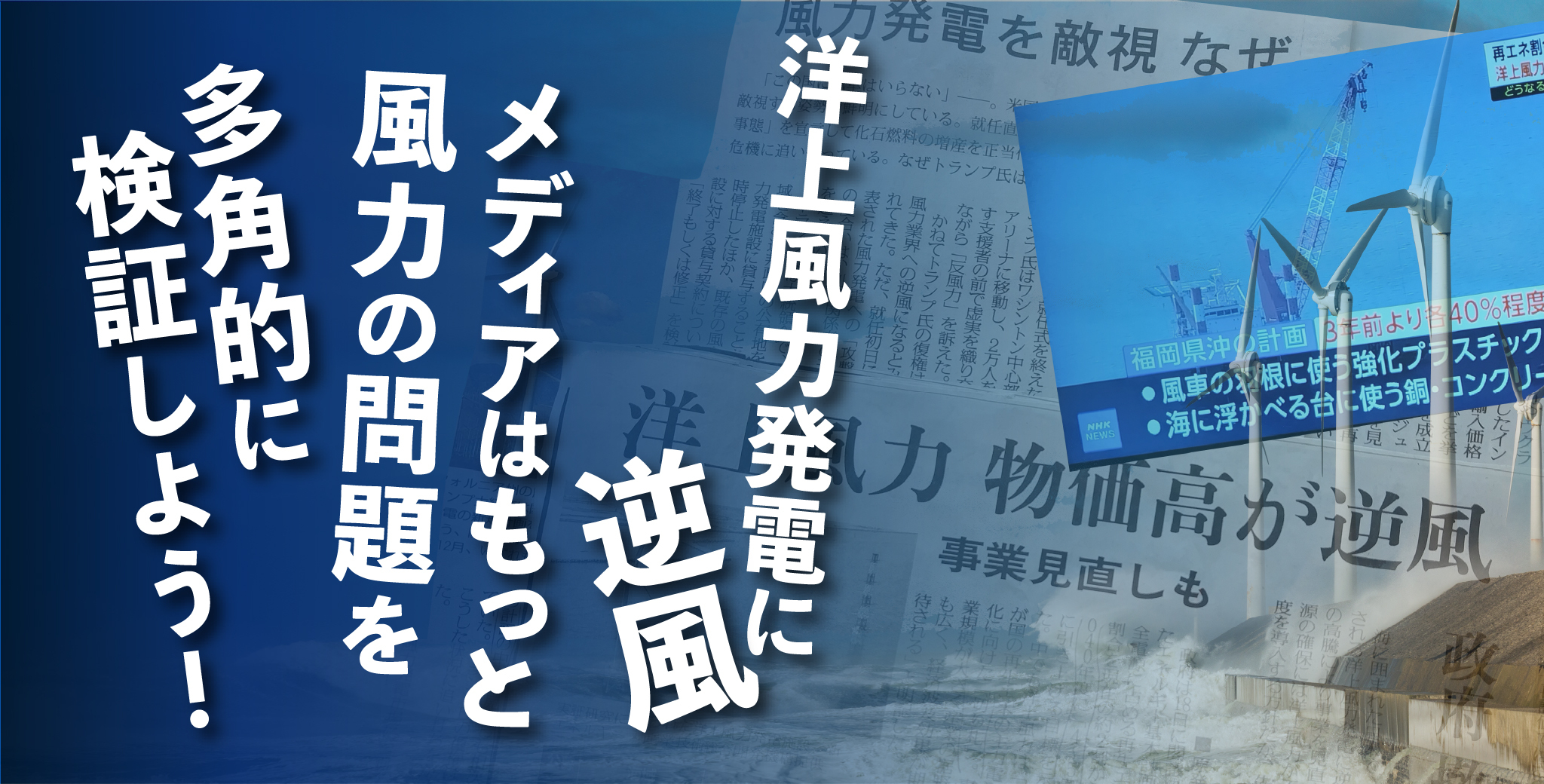
洋上風力発電に逆風 メディアはもっと風力の問題を多角的に検証しよう!
二〇二五年三月三日 風力発電に逆風が吹き始めたというニュースが目立ってきた。米国のトランプ大統領が風力を敵視しているのも逆風になっているようだ。ただ、よくよく考えてみれば当たり前の風が吹いているに過ぎない。大手メディアはもっと風力の限界を定量的にしっかりと検証してほしい。NHKのニュースウオッチ9 「洋上風力発電に逆風」と題して報じられたNHKの「ニュースウオッチ9」(二〇二五年二月十八日放送)を見た人は、日本各地の沖合で計画されている洋上風力発電事業がコスト高で暗礁に乗り上げているとの印象をもったのではないか。私も見ていて、そう思った。 同ニュースによると、卸電力大手の電源開発(J-POWER)が福岡県沖で工事を進める洋上風力発電事業において、風車の羽根に使う強化プラスチックやコンクリートなどの資材費が三年前に比べて約四〇%も上がり、黒字が確保できるのか先行きに不安が広がっているという。同社幹部の「お金の使い方として本当にいいのかと悩み、逡巡している」との悲観的なコメントまで流れた。 NHKは翌十九日にも水野倫之解説委員の「洋上風力に逆風 再エネの切り札に何が?」と題した解説記事をオンラインで公開した。その内容の一部はこうだ。 「洋上風力の先行きが見通せなくなってきている。 三菱商事と、中部電力の子会社などでつくる企業グループは、秋田と千葉県沖の三つの一般海域で、四年前に国の選定を受け洋上風力発電事業を進めており、大規模事業の先駆けとして注目されてきた。しかし今月、三菱商事が五百二十二億円、中部電力が百七十九億円の損失を計上し、『事業をゼロから見直す』と発表。トランプ大統領が風力に批判的なこともあり、すでに米国では事業見直しが相次いでいる」(一部要約)大手新聞も「逆風」を報道 NHKだけではない。読売新聞(二月六日付千葉版)は銚子市沖で進む洋上風力発電事業に関して「着工めど立たず 資材高騰で事業再評価へ」と報じた。翌七日付では全国版でも秋田県と千葉県銚子市沖の三海域で進む洋上風力事業について「洋上風力五百二十二億円減損 三菱商事 資材高騰 事業見直し」と報じた。さらに二月二十日付では全国版経済面で「洋上風力物価高が逆風 政府 撤退防止へ対策導入」との見出しで「政府は二〇四〇年度に再エネの割合を四~五割に引き上げる目標を示したが、政府目標に暗雲が漂い始めている」と長文の記事を載せた。 朝日新聞(二月六日夜オンライン)も三菱商事が洋上風力発電で「五百二十二億円の減損」と報じた。日本経済新聞(二月十九日)も「先行事業者の三菱商事が巨額の損失計上に追い込まれるなど逆風も吹き始めた」と報じた。 また、毎日新聞(二月十八日付)はトランプ大統領の「風車は鳥を殺し、美しい風景を台無しにする。大きく醜い風車はあなたの近所を破壊する」など過激な発言を紹介し、風力を敵視している状況を伝えた。記事自体はトランプ大統領を批判する内容だが、米国でも風力発電は資材費の高騰や金利の上昇などで計画の中止や見直しが相次いでいるとの内容も報じた。風力はバックアップ電源が必要 これらのニュースで分かるように、これまで洋上風力発電は再生可能エネルギーの切り札としてたたえられてきたが、もはやその名称にふさわしくない状況がうかがえる。 しかし、考えてみれば当たり前である。風力はそもそも風まかせの発電である。一年中、常に風が吹いているわけではない。雨や雪、夜に稼働しない太陽光発電よりはややましとはいえ、経済産業省によると、風力の平均的な設備利用率は陸上風力で約二〇%、洋上風力でも約三〇%しかない。 これは、風車が動いていないときは、火力発電や原子力発電などのバックアップ電源が必要になるという意味で根本的な弱点である。風力発電事業に関わる商社マンの知人の話では、「風力を導入する場合は、バックアップ電源として液化天然ガス(LNG)の火力発電所をセットで導入する必要がある。このことが一般市民にほとんど知られていない。それを言っちゃうと風力の魅力がなくなっちゃうからね」と話していた。 つまり、風力発電への投資はマクロ経済的に見れば、二重投資なのだ。バックアップ電源や電気を送るための送電網費用などを含めると、風力発電のコストはさらに高くなる。 大手メディアのニュースを読んでいて、何か物足りなさを感じるのは、風力発電に伴うバックアップ電源の必要性に関する検証内容が、ほとんど出てこないからだ。洋上風力のメリット これまでメディアでは洋上風力発電のメリットとして、①発電時にCO2を排出しない②発電コストが安い③化石燃料に依存せず、自国のエネルギー安全保障につながる④地域の雇用確保と地域経済の振興に寄与する⑤陸上風車よりも設置しやすく、騒音や景観問題が少ない⑥沖合では強い風が持続的に吹く──などが言われてきたが、どれも大きなメリットとは言い難いことが露呈してきたのではないか。 経産省によると、欧米での洋上風力発電(着床式)の発電コストはkWhあたり約九円といわれるが、その欧米でさえ、資材の高騰などで発電事業への入札が成立せず、事業の撤退や縮小が相次いでいる。 秋田県沖の二海域と千葉県銚子市沖での洋上風力発電事業で三菱商事が落札した価格はkWhあたり約十二円~十六円だった。この額は政府の想定を大幅に下回る額だった(読売新聞二月七日付)。コストを極力抑えようとした企業努力は評価したいが、事業の見直しが進めば、結局、電気料金の跳ね上がりとなって庶民の財布を直撃することになるのではと危惧する。自前の技術をもたない悲しさ いくら風力発電を増やしても、自国のエネルギー安全保障の強化につながるかが見通せないことも気がかりである。 かつては日本にも風力発電機メーカーが存在したが、いまでは二MW(二千kW)以上の大型風力発電機メーカーは存在しない(二〇二四年七月八日朝日新聞SDGs ACTION!)。つまり、日本が大型の風力発電機を導入したとしても、欧米のメーカーに頼らざるを得ないのが現状である。自前の技術者がいなければ、普段の維持運用だけでなく、何か故障が起きたときにも自前では復旧できないことを物語る。これではとてもエネルギーの安全保障が確保できるとは思えない。大手メディアは洋上風力の検証記事を 国が経済的な採算を度外視してまで洋上風力を推し進めるのは「脱炭素」という不可侵の目的があるからに他ならない。合理的な経済計算で判断すれば、コストの高い洋上風力よりも、いまは原子力の再稼働を一日も早く進めることが一番理にかなっているといえるが、大手メディアはそこまで踏み込めない。 洋上風力の舞台となっている秋田県能代市のホームページを見ていたら、次のような解説があった。 「洋上風力発電は一基二万点もの部品が必要で、事業規模も大きいため、関連産業への経済波及効果は大きいものがあります。風車設置後も設備メンテナンスや風車部品の供給など、地域活性化につながる産業となります。」 その通りになってくれればうれしいが、願望のように思える。大手メディアは、こうした洋上風力のメリットが本当に実現するかも含め、多角的な検証作業をしてほしい。
- 03 Mar 2025
- COLUMN
-
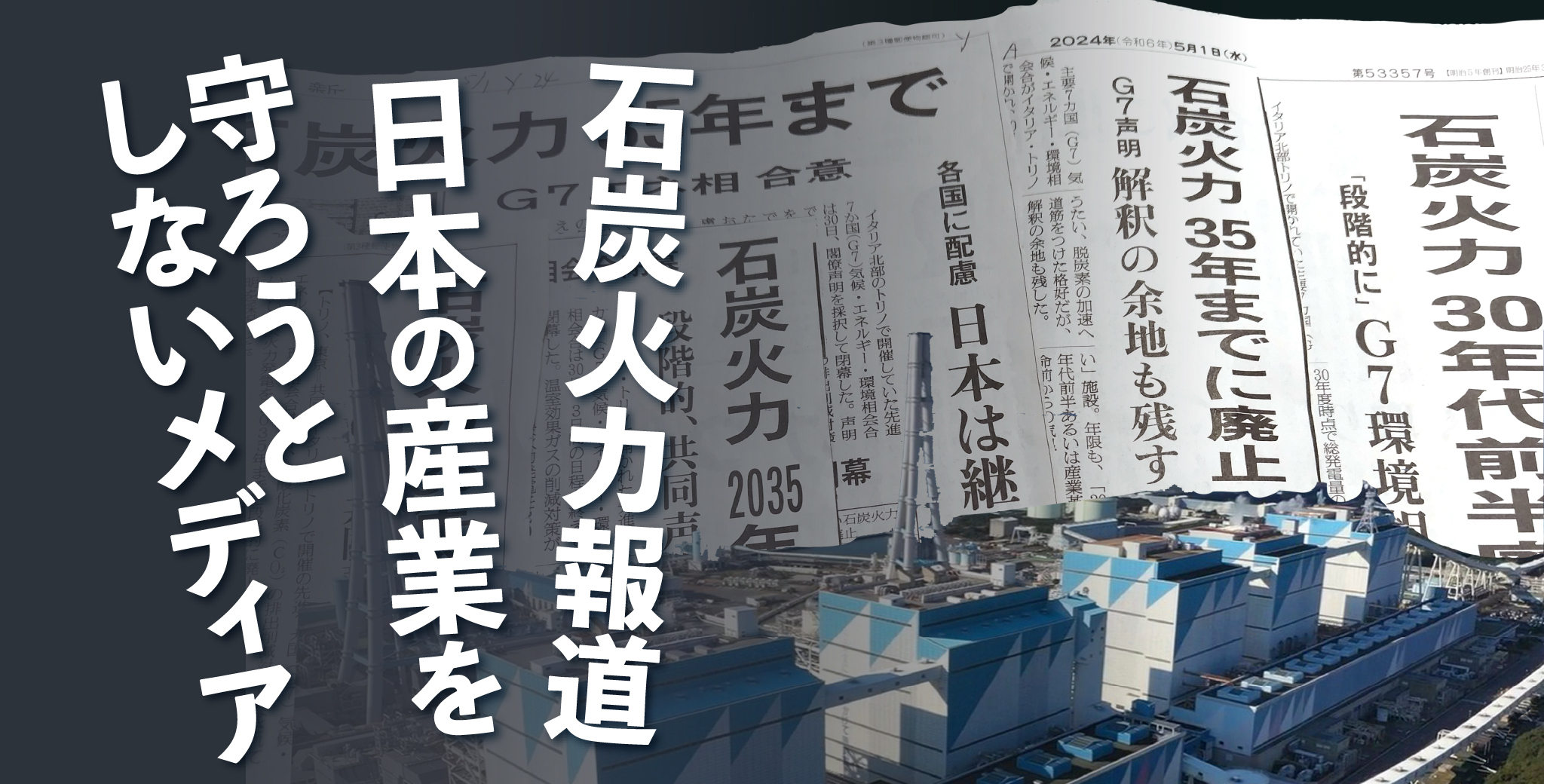
石炭火力報道
日本の産業を守ろうとしないメディア二〇二四年五月十七日 温室効果ガスの今後の削減対策などをめぐって、イタリア・トリノで開かれた先進7か国(G7)気候・エネルギー・環境相会合が四月三十日に閉幕した。その報道を各紙で比較したところ、やはり読売・産経と朝日・毎日・東京(もしくは共同通信)ではニュアンスがかなり異なり、気をつけて読まないとだまされてしまうことが分かった。見出しからは「石炭火力廃止」? G7で何が決まったかを報じた5月1日付新聞の見出しを見比べてほしい(写真1)。右から順に毎日、朝日、読売、産経、東京(共同通信)の見出しだ。石炭火力を廃止する年限に関して、「30年代前半廃止」と「35年までに廃止」と分かれた。どちらにせよ、共同声明では「石炭火力は廃止される」ことで合意したと読める。 これらの見出しを見て、ついに日本は世界でもトップレベルの環境性能を誇る石炭火力を手放すのか?アンモニアを混焼する脱炭素型石炭火力も放棄するのか?そんな絶望的なヒヤリ感を覚えた。写真1 ところが、丁寧に読み進めると読売新聞は前文で「35年以降の稼働を認める余地も残しており、石炭火力で多くの電力を賄う日本に配慮した形だ」とある。産経新聞も「石炭火力の依存度が高い日本は、燃焼時に二酸化炭素(CO2)が出ないアンモニアなどを活用して対応する」と報じた。これで単純に石炭火力を廃止するわけではないことが分かる。 そのことは東京新聞(トリノ、東京・共同)を読んで、確信に変わった。東京新聞は「環境団体は『排出削減対策が講じられていない』という条件が残る点を問題視し、『抜け穴』だと指摘する」という談話を載せた。環境団体が「抜け穴」だと批判しているということは、明るくて良いニュースだと考える習性を持つようになった私は、これらの記事でようやく、排出削減対策のない石炭火力は廃止するが、そうではない石炭火力は残りそうだ、と理解できた。 この点については、読売新聞の見出しだけは他紙と違い、「各国に配慮 日本は継続可」と「継続可」を強調していた。これは日本が誇る高性能の石炭火力は継続して残るという意味だ、と読み比べてようやく分かった。高性能の石炭火力を残すかどうかが焦点 そうであるならば、単に「石炭火力の廃止」という見出しはどう見ても、読者を惑わせる表現である。よく読むと、毎日、読売、産経、共同通信も「二酸化炭素の排出削減対策が講じられていない石炭火力を段階的に廃止」と書いている。さらっと読むと、その意味が理解できずに単に石炭火力が廃止されるんだと思ってしまう。日本が誇る脱炭素型で高効率の石炭火力を残す道が、明示的ではないにせよ認められたのであれば、それこそが価値あるニュースであり、私が見出し編集担当であれば、「日本の高性能石炭火力は廃止せず」との大見出しを飾ったであろう。 これらの記事を見ていると、記者たちの視点が、石炭火力の削減しか眼中にない欧米的思考に染まり過ぎているように思える。なぜ中国やインドを批判しないのか! 興味深かったのは朝日新聞だ。本文(五月一日付)の中で「今回の共同声明でも、廃止の対象に例外を設けたり、年限に解釈の余地を残したりすることで、各国が妥協した形だ」と書いたが、その詳しい意味がよく分からない。なぜ曖昧に書いているのだろうと思っていたところ、翌日の新聞にその解説版ともいえる大きな記事が載った。見出しは「脱石炭 孤立する日本 狭まる逃げ道 政府・電力、従来姿勢崩さず」だった。本文を読むと経済産業省の話として、今回の「排出削減採択のない施設」の定義について、「各国が合意したものではない。アンモニアの混焼、発電効率の高い石炭火力は対策を講じた施設と理解している」という内容が載った。これで昨日の記事の意味がより深く理解できた。 つまり、日本政府は高性能の石炭火力を何とかして残そうとしているが、他国からは批判を浴びている。この日本の奮闘ぶりを朝日新聞は環境団体のコメントを交えながら、「孤立する日本」と形容したわけだ。 この状況に対して、私なら「高効率石炭火力は、日本のエネルギーや電力の安定供給にとって不可欠だ。自国(他の先進国)に有利な政策を日本に押し付けてくる国際交渉の場でよくぞ自国の主張を貫き通してくれた」と絶賛する記事を書いたであろう。そもそも中国やインドはいまも電力の約六~七割を石炭火力に頼っている。日本が孤立するなら、中国やインドはとっくに孤立しているはずだが、いまもって国際交渉の場で堂々と渡り合っている。日本のメディアはなぜ、欧米側だけに立って、日本を責めるのだろうか。 石炭火力が電力の一~二%しかない英国やフランスが「石炭火力を全廃しよう」と提唱したところで自国にとっては痛くもかゆくもない。そのような国に対して、日本が高効率の石炭火力で対抗するのは理の当然である。どうやら日本のメディアは西欧の理念だけに共鳴し、自国の産業が滅んでも平気のようだ。なぜ、文化まで欧米人の視点を意識するのか? 日本人が欧米人の目を気にする習性は、何も外交交渉に限ったわけではない。 五月二日(日本時間三日)、米国のドジャー・スタジアムで行われた球団主催のチャリティーイベントに大谷翔平選手と妻の真美子さんがそろって登場した。その場面をテレビで見ていて、ご存じの方も多いだろうが、真美子さんは大谷選手の一歩、二歩と下がり、後ろから遠巻きに眺めていた。その光景を見て、あなたはどんな印象をもっただろうか。 六日のTBSテレビの情報番組「ひるおび」でゲスト出演していた落語家の立川志らくさんは「日本女性の謙虚な所って、外国の人が見たらどう思うんですかね。何で夫人は後ろに下がってんだろ、って(思わないかな)」とコメントした。 女性が男性の後ろに立つという日本的光景をどう感じるかは、人それぞれが自身の人生観や価値観で判断すればよい話だ。なぜこの場面で「外国の人が見たら、どう思うだろうか」というおかしな発想が出てくるのだろうか。ここでいう外国人は欧米人であって、中国やインドのようなアジア人ではない。 夫婦関係も含め、日本の伝統文化を重んじた行動をとる日本人がいたところで何の不思議もない。日本人がいちいち欧米人の気に入るような行動をとったら、そのほうがむしろ異常である。立川氏のコメントを見ていて、やはり日本人には、欧米人の視点が正しく、日本人の伝統的な価値観は劣っているという深層心理のようなものがあるのではないかと感じた。 話を石炭火力に戻す。石炭火力が電力の多くを占める国と、ほぼ石炭火力のない国が同じエネルギー戦略を採用することはそもそも無理だ。今世界各国が目指している共通目標は、「二酸化炭素の削減」のはずである。目指すは石炭火力をどうするかではなく、二酸化炭素をどう減らすかである。であるならば、石炭火力を残しながらも、二酸化炭素を減らす技術(CCSやバイオマス利用も含む)を日本は堂々と進め、主張していけばよい。無責任なメディアの論調を気にしていては、日本の産業は本当に滅んでしまう。
- 17 May 2024
- COLUMN
-
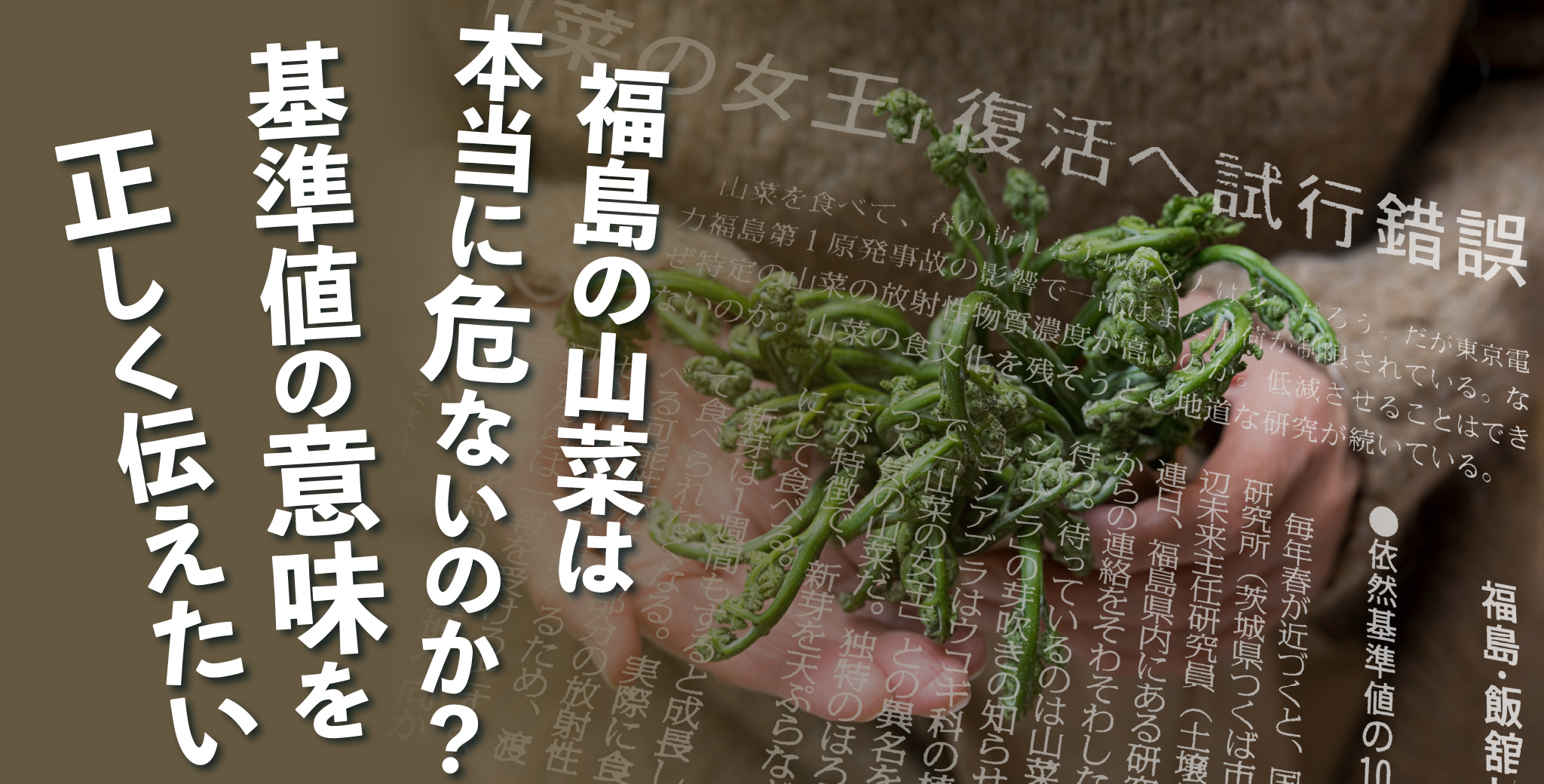
福島の山菜は本当に危ないのか? 基準値の意味を正しく伝えたい
二〇二四年三月二十五日 福島県内で採れる山菜を食べたら、本当に危ないのだろうか。毎日新聞が三月十二日付け朝刊で「『山菜の女王』復活へ試行錯誤 福島・飯舘村セシウム減らせ」と題した記事を載せた。基準値の意味を正確に伝えていないため、あたかも山菜を食べたら健康に影響があるかのような印象を与える、ミスリーディングな内容だ。では、記事のどこがおかしいのだろうか。コシアブラは依然として一〇八五ベクレル 記事を見てまず引っかかったのは、小見出しの「依然基準値の10倍」(写真1)だった。記事の骨子はこうだ。飯舘村が測定した山菜(ワラビ、ウド、フキなど)の放射性セシウムの濃度(二〇一四年~二〇二三年分)は二〇一一年の原発事故から低下しつつあるが、コシアブラだけは二〇二三年になっても、一キログラムあたり一〇八五ベクレル(二〇一四年は同二〇五五八ベクレル)を示し、基準値の十倍に上った。写真1 その理由は、森林の大部分が除染されていないため、多年生植物のコシアブラはセシウムの多い地表から十数センチのところに根をはり、しかもセシウムは根などに蓄積して植物体を循環するため、シーズンをまたいでも減りにくいのだという。そこで記事は「基準値を下回るにはさらに10年以上かかるだろう」という地元住民の言葉を載せた。 さらに、「山菜を塩水でゆでたあと、一時間、水に浸すとセシウムの量は調理前の三五~四五%程度に低減する」という方法を紹介している。 ちなみに、ベクレルは放射性物質が放射線を出す強さを表す単位で、一ベクレルは一秒間に一つの原子核が崩壊することを表す。セシウムの基準値は各国で異なる 放射性セシウムの現状を伝える記事自体に誤った記載があるわけではない。ただ全体を読んでいて誤解を与えかねないと感じたのは、一〇〇ベクレルという基準値にこだわるあまり、一〇〇ベクレルを超えた山菜を食べると健康に影響するかのような印象を与える点だ。 知っておきたいのは、基準値は健康影響をはかる指標値ではないということだ。そのことは各国の放射性セシウムの基準値を見ればすぐに分かる。図表1を見てほしい。日本の一般食品の基準値が一キログラムあたり一〇〇ベクレルなのに対し、EU(欧州連合)は一二五〇ベクレル、米国は一二〇〇ベクレル、コーデックス委員会(世界食糧機関と世界保健機関によって設置された国際的な政府間機関・百八十八か国加盟)は一〇〇〇ベクレルだ。 なんと欧米諸国の基準値は日本よりも十倍も緩い。記事は「コシアブラの一〇八五ベクレルは基準値の10倍」と書いたが、このコシアブラは欧米諸国では堂々と流通できる。確かに日本では一〇〇ベクレルを超えると出荷制限(販売禁止)がかかるが、欧米では基準値以下なのでそのまま流通するのだ。ということは、仮に欧米人が一〇八五ベクレルの山菜を食べても、健康に影響することはないことを意味する。 いうまでもなく、基準値の緩い(数値が高い)欧米の人たちがセシウムの影響を受けにくい体質をもっているわけではない。毒性は食べる「量」いかんで決まる もうひとつ押さえておきたいのは、基準値の一キログラムあたり一〇〇ベクレルという意味だ。これは一キログラムあたりの数値なので、一キログラムあたり一〇八五ベクレルのコシアブラの場合、十グラムしか食べなければ、体内に摂取されるセシウムはその百分の一の約10ベクレルで済む。逆に基準値以下のコシアブラでも、2~3キログラムも食べれば、体内摂取量は100ベクレルを超えてしまう。 この例でわかるように、基準値以下の食品でも大量に食べれば、基準値を超える。食べた人に健康影響が生じるかどうかは、食べる「量」によって左右され、基準値を超えたかどうかではない。つまり、一〇〇ベクレルという数値は、健康に影響するかどうかの指標ではなく、生産者に対して「出荷の際に気をつけてもらうためのシグナル」なのである。年間一ミリシーベルト以下が上限 では、健康影響をはかる指標値は何か。図表1の二段目にある「追加線量の上限設定値」の年間一ミリシーベルト(シーベルトは放射線が人体に及ぼす影響を表す単位)である。もちろん一ミリシーベルトを超える放射線を浴びたからといって健康影響が生じるわけではない(低線量による影響はいまも科学的な議論が続く)が、放射線の影響を管理する数値としては、年間一ミリシーベルトが世界的な標準管理値となっている(ただし米国は年間五ミリシーベルト)。 ここで強調したいのは、セシウムの基準値は各国の事情によって異なるが、健康影響の指標はほぼ同じという点である。欧米人も日本人も同じ人間なので、健康影響を測る数値が大きく異なるはずはない。一〇〇〇ベクレルの山菜を食べても影響はない では、仮に一キログラムあたり一〇〇ベクレルのセシウム(半減期が約三十年のセシウム137と仮定)が検出された山菜を一キログラム食べた場合、人体への影響(内部被ばく)はどれくらいになるだろうか。計算すると〇・〇〇一三ミリシーベルトである。一〇〇〇ベクレルのコシアブラを一キログラム食べた場合は、十倍の〇・〇一三ミリシーベルトとなる。仮に一〇〇〇ベクレルのコシアブラを一キログラム(そもそも一キロも食べる人はいないだろうが)食べても、一ミリシーベルトをはるかに下回り、健康への影響はないことが分かる。 EUの基準値が一二五〇ベクレルでも、西欧人の健康を守ることができるのはこれで分かるだろう。そもそも私たち日本人は自然界から年間約二ミリシーベルトの被ばくを受けながら生活をしている。それと比べても、山菜から摂取するセシウム量は極めて少ない。 実はこうした考え方は農薬も同じである。農薬の残留基準値は各国の気候や風土で異なるが、健康影響をはかる指標値の一日許容摂取量(ADI)は世界共通である。このあたりのからくりは、拙著「フェイクを見抜く」(ウエッジ)をお読みいただきたい。「安全・安心」のために一〇〇ベクレルを設定 では、なぜ日本は欧米よりも十倍も厳しい基準値を設定したのだろうか。福島第一事故後にセシウムの基準値がどのように決まっていったかを、私は現役(毎日新聞)の記者として当時、熱心に取材していた。そもそも事故が起きる前の一般食品の暫定基準値は、一キログラムあたり五〇〇ベクレルだった。厚生労働省や食品安全委員会などで活発な議論が行われたが、結局、「より一層、食品の安全と安心を確保する観点から」という理由で一〇〇ベクレルに決まった。 許容していた年間追加線量も、事故前は年間五ミリシーベルトだったが、一ミリシーベルトに引き下げられた。一〇〇ベクレルが導き出される計算式の裏には、日本国内の食品(流通する食品の半分と仮定)はすべてセシウムに汚染されているという非現実的な仮定があった。これに対し、EUの一二五〇ベクレルは、流通量の一割が汚染されているという現実的な条件で計算されている。当時は旧民主党政権。結局は政治的な思惑もあって、「安心」を重視した政治的な決着となったのだ。一九六〇年代はもっとリスクが高かった 原発事故から十三年もたつと、セシウムの基準値が政治的に決められていった経過を知る記者は、少なくなっている。毎日新聞の記事について言えば、一〇〇ベクレルは健康影響をはかる指標値ではなく、たとえ一〇八五ベクレルのコシアブラを一キログラム食べたとしても健康への影響はない、という解説を入れてほしかった。 今後、セシウムの影響を伝える場合は、中国などが核実験を行っていた一九六〇年代のほうがよほど健康へのリスクは高かったという事実を、記者たちは頭の片隅に刻んでおいてほしいものだ。福島第一原発の処理水の海洋放出は今のところ順調に進むが、魚介類からいつ何時一〇〇ベクレルを超えるセシウムが検出されるかもしれない。その際に冷静に「一〇〇ベクレルを超えても健康影響とは関係ない」と、記者たちがしっかりと書いてくれることを期待したい。
- 25 Mar 2024
- COLUMN
-
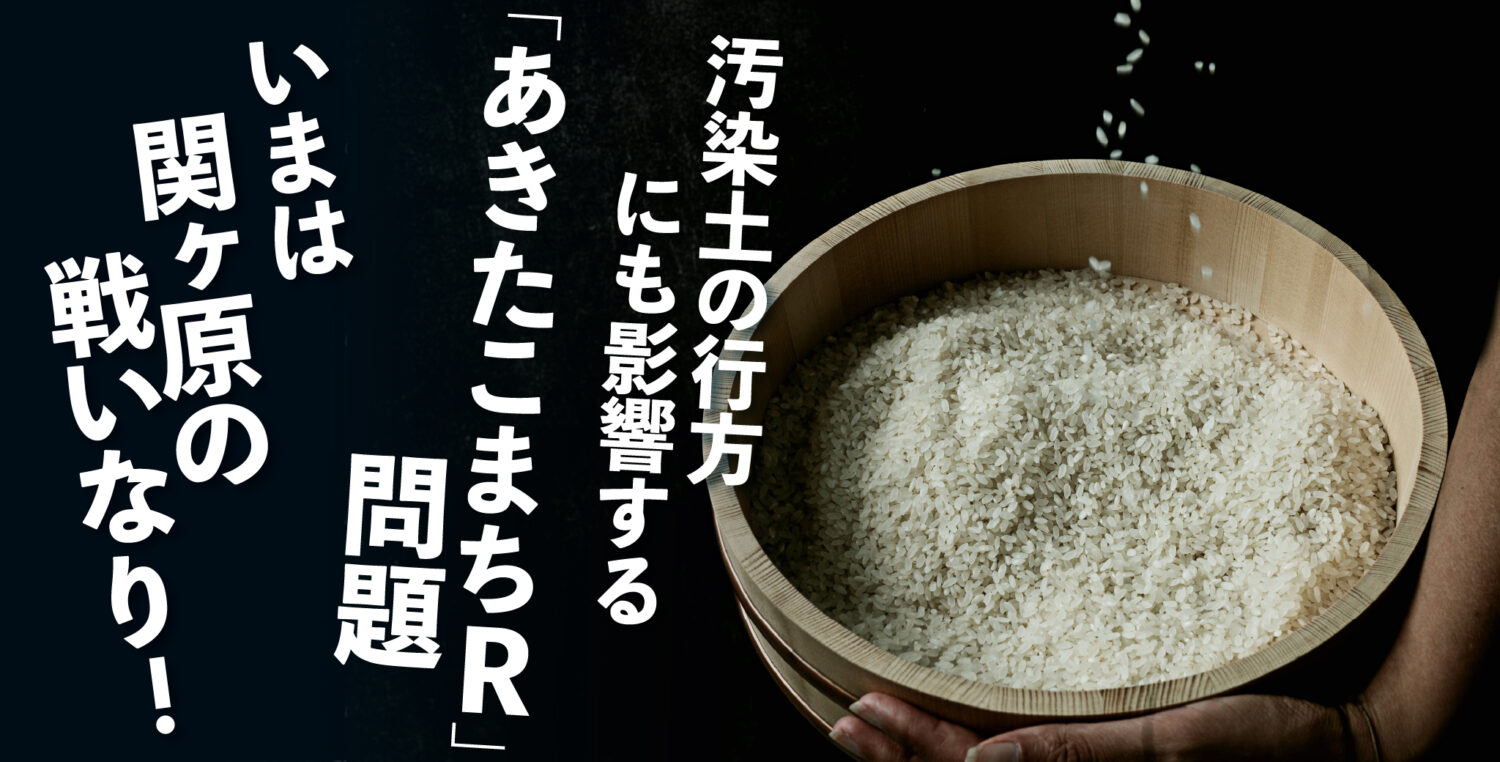
汚染土の行方にも影響する「あきたこまちR」問題 いまは関ヶ原の戦いなり!
二〇二三年十二月六日 今回も放射線育種米の「あきたこまちR」への反対運動にこだわる。この問題は福島第一原発事故後の除染で発生した汚染土の処理の行方にもからむ。「あきたこまちR」は科学的には全く問題がないのに、反対運動が起きている。ここでもし、このコメの普及が阻止されるような事態が起きれば、科学と政治の大敗北と言ってよいだろう。記者経験から見て理解不能な反対 単純なクイズを出そう。あなたは「発がん性物質のカドミウムがほとんど含まれていないコメ」と「カドミウムが多く含まれるコメ」のどちらを買いますか。 なぜ、こんなバカげた質問を出すのかといぶかる人もいるだろう。だれだって、カドミウムの含有量がほぼゼロのコメを選ぶはずだからだ。ところが、驚くべきことにカドミウムの多いコメを「消費者の権利」として支持する反対運動が起きている。毎日新聞社で約45年間、記者稼業を続けていたが、この「あきたこまちR」に反対する運動は、これまでに経験したことがない理解不能、そして摩訶不思議な領域に属する。 カドミウムは人の肝臓や腎臓などに蓄積する重金属である。国際がん研究機関(IARC)はヒトでの発がん性の証拠が十分にそろっているとするグループ1に分類している。体内への高い摂取量が長期間続けば、腎機能の低下など健康障害が生じるリスクもある。米国政府は、日本のコメはカドミウムとヒ素(発がん性物質)が多く含まれるため、乳幼児向けの摂取は制限するよう勧告しているほどだ。 日本人はカドミウムの約四~五割をコメから摂取している。それだけに、土壌中のカドミウムをほとんど吸収しない新品種「あきたこまちR」は、日本人のカドミウム摂取量を減らす画期的な品種なのである。カドミウムのリスクは意外に高い コメに含まれるカドミウムのリスクがどれくらいかを知れば、その画期的な点がさらにわかるはずだ。では、食品に含まれる残留農薬や食品添加物のリスクと比べてみよう。 ある化学物質の摂取量が健康に影響するかどうかは、実際の摂取量が健康影響の指標となる一日摂取許容量(ADI)をどれだけ下回っているかどうかで判断する。厚生労働省や内閣府食品安全委員会のサイトを見ればわかるように、食品に含まれる残留農薬や食品添加物の平均的な摂取量は、一日摂取許容量の百分の一~千分の一以下というのが普通だ。摂取量が許容量の百分の一以下(車の速度制限で言えば、六〇キロ制限の道路を〇・六キロで走るようなもの)なら、だれだって安全だと分かる。 では、カドミウムはどうか。カドミウムは意図して使う農薬や食品添加物と違い、許容量という言葉ではなく、耐容量という言葉を使うが、意味は同じだ。 食品安全委員会によると、健康影響の目安となるカドミウムの週間摂取耐容量(耐容週間摂取量ともいう。一週間あたりの摂取量がこれ以下なら安全だとみなされる目安)は、体重一キロあたり七マイクログラム(マイクロは百万分の一の単位)である。これに対し、日本人が平均的に摂取している一週間あたりの摂取量は体重一キロあたり約二マイクログラムだ。摂取量(約二マイクログラム)が耐容量(七マイクログラム)を下回っているため、コメを食べても確かに安全だといえる(食品安全委員会のリスク評価サイト参照)。しかし、食品中の残留農薬の摂取量が許容量の百分の一~千分の一以下というリスクと比べると、カドミウムのリスクは耐容量の三分の一程度なので、相対的なリスクはかなり高いといえる。だからこそ欧米は基準値を低く設定している。 このカドミウムのリスクを低くしてくれるのが「あきたこまちR」なのである。EUの基準値を楽々クリア 日本のコメのカドミウムの含有量が高いことは、カドミウムの基準値を決める国際会議でたびたび指摘されてきた。基準値の厳格化を求める欧米に対し、日本は肩身の狭い思いを味わってきたわけだ。現在、EU(欧州連合)のコメのカドミウムの基準値は〇・一五ppm(ppmは百万分の一の単位)だ。それに対し、日本は〇・四ppmと高い。日本がEU並みの〇・一五ppmを採用できないのは、それを受け入れると基準値を超えてしまうコメが出てくる可能性があるからだ。 しかし、「あきたこまちR」なら、EUの基準値を確実にクリアできる。カドミウムの含有量が〇・〇一ppm以下だからだ。カドミウムがほぼゼロであれば、今後は海外に輸出する活路も見えてくる。ついでに言えば、水管理が楽になり、地球温暖化の原因のひとつにもなっているメタンの発生量も少なくなる。であれば、秋田県が二〇二五年度から「あきたこまちR」に切り替えるのは当然であり、日本国民にとっても大歓迎すべきことである。アベプラでも俎上に このように、「あきたこまちR」を避ける理由は全く見当たらないが、今年九月、秋田県に約八〇〇〇筆の反対署名が届くなど反対運動が起きている。立憲民主党や社会民主党の一部国会議員も、東京の反対集会に顔を出し賛同している。日頃、食の安全を訴える国会議員がなぜ、カドミウムの高いコメを消費者に食べさせようとするのか理解に苦しむが、タイミングよく、この問題はインターネットテレビ局「ABEMA Prime」(アベプラ)で取り上げられ(十二月一日放送)、私はゲストとして出演した。 コメンテーターとして、経済学者の竹中平蔵氏や福島原発問題で独自の情報を発信するお笑いタレントのカンニング竹山氏ら四人が議論に加わった。四人とも「あきたこまちR」の画期的な品種性に納得し、反対運動に疑問を呈した。竹中氏は「何に対しても反対する人たちはいるなあ」とあきれた様子だった。 その番組で印象に残ったのは、カンニング竹山氏の「この問題は福島第一原発事故で発生した汚染土の再利用にも反対運動が起きて、行き場を失っているのと似ている」という内容の発言だった。確かにそうだと思う。「NEWSポストセブン」は名指しで反対運動を批判 いまのところ、メディアは「あきたこまちR」に批判的な姿勢を見せていない。小学館が運営するニュースサイトの「NEWSポストセブン」は日頃、食品添加物の危険性を煽る記事を載せているが、この「あきたこまちR」に関しては、極めて異例の記事を配信した。見出しは「カドミウム吸収を抑えた画期的なコメの新品種『あきたこまちR』 福島みずほ議員らの〝安全性への疑問〟は妥当なのか」(二〇二三年十一月二十七日・筆者はライターの清水典之氏)だった。国会議員を名指しして、反対運動に疑問を投げかける記事である。結びの内容はこうだった。 「長年の技術の蓄積、研究の成果である画期的な新品種に、風評被害や差別につながるようなレッテル貼りをする行為は、慎みたいものである」。 国家議員が風評被害に加担していると思わせる異例の記事である。やはりだれが見ても「あきたこまちR」は優等生なのである。科学の名において一丸となれ! 「NEWSポストセブン」にあるように、福島みずほ参議院議員は「消費者の権利を守りたい」とX(旧ツイッター)に投稿していた。確かに、「あきたこまちR」を食べたくない消費者もいるだろう。カドミウムの多い従来のコメを食べる権利も、権利には違いない。その選択は尊重したい。 ならば、その権利を他の消費者や生産者にも認めるべきだろう。なぜ、「あきたこまちR」を食べたいと思う私のような消費者の権利を反対運動によって阻止しようとするのだろうか。左派リベラルの人たちは日頃、多様性が大事だと主張する。しかし、その多様な選択を壊そうとしているのはどちらなのか。 気になるのは、秋田県内で「あきたこまちR」を栽培しようとする生産者に対しても、栽培をやめるよう抗議する運動があることだ。選択の権利は生産者の側にもあるはずだ。なぜ、外部の市民が生産者の栽培する権利を阻害するような圧力行為に出るのか。常軌を逸しているとしか思えない。ちなみに「あきたこまちR」の切り替えに反対する一部国会議員は福島の汚染土の再活用にも反対している。反対の根っこはいつも同じようだ。 結論。仮に「あきたこまちR」の普及が反対運動で滞るような事態が起きれば、科学と政治の大敗北である。だれが見ても画期的な「あきたこまちR」が阻止されるようでは汚染土の受け入れに未来はない。いずれ他のコメの品種にもカドミウム吸収抑制の特性が広がっていくことを考えると、「あきたこまちR」は秋田県だけの問題ではない。全省庁、全自治体が科学の名にかけて、「あきたこまちR」を守りぬくことが必要だ。いまはまさに関ヶ原の戦い(天下分け目の戦い)である。
- 06 Dec 2023
- COLUMN
-
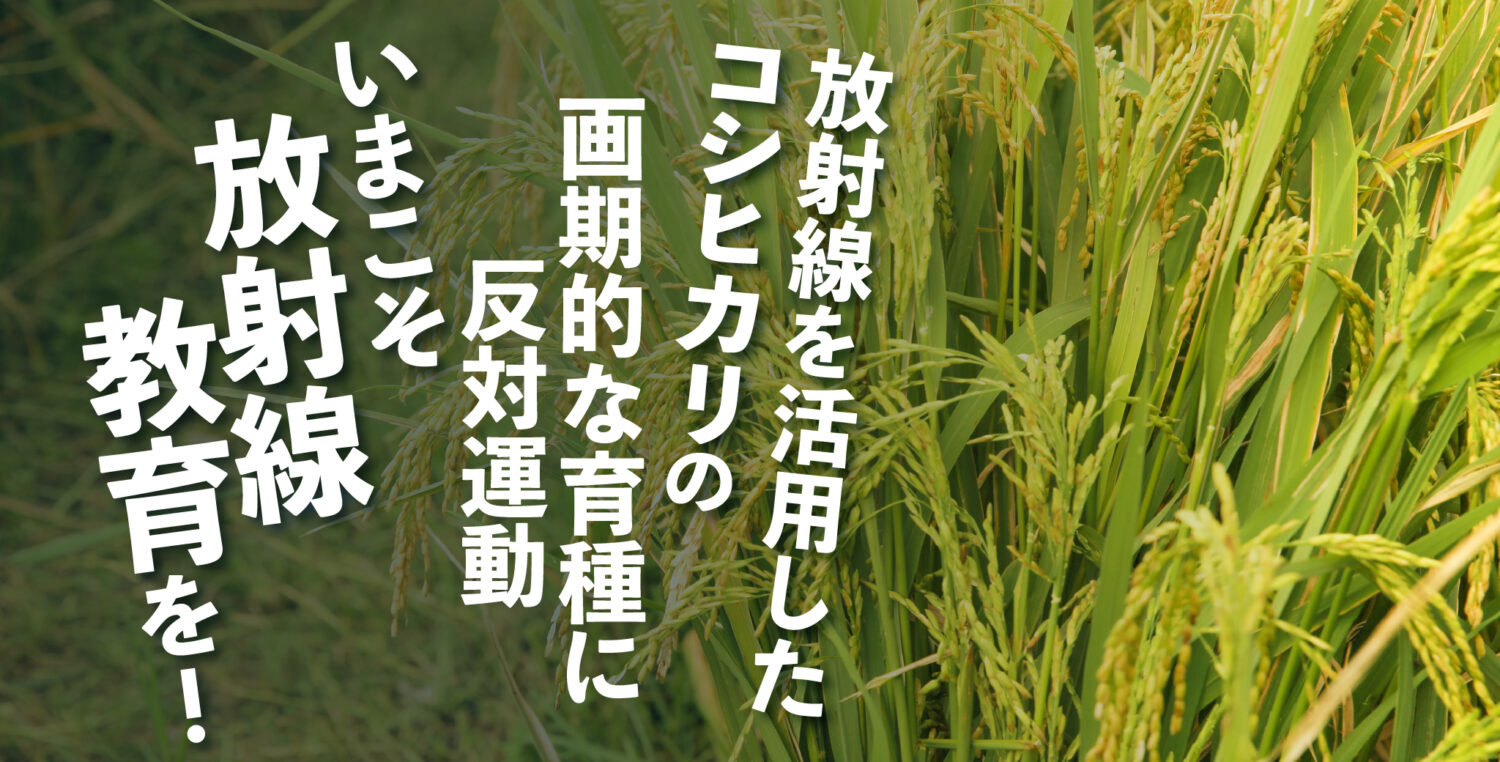
放射線を活用したコシヒカリの画期的な育種に反対運動 いまこそ放射線教育を!
二〇二三年十一月十六日 みなさんは「コシヒカリ環1号」という名の品種をご存じだろうか。人体に有害なカドミウムをほとんど吸収しない画期的なコメである。しかし、放射線を当てて育種したコメのためか、一部の生協や市民団体から反対運動が起きている。まさか、放射線を活用した育種にまで反対運動が起きるとは、予想もしていなかった。原子力関係者はこうした動きに無関心であってはいけない。イオンビームで画期的なコシヒカリが誕生 植物に放射線を照射して遺伝子に突然変異を作り出し、その中から有用な品種を選抜して育てていく品種改良は一九五〇年代から行われてきた。放射線(ガンマ線)を当てて生まれた、ナシ黒斑病に強い「ゴールド二十世紀」(一九九一年に品種登録)は、放射線育種の有用性を示す代表的な例である。 最近では、カドミウムをほとんど吸収しない画期的な稲の品種「コシヒカリ環1号」が生まれ、二〇一五年に品種登録された。農研機構農業環境研究部門の研究グループが開発した。なぜ、カドミウムを吸収しないコメが重要かと言えば、もともと日本のコメは他国に比べて、カドミウムが多く含まれる。鉱山の採掘や金属の製錬などでカドミウムが高濃度に含まれる土壌が各地にあるからだ。カドミウムが原因で起きたとされる富山県の神通川流域の「イタイイタイ病」はそうした弊害の典型的な例である。 意外に知られていないが、日本の主食のコメに含まれるカドミウムの濃度は、総じて他国よりも高い。そして、そのコメのリスクは、食べ物から時々検出される残留農薬のリスクよりも確実に高いことは、専門家の間でよく知られた事実である。 こうした背景を考えると、少しでもカドミウムの含有量の少ないコメが普及したら、日本人の健康度を上げることは間違いない。その意味で、農研機構の研究グループがコシヒカリの種子にイオンビーム(人工放射線の一種)を照射して突然変異を作り出し、その中からカドミウムをほとんど吸収しないコメを選抜育種したのは歴史的な快挙と言ってよい。 この画期的な品種は、照射によって、カドミウムの吸収にかかわる遺伝子(OsNRAMP5)が欠損して生み出された。植物の成長に必要なマンガンの吸収が低くなるという弱点(肥料としてマンガンを与えれば、この問題は解決される)はあるものの、すぐれた品種なのは間違いない。「あきたこまちR」も誕生 最近は、この「コシヒカリ環1号」と「あきたこまち」を交配させた「あきたこまちR」も生まれた。これは、カドミウムをほとんど含まない「あきたこまち」で、味、品質とも従来の「あきたこまち」と変わらない。すでに「あきたこまちR」は秋田県の奨励品種になり、二〇二四年度から種子生産が始まり、二〇二五年度から一般作付けが始まるという。 秋田県にはかつて鉱山があり、カドミウムの多い土壌が残る。実は、「コシヒカリ環1号」は秋田県出身の研究者が中心となって開発した。その意味でカドミウムのきわめて少ない「あきたこまちR」は秋田県民だけでなく、全国民待望のコメだと言ってよいだろう。秋田県が「あきたこまちR」に全面的に切り替えるのは極めて理にかなったことである。どう見ても、農業生産者、そして消費者にとって大きな朗報である。放射線育種に反対運動 ところが、悲しいことに、こういう素晴らしき品種改良に対しても反対運動が起きている。 秋田県が「あきたこまちR」を導入しようとしていることに対して、今年夏、秋田県で反対派による学習会がいくつかの地域で開かれた。他県でも「コシヒカリ環1号」の導入に対して、「自然派」と名のつく一部生協や市民団体が反対運動を始めた。十月三十一日には食品照射に反対する全国集会(主催・照射食品反対連絡会)が衆議院会館で行われ、立憲民主党の議員らが参加して気勢を上げた。 反対理由は①「自然界ではありえない致死量の重イオンビームを使って、人為的に遺伝子を破壊して生まれた品種は、従来の育種とは一線を画する。安全性の評価もない」②十年後、二十年後にどんな影響が起きるか予測できない③秋田県産のコメに対する風評被害が起きる──などだ。突然変異は自然界でも起きている 筆者から見れば、言いがかりとしかいいようのない反対である。そもそも植物の遺伝子の突然変異は、自然界において太陽の紫外線や宇宙線、大地からの放射線によっても生じている。放射線を人為的に当てて起こした突然変異も、自然界で起きている突然変異と何ら差はない。このことはほぼ科学者の共通認識だと以前から思っていた。反対運動が起きるとは夢にも思っていなかったが、筆者の認識は甘かったようだ。 いうまでもなく、植物の育種の最初の段階で一度だけ、致死量の放射線を当てたからといって、その種子から生まれてくる次世代以降の植物に放射線が残っているわけではない。後代の植物が放射線を出すこともない。食品照射は西欧でも認可 育種に限らず、食品に放射線を当てて殺菌する技術は世界50か国以上で認められている。英国、フランス、イタリア、オランダなどではタマネギやニンニク、ジャガイモ、シリアル類、冷凍エビなど幅広く照射されている。英国やドイツ、オランダなどでは健康食品類の約三割が照射されていたという調査結果があるくらいだ(「食品照射の海外の動向」等々力節子氏参照)。 もちろん、照射された食品や育種の最初の段階で放射線を用いた後代の植物が、健康被害をもたらしたというデータは存在しない。むしろ、カドミウムの含有量が極めて少ない「あきたこまちR」でいえば、カドミウムの残留基準値を厳しくしている海外への輸出も可能になり、販路拡大のチャンスにもなりうる。 放射線は人のがん治療でも大きく貢献している。人が全身に浴びれば致死的な量になるレベルの放射線を、がんの患部に当てて治す治療法まで行われていることを考えると、植物の育種の段階で放射線を活用する照射に対して、なぜ反対運動が起きるのか不思議でしようがない。植物への照射と人への影響は全く無関係である。放射線利用のジャガイモ供給が終了 ただ残念なのは、世界では常識となっている食品への照射が、日本では食品衛生法によって原則として禁止されていることである。その中で例外的に、一九七四年から北海道の士幌町アイソトープ照射センターで、ガンマ線を利用した芽止めジャガイモが出荷されてきたが、昨年で使命を終え、((運用開始から五十年を経過し、老朽化のため今年三月に閉鎖された。建て替えも検討されたが、昨今の建設費高騰や、線源であるコバルト60のコスト高の影響等で採算が見込めず、見送られた。))施設の解体が始まった。このジャガイモに対しても、市民団体は「反対運動の勝利」と自らの活動をたたえている。 原子力の平和利用は、エネルギーだけではない。放射線を用いた育種や食品照射も重要な貢献分野である。ジャガイモの放射線利用がなくなったことで、日本での食品照射はなくなった。かつて海外並みに日本の香辛料にも照射を認めてほしいという事業者の活動もあったが、反対運動によって頓挫した。こんなことで本当によいのだろうか。小学生から放射線教育を 日本は遺伝子組み換え作物を大量に海外から輸入しながら、自国ではだれ一人として栽培していない。いや栽培できない。反対運動があって、栽培できないからだ。これと似たことが食品照射でも起きていると言ってよいだろう。そして今度は、放射線を利用した育種にも反対運動が襲いかかる。 放射線育種に反対している人たちは、原子力発電だけでなく、遺伝子組み換えやゲノム編集食品にも反対している。このままだと日本では新しいテクノロジーの芽が生まれないのではないか。そんな危機感を痛烈に覚える。原子力に関係する人たちは、エネルギーとしての原子力だけに関心を持つのではなく、放射線育種や遺伝子組み換え技術にももっと関心を持つべきだろう。いわずもがなだが、しっかりとした放射線教育が小学校の段階から必要だとつくづく感じる。士幌町のアイソトープ照射センター
- 16 Nov 2023
- COLUMN
-
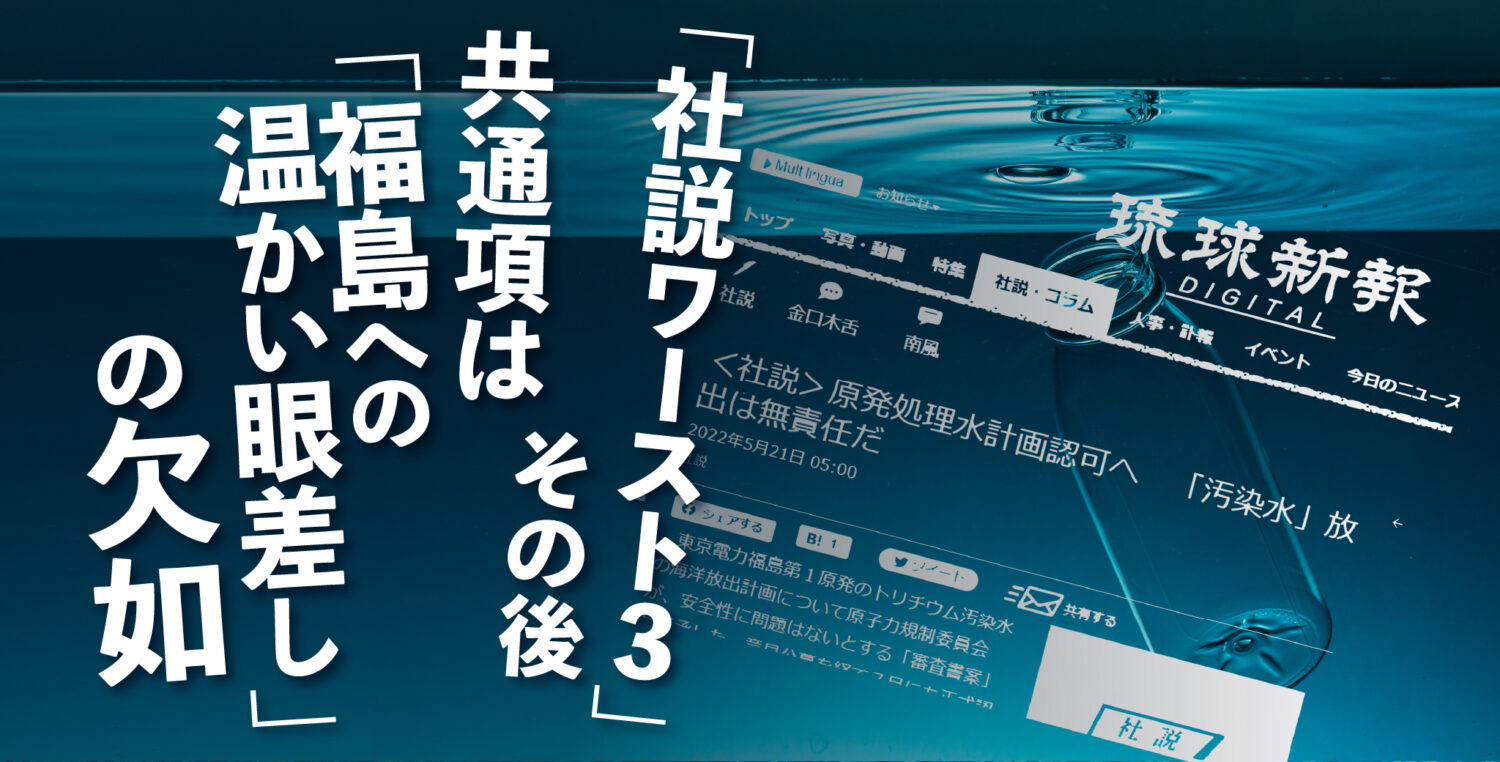
「社説ワースト3」その後 共通項は「福島への温かい眼差し」の欠如
二〇二三年九月二十七日 福島第一原子力発電所の処理水の一回目の海洋放出が無事終わり、近く二回目の放出が始まる。懸念された国内の風評被害はいまのところ、起きていない。だが、安心は禁物だ。メディアが風評に加担する恐れがあるからだ。以前に書いた「地方紙の社説ワースト3」は、その後、どう変わったのだろうか。いまなお「汚染水」にこだわり このコラムで今年一月、地方紙の社説を取り上げた。ワースト1は琉球新報の社説(二〇二二年五月二十一日)だった。当時、琉球新報は「『汚染水』放出は無責任だ」と主張し、「汚染水」という言葉を使っていた。それから一年余りたった今年七月四日の社説の見出しは「原発『処理水』放出迫る 強行は重大な人権侵害だ」だった。「汚染水」から「処理水」に変わっていた。しかし、中身を読むと処理水という言葉について、「『希釈した汚染水』というのが妥当ではないか」となおも汚染水という言葉にこだわりを見せていた。 さらに、「中国政府の『日本は汚染水が安全で無害であることを証明していない』という批判を否定できるだろうか」と書き、中国政府の心情をくみ取った形で「汚染水」という言葉を使った。やはり何としても「汚染水」と言いたい心情が伝わってくる。 そして、放出が翌日に迫る八月二十三日の社説では、中国の輸入禁止措置にも触れ、「放出開始前の対抗措置は強硬な手段だが、それだけ懸念が根強いのだろう」と書き、ここでも中国の心情に寄り沿うかのような内容だ。さらに「いくら安全だと説明されても、放射性物質が及ぼす影響への恐れは簡単に払拭されない」と書き、海洋放出に納得できない心境を吐露する。 この八月二十三日の社説には、さすがに「汚染水」という言葉は出てこない。ここへ来て「汚染水」という言葉を使い続けると世論の反感を買うと考えたのだろうと推測する。「トリチウムが残る限り汚染水である」と言っていた昨年五月二十一日の社説に比べると、言葉の上では改善された跡が見られるが、社説の論調自体は依然として、海洋放出によって魚介類に影響があるかのようなニュアンスを伝えている。立憲民主党の一部議員と通底 中國新聞はどうか。昨年七月二十四日の社説では「処理水に含まれる放射性物質トリチウムなどが健康被害をもたらす可能性は否定できない。…政府は『原発の排水にも含まれている物質』と危険性の低さを強調するが、体内に蓄積される内部被曝(ひばく)の影響まで否定できるものではない」と書いていた。まるで内部被ばくが起きるかのような論調だ。 一年余りたった今年八月二十三日の社説では、内部被ばくという言葉は出てこないが、相変わらず漁業者の反対を楯に「このまま放出に踏み切れば、将来に禍根を残す」と手厳しい。そして、「約千基のタンクが廃炉作業の妨げになっているのは確かだ」と言いつつも、「政府もIAEAも『国内外の原発の排水にも含まれる物質』と説明するが、通常運転の原発の排水と、デブリに触れた水では比較になるまい。トリチウム以外の放射性物質も完全に取り除けるわけではない」とやはり放射性物質の影響があるかのような主張だ。 「比較になるまい」という突き放した言い方がとてもひっかかる。この言葉から類推すると、中國新聞は「事故を起こした日本の処理水は海外の処理水に比べて危ない」と言いたいことが分かる。立憲民主党の一部議員は「海外の処理水と日本の処理水は異なる」という理由で「汚染水」という言葉を使い続けている。中國新聞は汚染水という言葉こそ使っていないものの、立憲民主党の一部議員と相通じる思考をもっていることが分かる。説明責任はメディアの側にある 中國新聞は九月四日の社説でも処理水問題を取り上げた。「処理水を巡っては、国際原子力機関(IAEA)が「国際的な安全基準に合致している」と評価したと殊更に強調するだけでは、好転しない。トリチウム以外の放射性物質も含まれる点や、その長期的な影響など、重ねて検討が必要な要素は多い。海洋放出が妥当なのかを検証しつつ、責任を持って説明を続ける姿勢が日本政府には求められる」と書く。処理水という言葉を使っているものの、長期的には処理水の影響が人や環境に及ぶかのような内容だ。 海洋放出が妥当かどうかはすでに政府内で検証され、政府は幾度も海洋放出の妥当性に関する説明を行ってきた。いまこの時点で中國新聞が「海洋放出が妥当ではない」と主張したいならば、その根拠を示す説明責任は中國新聞の側にある。海洋放出を批判する論説があってもよいだろう。だがそれを書くからには、どのような長期的な影響があるかについて科学的なデータを示しながら、詳しい情報を示してほしいものだ。「さすが中國新聞は違う」と科学者を唸らせるくらいの重厚な社説なら大歓迎である。 しかし、ただ脅すような言葉を並べているだけの主張では、福島産の魚介類に悪いイメージ、つまり風評被害をもたらすだけだ。海洋放出は社会的合意の問題 佐賀新聞はどうか。昨年七月二十三日の社説では、処理水について「トリチウムなど取り切れない放射性物質が含まれる汚染物質であることに変わりはない」と書き、さらに「海洋放出に関してより重要なのは、これらの科学的、工学的な評価ではなく、社会的な合意という問題だ。東電は『地元の合意なしには放出はしない』としている…」と書いていた。 約一年たった今年八月二十三日の社説では、昨年の「地元の合意なしには放出はしない」という部分が「関係者の理解なしには、いかなる処分も行わず…」となり、誤りだった「合意」は正しい「理解」という言葉に訂正されていた。ただ、どの読者もそうした知らぬ間の訂正に気づいていないだろうと思う。筆者は昨年と同じ共同通信の論説委員だ。 今回の社説は東京電力と政府への批判が大半を占めた。「…詳細な科学的、技術的な議論もないまま、三百四十五億円もの国費を投じて建設された凍土壁の効果も限定的だ。今回、過去の約束をほごにせざるを得なくなった最大の原因は、政府や東電が長期的なビジョンなしに、このようなその場しのぎの言説と弥縫(びほう)策を繰り返すという愚策を続けてきたことにある。…被災者の声を無視した今回のような事態を目にし、復興や廃炉を進める中で今後なされる政府や東電の主張や約束を誰が信じるだろうか。首相は今回の決断が将来に残す禍根の大きさを思い知るべきだ」。 海洋放出の問題は社会的合意の問題だとして、政府や東京電力の姿勢を批判するのはよいとしても、問題が科学的な評価ではないというならば、海洋放出に反対ではあっても、「福島産の魚介類に風評を起こしてはいけない。食べて応援しよう」くらいの一文があってもよさそうだが、この社説からは福島への温かい心情が全く伝わってこない。 不思議なことに同じ佐賀新聞でも、九月八日の社説は同じ処理水を論じていながら、論調はかなり違っていた。日本からの水産物の全面輸入禁止措置をとった中国に対して、「今回の中国の措置は、科学的根拠を欠き、貿易によって圧力をかける「経済的威圧」で、責任ある大国にふさわしい振る舞いにほど遠い。日本側が即時撤回を要求したのは当然だ。交流サイト(SNS)をきっかけに、中国から日本への嫌がらせ電話が殺到したのも常軌を逸しており、それを抑えようとしなかった中国指導部の姿勢も合わせ〝嫌中感情〟が増幅した…」と書いた。最後の筆者名を見ると、先に紹介した2つ(昨年七月二十三日と今年八月二十三日)の社説とは異なる記者だと分かった。同じ共同通信でも筆者が違うと、こうも論調が違うのかと驚くばかりだ。福島への温かい眼差しが見えない 今年一月のコラムでも書いたように、地方紙はおしなべて海洋放出に批判的なトーンが目立つ。北海道新聞は社説(八月二十六日)で「政府は風評被害で水産物需要が落ち込んだ際に、漁業者団体の一時的買い取りや冷凍保管を基金から全国的に支援するという。これでは問題の先送りだ。食卓に並ぶ見込みもつかぬまま金だけ渡すやり方は漁業者の誇りを傷つけよう。人材難に拍車がかかり水産業を衰退させかねない」と書いた。 政府はお金だけを渡すやり方をしているわけではない。各地でさまざまな支援イベントを行い、福島産などの水産物が食卓に並ぶよう努めている。北海道新聞の社説はどう見ても傍観者的である。水産業の衰退が心配なら、新聞社自らが支援キャンペーンをはって、漁業者が誇りをもてるようにすることのほうが大事なのではないだろうか。 地方紙の社説の多くを読んでいて常に感じるのは、すべての責任は政府や東京電力にあり、自分たち(メディア)は関係ないといった傍観者的な立ち位置だ。海洋放出に関して、「汚染」と書けば、結果的に「福島の海は汚染され、そこの水産物は危ない」という差別的なメッセージを送ることになるという想像力が足りないように思う。福島に自分の家族や友人・知人が住んでいたら、軽々に「汚染」と口にするだろうか。結局のところ、福島への温かい眼差しが足りないのだ。これが地方紙の多くの社説に見る最大の問題点だと悟った。
- 27 Sep 2023
- COLUMN
-
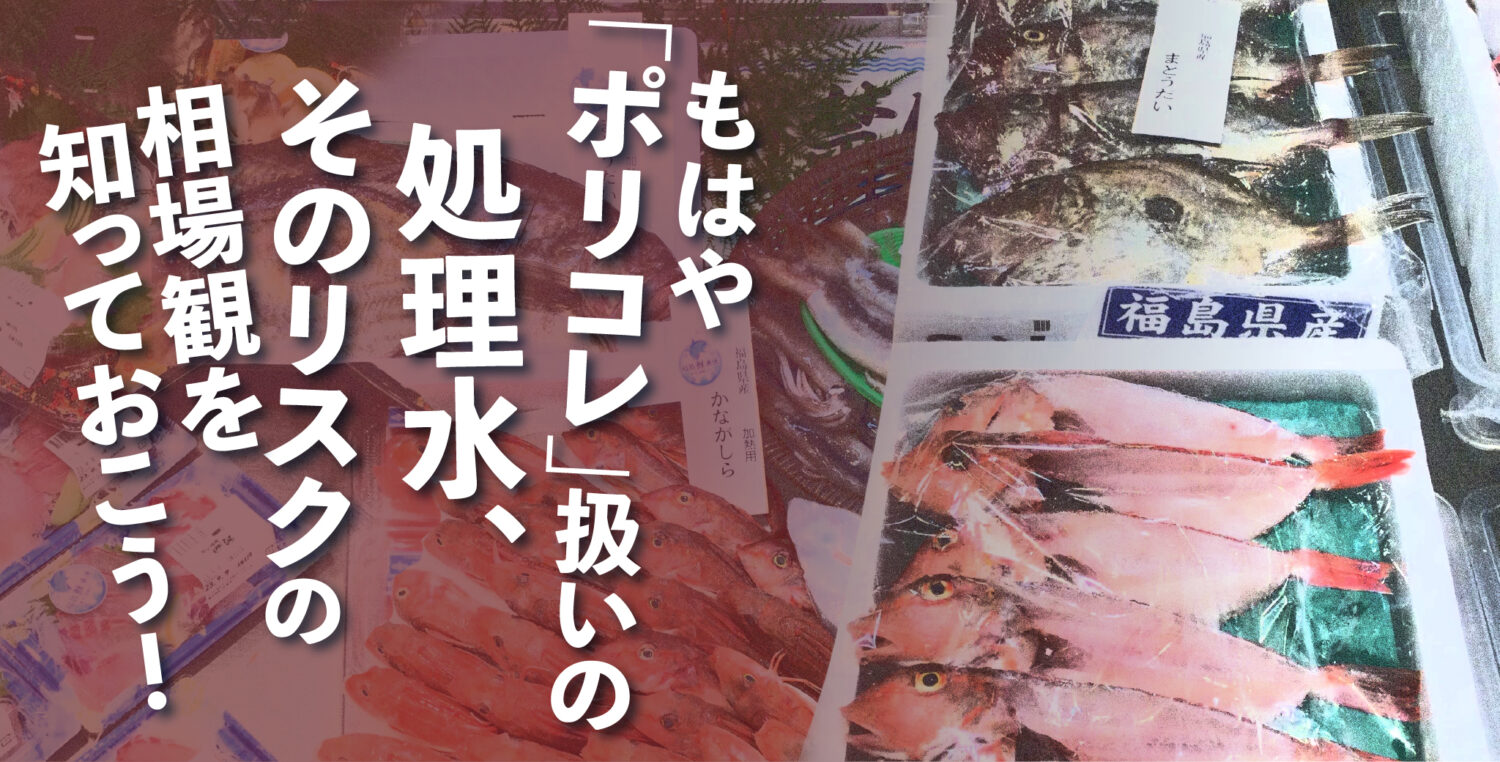
もはや「ポリコレ」扱いの処理水、そのリスクの相場観を知っておこう!
二〇二三年九月十三日 「処理水」か「汚染水」かをめぐって、政治の世界で争いが起きているようだが、この件は立憲民主党代表の一声で決着がついたといえよう。これからは、処理水の海洋放出によるトリチウムのリスクをいかに分かりやすく伝えていくかが課題だ。新聞ではあまり報じられていないリスクの相場観を考えてみたい。泉氏の発言は歴史的な転換点 八月二十四日、福島第一サイト内のタンクに貯蔵されている処理水の海洋放出が始まった。その一連の報道で一番注目したのは、野村哲郎農相(当時)が八月三十一日に「汚染水」と失言したことへの野党の反応だった。立憲民主党の泉健太代表は九月一日の会見で「不適切。今、放出されているものは処理水だ。所管大臣として気が抜けた対応で資質が感じられない」(産経新聞など参照)と批判した。 いつものことながら、岸田政権を批判する狙いで言ったのだろうが、「大臣としての資質が感じられない」という言い方を聞いて、とっさに同じ立憲民主党の中で堂々と「汚染水」と呼んで反対デモを行っている議員の姿が思い浮かんだ。 同じ政党にいる仲間よりも先に与党の大臣に向かって、「汚染水ではない。処理水でしょう」と詰め寄った意義はとてつもなく大きい。個人的には、この泉氏の発言は処理水報道の歴史に残る大転換点だとみている。 敵方の与党大臣に向かって、「資質が感じられない」と言った以上は、「汚染水」と呼んでいる仲間に対しても「あなたたちは議員の資質が感じられない」と言わねば帳尻が合わない。おそらく泉氏は、韓国の野党と一緒になって、処理水の海洋放出に反対するデモに加わっている一部議員に対しても、暗に「資質が感じられない」と内心では思っていたのだろうと勝手に空想をふくらませた(もっとも一部議員から見れば、泉氏の発言のほうが失言だと思ったかもしれないが)。 野村農相の失言に対して、中国政府は「事実だから」と擁護した。だが、さすがに社説で海洋放出反対を書いた主要な新聞でさえも、「野村農相の発言は事実なのだから、謝罪する必要はない。汚染水と呼んでいる一部議員のほうが正しいのだから、泉氏の批判は的外れだ」といった論陣を張ったケースは見られなかった。主要新聞は泉氏と同じく「処理水」に同意したわけだ。 政府を批判する立場の最大野党の立憲民主党代表が「処理水だ」と断言(お墨付きを与えた)してくれたおかげで、もはや「処理水」は最近のはやり言葉で言えば、良い意味でポリティカル・コレクトネス(直訳すると政治的正しさ=ポリコレ)並みに昇格したと言ってよいだろう。九月八日に開かれた衆参両院の閉会中審査で野村農相が再度、謝罪した際に野党から追及がなかったことを見ても、もはやポリコレ確定となったようだ。 泉氏の発言は、野村農相の失言がなかったならば、聞けなかった可能性が高い。その意味では野村農相の失言は、泉氏の歴史的な発言を引き出した点において、偉大なる怪我の功名といえよう。 泉氏の発言とそれを批判しなかった主要新聞のおかげで今後、言論と政治の世界では「処理水」は確たる言葉として流布していくだろうと予測する。トリチウムは核実験で一九六二年がピーク とはいえ、メディアに身を置く私としては、一部議員や記者、市民が「汚染水」だと公言すること自体は言論の自由があり、認めたい。発言まで禁止したら、それこそ自由のない、どこかの独裁国家と同じ三流国家になってしまう。大事なのは、汚染水だといっている人たちの言動に煽られないことだ。 では、海洋放出に伴うトリチウムのリスクを分かりやすく伝える方法はあるのだろうか。ここで大事なのは、リスクのおおよその大きさをイメージできる「リスクの相場観」をもつことである。 そこで紹介したいのが、二枚の図だ。ひとつは、環境省がホームページの「第2章 放射線による被ばく 身の回りの放射線」という解説欄に載せている「トリチウムの放射性降下物の経時的推移」と記された図だ(図1)。これを見ると、中国などが核実験を盛んにやっていた一九五〇年代~六〇年代には、いまとは比べものにならないくらいに、トリチウムを含む放射性降下物が地球全体に降り注いでいたことが分かる。トリチウムによる個人の平均被ばく線量がピークに達したのは一九六二年で、その量は七・二マイクロシーベルトに達していた。当時は、放射性セシウムやストロンチウムなども環境中に放出されていた。 一九六二年と言えば、東京オリンピックが開かれる二年前だ。愛知県犬山市に住んでいた私は小学五年生だった。学校の先生や親から「雨に当たらないように。髪の毛が抜けるから」と言われていたのを思い出す。当時はトリチウムが雨に混じって落ちていたのだ。現に一九六三年には、降水中のトリチウムの濃度が一リットルあたり百ベクレルを超えていた(日本原子力学会誌「アトモス」Vol.60など参照)。また、私たちはいまよりも濃度の高いトリチウムが含まれた飲み水を飲んでいたのだ。 その後、個人の被ばく線量は少なくなり、一九九九年になって、ようやくピーク時の七百分の一の〇・〇一マイクロシーベルトに下がった。つまり、私のケースで言えば、生まれてから高校を卒業(一九七〇年)するまで、いまよりもはるかに多いトリチウムにさらされていたということだ。核実験でも悪影響はなかったようだ では、一九六二年のピーク時に浴びていた七・二マイクロシーベルトとは、どれくらいの大きさだったのだろうか。資源エネルギー庁によると、福島第一の処理水が海に放出されたあとの被ばく線量は、多めに見積もっても、おおよそ〇・〇二マイクロシーベルト(〇・〇〇〇〇二ミリシーベルト)と推計されている。私が子供のころに浴びた七・二マイクロシーベルトは、その約三六〇倍にあたる。 ちなみに、〇・〇二マイクロシーベルトは、私たち日本人が自然界で浴びている自然放射線(宇宙線やラドン、大地、食物など)からの被ばく量(約二・一ミリシーベルト)のおおよそ十万分の一前後に過ぎない。処理水放出によるトリチウムのリスクがいかに小さいかが分かるだろう。 核実験で降り注いだトリチウムの影響について、環境省は同ホームページ(二〇二一年三月三十一日更新)で次のように解説している。 「トリチウムの公衆被ばくの影響に関して、これまでの疫学研究からは、トリチウム特有のリスクは確認されていません。また、一九六〇年代前半の核実験が盛んな時期以降においても、小児白血病の増加が認められていないことより、トリチウムの健康リスクが過小評価されている可能性は低いとされています」。 核実験の影響をもろに受けた私は幸いながら、新聞社を退職(二〇一八年)するまで健康を害することもなく、仕事を全うすることができた。「当時のトリチウム濃度が高かったのだから、いまの程度なら我慢すべきだ」と受忍論を主張しているのではない。海洋放出後のトリチウムのリスクを知る上で、過去の状況を知ることは、リスクの相場観を持つのに役立つのだということだ。イオンの自主基準は七千ベクレル もうひとつの図は、流通最大手イオンが公表している図だ(図2)。「福島鮮魚便」と称して、福島県内で水揚げされたヒラメなどを積極的に販売しているイオンは八月下旬、「これからも福島県産水産物を応援してまいります」とコメントしたうえで、トリチウムの自主検査を実施して、その結果をサイト上で公開すると公表した。 注目したいのは、国際的な基準よりも厳しい「自主基準」を設定した点だ。その自主基準を超えた場合には販売を見合わせるという。 イオン独自の自主基準値は、一リットルあた七千ベクレルである。世界保健機関(WHO)の飲料水に関する一リットルあたり一万ベクレルよりも低い。魚に含まれる水分をどのように測定して検査するかまでは分からないが、イオンのホームページによると、仮に七千ベクレルを毎日摂取し続けたとしても、国際的に安全管理目安とされる年間 一ミリシーベルト(追加被ばく線量)の十分の一になるよう設定したという。つまり、イオンの自主基準はより安全サイドに立った数値といえる。公開された図では、国際的な基準値と自主基準値と魚介類のトリチウム濃度の数値が視覚的に分かる。 これまでに福島県沖で検査された魚介類のトリチウム濃度はいずれも検出限界(百ベクレル)以下である。食品に関するトリチウムの公的な基準値はない。イオンが自主基準を設定して安全な魚介類を提供することは、消費者に安心感を与える上でもその意義は大きい。 東京電力は処理水に含まれるトリチウムの濃度を一リットルあたり千五百ベクレル未満で放出している。イオンの自主基準と比べても低いことが分かる。これもリスクの相場観を知る上で参考になるのではないか。
- 13 Sep 2023
- COLUMN
-

中国の理不尽な全面禁輸措置で「風評被害」の風向きが変わり始めた
二〇二三年九月一日 福島第一原発の処理水の海洋放出が八月二十四日、始まった。どの新聞を見ても、大きな懸念は「風評被害」だった。だが、中国が日本からの水産物輸入を全面的に禁止したことで、風向きが変わってきた。その後のテレビを中心とする報道を見る限り、今後の課題は国内の風評被害というよりも、いかに日本の国民が福島および国内産の水産物を買い支える連帯精神を発揮できるかどうかにかかってきたようだ。テレビのバラエティ番組が風評被害の抑制に貢献 毎週日曜日午前に放送されるTBSのジャーナリズム・バラエティ番組「サンデージャポン」(八月二十七日)を見ていて驚いた。風評を抑えようとする意図がはっきりと見えた番組構成だったからだ。日本からの水産物輸入を全面禁止した中国に対して、日本よりもはるかに多くのトリチウム量を放出している中国の原子力発電所の地図(フリップ)を見せたのだ。ゲストのタレント女性は「中国が日本よりも多くのトリチウムを放出していることを初めて知った。こういう情報をみんなが知ればよいのに」といった内容のコメントを寄せた。 さらに、同番組に専門家として出演した小山良太・福島大学教授は「通常の原子力発電所や再処理工場でもトリチウムは放出されている。これはあまり報じられてこなかったが」と話し、福島だけが特別ではなことを強調していた。 驚きは続いた。実業家の堀江貴文氏が自身のYouTubeチャンネルで、「アホが大騒ぎしている。こいつら本当に頭が悪すぎて、薄めるっていう概念が理解でないみたい。…お前ら中学からやり直せ。化学の教科書を読め…」と、内外の海洋放出批判を一喝する映像を公開したのだ。同映像は「サンデージャポン」の中でも紹介された。個人的な印象だが、堀江氏が怒りをあらわにしてまで、処理水の安全性に問題はないと訴える姿は、風評を打ち消す効果がかなりあると感じている。堀江氏があそこまで怒るからには、自身の意見に相当の自信があってのことだろう。この堀江氏の映像はエンタメ系やスポーツ新聞系のネットニュース(写真参照)でも紹介された。この威力は無視できないほど大きいだろう。 週明けて、八月二十八日に放映されたTBSの「ひるおび」でも処理水問題が特集として取り上げられた。番組全体のトーンは、中国が科学的根拠を無視して、無理難題を押し付けてくるという印象を伝えたように思う。ゲストの若い女性が「処理水(トリチウムの濃度)が国際基準を下回っていることはIAEA(国際原子力機関)も認めている。国際基準を守っているのに、なぜ中国はここまで批判してくるのか」といった内容のコメントを話した。 聞いていて、「中国だって、トリチウムを海へ放出しているのに、日本に文句をいう資格はないよね」といったメッセージに聞こえた。そこまで中国が文句をつけるなら、中国に依存せずに日本国内で水産物を消費すればよい。そんな気持ちを生じさせる番組だった。 これらの放送は、専門知識のない一般視聴者に対して「処理水は心配なさそうだ」という十分なメッセージを送ったのではないか。中国の強硬措置で連帯心喚起か? 風評被害は一般に、国内の大手スーパーなどによる「福島産の魚介類を販売しない」といった具体的なアクションと、それに同調するメディアと、消費者の連鎖が重なって生じる。ところが今回は、新聞やテレビ報道を見ている限り、そのような動きは一切出ていない。逆に、中国の理不尽な輸入禁止措置がオモテに出てきたことで、「負けてなるものか!」と、団結心を呼び起こすような声が強い。 現に、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏はフジテレビ『日曜報道THE PRIME』(八月二十七日)で、強硬な中国に対して「武力を使わない、ある意味、中国との戦(いくさ)ですよ。いままで日本は、こういうときに黙っていたけど、ここは絶対に勝たないといけない」と持論を述べた。橋下氏は、「僕、ホタテ大好きなんで、食べますよ。国民のみなさん、朝昼晩、必ずホタテをひとつ食べるとか、給食で使うとか」とも述べている。これを機に食料安全保障を強化することも可能だという見解はSNSで賛同が多かったようだ。 今回の中国の強硬措置で多くの日本人は、橋下氏と似た気持ちになびいたはずだ。何を隠そう、私も同様の気持ちを抱いた。 いまこそ日本は連帯心を発揮すべきだといったトーンは、八月二十八日夜に放映されたNHKの「クローズアップ現代」の処理水特集でも見られた。桑子真帆キャスターの「今後、日本はどうすればよいか?」との問いに対して、開沼博・東京大学大学院情報学環准教授は「中国への水産物の輸出額は千六百~千七百億円なので、国民一人が福島産の魚介類を一年間で千六百~千七百円、余分に買えばよい」と提案した。 この極めて分かりやすい具体的な提案を聞き、「そうだ。その通りだ!」と拍手喝采を送りたい気持ちになった。新聞はもっとこういう具体的な提言を盛り込んだ記事を、どしどし載せるべきだと感じた。 福島への応援を呼び掛ける訴えは、八月二十六日に放映された読売テレビの報道番組「ウェークアップ!」でも見られた。キャスターの野村修也・中央大学法科大学院教授は中国の禁輸措置を念頭に「いまこそ福島産魚介類を対象に、Go To Eat キャンペーンをやるべきだ」と提唱した。全くその通りだ。 岸田首相はいますぐ、「福島産魚介類を対象に大々的に『Go To Eat キャンペーン』をやります。みなさんの力で福島の復興を支えましょう」と強烈なメッセージを発信すべきだろう。その力強いリーダーぶりを見せれば、支持率も上がるだろう。朝日新聞や毎日新聞も 新聞は相変わらず、これまで述べてきた通り、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞の三陣営と読売新聞、産経新聞の二陣営に分かれ、前者の陣営は放出反対を訴える漁業者の声を大きく取り上げている。しかし、中国の傍若無人ぶりが見えてきたことで様相は少し変わってきた感じがする。 朝日新聞は八月二十五日付朝刊で、処理水放出に反対する漁師や市民団体の動きとともに、風評被害を防ごうとする企業の活動についても、三つの事例を二段見出しで紹介した。これまではあまり見かけなかった記事だ。 毎日新聞の社説(八月二十六日)は、中国が水産物を全面禁輸したことに、明確に反対する主張を載せた。その理由が面白い。「トリチウムを含む水は、中国など各国の原子力施設から海や河川に放出されている」と書いた。中国がトリチウム水を放出していることをもっと以前から大々的に書いてほしかったが、さすがに中国の身勝手な振る舞いがここまでくると「中国もトリチウムを放出しているじゃないか」と言いたくなるのだろう。そして、同社説は「国際原子力機関(IAEA)は包括報告書で国際的な基準に合致すると処理水の安全性にお墨付きを与えている。日本政府は専門家による協議を呼びかけてきたが、中国は拒んできた」と書いた。一般的に新聞は「お墨付き」という言葉を否定的かつ皮肉っぽく解釈して記事を書く習性がある。ところが、中国の理不尽さに対抗するための武器として、この社説ではIAEAのお墨付きという言葉を肯定的にとらえている。 やはり中国の全面禁輸措置は日本人の連帯心に火をつけたのではないか? もはや国内の風評被害云々よりも、威圧的な中国に負けてなるものかとの気持ちが強くなっている。私のように、「福島産を買って応援したい」と思っている人は多いはずだ。ただ、いつ、どこで、どういう支援イベントがあるかが分からない。新聞はぜひとも、具体的な支援イベントの告知をどしどし載せてほしい。いまこそ新聞の力を見せるときだ。
- 01 Sep 2023
- COLUMN
-

「福島」をためらう消費者は過去最小だが、報道の援護なし!
二〇二三年五月十九日 福島第一原子力発電所の処理水の放出がいよいよ目前に迫ってきた。ことの成否は消費者の意識次第だが、タイミングよく今年三月、消費者庁が「風評に関する消費者意識の実態調査」(第十六回)を公表した。とても重要な調査結果なのだが、ほとんど報道されていない。たとえ地味な結果でも、メディアはもっと現状を伝えてほしい。「福島産をためらう」は過去最小 処理水が実際に海へ放出された場合、最も注目されるのが、どのメディアも再三報じているように風評被害が生じるかどうかである。消費者が福島産の食品を従来通りに買ってくれれば、風評被害は発生しない。そこでポイントとなるのが、どれだけの消費者がいまなお「福島産食品を避けたい」と思っているかどうかである。 その重要な指標となる意識調査が今年三月十日、消費者庁から公表された。食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ、第1回(二〇一三年二月)の調査では「福島」を挙げる人が一九・四%もいた。ところが、今年一月(第十六回)の調査では五・八%と過去最小に減った。 放射性物質を理由に購入をためらう産地として、東北(岩手、宮城、福島)を挙げる人の割合も同様に減り、二〇一三年の一四・九%から、今回は三・八%に減った。安全な情報は国民に届かない これらの数字を見ていると、スーパーなどで放射性物質を理由に福島産や東北産を避ける人は確実に減っていることが分かる。こういう調査結果こそ大々的に報じてほしいのだが、新聞を見ていてもほとんど報じられていない。 「福島産が危ない」といったニュースは瞬時に流れるが、安全だというニュースはなかなか国民に届かない。「そもそもニュースとはそういうものだ。記者とは危ない情報を好む職業だ」といってしまえば、身もふたもないが、処理水の放出が目前に迫ったいまだからこそ、逆に安全な情報にニュース価値があるはずだ。どうもいまの記者の感度は鈍いと言わざるを得ない。 どの新聞の記者たちも処理水の放出で最大の懸念は風評被害だと書いてきた。ならば、風評被害が生じにくい空気が醸成されつつあることは喜ばしいことなのだが、記者にとって「喜ばしいことはニュースとしておもしろくない」となってしまう。風評被害の解消にはメディアの的確な報道が欠かせない。にもかかわらず、安全な情報をシャットアウトしてしまう。こういう記者のスタンスでは、やはり風評被害の解消は難しいのではないかと思いたくもなる。「検査知らない」は最高の六三% 一方、福島県ではいまも魚介類や食品の放射性物質の検査は継続して行われている。その結果も公表されているが、地味な話題のせいか、最近ではほとんど報じられない。その弊害は今回の調査結果にも表れた。 食品中の放射性物質の検査が行われていることを「知らない」と答えた人の割合は、二〇一三年の二二・四%から徐々に増え、今回はなんと過去最高の六三%にはね上った。「検査結果を知らない」ということは、よい意味に解釈すれば、もはや放射性物質のことは気にしていないということになるのだろうが、そういう無意識に近い状態のままだと突如、危ない情報が飛び込んでくると一気にひっくり返る恐れがある。 福島県の農林水産物のモニタリング検査結果(二〇二二年度)によると、米、野菜、果物、肉類、水産物など四七〇品目で一万二六四件が検査されたが、基準値の一キログラムあたり一〇〇ベクレルを超えた件数は、牧草・飼料作物の一件だけだった。もはや福島産を気にする理由は全くない状態になっている。こうした地味な調査結果を伝えるのが記者の仕事である。いや記者にしかできない仕事である。その自覚がいまこそ必要だろう。流通事業者の存在意義を示すとき 風評被害の解消に欠かせない存在として、記者以外に見逃せないのが流通事業者である。特に大手スーパーの存在意義は大きい。 もう昔の話になるが、一九九九年に埼玉県所沢市でダイオキシン騒動があった。所沢産のホウレンソウが焼却場由来のダイオキシンで汚染されているというニュースが民放テレビ(テレビ朝日)で流れた。この問題が一気に大きな話題となったのは、大手スーパーが所沢産ホウレンソウの取り扱いを中止したときだった。大手スーパーが取引を中止すれば、当然ながら、記者たちは「危ないネタ」に喜び勇んで駆けつけ、ビッグニュースに仕上げる。以来、ハチの巣をつつくような大騒ぎになった。 この問題は結局、訴訟になり、五年後の二〇〇四年、テレビ局が謝罪し、和解金一千万円を支払うことで終決を見た。深く考えることなく、危ないニュースに飛びつく報道のDNAに警鐘を鳴らす事件でもあった。 結論。処理水の放出にあたって、過去の経験から学ぶべきことは何だろうか。 まず記者は現状を冷静に伝えること、そして安全な情報はたとえ地味ではあっても国民に伝える価値があることを自覚して報じることだ。 一方、流通事業者は風評被害の火付け役になりうる自覚をもち、福島産食品をしっかりと店の棚に置いてほしい(もちろん科学的に安全だという条件付きだが)。店に福島産食品があれば、あえて買うことで福島を応援する消費者もいるだろう。店にモノがなければ、選びようがない。記者と流通事業者が「風評被害を生じさせない」という意識をもつことこそが、処理水放出の成否を握っているのではないだろうか。
- 19 May 2023
- COLUMN
-
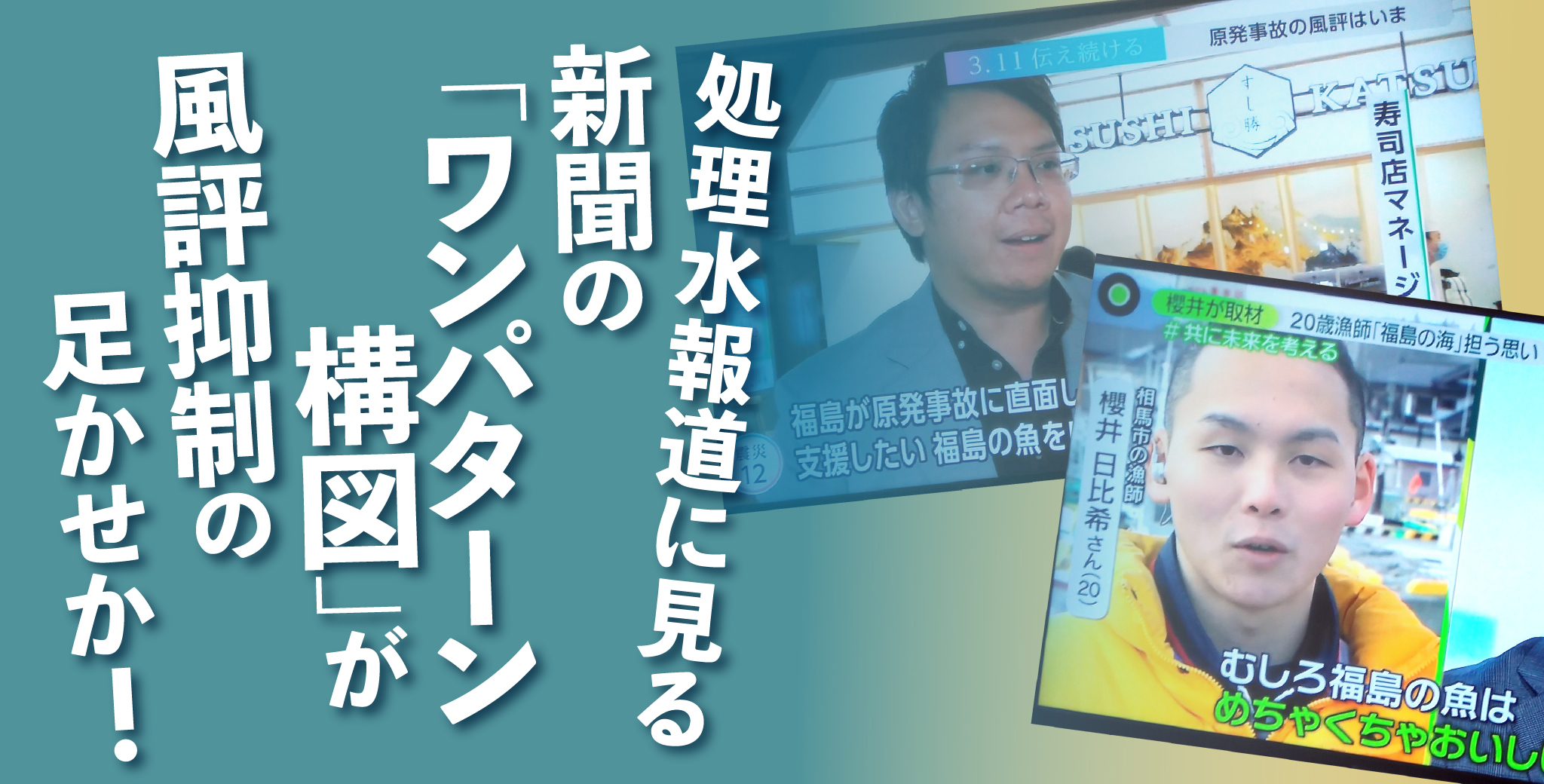
処理水報道に見る新聞の「ワンパターン構図」が風評抑制の足かせか!
二〇二三年三月十七日 一〇〇〇回の説明会 福島第一原発に溜まる処理水の放出に関する最近の新聞記事を読みながら常に感じるのは、報道の構図が以前と全く変わらないことだ。悪く言えば、どの記事も代わり映えのしないワンパターン記事なのである。 処理水に関する報道舞台に登場する役者は、主に政府、東京電力、漁業関係者、国民(消費者)、流通事業者、学者、メディアの7人だ。大半の新聞記事では、役者たちの役割は決まっている。政府と東京電力に対しては、「風評の払しょくに向けて、もっと努力すべきだ」という役割が与えられ、国民は「不安と風評への懸念を表明する」立場であり、漁業関係者は「反対」を表明する位置づけだ。福島の食品を扱う食品流通事業者の役割はきわめて重要だが、登場頻度は低い。学者は媒体の性格に合わせて、安全と言ったり、危ないと言ったりする役目だ。メディアはこれらの役者の声を聞いて、「風評への懸念は根強い。国民の理解は不十分だ。政府はもっと国民の理解促進に努めるべきだ」と書き立てて騒ぐだけである。まとめ役のメディアがまるで他人事のように記事を書いているせいか、ワンパターン記事が量産されているのが実情である。 こうした報道の構図が続く限り、風評の解消は難しい。読売新聞は三月八日付朝刊の「東日本大震災12年 新たな課題③」で、政府はこれまでに正しい知識や理解を広げる説明会や座談会を約一〇〇〇回も開いてきたと報じていた。政府や東京電力がここまで努力しても、風評被害の懸念がなくならない背景には、報道に何か構造的な欠陥があるのではないか。記者の突っ込み不足 まず気づくのは、記者たちが風評を抑えるためにどういう情報を出せばよいかを真剣に考えていないことだ。風評を抑える役目はあくまで政府と東京電力であるといった報道の構図があるのだろう。 ところが、ここへ来てややトーンが変わってきた兆しが見えた。読売新聞は三月八日付朝刊で野崎哲・福島県漁連会長の談話を載せた。「放出は了解できない」とした上で「廃炉が確実に進むことが重要だ。極端な対立構造にするつもりはない」との見方を載せたのだ。これまで漁業関係者の言葉はたいてい「断固反対」だったが、「極端な対立構造にするつもりはない」というコメントは新鮮であり、何かしら前進へのシグナルにも思えた。 残念なのは、記者の突っ込み不足だ。「対立構造にするつもりがない」という言葉を聞いたならば、「では、どういう着地点、解決策を考えているのか」を聞き出して、提案型の記事にしてほしいのだが、その突っ込みがない。 仮にこの記事をきっかけに関係者が歩み寄れる接点が見つかれば、記者冥利に尽きると思うが、こういう問題解決型の記事を記者は志向していないようだ。「反対ばかりもしていられない」の先は? 同様のことは朝日新聞の記事でも見られた。今年二月二十六日付朝刊で「近づく海洋放出、福島の葛藤」との見出しで風評懸念を報じたが、私の注意を引いたのは、漁業者が「海洋放出には反対だ」とする一方、「ただ反対ばかりもしていられない」との言葉だった。記者が「反対ばかりもしていられない」という漁業者の気持ちを載せたということは、おそらく記者も同じような思いを抱いたに違いない。ならば、何をすればよいのかをさらに漁業者に尋ね、その思いを記事にしてほしかったのだが、その肝心な点がない。 せっかく漁業者の「反対ばかりもしていられない」という肯定的な話を引き出したのだから、何か建設的な提案を漁業者から引き出して報じてもよさそうだが、記者はそれ以上深く突っ込んでいない。NHKはお手本のような報道だった もはや新聞記事には風評の払しょくは期待できないかと諦めかけていたときに、NHKが風評を抑えるお手本のようなニュースを流した。 それは三月九日夜のNHK「ニュースウオッチ9」の処理水に関するニュースだった。これは明らかに風評被害を食い止めようとする記者の熱い意志がひしひしと感じられる構成だった。前述の新聞報道と明らかに異なるのは、消費者や流通事業者が福島産の魚を肯定的に受け止めている光景を大きく取り上げたことだ。東京都内で行われたイベント紹介で、女性2人が「原発のイメージとか関係なく、福島の美味しいものは積極的に食べておきたい」と笑顔で話す内容を流したのだ。 さらに東南アジア諸国からの輸入規制も緩和されている様子を伝え、タイのすし店のマネージャーが「支援したい福島の魚を自信をもって提供したい」と語り、それを美味しそうに食べる女性まで映し出した。また、福島県の小名浜魚市場を視察した流通事業者の姿も追い、飲食店のプロデューサー2人が「ここまで徹底して安全性を確かめていることを伝えていくことは協力できる」と語る感想も報じた。新聞と異なり、テレビの映像のインパクトは強い。 このNHKのニュースからは、風評被害を止めるのは政府と東京電力の役割だといった固定観念が見られない。若き漁師の熱きメッセージ さきほどのNHKのニュースに感心さめやらぬ中、今度は三月十三日夜の日本テレビ「news zero」で、福島の漁師から頼もしい言葉を聞き、胸が熱くなった。 同番組は、トリチウムを含む処理水は世界中の原子力施設から海などに放出されているという地図を見せたあと、タレント・俳優の櫻井翔氏のインタビューに応じた福島の若き漁師(20歳)を映し出した。その漁師が「『福島の魚嫌だ』という人がいるかもしれないけれど、福島の魚は実際に食べてみると安全で、メチャクチャ美味しい」と熱く語ったのだ。 福島の魚に抵抗感をもっている人をはねつけるのではなく、そういう不安な感情に寄り沿って共感しながらも、「でも、福島の魚は安全だし、絶対に美味しい」という自信あふれるメッセージを発信したのだ。私がメディアの世界で漁業関係者に期待していたのは、この青年のような言葉だった。 海洋放出に反対する国民の気持ちも理解できるが、それでも「福島を支援してください」という温かいメッセージを届けることが共感を得るのだ。あの青年を見ていて、私は福島の魚を大いに応援したいという気持ちになった。これこそが共感を呼ぶニュースだ。新聞に見られる傍観者的なニュースとは正反対である。 とはいえ、「風評の解消に努めるべきは政府と東京電力であり、なぜ国民や漁業関係者がそれに協力しなければいけないのか」という疑問を持つ人もいるだろう。しかし、いくらSNSが発達しているとはいえ、政府がTwitterやYouTubeなどで福島の情報や動画を流したところで国民に届く情報量はたかが知れている。やはり、いまなおマスメディアの役割は大きい。 新聞をはじめ、メディアの主要な役割は政府の権力が暴走しないよう監視することだと心得ているが、こと風評の抑制が目的なら、メディアと政府が対立する必要はなく、ともに連携してもおかしくないはずだ。処理水の海洋放出が始まれば、おそらく中国や韓国から『福島産の魚介類は危ない』といった声が上がるだろう。そうした海外からの圧力をはね返すためにも、新聞はもっと風評への懸念解消を志向した記事を心掛けてほしい。
- 16 Mar 2023
- COLUMN
-
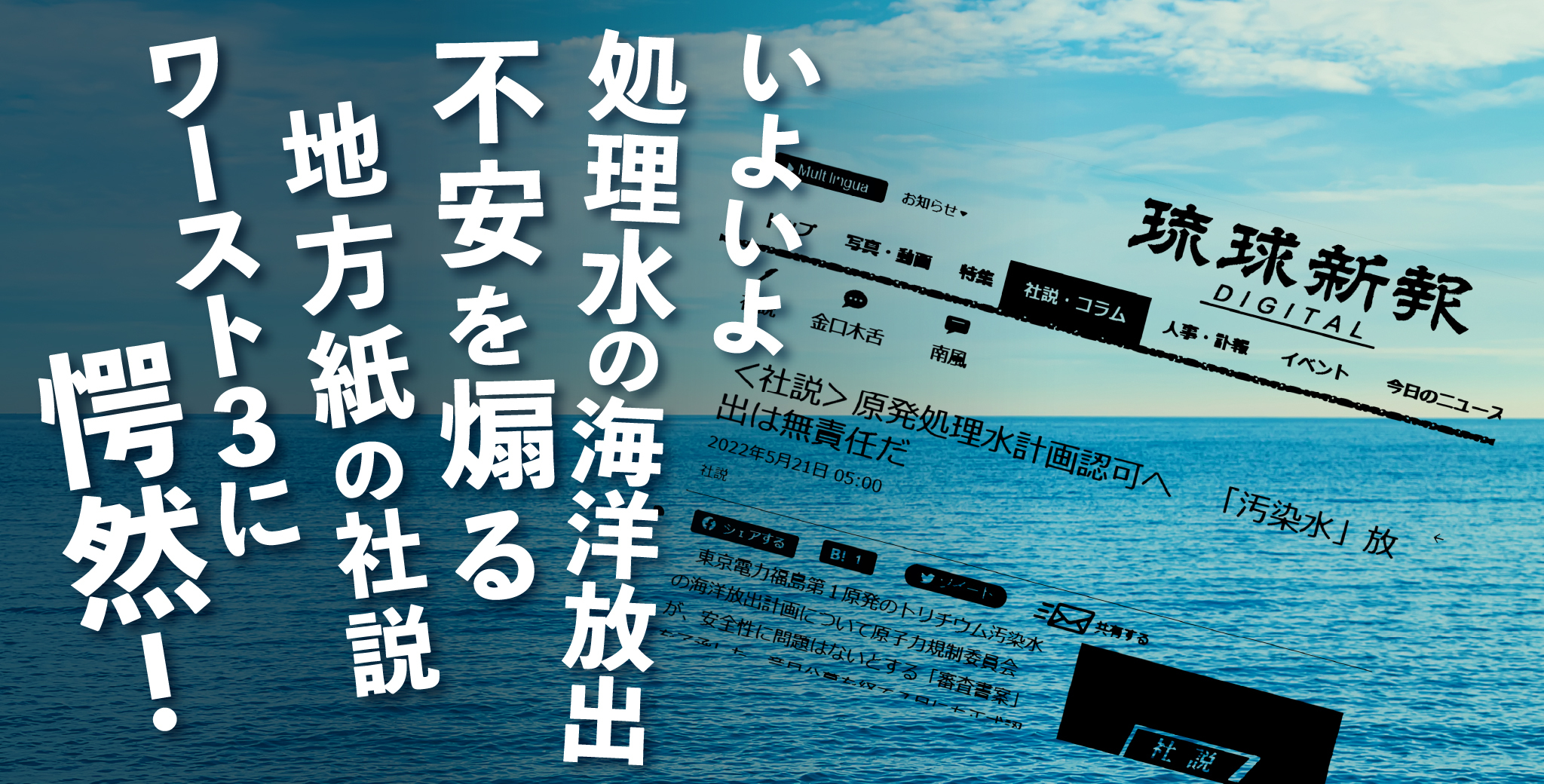
いよいよ処理水の海洋放出 不安を煽る地方紙の社説ワースト3に愕然!
二〇二三年一月十八日 福島第一原子力発電所に林立するタンクの処理水が今年、いよいよ放出を迎える。風評被害が抑えられるかどうかが最大の懸念材料だが、地方紙の社説が風評を起こす盲点になっていることに気づいた。大半の地方紙は福島から遠く離れているせいか、まるで他人事のように不安を煽る社説が多い。社説ワースト3を紹介しよう。 処理水に関する社説は、これまで主要6紙(読売、朝日、毎日、産経、日経、東京)ばかりを読んでいたが、改めて地方紙の社説をネットで検索して読んでみたところ、そのあまりのヒドさに絶句する心境に何度か陥った。福島から離れた県民ほど、福島産食品の実態(放射線量が検査されて安全だという事実)を知らない人の割合が多いという事実をよく聞くが、その背景には、不安や恐怖を煽る地方紙の社説があるのではないか。そう思いたくなるほど劣悪な内容の社説に出合った。驚嘆に値する琉球新報 たとえば、琉球新報(二〇二二年五月二十一日付)。見出しは「原発処理水計画認可へ『汚染水』放出は無責任だ」。海へ流すときの処理水は、汚染水とは言わないが、あえて不安をかきたてる「汚染水」という言葉を使う。見出しを見ただけで悪意ある社説だとわかる。 中身は驚嘆に値する。自然界や人体にも微量ながら存在するトリチウムについて、同社説は次のように書く。 「水素の同位体トリチウム(三重水素)は放射性物質である。希釈すれば放出してもいいということに、地元関係者をはじめ多くの人が疑問を持っている。…廃炉作業が続く限り生成が続き、排出量は増していく。漁業者が反対し、住民が懸念するのは当然だ。海洋放出は無責任だ。…東電は『処理水』とするが、トリチウムが残る限り『汚染水』である」。 トリチウムは通常の原子力発電所の運転でも発生する。世界中の原子力施設が放出基準を順守しながら、トリチウムを海などに放出しているという事実を無視し、一方的に「汚染水だ」と決めつけて不安を煽る。 社説は続く。「矢ヶ崎克馬琉球大名誉教授(物性物理学)は『トリチウム水は普通の水と同じ性質だが、質量が大きい分、気化もしにくく生物濃縮も起きやすい。細胞内でDNAを傷つける可能性がある』と指摘する」と恐怖を煽る。 水と同じ性質をもつトリチウムが生物の体内で濃縮することはないというのが科学者の共通認識である。つまり、「生物濃縮が起きやすい」は間違いである。もし濃縮する生物がいるならば教えてほしい。そのような生物がいるならば、むしろ濃縮に活用できるからだ。 この社説は、現在の科学的な共通認識とは明らかに異なる一部の異端的な意見だけを取り上げて恐怖を煽る手法そのものである。社説を書く論説委員は科学を重視するタイプの記者だと思っていたが、違うようだ。福島の痛みがまるで分っていない 琉球新報は約二か月後の七月二十七日付社説でも、同様の論説を繰り返した。 「安全性に問題はないというのが理由だが、果たしてそうなのか。疑問は尽きない。海に流してしまうということには地域、漁業者らに加えて国際社会にも批判がある。…このまま海洋放出計画を進めるのは無責任である。放出以外の方法を引き続き検討すべきだ。トリチウムは放射性物質である。トリチウムが残る限り『汚染水』である。いくらトリチウムの濃度を下げるといっても、これを海洋に出すことの影響はどうなのか」。 またしても悪意に満ちた「汚染水」という言葉を使っている。不安を煽って福島産食品の悪い風評を広めれば、福島県民が悲しむことくらいは、米軍基地を抱える沖縄であればわかりそうなものなのに、まるで傍観者である。中国や韓国の立場に立つ中國新聞 中國新聞(二〇二二年七月二十四日付)もひどい。 「処理水に含まれる放射性物質トリチウムなどが健康被害をもたらす可能性は否定できない。それが確認されなくても風評被害を招くことは避けられまい。地元の漁業者を含め、全国漁業協同組合連合会が激しく反対している。政府や東電が放出計画を強引に進めることなどあってはならない。ただALPSでトリチウムは除去できない。政府は『原発の排水にも含まれている物質』と危険性の低さを強調するが、体内に蓄積される内部被曝(ひばく)の影響まで否定できるものではない」。 トリチウムは人の体内で蓄積しないというのが科学者の共通認識だが、琉球新報と同様にトリチウムの体内蓄積で健康被害が起きるかのような論説だ。 さらに「規制委の認可に韓国は『潜在的影響』への憂慮を示し、責任ある対応を日本政府に求めることを決めた。中国は『無責任』と激しく反発している。福島第一原発事故に由来するセシウムが北極海にまで広がっていた事例も報告されている。人体に静かに蓄積され、長期間にわたり被害を及ぼしかねないことを踏まえれば、海洋放出の判断には慎重を期すべきだ。子や孫やその先の世代に影響が出ても、その時に今回の認可の責任を取れる人は誰もいないことを忘れてはならない」。 いったいどこまで脅せば気が済むのか。これはもはや論説というよりもアジテーション(煽動)である。中国や韓国の立場に立って、日本を非難するのも琉球新報と同じ手法だ。孫の代まで影響が及ぶかのごとく主張するが、何の根拠もない。こんなひどい社説が堂々とまかり通っているという事実に愕然とせざるを得ない。言葉を捻じ曲げて伝えた佐賀新聞 佐賀新聞(二〇二二年七月二十三日付)も悪意に満ちている。 「第一原発では炉内冷却のための注水や建屋に流れ込む地下水、雨水によって大量の汚染水が発生している。これを特殊な装置で浄化したものを『処理水』というが、トリチウムなど取り切れない放射性物質が含まれる汚染物質であることに変わりはない」 やはり、この社説でも「汚染」という言葉を強調する。どの新聞が不安を煽っているかを知る指標は、海に放出する水を「汚染」と呼ぶかどうかでわかる例でもある。 続けて、同社説は「海洋放出に関してより重要なのは、これらの科学的、工学的な評価ではなく、社会的な合意という問題だ。東電は『地元の合意なしには放出はしない』としているし、立地自治体と結んでいる協定では、放射性物質の影響が及ぶ可能性がある施設を新増設する場合、地元の事前了解を得る必要がある。だが、東電はどのような形なら地元合意が得られたと考えるのかを明確にしていない」と書く。 ここでは絶妙なトリックも披露している。「地元の合意なしには放出はしない」は誤りで、正しくは「地元の理解なしには」である。「理解」と「合意」では雲泥の差がある。たとえ海洋放出に反対であっても、理解を示すことはありうるからだ。この部分は、本来なら、「『合意』は『理解』の間違いでした」と訂正が必要だろう。社説の筆者は、勝手に「理解」を「合意」という言葉にすり替え、「東京電力は合意を無視して、海洋放出を強行した」というイメージを作り出したいのだろうと推測する。 この佐賀新聞の社説は最後に署名があり、共同通信社の論説委員が書いたものだと分かった。共同通信社の体質がよくわかる好例でもある。地方紙の大半は「海洋放出に反対」か ここに挙げたワースト3以外にも京都新聞、神戸新聞、西日本新聞の社説は風評被害を助長する内容だった。ネット検索だけでは、すべての地方紙の社説が読めるわけではないため、ワースト3といっても、おそらく氷山の一角だろう。 これらの社説を通じてわかることは何だろうか。確たることは言えない(おそらく当たっていると思う)が、福島県の地方新聞を除き、地方紙の大半の社説は「海洋放出」に否定的もしくは反対の論説を掲げていることが推測される。その背景には地方紙にニュースを提供している共同通信社の影響が大きいだろうとみている。処理水の海洋放出に対する共同通信社の姿勢はたいていの場合、不安を呼び起こすネガティブな内容だからだ。社説も例外ではない。 共同通信社は一九四五年に全国の新聞社やNHKが組織した一般社団法人の通信社(職員約一七〇〇人)である。新聞を発行しているわけではないが、全国の都道府県に記者を配置し、地方紙に記事を配信しているため、実は予想以上に大きな世論喚起力をもっている。地方紙は一般的に自らの県と東京・大阪以外には記者を配置していないため、記事の大半を共同通信社からの配信記事で埋めている。 つまり、地方紙を読んでいる読者は、共同通信社の記事を読んでいるのに等しいのだ。私があえて「共同通信社の影響が大きい」と形容したのは、そうした地方紙と共同通信社の関係を指しているわけだ。 地方紙に記事を配信している通信社としては、他に時事通信社(株式会社)もあるが、従業員は共同通信社の半分の約八七〇人しかいない。国内の五十四か所に記者を置いているが、地方紙に採用される率は低いので、影響力は共同通信社に比べて弱い。地方紙の多くは福島の痛みに共感せず そして、もうひとつ地方紙に共通することは、ここに挙げた琉球新報、佐賀新聞、中國新聞のように、福島の痛みを自分事の痛みとして感じていないことだ。どの社説も中国や韓国の言い分を嬉々として載せているのも、不快な気持ちにさせる。中国や韓国はトリチウムを含む水を福島の海洋放出基準以上の濃度で海へ放出している。それに触れることなく、中国や韓国側の非難の声を載せるという報道行為は、日本が海外から批判され、風評被害が生じるのを喜んでいるとしか思えない。 三つの社説を読んだだけでも、多くの読者は「ここまでひどいとは思わなかった」と嘆きの声を抱いていることだろうと想像する。中央の主要6紙の購読部数が大きく減る中、地方紙の影響力が相対的に大きくなっている。そういう中で煽動的な地方紙の社説はまさに盲点だった。共同通信社と地方紙の論調にもっと目を光らせていくことが必要だろう。
- 18 Jan 2023
- COLUMN




